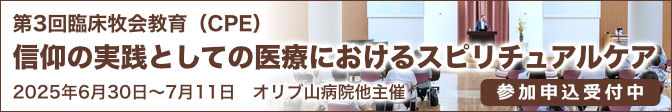神学書を読む
-
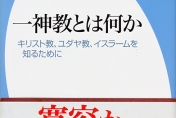
神学書を読む(24)小原克博著『一神教とは何か―キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために』
三宗教の解説書、入門書は巷にあふれている。しかし、小原氏はこの三宗教の関係性について問う。さらに宗教界の独自性だけでなく、おのおのの教えが実社会にどのような影響を与えているか、という意味での「間」を問う。
-
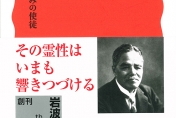
神学書を読む(23)若松英輔著『内村鑑三 悲しみの使徒』
クリスチャンなら、内村鑑三のことを聞く機会が多いだろう。私の周りの方は、皆が彼を好いている。本書は、内村の信仰列伝ではない。むしろ、歪(いびつ)な性格の故に周囲がかなり人間関係に苦慮せざるを得なかったことを赤裸々に語る告白本である。
-

神学書を読む(22)出村和彦著『アウグスティヌス「心」の哲学者』
宗教改革500周年。当然、プロテスタントは活気づく。しかし、カトリックが歴史的に意味をなさなかったというわけではない。両陣営とも、「三位一体」や「恩恵」という概念を受け入れている。その根幹を築き上げたのがアウグスティヌスである。
-
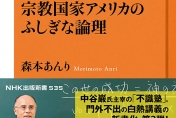
神学書を読む(21)森本あんり著『宗教国家アメリカのふしぎな論理』
本書は、私が(勝手に)二分してきた神学の概念的側面と実学的側面、それを見事に組み合わせて、現代における「正統」の概念と実際を考察している。具体的には「宗教国家」である米国を取り上げ、その特徴を「富と成功の福音」「反知性主義」と整理して詳述している。
-
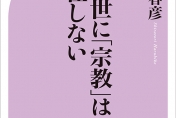
神学書を読む(20)白取春彦著『この世に「宗教」は存在しない』
哲学、宗教などの専門家として、このような分かりやすい本を次々とお書きになっていることは、すごいことである。特にキリスト教に関しては、私たちが彼の主張から学ぶべきことが多くあるように思われる。
-
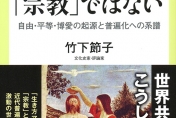
神学書を読む(19)『キリスト教は「宗教」ではない 自由・平等・博愛の起源と普遍化への系譜』
わずか200ページ余りの新書であるにもかかわらず、読み通すのに2週間かかった。著者はフランス在住の比較文化史家であり、カトリック信者でもある。この視点が本書を他のキリスト教史とは異なる存在に押し上げている。
-

神学書を読む(18)藤本満著『歴史―わたしたちは今どこに立つのか―』
本書は「わたしたちと宗教改革」シリーズ第1巻として発刊された。今年(2017年)がルターの宗教改革から500年ということもあり、さまざまな「宗教改革本」が出版されている。その中で本書は白眉だと言っていい。
-

神学書を読む(17)冷泉彰彦著『予言するアメリカ 事件と映画にみる超大国の未来』
本書は、プリンストン在住のフリージャーナリスト、冷泉彰彦氏の新刊である。トランプ政権誕生を踏まえ、どうしてそのような米国になっていったのか、を映画というフィルターを通してつまびらかにしようとする意欲作である。
-

神学書を読む(16)ジョン・C・マクスウェル著『「人の上に立つ」ために本当に大切なこと』
世界累計1800万部を越える超ベストセラー作家にして、リーダーシップの大家、ジョン・マクスウェル。彼がかつて牧師であり、その牧会理念に基づいて「リーダーシップ」を語り出したことをどれくらいの方がご存じだろうか?
-
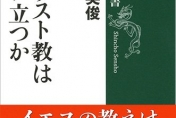
神学書を読む(15)来住英俊著『キリスト教は役に立つか』
ストレートなタイトルである。テレビドラマの影響か、「~役に立つ」はちょっとした流行語なのかもしれない。本書は、キリスト教的世界観をカトリック的視点から、誰でも理解できるように解説してくれている。組織神学的トピックスがほぼ網羅されているのも秀逸である。
-
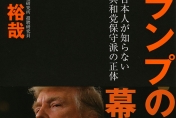
神学書を読む(14)渡瀬裕哉著『トランプの黒幕 日本人が知らない共和党保守派の正体』
著者の渡瀬氏は、初めからトランプ優勢を伝え、しかもその分析も丁寧に行っている。特にセンセーショナルな言葉が飛び交う最近のメディアに対する辛辣(しんらつ)な批判は秀逸である。
-

神学書を読む(13)深井智朗著『プロテスタンティズム 宗教改革から現代政治まで』
自分の教派がカトリックでもギリシャ正教でもない、ということは分かっていても、そのルーツがルターに行き着くということに今一つリアリティーを感じられない方もおられるだろう。本書はそういう方にこそ手に取ってもらいたいものである。
-
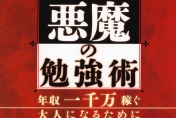
神学書を読む(12)佐藤優著『悪魔の勉強術 年収一千万稼ぐ大人になるために』
まず、タイトルにだまされてはならない。「悪魔の―」となっているが、中身は至って実践的な大学生向け指南書である。しかも「神学」という概念をここまで敷衍(ふえん)して実学とリンクさせている書物は近年お目にかかったことがない。
-
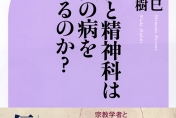
神学書を読む(11)島田裕巳・和田秀樹著『宗教と精神科は現代の病を救えるのか?』
タイトルからして刺激的である。宗教の目的、そして精神科の目的。これらに共通するのは、苦しんでいたり悩んでいたりする人間を「救い」へと導くことである。
-

神学書を読む(10)ノーマン・V・ピール著『新訳 積極的考え方の力―成功と幸福を手にする17の原則』
本書は、厳密には「神学書」とは言えない。しかし、書かれている内容は、一般ビジネスマン向けではあるものの、聖書に基づいている。なぜなら、作者のピールはニューヨークで1950年代に活躍したキリスト教牧師である。
-
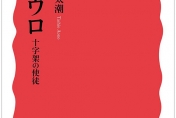
神学書を読む(9)『沈黙』と共鳴するキリスト教の犠牲批判 青野太潮著『パウロ 十字架の使徒』
新書版であるため、ページ数としてはわずか200ページ足らずであるが、その内容は深く、既存のキリスト教に対してセンセーショナルな議論を吹っかけている問題の書である。
-
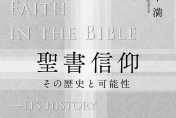
神学書を読む(8)『聖書信仰』後編:聖書無誤主義を福音主義はどう超克するか?
前編では、13章までで提示された歴史的見地から見た聖書信仰の変遷について言及した。後編では、藤本氏が本書を書く動機ともなったであろう、モダン主義を越えた聖書信仰の在り方について、評していきたい。
-
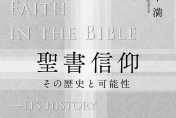
神学書を読む(7)『聖書信仰』前編:聖書無誤主義を福音主義はどう超克するか?
もしもあなたが「聖書の書いてあることは本当にあったことなんだろうか?」とか、「こんな出来事が本当にあったとしたら、これをどう説明したらいいのだろう?」と一度でも思ったことがあるなら、ぜひ本書を手にすることをお勧めする。
-
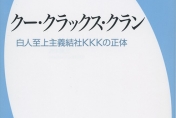
神学書を読む(6)『クー・クラックス・クラン 白人至上主義結社KKKの正体』
KKK(クー・クラックス・クラン)といえば、白い目出し帽子の三角頭巾にワンピース状の白いローブをまとい、炎の十字架を掲げて黒人たちをリンチして回る恐ろしい集団、というイメージがあるのではないだろうか。
-
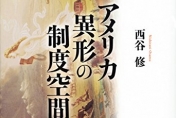
神学書を読む(5)『アメリカ 異形の制度空間』 気鋭の哲学者が読み解くアメリカの誕生と歴史
米国発の諸神学(黒人神学、フェミニズム神学など)がどうして生み出されたのかをはっきりと示してくれるという意味で、本書は広い意味での神学書と位置付けることができる。著者の西谷修氏は、専門が哲学であるため、内容はかなり抽象的な分野にまで言及している。
人気記事ランキング
-

次期ローマ教皇の有力候補4人
-

ローマ教皇フランシスコの死に相次いで哀悼のコメント キリスト教指導者7人の反応
-

教皇フランシスコの献花台や記帳所、東京カテドラル聖マリア大聖堂などに設置
-

2026年に東京のスタジアムで伝道集会開催へ 「過去に見たことのないリバイバルを」
-

「苦しみ」と「苦しみ」の解決(4)神が人を引き寄せてくださる(後半) 三谷和司
-

人生をまるまる楽しもう! 菅野直基
-

「苦しみ」と「苦しみ」の解決(4)神が人を引き寄せてくださる(前半) 三谷和司
-

シリア語の世界(22)辞書2・ヨハネ黙示録の賛美歌5―11章15節― 川口一彦
-

【イースターメッセージ】陰府(よみ)帰りの福音 金井望
-

コヘレトの言葉(伝道者の書)を読む(2)太陽の下の世界 臼田宣弘
-

2026年に東京のスタジアムで伝道集会開催へ 「過去に見たことのないリバイバルを」
-

教皇フランシスコの献花台や記帳所、東京カテドラル聖マリア大聖堂などに設置
-

ローマ教皇フランシスコ死去、88歳
-

【イースターメッセージ】陰府(よみ)帰りの福音 金井望
-

次期ローマ教皇の有力候補4人
-

ローマ教皇フランシスコの死に相次いで哀悼のコメント キリスト教指導者7人の反応
-

聖職者への唾吐き、教会施設への攻撃など イスラエルで反キリスト教事件が増加
-

映画「パッション」続編、今年8月にもイタリアで撮影開始へ
-

「苦しみ」と「苦しみ」の解決(4)神が人を引き寄せてくださる(後半) 三谷和司
-

英国で「静かなリバイバル」 教会の礼拝出席率が増加、Z世代の男性で顕著
-

2026年に東京のスタジアムで伝道集会開催へ 「過去に見たことのないリバイバルを」
-

映画「パッション」続編、今年8月にもイタリアで撮影開始へ
-

救世軍、ブース記念病院を事業譲渡 7月から「タムス杉並病院」に
-

教皇フランシスコの献花台や記帳所、東京カテドラル聖マリア大聖堂などに設置
-

ローマ教皇フランシスコ死去、88歳
-

「山田火砂子監督、さようなら」 教会でお別れの会、親交あった俳優らが思い出語る
-

英国で「静かなリバイバル」 教会の礼拝出席率が増加、Z世代の男性で顕著
-

【イースターメッセージ】陰府(よみ)帰りの福音 金井望
-

「カトリックジャパンニュース」がスタート カトリック新聞は休刊
-

聖職者への唾吐き、教会施設への攻撃など イスラエルで反キリスト教事件が増加