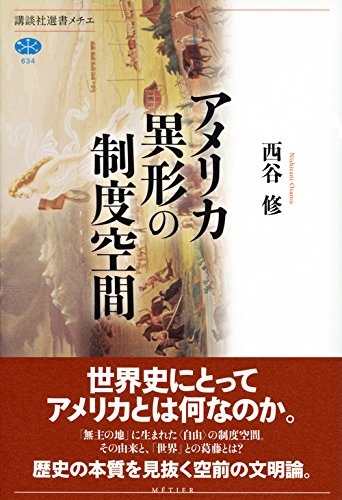米国発の諸神学(黒人神学、フェミニズム神学、繁栄の神学など)がどうして生み出されたのか、またそもそもこれらの諸神学がどうして今のような特質を持ち、独自の形態を取るようになったのかをはっきりと示してくれるという意味で、本書は広い意味での神学書と位置付けることもできるし、「米国諸神学エピソードゼロ」を知ることができる書といえる。
著者の西谷修氏は、専門が哲学であるため、内容はかなり抽象的な分野にまで言及している。このような形態で「アメリカ」を語った研究者は他にいないのではないだろうか。
新しい理想や希望が投影された想像の世界としての「アメリカ」
本書の「結び」で、西谷氏は自分の考察方法を「唯名論的」として、次のように解説している。「事象を考察するとき、その名前が示すとみなされる実在を自明の対象として扱うのではなく、その名前がどのような成り立ちをもち、どのように振る舞い機能して対象を造形してゆくのかを考える。名前が示す実在は、そのような造形作用によって形成されるのである」(198〜199ページ)
この原理にのっとるなら、〈アメリカ〉という言葉が指し示すものは、南北アメリカ大陸のことではなく、その場を発見したとされるアメリゴ・ヴェスプッチにちなんで命名された土地を指すものでもない。西谷氏によれば、「輪郭も定かではない未知の対象につけられた名前、その名前で示される空間に人びとが移り住んでそれを実質化することで〈アメリカ〉という一世界は作り出された」ことになる。つまり、これは欧州キリスト教世界に存在していた、いわゆる「西洋人」が恣意的に名付けた制度と空間を指すものであり、彼らの世界観には存在してこなかった概念、考え方を〈アメリカ〉と呼んだということである。
本書の1章から3章までは、カトリック支配が次第に瓦解(がかい)しつつある時代に、人々が大西洋の向こう側の世界に思いをはせるさまを描き、欧州諸国が、宗教改革とその後の近世という時代に、どんな思惑で新しい世界を見ていたかが分かる。
いわゆる「大航海時代」といわれる時代、人々はカトリック世界の窮屈さを嫌い、そこからの自由を求める思いが潜在的に拡大しつつあった。その自由を象徴するものが〈アメリカ〉だった。ここでいう〈アメリカ〉とは、南米をも含んでいる。そしてカトリック国スペインとポルトガルは教皇との間に密約(トルデシリャス条約)を結び、まず南米にその足掛かりを得た。しかしやがてプロテスタントのうねりが欧州を席巻するようになると、教皇の権力の低下に伴って、英国やフランスなどはこぞって北米へと進出するようになっていく。この辺りの描写はとても分かりやすく、また当時の大航海が単なる「冒険」や「ロマン」だけに留まらず、とても政治的かつ神学的な動機から登場人物が複雑に絡み合っていたことが分かる。
〈アメリカ〉とは、このような旧世界の支配が及ばないという意味で、当時の欧州人の「理想」や「希望」が投影された想像の世界ということができる。それを彼らは「自由」と表現した。そして〈アメリカ〉と呼ばれた土地は、教皇や諸侯に代表される旧キリスト教勢力の及ばない「無主の地」であり、その広大な土地に立つことができる者なら誰でも、その「所有権」を自由に主張しても構わない、と考えたのである。このように、「所有権秩序を『自由』の根幹として維持する」のが、国家としての「アメリカ」の特徴であり、また彼らにとっての全世界へ向けての使命となっていった。これはまさに「新世界」観の誕生であり、旧世界から見るならば「異形」としか見えなかった。そのような新しい世界〈アメリカ〉を体現しているという意味で、「新大陸アメリカ」と表現し得る土地が生み出されたのである。本書のサブタイトルが「異形の制度空間」となっているのもうなずけるというものだ。
黒人神学、フェミニズム神学などがなぜ「アメリカ」で生まれたのか?
そしてこの〈アメリカ〉的な考え方は、米国の発展と共に北アメリカ大陸を征服し、やがて太平洋を越えて全世界へとその勢力を拡大させていく。
西谷氏はこれをもっぱら経済の世界で語ろうとしている。確かに世界がグローバル化する中で、異なった世界をつなぐ要素として、経済は重要かつ分かりやすい指標である。しかしここで私は神学を志した者として、この〈アメリカ〉なるものを神学の世界に適用させてみたい。
米国で生み出された神学として、世界的に有名なのは「黒人神学」と「フェミニズム神学」であろう。この人種とジェンダーは、米国における2大マイノリティーであり、長い年月をかけて改善に向かっている。その証左が大統領選挙だともいえよう。2008年は初の黒人(系)大統領が誕生し、2016年には初の女性大統領が誕生する可能性が生まれてきている(本原稿執筆時はまだ選挙結果が出ていない)。しかしここに至るまでの過程は、旧世界から新世界へと移行した〈アメリカ〉の本質とかなりリンクしている。
旧来の価値観を打ち捨てたとはいえ、その文化や習慣において残滓(ざんし)がある。それを的確に見いだして、新世界にふさわしい考え方を定着させていく。このパターンに米国生まれの神学も当てはまる。黒人神学は、公民権運動の時に盛んになり、フェミニズム神学は1960年代以降のウーマンリブ運動の高まりと共に一般化した。共通しているのは、既存の枠で不当に扱われていた者たちが、他者の管理下にある状態から抜け出し、自由を勝ち取るという図式である。これこそ〈アメリカ〉である。旧世界キリスト教の支配を逃れ、自由を求め、自らが所有者となるために前人未到の地へと踏み出した人々は、自らを「アメリカ人」と称したという。その意味で、上記の神学は、まさに〈アメリカ〉でこそ生み出される運命であったといえよう。
また、1970年代以降、特に保守的なキリスト教徒(福音派・ペンテコステ諸派)を中心として、神の恵みは、精神的なものだけでなく物質的にも信者を豊かにすると主張する「繁栄の神学」が盛んになってくる。これも米国の経済と神学を直結させたオリジナリティーあふれる考え方だといえる。豊かになっていい、自由に資産を用いて、その神の影響力を拡大させていけばいいと語るこの神学は、賛否入り乱れて今なお信奉者が絶えない。
本書は、神学に対するキリスト者の視点を大きく変えてくれる可能性がある。ある人は、神学をまるで天から降ってきた真理かのように受け止める。各教派が対立し合うと、その亀裂がなかなか埋まらないのはそのためである。しかし本書は、〈アメリカ〉という概念を導入する。すると、閉塞感を抱いた人々がそれを解消するために夢や希望を具体的な何かに投影することで、状況を打開してきたことがはっきりと示されることになる。
つまり私たちが現在、「真理」として受け止めている神学的諸要素は、その真理性を失うことなく相対化できるものであり、これを絶対化してきた旧世界から抜け出す術を欧州の人々は見いだし得たということである。そしてこの考え方は、決して西洋人だけのものではない。〈アメリカ〉は今や世界を席巻し、その価値観を確実に浸透させてきている。そうであるなら私たちは、この〈アメリカ〉なるものの成り立ちをしっかりと見据え、自分たちの未来を創造する者となれるのではないか。そんなことを思わされた良書であった。
西谷修著『アメリカ 異形の制度空間』(2016年10月、講談社)
◇