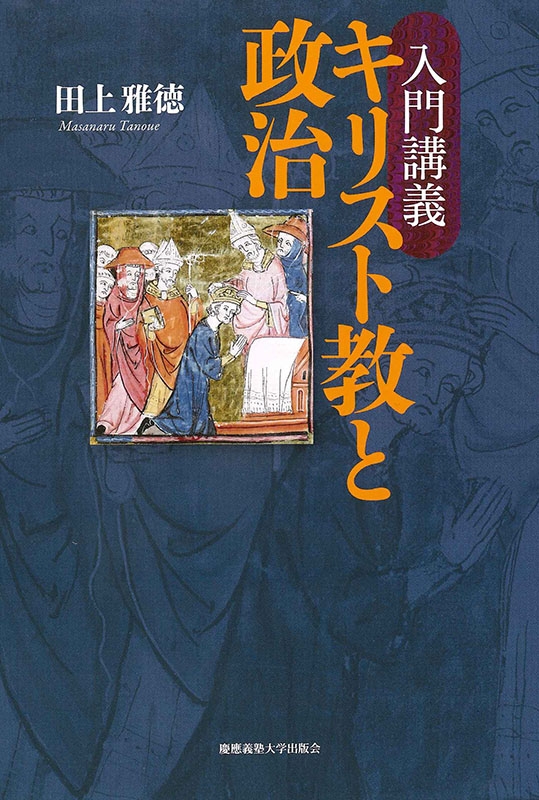「キリスト教史」とはほぼ「西洋史」そのものだ!
私の専門は歴史神学である。そのため、キリスト教史について語る機会が多いが、聞いておられる方からの反応で「キリスト教史ってもっと宗教的(霊的、またはキリスト教内の閉じられた歴史)だと思っていました」というものがよくある。いや、ほとんどの場合がそうである。
どうも「世界史」に対して「キリスト教史」というと「別の次元の歴史」と思ってしまうようである。しかしはっきり申し上げるが、キリスト教とは、歴史的宗教である。この世界(主に西洋史)との連関が最も深いのがキリスト教史であると言っても過言ではない。その証拠に、高校の世界史の教科書を開いてみると、「宗教改革」や「ピューリタン革命」、「米国独立宣言」など、おのおのの時代のキリスト教を反映した出来事が数多く掲載されている。つまり、キリスト教史とは西洋史のことであり、世界史の主要な構成要素として、この観点を見失っては歴史理解など望むべくもないということである。
その前提に立つなら、本書『入門講義 キリスト教と政治』は世界の政治形態がいかにキリスト教によって成り立っているかを詳(つまび)らかにする一読本だと言えるだろう。そして本書を読むと、「政治」が実は聖書をどのようにこの地上に実現するかという人間の営みであり、同時にどうやって聖書やキリスト教的な縛りから解放されて現実に適した指針を導き出せるかという、人々の葛藤のドラマだったということが見えてくる。
構成はいたってシンプル。古代世界から始まり、中世、近世、近代と続き、現代ドイツや米国の政治形態について述べられている。全14章(5部)構成である。もともと本書は大学の講義用に筆者の田上教授がまとめたものらしく、毎回きちんと練り上げられた講義ノートがそのまま文字化されたという。
「共同性」という観点から旧約聖書を読み解くと?
その中で、今回特に注目したいのが第1、第2章である。旧・新約聖書を政治思想のテクストとして考察しているこの章は、聖書の読み方に新しい視点を与えてくれる。第1章では、旧約聖書を「共同性」という観点で考察し、イスラエルの民が王政を求めるようになった経緯が描かれている。そしてこのヒエラルキーに対抗する意味で旧約聖書の物語が描かれているというところから、制度やしきたりではない、人々の「共同体」としての理想の在り方が聖書に物語られていることを示している。
さらに、思うようにならない現実の中で、人々を束ねる装置として「メシア」が配置される。人々の終末意識が微妙に絡み合う中で、このメシア思想が生み出され、やがて体系化されていく。これは、宗教書として聖書を読むだけでは見えてこない視点である。
第2章は、新約聖書に透けて見える終末意識について語られている。実はこの観点が後の西洋社会の政治形態を生み出すソース(素)となっている。イエス・キリストが復活し、天に還(かえ)っていった。そして再び来られるという約束を人々は真実と受け止めた。これにより、いつかある時に神がこの歴史に介入し、現状の政治形態を崩壊させるという思想になっていく。
これが、現存する政府や政治権力者に反対する者たちの反乱を正当化することになっていく。革命、一揆、政治闘争全てはこの「間もなく来られる主」という終末思想に基づいている。そう考えると、宗教改革、ピューリタン革命、そして米国独立戦争もこの範疇(はんちゅう)で解釈することが可能となる。「この世はいつか終わる」という漠然とした危機意識が、歴史を時には急激に、ある時は緩やかに顕在化されてくることが「世界の歴史」となる。
食事・生活不安の中、求心力を持ったキリスト教会
第3章以降、2章までの大まかな方向性に基づいて、古代、中世のキリスト教と政治との関連が語られていく。3章で最も得心がいったのが、以下の記述である。
「人々の宗教儀式を持っていることが、最初期のキリスト教のセールスポイントだったのである。これは決して馬鹿にすべき話ではない。食糧事情が不安定だった古代社会にあって、飲食の問題もケアできる宗教共同体に対して向ける人々の帰属意識は、当然高まったであろうからである」
このような事情から、一種の共産制がキリスト教徒同士の連帯モデルとして形成されていったと田上氏は語る。生活実感に訴える連帯を実践できたコミュニティー、これがキリスト教会であった。政治が実生活と密接な関係であることを認める現代の私たちにとって、この感覚はとても理解できるものである。私的感想になるが、ここに現代日本への福音宣教の鍵が垣間見えると思わされた。
さて、このような人々の必要を満たす共同体を形成し始めたキリスト教会は、当時の権力者から迫害される憂き目に遭った。2世紀は権力者の気まぐれで迫害の時期も期間もまちまちであったが、3世紀になると常に身の危険にさらされるようになる。
しかし驚くべきことが起こる。それは権力者側から、自分たちの在り方(人々の生活に密着した共同体形成)を擁護してくれる人物が現れたことである。彼はローマ皇帝コンスタンティヌスであった。
私たちは、迫害状態が終わりを告げ、自由になるのだからこの変化はとてもいいことだと受け止めたくなる。それは間違いないが、さらに進んで公的認知を得られたとしたら、今までの古代教会の在り方とは異なるアプローチを社会や人々に対してしなければならなくなることは明らかである。この変化にキリスト教会は戸惑った。そして皆が困惑してしまった。ここに登場してきたのが、神学者のエウセビオスであった。
この展開も私たちキリスト者に強く訴えるものである。1つは、現実の政治に対して批判の声を上げることは簡単で、相手の非を突いていれば何とか体裁を保つことはできる。しかし一度その政治と結託して、政(まつりごと)を行う側になった場合、事情は異なってくる。何かを打ち壊すのは簡単にできても、以前からあるものを受け継ぎながら新たなものを生み出すということは、とても骨の折れることである。この任を担ったのが神学(者)であったこと、これが新たな歴史の展開を生み出したと言える。
キリスト教というと、近代以降の理性の台頭や科学の進歩によって、過去の遺物と思われがちである。しかし本書は古代社会の有り様を描きながらも、その所々で「現代日本」を彷彿(ほうふつ)とさせる実情が挿入されている。「旧(ふる)くて新しい」という形容がぴったりの政治形態の中にこそ、キリスト教の存在意義があると本書を読んで思わされた。
次回は後編として、具体的に宗教改革以降の政治思想について考えていきたい。(続く)
田上雅徳著『入門講義 キリスト教と政治』(2015年、慶應義塾大学出版会)
◇