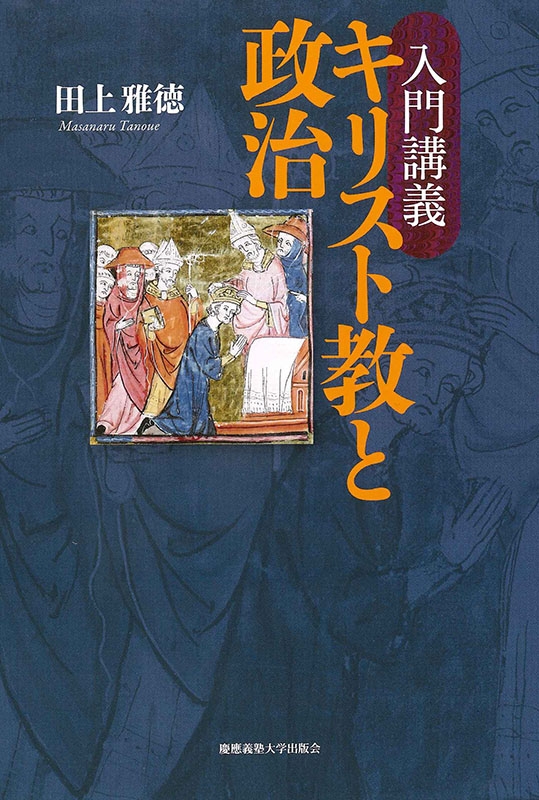キリスト教と政治という、一見すると水と油のようなものが、実はコインの裏表であったことに気付かせてくれるのが本書である。その後編として、宗教改革以降のキリスト教と政治の在り方を本書に沿って紹介してみたい。
ルターの宗教改革の「宗教の非政治化」は同時に、政治を宗教の拘束から解き放った
宗教改革というと、プロテスタントの始まりということになり、とかく神格化されやすい。本書第9章では、ルターの実像と、彼を周囲の人々がどう受け止めていったかの切り分けがきちんと行われている。そして両者に共通し、歴史を大きく突き動かしていく要素として「聖書主義」と「信仰義認」を取り上げている。
ルターと聞いて上記の2つを思い浮かべることは、私たちにはできる。世界史の授業で習ったり少し専門的な書物を読むなら、それについての解説は必ず書かれているだろう。しかし、それが欧州社会をどのように導き、その結果、どんな政治的形態を生み出していったかについて、ここまで深く切り込んだ解説を聞く機会はなかったように思う。それは、本書164~165ページにクライマックスを迎える。
「考えてみるとルターという人は、福音主義という理念を掲げつつ、『宗教の非政治化』を目指そうとした、といえる。(中略)けれども、ここでの『宗教の非政治化』は『政治の非宗教化』を伴っていた。すなわち、16世紀にあって宗教家が『既存の世俗的な政治秩序に私は口出ししない』と宣言するとき、政治権力は、宗教が説く規範の拘束から脱するチャンスを得たのである」
ルターを神格化したり超人間的な存在に置くなら、宗教改革はプロテスタントにとって輝かしい出来事以外の何物でもないことになる。しかし現世に生きる人々の営みを「政治」というある種冷徹な観点から見るなら、ルターの行状は結果的に政治権力を宗教的な拘束から解放し、自らの欲望のままに生きる道を開いたことになってしまう、と著者は述べているのである。ここに、宗教的熱狂によって歴史をゆがめてしまう愚を犯すことなく、アカデミズムに立脚し続ける論考を見て取ることができる。
10章から12章までは、ルターが切り開いたプロテスタント的世界観をどのように受け止めてきたかを、欧州中心に描いている。このあたりも、世界史のマッチング問題で苦闘したような単語の結び合わせではなく、ルターの主張を後の人々が検証し、その中のどこを強調して受け止めてきたのか、逆に反論したり反動形成を生み出してきたか、について述べられている。
このあたりから、政治的な概念が次第に神学的なそれと結び合わされて、若干内向的(哲学的)に振れているように思われる。それは著者の叙述傾向というよりも、むしろ欧州での新神学(リベラル神学)の特質がこのような内向的なもの(あるいは宗教が「心の中の問題」になった)故であろう。神学的専門用語が随所にちりばめられているため、初心者には少々骨が折れる箇所である。しかし何度も読み返すことで、歴史の表舞台を動かしてきた人々の内面の動機づけを知ることができるため、とても有用であることは変わりない。
理念によって国家は建設できるのか?という壮大な問いとしての米国
この雰囲気が、13章からはかなりアクティブなものになっていく。ピューリタンたちが新天地を求めて米国へ渡るくだりである。ここで、理念によって国家は建設できるのか、という壮大な実験に彼らは挑むことになる。そして再び、「共同体」という概念が呼び起こされることになる。
これは、本書が旧約聖書の中の政治形態に言及したときに取り上げた概念である。これが17世紀に再び取り上げられることで、米国という国家がいかに宗教色強いものであるか、さらにそのような国家の中で、いかにして政治は発展することになるのかが、第14章のテーマとなっている。
著者が米国におけるキリスト教と政治の在り方を論じることで、本書を閉じたのはなぜであろうか? それは単に世界の最先端に米国が位置しているという意味ではない。実は米国こそ、宗教的な理念と世俗的な現実との相克(そうこく)をはっきりと示してきた国は他に類を見ないからである。本書の最後はこんな言葉で締めくくられている。
「本書が取り扱ってきたキリスト教は二千年におよぶ歴史を持つ。そしてこの宗教がかくも長き時間にわたって命脈を保ちえたのは、それが、特にその聖典(聖書)が特定の政治的立場に回収されない豊かで深みのある教説を保持してきたからに他ならない。戦後アメリカの例にあったように、時代は時代ごとにこの宗教と聖書から、まさに当の時代が必要とするメッセージを取り出してきた」
そして冒頭に書いたように本書においては「政治的な事柄」として語られてきたことが、実は聖書をどのようにこの地上に実現するかという人間の営みであり、同時にどうやって聖書やキリスト教的な縛りから解放されて現実に適した指針を導き出せるかという、人々の葛藤のドラマだったと結論付けられている。
そういった意味で本書は、政治学のテキストであると同時に、まさに神学的なテキストと言うことができる。ちょうど車の両輪のように、一方に政治、一方にキリスト教(宗教)が位置付けられている。双方が並び立つことで、現実的な社会が動き始めるのである。
このような形態は、欧州や米国だけでなく、実はアジアにおいても十分機能している。言い換えるなら、このような研究方法は、キリスト教世界だけに留まらず、どんな宗教、どんな国家の政治的推移を考察するためにも援用可能なものであると言えよう。
秋の夜長、じっくりと1日1章ずつ読み進めていくことをお勧めする。そして各章のまとめや感想を書き留めていくことである。すると2週間(14章)の果てに、あなたが無意識に抱いていた世界観を自覚することができ、その環境で生きる私たちのアイデンティティーをあらためて認識することができるであろう。
田上雅徳著『入門講義 キリスト教と政治』(2015年、慶應義塾大学出版会)
◇