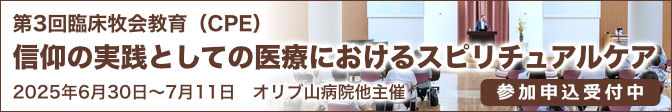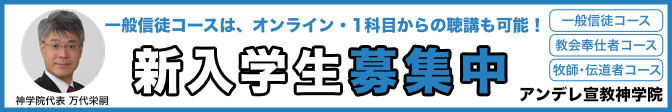本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。
―心を神に向ける―
「苦しみ」の原因は見える困難にあると、誰もが思い込んでいる。そのため、誰かが困難を生じさせ、そのことで「苦しみ」を覚えたなら、人は困難を生じさせた相手を憎み、その人さえいなければいいのにと考えてしまう。その考えが発展すると、最悪、殺人に至ってしまう。実際、イエスによって自分の評判が傷つくという困難が生じ、「苦しみ」を覚えた祭司長や律法学者たちは、イエスを殺そうと画策し、十字架刑で殺してしまった。
しかし、それは「苦しみ」に対しては、「的外れ」の解決だったので、イエスは彼らのために祈られた。「父よ。彼らをお赦(ゆる)しください。彼らは、何をしているのか自分でわからないのです」(ルカ23:34)。この出来事は、人が「苦しみ」の真の原因を知らないために、「的外れ」の解決にまい進してしまうことを物語っている。この「的外れ」のまい進が、人の「罪のありさま」なのである。
そこで、前回までの話では、「苦しみ」の原因がどこにあるのかを探ってきた。その結果、「苦しみ」の原因は、心を神に向けられないことにあることが分かった。なぜなら、人は神によって造られ、神を慕い求めるようになっているからである。「神よ、わたしの魂はあなたを求める」(詩篇42:2、新共同訳)。つまり、人は神に向かって進むように、「聖霊の風」に動かされているので、心を神に向けなければ「聖霊の風」に逆らうことになり、何をしても空しさを覚え、「苦しみ」を覚えてしまうのである。ただ見える困難に、その「苦しみ」が投影されるだけである。

ということは、「苦しみ」の正しい解決は、心を神に向けることにこそある。ならば、心を神に向けるとはどういうことなのか、今回はそれについて考えていく。その前に、人が「苦しみ」を覚える仕組みを簡単におさらいしておきたい。
「苦しみ」を覚える仕組み
神がぶどうの木であれば、人はその枝である。「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)。そのため、枝である人が「苦しみ」を覚えると、枝を支える木である神も、一緒になって「苦しみ」を覚える。
彼らが苦しむときには、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛とあわれみによって主は彼らを贖(あがな)い、昔からずっと、彼らを背負い、抱いて来られた。(イザヤ63:9)
では、人はいつ「苦しみ」を覚えるのか。それは先述したように、「聖霊の風」に逆らい、心を神に向けないときであり、それは神に逆らっている状態なので、それを「罪」という。つまり、人は「罪」に対して「苦しみ」を覚えるのである。ただし、心を神に向けないという「罪」の状態は、意識できない心の奥底での話なので、人は「苦しみ」を覚えても全く意識できない。ただ、心の奥底で、漠然とした「不安」を覚えるだけである。
そこで神であるキリストは、私たちが意識できない「苦しみ」を、すなわち私たちの「罪」をその身に負い、それを私たちに訴えてくださる。訴えることで、私たちが「罪」を離れ、心を神に向けられるように助けてくださる。
そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。(1ペテロ2:24)
この神からの訴えが「心の声」であり、それが見える困難と結び付くことで、人は「苦しみ」を意識できるようになる。すなわち、人が覚える「苦しみ」は、「心を神に向けよ!」と叫ぶ、神からの訴えなのである。
このように、人が「苦しみ」を覚えられるのは、心を神に向けられない「罪」の「苦しみ」を人が意識できないので、その「罪」をキリストが背負い、キリストの「苦しみ」として人に訴えてくださるからである。これが「心の声」であり、それが見える困難と結び付くことで、人は「苦しみ」を意識できるようになる。そうであれば、人の覚える「苦しみ」はキリストの覚える「苦しみ」であり、それはキリストによって賜ったということなのである。
あなたがたは、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。(ピリピ1:29)
賜った「苦しみ」のおかげで、人は心を神に向けることが可能になった。それで聖書に、「苦しみのうちから、私は主を呼び求めた」(詩篇118:5)とある。そして、心を神に向ければ、「苦しみ」は真に解決するので、この詩篇の続きに、「【主】は、私に答えて、私を広い所に置かれた」とある。こうして、心が神に向くことで、心のおおいとなっている「苦しみ」は取り除かれていく。
彼らの心にはおおい(苦しみ)が掛かっているのです。しかし、人が主に向くなら、そのおおい(苦しみ)は取り除かれるのです。(2コリント3:15、16)※( )は筆者が意味を補足
以上が、人が「苦しみ」を覚える仕組みの簡単なおさらいである。この仕組みが分かれば、「苦しみ」を覚えたならば、心を神に向ければいいことも見えてくる。「苦しみ」を覚える真の原因は、心を神に向けられないことにあるので、心を神に向ければ、「苦しみ」は解決する。ところが、ここに問題があった。何と、自力では、心を神に向けられないのである。ここからが、今回の新たな話となる。
心を神に向けられない
心を神に向けると、確かに「苦しみ」は解決する。ところが、入り込んだ「死」によって、人は心を神に向けられないのである。人は「死の恐怖」の奴隷となり(ヘブル2:15)、心を神に向けたくても向けられない中にある。それは、何が良いことで悪いことかが分かっていても、良いことの方にハンドルを切ることができないということである。
私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています。(ローマ7:19)
それはまるで、神の方に向かって歩きたくても、目の前に壁が立ちはだかり、前には進めないようなものである。実際、神の方に向かって歩き出すと、神と人とを分離する「隔ての壁」(エペソ2:14)があり、神に近づくことが全くできない。この「隔ての壁」の正体が、入り込んだ「死」である。
聖書によれば、アダムの罪に伴い「死」が入り込み、その「死」がすべての人に及んだという。「一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)。入り込んだ「死」とは、この世界を見れば分かるように、それは人を滅ぼす「有限性」であり、この世界のすべてが「有限性」になったということである。「有限性」は、「永遠性」の神を完全に遮ってしまうので、これでは心を神に向けることも、神に近づくこともできない。
つまり、神と人との間に「有限性」という「死の壁」が入り込んだことで、人はもう自力では、心を神に向けることが不可能になったということなのである。

そうなると、人が自由に歩き回れるのは、「死の壁」に囲まれた「この世界」だけということになる。このことは、「この世界」の中でしか、人は神を慕い求めることができないということを意味する。人は、「聖霊の風」によって神に向かって動かされているので、すなわち神の「いのち」である「魂」が神を慕い求めるので――「神よ、わたしの魂はあなたを求める」(詩篇42:2、新共同訳)――、人は神を慕い求めて生きているが、その神を「この世界」の中で探すしかないということである。では、「この世界」の何が神になるのだろう。
それは、神は完全なお方なので、「この世界」での理想(完全)が神になる。そこである人は、理想の芸術を神として慕い求める。ある人は理想の社会を、ある人は理想の容姿を、ある人は理想の自分を、神として慕い求める。そのことで、神を目指させる「聖霊の風」、すなわち「魂」の要請に応えようとする。しかし、これは紛れもなく「偶像礼拝」である。
このように、人は「死の壁」という「有限性」の世界に閉じ込められているので、「偶像礼拝」をするしかない。そこからでは、「永遠性」である神に近づくことも、「永遠性」の神を見ることもできないからである。これを、「死」の牢獄に閉じ込められているという。
そして、「有限性」でできている「死」の牢獄の「壁」の具現化が、人の価値を規定する「律法」である。神と人とを分断する「有限性」という「死」は、その姿を「律法」に変え、人を「律法」に閉じ込めている。そのせいで、人は心を神に向けることができない。
「律法」に閉じ込められている
アダムの罪に伴い「死」が入り込み、人は「死」の牢獄に閉じ込められてしまった。その結果、「有限性」の中の理想を神とするしかなく、偶像の神にしか心を向けられなくなった。心を真の神に、すなわち「永遠性」の神に向けられない状態になった。その状態が「罪」であり、その「罪」の力が、真の神が規定した人の価値を無視させ、偶像の神が定めた行いの規定の「律法」に、人の価値を託させてしまったのである。
つまり、「死」の牢獄の「壁」が、心を神に向けられない「罪」となり、その「罪」の力が、「律法」になったということである。聖書はそのことを、端的に教えている。
死のとげは罪であり、罪の力は律法です。(1コリント15:56)
確かに、誰もが「律法」に頼って生きている。「律法」の行いによって少しでも自分の価値を引き上げ、周りから良く思われようとして生きている。これは、誰もが「律法」の監督の下に置かれ、閉じ込められているということなので、聖書にはこうある。
私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていました。(ガラテヤ3:23)
これでは、「聖霊の風」に乗って、真の神に心を向け、真の神との距離を縮めることはできない。心が向くのは、偶像の神が規定する「律法」の行いであり、それによって自分が周りからどう思われるかである。まことに「律法」の下にある限り、人は神との距離を縮めることが全くできないのである。それは「絶望」でしかない。しかし、「絶望」の中にあっても、心を神に向けられる手段が一つだけある。それが、今回の話の結論になる。
心を神に向けられる手段が一つだけある
人は確かに、「律法」の下にあり、「律法」の牢獄に閉じ込められている。そのため、いつも「律法」の行いに目が向き、どうすれば自分が良く思われるかと考えてしまう。神のことよりも、人のことを思ってしまい、心を神に向けられない中にある。それは、あのペテロも同じだったので、イエスはペテロに、「あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている」(マタイ 16:23)と言われたのである。この状態は、心を神に向けようとする者にしてみれば「絶望」でしかない。この「絶望」を、パウロ自身も次のように告白している。
私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから(「律法」の牢獄から)、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)※( )は筆者が意味を補足
しかし、心を神に向けられない、「律法」の牢獄という「絶望」の中にあっても、神に対してできることが一つだけある。それは、神に助けを求めて叫ぶことである。絶対に出られない「律法」の牢獄の中にあっても、神に叫ぶことはできる。
というより、どうにもならない「絶望」の中にいる自分に気付けば、神に助けを叫ぶようになる。どうにもならない「罪」の「苦しみ」に気付けば、すなわちキリストによって賜った「苦しみ」から目を背けるのではなく、それを真正面から見ることができたなら、あの取税人のように、神にあわれみを乞うことができる。
神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。(ルカ18:13)
これこそが、心を神に向けることなのである。あの取税人の心は、神に叫んだ瞬間、もう神を向いていた。そこでイエスは、神に叫んだ取税人に対し、「あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:14)と言われたのであった。
つまり、キリストによって賜った「苦しみ」から目を背けず、真に「絶望」する勇気を持つことができれば、あの取税人のように、心から神にあわれみを乞うことができるのである。それこそが、心を神に向けることである。
このように、「死」の牢獄の中にあって「律法」の監督の下に置かれていても、心を神に向けられる手段が一つだけある。それは「絶望」の中にいる自分に気付き、神にあわれみを乞うことである。具体的には、自分の「苦しみ」を神の前で言い表すことであり、それはそのまま、神の前で自分の罪を言い表すことを意味する。
罪を言い表す
神にあわれみを乞うことができるのは、キリストによって賜った「苦しみ」があるからである。その「苦しみ」は、人が意識できない罪の「苦しみ」をキリストが負い、それを人に訴えてくださるからである。この神の訴えが見える困難と結び付くことで、人は「苦しみ」を覚えることができる。従って、罪の意識化が「苦しみ」であり、その意識化をさせてくださるのがキリストだということである。
いずれにせよ、人が覚える「苦しみ」は、本人には自覚がなくても、自分の「罪」に対する「苦しみ」なのである。そのため、覚えた「苦しみ」を神の前で言い表せば、それは自分の罪を神の前で言い表していることになる。この言い表しこそ、神にあわれみを乞うということであって、心を神に向けるということの実際になる。すると、神は真実で正しい方なので、その罪を赦してくださる。ここに、「苦しみ」を解決する神の福音がある。
もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(1ヨハネ1:9)
このように、心を神に向けるというのは、自分の「苦しみ」を言い表すことであり、それは自分の罪を言い表すことを意味する。そうすれば、罪が赦される。それこそが、「苦しみ」の真の解決であって、「苦しみ」の解決は、見える困難の解決にあるのでは決してない。
まことに「苦しみ」の真の解決は、心を神に向けることにある。とはいえ、それは自力では不可能なので、人はキリストによって「苦しみ」を賜ったのである。そのおかげで「絶望」することが可能になり、心から神の助けを乞うことができる。それが、神の目には人が心を神に向けるということであり、心を神に向ければ、神はその人を引き寄せてくださる。つまり、神によって引き寄せられない限り、誰も神に近づくことはできないということである。
父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。(ヨハネ6:44)
神が人を引き寄せてくれることが、罪が赦されるということなのである。ここにこそ、「苦しみ」の真の解決がある。では、神が人を引き寄せてくださるということを、次回は具体的に見ていきたい。(続く)
◇