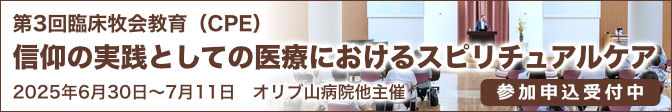キリスト教の隣人愛を理念に掲げる社会福祉法人賛育会は3月31日、親が育てられない子どもを匿名で預かる「赤ちゃんポスト」と、病院にのみ身元を明かして出産する「内密出産」を、運営する賛育会病院(東京都墨田区)で開始したと発表した。いずれも医療機関としては東京では初めてで、国内でも同じくキリスト教系の慈恵病院(熊本市)に続き2例目となる。
開設された専用のウェブサイトによると、赤ちゃんポストは「ベビーバスケット」の名称で運用し、生後4週間以内の新生児を対象とする。病院1階に設けられた専用の部屋で、24時間体制で受け入れる。手紙や記念品も一緒に預けることができ、子どもは病院のスタッフが健康状態を確認した後に保護する。
内密出産は、個人情報を病院の一部スタッフにだけ明かせば、入院期間中は匿名で過ごし、出産ができる。相談は電話(03・3622・1651、平日午前9時~午後4時)で受け付ける。内密出産については、法務省などが2022年にガイドラインを発表しており、それに沿って対応するという。
31日には、東京都庁で記者会見を開き、概要を説明した。会見内容を伝える読売新聞の報道によると、赤ちゃんポストに子どもが預けられると、病院は児童相談所(児相)と警察に連絡し、児相が乳児院などにつなぐ。病院がある墨田区が戸籍を作成し、子どもの名前は区長が命名する場合もある。内密出産についても、子どもは児相が保護する。出産費用については原則、母親側に負担を求めるが、相談に応じるという。
赤ちゃんポストと内密出産は、「赤ちゃんの命を守るプロジェクト」として始める。プロジェクトに関する賛育会の発表によると、約5年をかけ、各所の見学や検討を重ね、行政にも相談しながら準備を進めてきた。
賛育会病院は既に、複雑な事情・背景のある妊婦や、外国籍の妊婦を含めた一定数の飛び込み出産、出産前から支援が必要とされる特定妊婦などを受け入れており、赤ちゃんポストと内密出産は「これまでの病院の働きの延長上にあるもの」と説明。さまざまな課題やリスクを伴うものの、「将来、このような取り組みが必要のない社会になることを願って、赤ちゃんのいのちを守る最後の砦(とりで)」として始めるとしている。
賛育会は、東京大学学生キリスト教青年会(東大YMCA)の有志が1918年、キリスト教の隣人愛に基づいた⺟⼦の保護・保健・医療を⽬的として設立。現在は賛育会病院のほか、東京、長野、静岡の3都県で、複数の病院や高齢者福祉施設、保育園などを運営している。
賛育会病院は、助産師の分娩支援による自宅出産が一般的だった当時、国内初の一般市民向け産院として誕生した。現在は新生児集中治療室(NICU)を併設した周産期医療を担う専門施設「東京都地域周産期母子医療センター」に認定されており、墨田・江東・江戸川区エリアでは、年間分娩件数が最も多い病院となっている。
赤ちゃんポストと内密出産の準備を進めていることは、2023年に明らかになっていた。昨年7月には、夜間の匿名相談「妊娠したかもSOS賛育会」も始めている。
赤ちゃんポストは07年、慈恵病院が「こうのとりのゆりかご」の名称で、国内で初めて運用を開始。24年3月末までに179人の子どもが預けられた。また、19年に始めた内密出産では、21年12月の初事例以来、3年間で約40人が生まれている。
NHKによると、慈恵病院の蓮田健院長は31日に記者会見を開き、東京で赤ちゃんポストと内密出産が始まることは、「喜ばしいことで私の悲願でもあった」と歓迎した。一方、内密出産の費用を母親側に求める方針については、「失望した。孤立した女性はほとんどがお金を持っておらずあまりにも非現実的だ」と批判し、懸念も表明した。