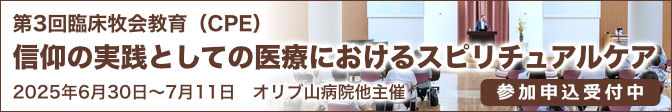本文での聖書の引用は新改訳聖書第三版を使用し、そうでない場合は、その都度聖書訳名を表記する。ただし、聖書箇所の表記は、新改訳聖書第三版の表記を基に独自の「略語」を用いる。
前回までのおさらい
人は神によって造られた。神を愛し、神を目指して生きるように造られた。「神よ、わたしの魂はあなたを求める」(詩篇42:2、新共同訳)。つまり、人は神に向かって進むように、「聖霊の風」に動かされているということである。そのため、「聖霊の風」に逆らって神ではない方向に進むと、何をしても空しさを覚え、「苦しみ」を覚える。それは、神にあらかじめ定められていたゴールからは「的が外れている」状態である。
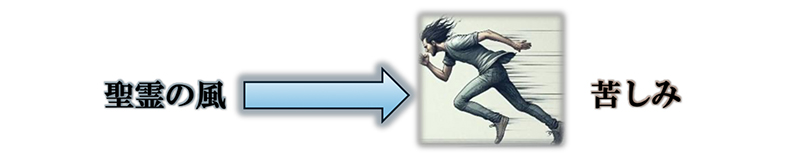
この「的が外れている」状態を、すなわち心が神に向いていない状態を、聖書は「罪」と呼ぶ。この「罪」の状態に、人は「苦しみ」を覚える。しかし、心が神に向いていないこの「罪」の状態は、心の奥底での話なので、その「苦しみ」を、人は意識することができない。ただ、漠然とした「不安」を覚えるだけである。
そこで神は、人が意識できない「苦しみ」、すなわち「罪」を自らが負い、――「私たちの罪をその身に負われました」(1ペテロ2:24)――、その「苦しみ」を人に訴えてくださる。これを、「心の声」という。その「心の声」は、この世界で人が遭遇する困難と結び付き、意識できる「苦しみ」となる。
例えば、友達から悪口を言われ、友達との関係に困難を覚えると、その困難に「心の声」が結び付いて、人は「苦しみ」を覚える。それで、自分を苦しめたのは悪口を言った友達だと思い、友達を裁いてしまう。裁くことで、「苦しみ」から開放されると思ってしまう。
しかし、「苦しみ」の原因は悪口を言った友達にあるのではない。友達は、心が神に向いていなかったことを気付かせてくれたに過ぎない。にもかかわらず、友達を裁くことで「苦しみ」から開放されようとする。当然それは誤った対処なので、「人を裁くな」(マタイ7:1、新共同訳)とイエスは言われた。
ならば、「苦しみ」を覚えたときの正しい対処は何なのか。それは、心を神に向けることである。ところが、この世界は滅びに向かう「死」に支配されている。滅びに向かう性質を「有限性」というが、人が暮らしている所は「有限性」の世界である。それに対し、目指す神は「死」に支配されない方であり、神のおられる所は「永遠性」の世界である。そのため、人が暮らす「有限性」の世界からは、「永遠性」の神を見ることも、神に近づくこともできない。「聖霊の風」に逆らわずに神を目指しても、「有限性」という「死の壁」がそれを遮ってしまうのである。
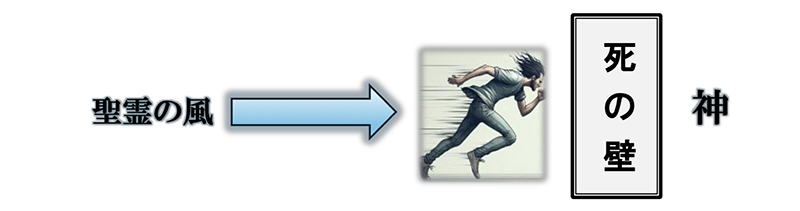
ならば、人は心を神に向けることを諦めるしかないのだろうか。いや、一つだけ心を神に向ける手段がある。それは、神に助けを求め、神に叫ぶことである。「絶望」の中にいる自分に気付き、あの取税人のように、神にあわれみを乞うのである。
神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。(ルカ18:13)
これこそが、心を神に向けることである。人の側からでは、神に近づくことはできないが、神に叫ぶことならできる。たとえ神が見えなくても、たとえ神に近づくことができなくても、神に叫ぶとき、人は心を神に向けている。すると何と、神が人を引き寄せてくださるのである。これを、「義」とされるという。そこでイエスは、神にあわれみを求めた取税人に対し、その者は「義」とされたと言われたのであった。「あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:14)
ここに「苦しみ」の解決がある。それは、神にあわれみを乞うことである。そうすれば、神が人を引き寄せてくださるからである。すると、人は神に向かって動き出すので、「的が外れている」状態は是正され、「苦しみ」は解決する。これを、「罪」が赦(ゆる)されるという。
このように、神にあわれみを乞えば、神が人を引き寄せてくださるので、「苦しみ」は解決する。大事なのは、神が人を引き寄せてくれない限り、誰も自力では、神に近づくことはできないということである。
父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません。(ヨハネ6:44)
それはつまり、人の「苦しみ」である重荷は、自力では解決できないということである。神にしか、人の重荷は解決できない。それでイエスは「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)と言われたのである。
以上が、前回までの簡単なおさらいである。そこで今回は、神が人を引き寄せてくださるということの中身を掘り下げてみたい。
神が人を引き寄せてくださる
人を支え動かしているのは神の「いのち」であり、その「いのち」は神を目的地に定め、そこに向かって人を動かしている。人は神の「いのち」に動かされ、神を目指して生きている。「神を、生ける神を求めて渇いています」(詩篇42:2)。しかし、「有限性」という「死の壁」が人の前に立ちはだかり、誰も「永遠性」の神のもとに行くことができない。「有限性」は終わりを目指して変化し続けるので、終わりのない、全く変化しない「永遠性」には近づけないのである。
では、どうすれば「死の壁」を越え、神を目指すことができるのだろう。それには、神にあわれみを乞うしかない。神にあわれみを乞えば、神が人を「永遠性」である神のもとに引き寄せてくださる。
ただし、その神がおられる「永遠性」の世界は、何と自分の中にある。例えるなら、自分の中に、「神の国」の大使館があるということである。その大使館から、神は私たちを引き寄せてくださる。それ故、目指すべき場所は自分の中にある。
では、なぜそう言えるのか。それは人を支え動かしている人の土台が、神の「いのち」だからである。神は大地の塵(ちり)で人の「体」を造り、そこに神の「いのち」の「息」を吹き込まれ――「いのちの息を吹き込まれた」(創世記2:7)――、その神の「いのち」が人を生かす土台となり、人は生きる者となったので、目指すべき場所は自分の中にある。そして、その土台の神の「いのち」の「息」が、「神の国」の大使館であり、言い換えるなら「神の神殿」であり、それが私たちの中にある。
あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。(1コリント3:16)
従って、神が人を神のもとに引き寄せてくださるというのは、神が私たちの中にある「神の神殿」に引き寄せ、神との交わりを再開されるということである。ということは、人は初めから神に支えられ、愛されていた者であって、それが人の「真実な姿」である。人は、初めから神と一つ屋根の下で、神に愛されながら暮らしている者なのである。
ところが、入り込んだ「死」のせいで――「罪によって死が入り」(ローマ5:12)――、目があっても、一緒に暮らす神が見えなくなり、耳があっても、神からの生の声が聞こえなくなり――「目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか」(マルコ8:18)――、一緒にいる神に気付けなくなった。これが、「苦しみ」の原点である。
そこで、神が人を引き寄せ、一緒におられる神に気付かせてくださるのである。神は人の土台に「神の神殿」を据え、それを「神の国」の大使館とされたので、例えるなら、神がぶどうの木であれば、人はその枝なので――「わたしはぶどうの木で、あなたがたは枝です」(ヨハネ15:5)――、枝である人に呼びかけ、人を引き寄せようとされる。
では、神が人を引き寄せる様子を時系列で見てみよう。最初は、人が神に引き寄せられ、神と和解するまでの話である。
神と和解する
人の「体」にがんができても、初期の段階では何も気付かない。しかし、それを放置すれば、人は死んでしまう。同様に、心が神に向いていないことで生じる「苦しみ」も、気付かないからと放置すれば、神との和解がないので、その人は肉体の死と同時に滅んでしまう。
どういうことかというと、「体」は塵で造られたので、肉体の死と同時に「体」は元の大地に帰り、その「体」に吹き込まれていた「いのちの息」(創世記2:7)の「息」は、神から貸し出されていたものなので、神に帰るということである。それは、「神の国」の大使館が閉鎖されるということである。
塵は元の大地に帰り、息はこれを与えた神に帰る。(コヘレトの言葉12:7、聖書協会共同訳 ※「コヘレトの言葉」は、新改訳聖書では「伝道者の書」のこと)
そうなると、その人はもう「神の国」には入れないので、滅びるしかない。これこそ、人を支えてきた神にとっては最大の「苦しみ」となる。そこで神は、人が気付いていない「苦しみ」をご自分の「苦しみ」として負い、人にその「苦しみ」を訴える。それができるのは、人が神のからだの部分だからである――「私たちはキリストのからだの部分」(エペソ5:30)――。
神が「苦しみ」を人に訴えると、それが人の遭遇する困難に投影され、人はようやく「苦しみ」を意識できるようになる。その「苦しみ」こそ、「わたしのもとに来なさい」という、神からの呼びかけであり、神が人に差し出された御手である。これを、「心の声」という。
このように、人が覚える「苦しみ」の裏側では、神が人に呼びかけてくださっている。人は困難に遭遇するたびに、その裏で「心の声」を、すなわち神の呼びかけを聞いているのである。それは、「潜在意識」で聞いている。意識というのは、意識できない「潜在意識」と、意識できる「顕在意識」とに分かれていて、「顕在意識」を支えているのが「潜在意識」であるが、誰もがその「潜在意識」の中で、困難に遭遇するたびに、神の呼びかけを聞いている。
しかし人は「苦しみ」を意識しても何かで紛らわし、「苦しみ」の裏にある神の呼びかけを無視してしまう。すると神の呼びかけはますます強くなり、やがて人は耐えられない「苦しみ」に遭遇し、「絶望」に追い込まれる。その時、神の呼びかけに応答し、差し出された御手につかまれば、人は神に引き寄せられるのである。その応答が、神にあわれみを乞うということである。
差し出された御手につかまり、神に引き寄せられれば、人は神と和解でき、「死」から「いのち」に移される――「死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24)――。それは、入り込んだ「死」によって死んでいた者が――「アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)――生きる者になるということである。イエスはこの出来事を、「死人」が神の声を聞くなら、生きる者になると言われた。
まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。(ヨハネ5:25)
聖書は、イエスが言われたこの時系列の流れを、「人は心に信じて義と認められ」(ローマ10:10)ともつづっている。「潜在意識」の中で神の声を聞き、神にあわれみを乞う選択をすることを「信仰」というが、それは「潜在意識」の「心の中」で行われるので、「心に信じて」という。また、「死」から「いのち」に移されることを、「永遠のいのち」が与えられるといい、「義」と認められるという。
見てきたように、人は「潜在意識」の中で、神とやりとりをしている。そのやりとりで、神の呼びかけに応答できれば(心に信じれば)、その人は神と和解することができる。これを「救い」という。それは「死」から「いのち」に移され、「永遠のいのち」を持つようになることである。しかし、この出来事は「潜在意識」での話なので、「永遠のいのち」が与えられても本人には意識がない。意識がなくても、この時点で人は義とされる神の救いにあずかっている。
さて、神が人を引き寄せる話は、これでおしまいではない。神と人との間は無限に遠く、この時点での人は、神と和解し、無限に遠い神に向かうレールに乗せられたに過ぎない。そこから、さらに神に引き寄せてもらうことができる。それは、さらに神に引き寄せられ、神から友と呼ばれるようになるまでの話である。
神から友と呼ばれる
神と和解し、「永遠のいのち」が与えられても、人は肉体の死までは「有限性」の世界で暮らすので、再び心は神ではなく見える安心に向くようになり、再び「苦しみ」に襲われるようになる。だがその「苦しみ」も、人にはやはり意識できない。そこで神は、再び人の「苦しみ」を負い、それを続けて人に訴える。その訴えが再び「心の声」となって意識できる困難と結び付くので、人は意識できる「苦しみ」に襲われ、「絶望」に追い込まれる。
その際、再び神にあわれみを乞う「信仰」の選択ができれば、神に引き寄せられるので、以前よりも神との距離は縮まっていく。これを繰り返す中で、キリストについての御言葉を聞くと、キリストへの信仰を持つようになる。「信仰は聞くことから始まり、聞くことは、キリストについてのみことばによるのです」(ローマ10:7)。こうして、与えられた「永遠のいのち」は、イエス・キリストを知る信仰となって具現化する。それでイエスは、次のように祈られたのである。
その永遠のいのちとは、彼らが唯一のまことの神であるあなたと、あなたの遣わされたイエス・キリストとを知ることです。(ヨハネ17:3)
ここでイエスは、イエス・キリストを信じられるのは「永遠のいのち」が与えられたからであることを証ししておられる。つまり、イエスが約束の救い主「キリスト」だと信じられたのは、神が与えた「永遠のいのち」を介し、神が示してくださったということである。イエスはそのことを、次のやりとりでも教えておられる。
シモン・ペテロが答えて言った。「あなたは、生ける神の御子キリストです。」するとイエスは、彼に答えて言われた。「バルヨナ・シモン。あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいますわたしの父です。」(マタイ16:16、17)
ということは、イエス・キリストを信じている者は、もう「永遠のいのち」を持っていて、その者は「死」から「いのち」に移されているということになる。これは大変重要なことなので、イエスは、「まことに、まことに」と、強調して教えられた。
まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて、わたしを遣わした方を信じる者は(信じている者は:原文は現在形)、永遠のいのちを持ち(永遠のいのちを持っていて:原文は現在形)、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです(死からいのちに移された状態にある:原文は現在完了形)。(ヨハネ5:24) ※( )は筆者が意味を補足
さらにイエスは、「まことに、まことに、あなたがたに言います。信じている者は、永遠のいのちを持っています」(ヨハネ6:47、私訳)とも言われた。イエスの弟子のヨハネも、「私が神の御子の名を信じているあなたがたに対してこれらのことを書いたのは、あなたがたが永遠のいのちを持っていることを、あなたがたによくわからせるためです」(1ヨハネ5:13)と、強く訴えている。
神との距離が縮まることで、「永遠のいのち」を持っているというこの事実を、人は心から信じられるようになっていく。神との距離が縮まる過程は、「苦しみ」を覚えるたびに、神にあわれみを乞うことなので、それは言ってみれば、多くの罪に気付き、多く赦されるということである。それを経験することで神を多く愛せるようになり、神の言葉も多く信頼できるようになり、「永遠のいのち」を持っているという神の言葉も信じられるようになる。イエスは、このようにして神との距離が縮まるその原理を、次のように言われたのである。
だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。(ルカ7:47、新共同訳)
こうして、人は多くの罪を赦されることで、すなわち神に多く引き寄せられることで、イエス・キリストとの関係が築かれていき、友と呼ばれるようになる――「わたしはあなたがたを友と呼ぶ」(ヨハネ15:15、新共同訳)――。
このように、人が神と和解した後は、神から友と呼ばれる関係にまで、神は人を引き寄せてくださる――「彼は神の友と呼ばれたのです」(ヤコブ2:23)――。言い換えるなら、それは、神が人を「死」から「いのち」に移し、「永遠のいのち」を得させ、得させた「永遠のいのち」を豊かに持てるようにするということである。それでイエスは、こう言われたのである。
わたしが来たのは、羊がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。(ヨハネ10:10)
「永遠のいのち」を豊かに持てるようにするというのは、「永遠のいのち」を持っていることを信じられるようにする、ということである。
まことに神の願いは、人を神のもとに引き寄せることで、神と和解させ、「永遠のいのち」を得させ、さらに人を神のもとに引き寄せることで、「永遠のいのち」を持っているという事実を、人が心から信じられるようにすることなのである。なぜなら、どのような「苦しみ」も、そして「苦しみ」を持ち込んだ「死」も、「永遠のいのち」の前では「無」となってしまうからである。ここにこそ、「苦しみ」の真の解決がある。
以上が、神が人を引き寄せる様子を時系列で見た話である。だが、話はこれでおしまいではない。神が人を引き寄せることの中身を、さらに掘り下げて説明する必要がある。それは、神に引き寄せられれば引き寄せられるほど、実は「苦しみ」が減るどころか、増し加わるという話である。どういうことなのかを続けて説明したい。(後半へ続く)
◇