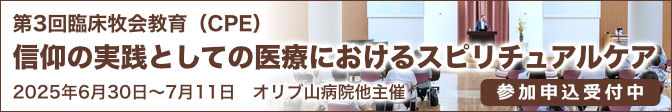直線的世界観と円環的世界観
コヘレトの言葉は、インクルージオ(囲い込み)という修辞法が使われていて、冒頭と末尾が対になっています。ですから、冒頭に合わせて末尾も見ておくことが、読み始める際には大切だと思います。この書の最後は、「神は善であれ悪であれ、あらゆる隠されたことについて、すべての業を裁かれる」(12章14節)として閉じられています。
これはとても大切なことで、そこには「最終的には全て神が裁かれる」というヘブライニズムの考え方が示されているのです。「歴史は神が支配しており、最終的な目的は神なのだ」という直線的な世界観だということです。しかし、当時イスラエルに浸透していたヘレニズム的な世界観は「円環的」であり、ヘブライニズムの世界観とは違っていました。1章3節からは、その円環的世界観が示されます。
「コヘレトの言葉の結論は直線的世界観である」ということを踏まえた上で、3節以下に示されている円環的世界観を読んでいくことにしましょう。コヘレトの言葉は、円環的世界観で書き出され、それによって読者に「それは空なのか」という疑問を抱かせ、対峙したり融合したりしながら読者自身に内面的な問いかけを促しつつ、文が進められていきます。今回は、3~11節を読みましょう。
3 太陽の下、なされるあらゆる労苦は、人に何の益をもたらすのか。4 一代が過ぎ、また一代が興る。地はとこしえに変わらない。5 日は昇り、日は沈む。元の所に急ぎゆき、再び昇る。6 南へ向かい、北を巡り、巡り巡って風は吹く。風は巡り続けて、また帰りゆく。すべての川は海に注ぐが、海は満ちることがない。7 どの川も行くべき所へ向かい、絶えることなく流れゆく。
8 すべてのことが人を疲れさせる。語り尽くすことはできず、目は見ても飽き足らず、耳は聞いても満たされない。9 すでにあったことはこれからもあり、すでに行われたことはこれからも行われる。太陽の下、新しいことは何一つない。10 見よ、これこそは新しい、と言われることも、はるか昔、すでにあったことである。11 昔の人々が思い起こされることはない。後の世の人々も、さらに後の世の人々によって、思い起こされることはない。
ヘレニズム文化との融合
直線的であったイスラエルの世界観・歴史観に、「誕生していつかは死を迎え、しかし次の世代が繰り返されていく」という、人類の循環という円環的な歴史観が示されます(4節)。それを見守るのは大地ですが、大地もまた、天体と自然がそこを循環しているのです。
最初に、太陽の循環が挙げられています(5節)。太陽の運行については旧約聖書の他の箇所にも記述がありますが、コヘレトの言葉では、特にその動きが循環的に描写されています。ここには、コヘレトの言葉が書かれた時代のヘレニズム的背景において、ギリシャ思想の影響を受けた可能性が考えられます。イスラエルがギリシャ国家に支配される前の時代のヘブライニズムにおいては、太陽の動きは神の秩序として理解されていましたが、ギリシャ国家の支配を受けていたヘレニズム時代には、その動きの円環的な特徴が、より強調されるようになったと考えられます。
旧約聖書の偽典である「エチオピアエノク書」の72~82章は、「天文の書」とされていいます。天文の書は、ペルシア時代からヘレニズム時代に成立したとされています(『聖書外典偽典〈第4巻〉旧約偽典Ⅱ』164ページ)。この天文の書には、太陽や月や星の運行の行程が細かく記されています。
天文の書に含まれる72章17節には、「太陽はこの第6の門を通って西(の空)から姿を消し、東へ進んで第5の門から昇ること30朝に及び、ふたたび西のほうにある第5の門を通って西に没する」(同書240ページ)とあります。これらの記述は、ヘレニズム思想からのものでしょう。
コヘレトはこの書を知っていて、そこに記されているこのような太陽の運行を基にして、5節を書いているように私は感じました。コヘレトが伝える「太陽は地の回りを循環しているという概念」は、このような書を通じて、ヘレニズム思想から伝わったのでしょう。旧約聖書の神観やエノクなどの人名と、ヘレニズム思想が融合しているのが、このエチオピアエノク書なのだと思います。
コヘレトの言葉の1章6節は風の循環、7節は川の水の循環を伝えています。実は、風の循環はエチオピアエノク書76章(同書244~245ページ)で、川の水の循環は77章(同書246ページ)でも伝えられているのです。そして、4~7節で触れられている「地、日(火)、風(空気)、水」は、ギリシャ哲学における万物の4元素でもあります。こういったことからも、この個所がヘレニズム文化の影響を受けているといえるのではないかと思います。
日本古典文学における「儚い」

コヘレトは、これらの自然の営み全てが、人を「疲れさせる」と言います(8節)。コヘレトにとってこれらのことは、「空」だからなのです。新共同訳で「空しい」と訳されていた語が、聖書協会共同訳では、口語訳で用いられていた「空」に戻ったことを、前回お伝えしました。この語は、ヘベルまたはその複数形のハバリームです。
ここで、この語についてもう一度考えてみたいと思います。へベルは、創世記4章に登場するアベルと同じ綴りであることも前回お伝えしました。アベルの人生について考えてみましょう。彼はアダムとエバ夫婦の間に、カインの弟として生まれました。カインが土地を耕すようになったのに対し、アベルは羊飼いになりました。神である主の前に出たとき、カインは作物をささげましたが、アベルは肥えた羊の初子をささげました。
主はカインのささげた作物よりも、アベルのささげた羊に目を留められ、そして喜ばれたのです。アベルに対して嫉妬したカインは、彼を殺害してしまいます。その殺害されたアベル(הֶבֶל)の名が、へベル(הֶבֶל)と同じ綴りなのです。私は、アベルの人生こそがヘベルを最もよく具現していると考えています。
殺害されたアベルの人生は確かに「空」ですが、アベル自身は「カインにまさるいけにえを神に献(ささ)げ、それにより正しい者であると認められ」(ヘブライ人への手紙11章4節)た者であり、そこにおいて一筋の光が差している者でもあります。そのため、へベルもそのような光や救いのニュアンスを包含しているともいえるのではないかと思えるのです。
私は、「空、空しい、蒸気、虚(うつ)ろ、儚(はかな)い」といった意味のある、へベルという語を日本語に訳すのであれば、「儚い」が良いのではないかと考えています。この語は、日本古典文学にもよく出てきます。
日本古典文学の代表作品ともいえる『源氏物語』において、主人公の光源氏の妻である紫の上が、「おくと見るほどぞはかなきともすれば風に乱るる萩(はぎ)の上露(うえつゆ)」という歌を詠んだことが伝えられています(岸本久美子著『源氏物語花筐 紫式部の歳時記を編む』35~36ページ)。
この歌は、萩の葉の上にある露が風に乱れる様子を、紫の上が自身の命に重ね合わせ、「儚さ」を象徴的に表現しているといえましょう。儚くとも、その儚さの中に、一輪の萩の花を取り巻く情景の美しさが感じられます。儚いという語は、そのようなニュアンスを持ち合わせた言葉だと思うのです。アベルの人生もそのように表現することができるでしょう。ですから私は、へベルに儚いという訳語をつけたいのです。
また日本古典文学の中には、「つれづれなるままに」というしんみりした書き出しで始まる『徒然草』や、「ただ春の夜の夢の如(ごと)し」と語られる『平家物語』など、儚さを伝えている作品が多くあります。そのため、こうしたニュアンスになじんでいる日本人が、コヘレトの言葉を読むにあたっては、「儚い」という訳語がふさわしいのではないかと考えているのです。
コヘレトの言葉を読み進めていきますと、死について語られている部分があります。死は確かに厳しい現実ですが、アベルの生涯や、紫の上の詠んだ歌に思いをはせるならば、命の儚さという観点で捉えることができるのではないでしょうか。人の死には厳しさやつらさがありますが、そこから与えられるものもあるということを、コヘレトは伝えているのであり、そういったことを読み取っていきたいと思います。
循環的な時間観
9~11節では、循環的な時間観が示されています。これは、「すべての業を裁かれる」(12章14節)神の支配の下に時間があるとする、ヘブライズムの直線的な時間観とは相反するものです。ヘレニズム時代のイスラエルに生きるコヘレトが、このことをどのように受け止めていたのかは、興味深いことです。コヘレトは、「時の賛歌」といわれる3章1~17節において、自身の時間論を展開していますので、そこを読む際に、この1章9~11節を重ねて読んでみたいと思います。(続く)
◇