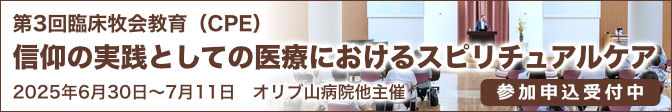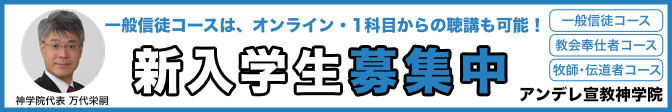善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや。
前回は、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』が、他国から伝わって来たという内容でしたが、今回は、親鸞聖人の言葉とされている『歎異抄』の「悪人正機説」について考察したいと思います。これは、浄土真宗の真髄とされる教えですが、これも親鸞聖人がゼロから考え出したものではないことが分かっています。
浄土真宗本願寺第三世覚如が、これは「元は法然上人の教えである」と言及していますし、法然上人が示唆を受けた人物として、7世紀の新羅の華厳宗の学者であり、「易行道」の先駆者である元暁(がんぎょう)にまでさかのぼって考える必要があります。
ここで、ご存じの方も多いと思いますが、悪人正機説の内容について少し深堀りしてみましょう。まずは『歎異抄』第3章の内容を現代的に訳すると、以下のようになります。
自分の力で善行を積む人(善人)は、他力を頼む心が足りないため、弥陀仏の本願から遠ざかっています。逆に、自分の努力だけでは難しいと悟り、他力を頼って弥陀仏に祈り、その本願に従うならば、真実の極楽浄土への往生がかなうのです。悩みや欲望に満ちた私たち(悪人)は、どんなに善行を積もうとも生死を超えることは難しいでしょう。しかし、慈悲深い弥陀仏は、悪人が真心で願い求めるならば、その願いをかなえてくれるのです。ですから、悪人であっても、他力を信じて祈り求めることにより往生することができるのです。ですから、自ら善人であると思っている人ですら往生できると主張するのであれば、むしろ悪人だと自覚して他力を信じて祈り求める人が往生できるのは言うまでもないことなのです。
医者を必要とするのは丈夫な者ではなく
私は幼い頃から聖書を何度も読んでいたので、初めて「悪人正機説」を聞いたときに、聖書の内容と酷似しているということに戸惑いを覚えました。仏教とキリスト教の間に、何かつながりがあるとは考えたこともありませんでしたので、とても驚いたのです。
しかし、内容を精査すればするほど、歎異抄と聖書の間に非常に共鳴する主題があることに気が付きました。まずキリストは、元暁よりも600年以上前に、このように語られました。
イエスはこれを聞いて言われた、「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。わたしがきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」。(マルコの福音書2章17節)
ここでいう「正しい人」というのは、自力で善人になろうとしている人のことです。キリストは、自らを正しい人と自認していた律法学者やパリサイ人たちを、人一倍厳しく糾弾されました。そして、自ら義人となり得ないことに気付き、自分の罪を告白して神に頼る者たちを喜んで招いてくださると教えられたのです。また、キリストの愛弟子であるヨハネも、このように語っています。
もし、罪がないと言うなら、それは自分を欺くことであって、真理はわたしたちのうちにない。もし、わたしたちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しいかたであるから、その罪をゆるし、すべての不義からわたしたちをきよめて下さる。もし、罪を犯したことがないと言うなら、それは神を偽り者とするのであって、神の言はわたしたちのうちにない。(ヨハネの手紙第一1章8〜10節)
それだけではなく、キリストよりもさらに600年も前に、エゼキエルという預言者はこのように語っています。
あなたは彼らに言え、主なる神は言われる、わたしは生きている。わたしは悪人の死を喜ばない。むしろ悪人が、その道を離れて生きるのを喜ぶ。(エゼキエル書33章11節)
つまり、旧約の時代から新約時代に至るまで、聖書は「悪人正機説」と同質の内容を教えているのです(もちろん、聖書の教えはこれだけではないですが)。それは「自らを善人(正しい)とする者ではなく、自らを悪人(罪人)だと自覚し、他力(超越者、神様)に頼る者こそが、往生できる(救われる)」というものです。
本願ぼこりへの言及
当時、「悪人正機」の意味を誤解し、阿彌陀仏の本願は絶対なので、どんなことをしても救われるのだから悪事を働こうではないかという「本願ぼこり」の心を持つ人々がいたそうです。これに対して、親鸞聖人は「薬あればとて、毒を好むべからず」と戒めたとのことです。
本願ぼこり:本願にあぐらをかく心のこと
「本願」= 阿弥陀仏が全ての衆生を救おうと誓った「本願」(四十八願)
「ぼこり」= 古語「誇り」から来た語で、うぬぼれ・慢心の意
そして実は、この点もまた聖書と酷似しているのです。初代教会の創始者ともいわれる使徒パウロが、ローマ人たちに宛てた手紙の中で次のように書き送っています。
それでは、どうなのか。律法の下にではなく、恵みの下にあるからといって、わたしたちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。(ローマ人への手紙6章15節)
現代のキリスト教の極端なグループの中でも、恵みを強調するあまり、道徳的義務、悔い改め、聖化といった重要な要素を軽視してしまうことがあります。
このように「慈悲」や「恵み」を説くと、それにあぐらをかいてしまう人々がいて、そのことに対して警告を発しているという点でも両者は共通しているのです。
「悪人正機説」というのは、日本仏教において、とりわけ浄土真宗の真髄とされていますが、その教えと聖書との間に有機的なつながりがあることがお分かりいただけると思います。
その理由については、本書の後半部分で詳しく書かせていただきたいと思いますが、ここでいえることは、このような真理(まことのことわり)、もしくは普遍的な宗教性は、日本人であれ外国の人々であれ、時代を超えて、全ての人の心の琴線に触れ得るものであるということなのです。
さて、ここからは本書にはない部分を、少し加筆させていただきたいと思います。今日の箇所では、仏教とキリスト教の共通する部分にフォーカスしましたが、やはり差異もあります。それは、一言で言うなら、仏教は「慈悲」を説き、キリスト教は人格(ペルソナ)を有されている神の無条件で一方的な「愛」を宣言しているということです。
そしてキリスト者は、自分の罪を認めて、悔い改めつつも、神に無条件に一方的に愛された者として、神を愛し、隣人を愛するという魂の内なる願いを自分の心とし、神と一つ心とさせられていくのです。
以下、参考までに少し整理しておきました。
仏教の「慈悲(じひ)」
慈(maitrī)=「楽を与える」(光を照らす太陽のようなぬくもり)
サンスクリット語「maitrī」は「友情・親しみ・友愛・親愛なる思い」
意味:他者に “安楽” や “安心” を与えたいという心悲(karuṇā)=「苦を取り除く」(雨となって乾いた地を潤す心)
サンスクリット語「karuṇā」は、苦しみを見て「心が痛む」
苦しみを自分のことのように感じ、共有し、取り除いてあげたいという動き「無我」や「空」を前提にした、執着を離れた思い。つまり、「自分を捨てて他者の苦をなくす」という心の在り方。
キリスト教の「愛(アガペー)」
ギリシャ語「ἀγάπη(agape)」= 無条件・無償の愛
神は人格的存在であり、ご自身のかたちに似せて創造された人間を深く愛する。神ご自身が愛である(1ヨハネ4:8)という宣言。
神は愛に満ちていて、十字架での犠牲と贖(あがな)いがその究極形。
つまり、「人格的な神が、個としての私を愛してくださる」関係性の愛。
そして、キリスト者は自らの正しさを修練によって獲得するのではなく、その愛に応える歩みをする。
本の全文を読みたい方は、書籍『Gゼロ時代の津波石碑―再び天上の神様と繋がる日本―(21世紀の神学)』を手に取っていただければと思います。
◇