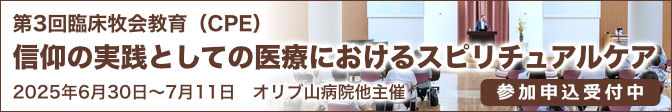1年ほど前に、『Gゼロ時代の津波石碑―再び天上の神様と繋がる日本―(21世紀の神学)』という本を出版させていただきました。この本で私は、日本人が聖書の神様をもっと深く理解していくために、歴史や文化、宗教、哲学、社会構造など、さまざまな角度から光を当ててみようと試みました。
今回から、この書籍の一部を、クリスチャントゥデイの読者の皆さん向けに新たにリライトしてお届けしたいと思っています。連載では、書籍には書かなかった内容や、新たな気付きを含めてお伝えしていけたらと考えています。初回は、プロローグ&最初の問題提起の部分をお届けします。
プロローグ
私の幼い記憶の中で最も古い風景は、家の礼拝堂の片隅で、弟と一緒にチラシを折っていた場面です。折っていたのは教会の案内ではなく、父が副業として営んでいた便利屋の広告でした。その礼拝堂には、賛美歌と紙飛行機が飛び交っていたのを今でも鮮明に覚えています。
クリスマスには教会の青年たちがツリーの飾りつけをし、お正月にはお汁粉を囲んで語り合うひとときがありました。春にはイースター、夏には河原でのキャンプが恒例で、たき火で焼いたさつまいもや、おにぎりの味は今も忘れられません。
父は牧師でありながら、生活のために便利屋としても働いていました。掃除や運搬、ペンキ塗りや大工仕事まで、何でもこなしていたのです。私も中学生になると、そうした仕事を手伝うようになりました。ペンキにまみれた休日と、日曜日の礼拝で語られる聖書のメッセージ。その2つが、私の信仰の原風景となっています。
高校に進学する頃、私の心は大きく揺れ動きました。ダウンタウンの漫才や、村上春樹の小説との出会いがきっかけでした。そこに描かれていた世界は、それまで教会で語られていた「善と悪」「戒めと祝福」といった枠組みとは、まるで別物のように感じられました。
聖書には、性倫理や節制などが語られています。一方で、当時触れたお笑いや小説の中には、感情や欲望を率直に表現する自由がありました。正しいかどうかではなく、どちらに「引かれるか」が当時の私には重要だったのです。そして私は、後者の世界に引き込まれていきました。
教会から心が離れ、サークルのバンド活動に没頭し、夜の街へと繰り出す日々。その時、父が私に手渡してきたのが、海外で行われるクリスチャン学生キャンプの航空券でした。私は、サークルのイベントと日程が重なっていたので迷いましたが、結局、そのキャンプに参加することにしました。
キャンプで出会ったのは、神様を心から信じ、喜び、賛美し、祈っている大勢の異国の若者たちでした。彼らの姿に、私は圧倒されると同時に、「神を信じることは、息苦しいものではなく、喜びでもあるのだ」という気付きを得ました。それは、それまで日本の教会では得られなかった経験でした。その出会いをきっかけに、私の人生の方向は少しずつ、しかし確かに、変わり始めていきました。
その後、東京、韓国、ニューヨーク、沖縄、オランダといったさまざまな土地で聖書を学び、多様な背景を持つ人々と語り合う機会を持ちました。そして、国や文化が違っても、人が抱える葛藤や願い、価値観には、多くの共通点があることに気付かされました。言葉や肌の色が違っていても、私たちは似たような希望や問いを胸に生きているのです。
そうした経験を通して私は、牧師の家庭で育った者として、「信仰とは何か」「宗教とはどのような意味を持つのか」「聖書は日本人にとってどんな価値があるのか」といった問いを、より多くの方に分かりやすく伝えたいと願うようになりました。
もちろん、私自身の理解にも限界はありますし、十分な知識があるわけでもありません。それでも、この本を通して他では語られていない大切な “ミッシングリンク” の片鱗を描き出すことができたのではないかと思っています。
本書を読んでいただくと、文章があちこちに飛んでいるように見えるかもしれませんが、全体としては一つの方向に向かう構成になっています。ページをめくるたびに、少しずつつながっていく感覚を味わっていただければ幸いです。
序章 自国起源説と世界文化との有機的なつながり
しかし、もしある枝が切り去られて、野生のオリブであるあなたがそれにつがれ、オリブの根の豊かな養分にあずかっているとすれば、あなたはその枝に対して誇ってはならない。たとえ誇るとしても、あなたが根をささえているのではなく、根があなたをささえているのである。(ローマ人への手紙11:17、18)
『蜘蛛の糸』は芥川龍之介のオリジナルではない?
芥川龍之介の名作『蜘蛛の糸』から、お話を始めてみたいと思います。地獄に堕ちたカンダタという男が、かつて蜘蛛を助けたことをお釈迦(しゃか)様が思い出し、一本の糸を垂らして救済の機会を与えるという有名な物語です。
しかしこの話は、芥川による完全な創作ではありません。19世紀ロシアの文豪ドストエフスキーが著した『カラマーゾフの兄弟』には、よく似たエピソードが登場しています。地獄に落ちた意地悪な女性が、かつてネギを一度だけ他人に施したことを理由に、天使がそのネギを使って彼女を助けようとします。ところが、彼女が他の罪人たちを蹴り落とそうとした瞬間、ネギは切れ、彼女は再び地獄へと落ちてしまいます。
物語の筋や教訓が、非常に似通っていることに驚かされます。専門家によると、ドイツ生まれの米国人作家で宗教研究者のポール・ケーラス(1852〜1919)が1894年に書いた「The Spider-Web」が、この作品の材原であったということが定説となっていて、さらに言えば、ケーラスは自分の作品が、スウェーデンの女流作家セルマ・ラーゲルレーヴが1905年に書いた「わが主とペトロ聖者」に依拠したと述べています。さらに古くには、イタリアとスペインにも同様の民話が伝えられているとのことです。
日本文化のオリジナル性とは?
つまり、『蜘蛛の糸』という作品は、悪く言えば模造品の模造品の模造品・・・、良く言えば世界中の作品群と有機的なつながりのある作品ということになります。私はこの事例に鑑みて、冒頭に当たって次の2つの点を指摘したいと思います。
一つは、芥川龍之介の文学作品に限らず、われわれが日本固有の文化や習俗だと考えている多くのものが、渡来してきたものであるということ。そしてもう一点が、渡来した文化であっても日本人の琴線に触れ得るという事実です。それは至極当然のことなのですが、どこの国の人であっても、同じ人間であり、表層的な違いはあれど、基本的な感覚は同じであるということなのです。
自国礼賛の言説への違和感
最近では、ユーチューブや書籍などで「日本スゴイ論」と呼ばれるような言説が目立つようになっています。「日本人の精神性は特別である」「わが国の歴史は誇るべきものが多い」「日本の文化は独自のものである」といった主張に、同調される方も多いかもしれません。
しかし私自身は、そうした語りにどこか腑に落ちない違和感を感じてきました。戦後の日本社会が抱えてきた精神的な空白やアイデンティティーの混乱を、「日本は素晴らしい」という感情的な表現によって埋めようとしているように見えるからです。
それは、ある意味で西欧文明の影響にさらされ続けた日本人の「根無し草のような不安」の現れであり、自己のアイデンティティーを確立しようとする情緒的な叫びのようにも受け取れます。
もちろん、日本の文化には素晴らしい側面がたくさんありますし、日本人の長所も数えきれないほどあります。それは、海外に住んでみて私自身も日々実感することですし、ありがたいことに、周りの方から言われることも多くあります。ただし、そのことに甘んじて、「日本(人)はすごい」「われわれは特別だ」と自我自賛するだけでは、漠然とした不安の解消にも、聡明な帰結に至ることも、未来へのグランドデザインを描くこともできないのではないかと考えています。このような問題提起が、本書の最初のテーマとなっています。
「津波石碑」に込めた思い
やや挑発的な書き出しになってしまい恐縮ですが、問題の本質を共有しなければ、どんなに処方箋を示しても真剣に受け取っていただけないと思います。ですので、冒頭の数章では、現代社会が抱える孤独や虚無感、不安といった心の問題に率直に向き合っていきたいと考えています(なお、これは日本に限らず、啓蒙思想の進展とともに世界中を覆っている現象であり、グローバルな病理でもあります)。
そして本書の後半では、具体的な「道標(みちしるべ)」をしっかりと提示していきたいと思っています。討論番組などでは、過去の失敗や問題点について多く語られる一方で、「では、これからどうすればよいのか」といった話になると、しばしば「ほぼ絶望的です」といった発言や、「それぞれができることから取り組んでいきましょう」といった曖昧な締めくくりに終始しがちです。
本書では、「宗教」という、世界中の文化と精神性の根幹にある普遍的なテーマを、現代における “津波石碑” として新たに捉え直し、一つの明確な指針を提示していきたいと思います。
本の全文を読みたい方は、書籍『Gゼロ時代の津波石碑―再び天上の神様と繋がる日本―(21世紀の神学)』を手に取っていただければと思います。
◇