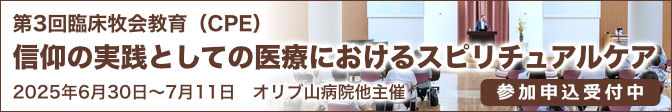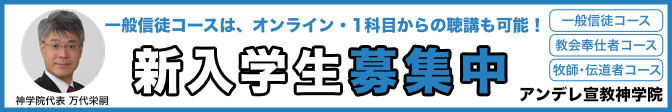だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心配します。労苦はその日その日に、十分あります。(マタイ6:33、34)
私たちは、過去、現在、未来という時間域の中に生かされています。誰も過去を変えることはできませんし、未来をコントロールすることなどできません。ただ、過去があって今があるし、今の努力が将来に実を結ぶことを信じるだけです。私たちにできることは、与えられている現在において努力に生きることだけです。
明日の生活を心配し、不安を口にすることは、自分の人生を真面目に考えているかのように見せかける偽善であり、神の支配への冒瀆(ぼうとく)ではないかと思います。「明日のことは明日が心配します」ということは、明日は神の支配下にあり、神の領域であるということです。明日のことを思い煩うということは、神の領域を冒す不遜な生き方になるのではないでしょうか。
私はキリスト教冠婚葬祭の働きに携わっていますが、葬儀に立ち会ったときに、自分自身の葬儀について考えることもあります。また、終活のセミナーに参加するときには、自分が何と多くの余計な物を抱え込んでいたかが分かります。少しでも捨てられるものは捨てて、身軽にならなければと思いながら、なかなか実行できない優柔不断な自分に気付きます。
物を捨てられないだけでなく、過去にこだわり、あの時はもう少し違うことができたのではないかと自分を責めることもあります。子育てについて、もう少し努力すべきだったのではないかと、反省モードに入ることもあります。
その時、倫理運動の創始者、丸山敏夫氏の言葉が示されました。「結果が悪かったと心を乱したり、良かったと有頂天にならない。与えられた結果が今の自分にふさわしい。結果は “天の領分” にある」というのです。この表現を借りるなら、過去は神の領域になるということになります。
過去を振り返りながら、自分を責めて、落ち込んでいた私は、神の領域を冒していたトンデモナイ不信仰者ということになります。私の生きざまが良かったのか、悪かったのか、結果がどうだったのか、裁かれるのは神様なのではないでしょうか。いくら私の人生だからといって、自分勝手にジャッジしていいはずはないと思います。
使徒パウロはとらわれの身となり、いよいよ自分の命運も尽きたかもしれないというとき、愛弟子テモテに書簡を送り、自分の真意を伝えました。
「私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです」(2テモテ4:6〜8)
使徒パウロの最期の言葉は圧巻です。しかし、彼は「主の現れを慕っている者には、だれにでも授けてくださるのです」と書き添えています。自分の生涯が華々しくなくても、失敗と思えても、主を慕うだけでパウロと同じような栄光が与えられるというのは、何という慰めでしょうか。
世界の歴史を見ると、信じられないような奇跡が示されています。2千年前に完全に消滅してしまったと思われたイスラエルという国家が復興し、失われた言語といわれるヘブル語が日常会話として用いられています。
また、失われた10部族といわれた古代イスラエルの末裔(まつえい)も、東の果ての島国と呼ばれた日本にたどり着き、縄文人に同化吸収されたと考えます。古代ユダヤ文化が脈々と日本で受け継がれているということが、歴史学者によって証明されようとしています。
世界最長といわれる日本文化の歴史とその精神が、敗戦によるダメージと、GHQの政策による8千書近くの焚書(ふんしょ)と情報統制により見失われ、反日思想にじゅうりんされています。精神的バックボーンとなるべき宗教は衰退しています。全国津々浦々のキリスト教会から聞こえるのは、先細りの声です。
しかし、これくらいのことで日本は終わらないと思います。歴史の真の支配者は神であり、その深部は神の領域なのです。必ず、神ご自身が働いて、神の国を復興してくださることを信じています。
「人事を尽くして天命を待つ」ということわざがありますが、英語では「Do the best you can and leave to God(最善を尽くし、あとは神に委ねよ)」というらしいです。昔の人々は神の領域のことをよく心得ていたから、心安らかにいることができたのではないかと思います。
あなたがたの思い煩いを、いっさい神にゆだねなさい。神があなたがたのことを心配してくださるからです。(1ペテロ5:7)
◇