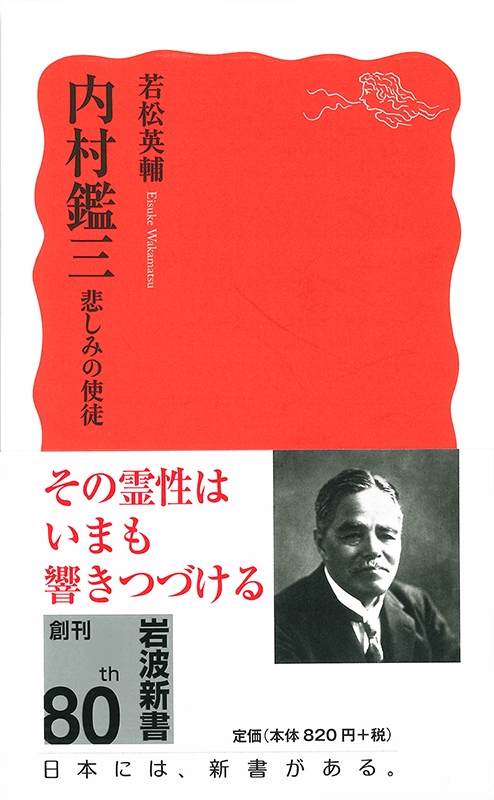クリスチャンなら、内村鑑三のことを聞く機会が多いだろう。そして少なくとも私の周りの方は、教派・教団を問わず、皆が彼を好いている。
私も学生時代のキャンプで、講師の先生が「昔、内村鑑三という信仰者がいて・・・」と話を始め、最後に「彼は2つのJに生きる、と決心しています。それはジーザス(JESUS)と日本(JAPAN)です!」と、まるで自分のことのように誇らしげに語ってくれたことを覚えている。やがて神学校に入り、彼に関する幾つかの有名なキーワードを知るようになる。「不敬事件」「再臨運動」「無教会」などである。
そしてそのどれもが、現代のキリスト教にはあまり縁のないもののように思っていた。しかし本書を手にし、実際にむさぼるようにして読んでみて、その浅はかな考えはまったく間違っていたことを知る。
本書は、内村の信仰列伝ではない。むしろ、歪(いびつ)な性格の故に周囲がかなり人間関係に苦慮せざるを得なかったことを赤裸々に語る告白本である。そういった意味で、内村の人となりをその弟子たちが語るというスタイルで貫かれた評伝という一面がある。
同時に、内村自身の言葉とその言わんとすることを現代的な視点から解説しているという側面もある。彼の言動が与えてしまった誤解や逸脱を、著者の若松英輔氏が現代の私たちに優しく丁寧に(そして内村を傷つけない程度に正確に)ひもといてくれているとも言えよう。
序章「回心」から第二章「死者」までは、比較的時系列に沿って内村の生涯がつづられている。特筆すべきは、彼が離婚後、単身米国へ留学することを決断したとき、父親から贈られた歌である。
聞しのみまだ見ぬ国に神しあれば 行けよ我が子よなにおそるべき
私はこのところで号泣してしまった。内村の人生は「武士道と神の道」だと多くの研究者が述べているが、それは父親から受け継いだ純粋かつ熱い生き方だったのだろう。その彼が米国での進学先として選んだのは、くしくも新島襄が卒業したアマースト大学であった。しかし彼は新島のように教育者としての生涯を送るのではなく、まさに神に献身する生き方を選ぶ。しかも既存の西洋キリスト教の在り方に従うことを良しとせず、独自の「無教会」を旨とする生き方を提唱し、弟子を生み出していく。
三章「非戦」から第六章「宇宙」までは、彼の思想とそれを受け止めつつ、継承していく弟子たちとの(激烈な)交流が描かれている。読んでいて最も心に残ったのは、彼の弟子たちの「内村鑑三」像がまちまちであることだ。ある人にとっては優しい兄のようであり、ある人にとっては自分を激しく叱りつける頑固な兄貴であったようだ。しかし皆一様に、内村のことを師として尊敬している。
その好例は、無教会(主義)の在り方や自身の結婚をめぐって師と対立せざるを得なかった塚本虎二の言葉である。
「私は先生の思い出を書こうとはおもわない。それは私の自叙伝を書くと同じであるからである」(「内村先生の死と私」)
ここまで弟子に言わせる師とはどんな存在か。若松氏は「衝突の機会は、その関係を深化させる時期を告げる合図」であると語る。そして内村と弟子たちとの関係は、単に徒党を組んだり、なれ合いになったりしてしまう意味での「集団」とはまったく対極にある苛烈な(と若松氏は評する)関係を取り結ぶのである。
さらに東大総長となった矢内原忠雄は次のように語る。
「われわれが彼(内村)から学んだものがあるとすれば、この何ものにもとらわれず、内村鑑三によってさえもとらわれないところの、聖霊による自由な信仰的態度であると言えよう」(「内村鑑三とともに」)
このような内村と弟子たちとの関わりは、彼が提唱した「無教会」という考え方にも通じている。私は本書を読むまで、内村の「無教会」とは既存の教会内でうまくやっていけない人たちが勝手に生み出した自由奔放なキリスト教、ぐらいの理解しかなかった。しかし筆者はこれにも丁寧に解説を加えてくれる。「無」とは、Nothing Church を意味しているのではない。既存の教会、その在り方を否定するものではない。むしろ既存の教会の在り方を越え(Beyond Church)て、キリストの福音をどう実現させるかという救済への根本的な態度を重要視する、その信仰の純粋さと熱さを言い表しているという。
だから彼は「再臨運動」に傾倒することになったし、逆に人々がこの Beyond を無視して単に「いつ主が来られるか」という終末的現象のみにとらわれ始めた聴衆を見たとき、彼はむしろこの運動から距離を取り始めるのであった。そこには、彼が常に感じていた「超克(Beyond)」の精神がその本質を失っていくことを実感したからであろう。
興味がそそられる方はぜひ本書を手に取ってもらいたい。新書のため、短い時間で「内村鑑三ワールド」を体感できるであろう。
若松英輔著『内村鑑三 悲しみの使徒』(岩波書店、2018年1月)
◇