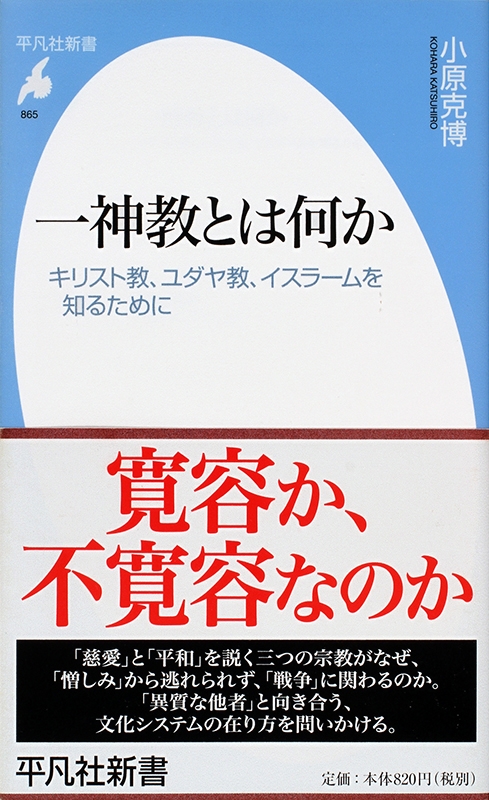「異質な他者」を受け入れ、「寛容な文化」を生み出すための歴史観を大胆に提示!
著者は同志社大学神学部教授の小原克博氏。私は大学院時代に小原教授の授業を幾つも取り、そこで大いに神学的刺激を受けた。あれから7年がたち、本書を通して再び「小原氏の授業」を受けられた喜びがあった。だから今回は「書評」ではなく、もしかしたら「賛辞」に偏ってしまうかもしれない(笑)。しかし、それはお許しいただきたい。なぜなら私が「神学」の奥深さと面白さを体験できたのは、小原氏あってのことだからである。
「博覧強記」という言葉が最もぴったりくるのが小原氏であった。先生の授業では、ドイツの難しそうな名前の神学者からエヴァンゲリオン、ジブリ作品、「セイントお兄さん」まで、登場するトピックスが多岐にわたっていた。そして、どれもがきちんと系統だって語られることで、私たちの理解が数段深まることは間違いなかった。
そんな小原氏が『宗教のポリティクス』以来、数年ぶりに著書を出されるということで、私は予約購入をしてしまった。そして、本が届くと、貪るように読み始めた。だが・・・なかなか進まない。それは、書かれている内容が示唆に富み、1ページ読むごとにあれこれと考え込んでしまうからである。電車の中でこの思索状態に陥り、危うく電車を乗り過ごしてしまいそうになったこともある。
わずか新書200ページくらいの著作ながら、描き出している内容は読み手の知性を刺激し、さらに思いもよらない関連を私たちに投げ掛けてくれるのである。私としては、読んでは考え込み、考え込んでは読み進め・・・という至福の時間を過ごさせてもらった。820円(税抜)以上の価値が十分あることは間違いない。
さて、私の興奮はここくらいまでにして、肝心の中身に入ろう。
本書は「はじめに」にて明確な方向性が示されている。それは「間」を見ることである。キリスト教、ユダヤ教、イスラームの「間」、実社会と一神教(ヘブライ語聖書を聖典とし、アブラハムを父祖とする「唯一まことの神」を信奉する宗教)の「間」、そして、日本社会と一神教の「間」である。
これら三宗教の解説書、入門書は巷にあふれている。しかし、小原氏はこの三宗教の関係性について問う。さらに宗教界の独自性だけでなく、おのおのの教えが実社会にどのような影響を与えているか、という意味での「間」を問う。さらに、本書が日本の研究者によって日本語で書かれていることからも分かるように、一神教と私たちに日本社会との関係性を問うている。
そういった意味で、今まで日本で安易に語られてきた「一神教批判・多神教礼賛」の流れに歯止めをかけ、一般的になじみのない中東近辺の諸宗教を私たち日本人がどう扱うかということによって、真にグローバルな視点で世界を見、同時に日本を見る視点を培おうとしている。
それは、数千年前に生まれた(イスラームは1400年近く前)古めかしい宗教を帰納的に描き出すことではなく、むしろ21世紀の世界で実際に引き起こされている事象を演繹(えんえき)的に示すことによって主張に説得力を増していく、というやり方である。現実社会と三宗教との関連性をリアリティーある形で示そうとしているともいえる。
第一章では、日本と一神教の関係が語られている。従来の「一神教は偏狭で寛容さが足りない」という論調をかっこに入れ、逆に「多神教は本当に寛容なのか」と問う。さらに一神教が生み出された風土にも言及し、決してこの三宗教が特別なものではなく、私たちが理解可能なシステムと教えを有していることを示している。
第二章では、一神教の起源や歴史をなぞり、返す刀でいかに私たち日本人がこれらの諸宗教にバイアスをかけて眺めていたかを明らかにしていく。特に、イスラームに関してはその傾向が強い。これは(おそらく本紙読者の大半がそうであろう)キリスト教徒が最も陥りやすい誘惑でもある。その指摘に思わずはっとさせられる。
第三章からは、各宗教における「創造論」「終末論」「偶像崇拝」に言及し、それぞれの違いだけでなく、ここ数年間に世界で起こった出来事を事例として挙げながら、各宗教の色合いを叙述している。
私が特に面白く思えたのは、「見えざる偶像崇拝」の項目である。一般的な意味での「像(銅像・彫像)」のみならず、私たちが心の中に抱く偶像(自己神格化・絶対化)をも視野に入れての展開は、読み手の心を深く探る内容になっている。
第四章では「戦争」が取り上げられている。世界の現実であると同時に、日本人が現在最もリアリティーを感じられないテーマである。だが、移民問題や隣国との軋轢(あつれき)が死活問題であるヨーロッパ、中東においては最も卑近なテーマであるといえよう。
これを安易に看過して、「一神教は偏狭で寛容さが足りない」と訴えることのいびつさを、小原氏は次のように語る。
「一神教=不寛容、一神教=好戦的といった単純な等式を振り回すことは、アイデンティティを矮小化し、結果的に暴力や戦争の抑制や原因究明から目をそらすことになってしまうだろう」
第五章では、「世俗主義」「原理主義」という用語を駆使しながら、諸外国の現状を概観している。しかし、それらは「外国の現状」と見なすことはできず、実は私たち日本社会も知らず知らずに内包していることが最後に指摘されている。
一見「寛容に見える」私たち日本社会が、いつしか陥ってしまった「不寛容さ」を際立たせているといってもいい。このあたりは神学者・小原克博氏の面目躍如といったところだろう。
そして「おわりに」で、どうして今、日本社会で一神教を問わなければならないのか、ということがつまびらかにされる。私たちはいつしか「異質な他者」をあぶり出そうとする「憎しみの文化」を抱いてしまっている。これは日本も例外ではない。教育の現場にいじめが絶えず、社会においては「~ハラスメント」が頻出しているのもその証左といえよう。
この「憎しみの文化」が、日本社会には間違いなく存在する。するとさらに悪いことに、「寛容」という偽りの衣をまとうことで、「無関心に基づく適度な距離感」を生み出してしまう。だから本書の最後で小原氏はこう語っている。
「同質性を共通基盤としてきた日本社会は、『異質な他者』と向き合うことによって、文化的なタフネスを獲得していかなければならない。その点で一神教は日本社会にとって、実に取り組み甲斐のあるカウンター・パートナーとなり得るであろう」
本書は、学術的に「一神教」に興味関心を持つ方はもちろんのこと、長年キリスト者として信仰を培ってこられた方にこそ手に取ってもらいたい一冊である。
私たちの信仰を破壊したり揺るがせたりする必要はない。しかし、今までの信仰姿勢の中にいつしか入り込んでいる「異物排除の論理」に対し、これからのグローバル社会を生きる私たちは無関心ではいられない。それを異なった確かな視点から考察することで、私たちの信仰を現実社会で有効に機能するものへとバージョン・アップさせることができるはずである。本書はその一助となることは間違いない。
小原克博著『一神教とは何か キリスト教、ユダヤ教、イスラームを知るために』(平凡社、2018年2月)
◇