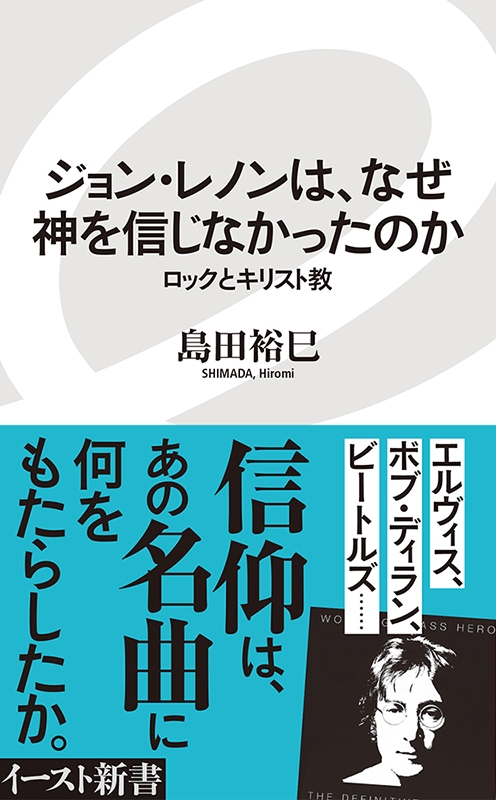米国南部との関わりが増えるにつれ、不思議な感覚にとらわれていく。それは、音楽という世界の広がりといっていい。幼き頃より、音楽にはジャンルがあると聞かされてきた。それほど熱心に音楽をやる環境にあったわけではないのに、そんなこましゃくれた見解を受け入れて育ったと思う。
クラッシック、ジャズ、ロック、ブルース、ポップス・・・いろんなジャンルが音楽にはある。そう聞かされてきたし、それらの違いを指摘する程度には耳を慣らしてきたつもりだ。
だが、「ナッシュビルからの愛に触れられて」シリーズでも語っているように、米国南部の友人たちとの交わりが深まるほど、こういったジャンル分けに何の得があるのだろうか、という疑問が頭をもたげてくる。それくらい彼らの中の音楽はクロスオーバーしている。
そして本書を読んだ。大いに納得した。タイトルはビートルズやジョン・レノンの人気にあやかっているが、中身は四部構成となっている。一章、二章でエルビス・プレスリーが取り上げられている。三章では昨年ノーベル平和賞を受賞したボブ・ディラン。四章はタイトルにもなっているジョン・レノン。そして第五章で今までのまとめ、そしてキリスト教とロックに関する筆者の考察が語られている。
時代順に並べられたアーティストたちが、それぞれどのようなスタンスでキリスト教と向き合ったかが紹介され、その例証として発売されたアルバムや収録されている楽曲が挙げられる。しかし、私が面白いと思ったのは、彼らの生い立ちである。私がテネシー州メンフィスにあるグレイスランドへ行ったことがあるためか、プレスリーにはとても親近感を覚えた。
幼い頃に、貧しい家庭の中で唯一の楽しみが歌うことだったプレスリー。彼が教会の聖歌隊で歌う中で次第に音楽的才能の頭角を現していく。しかし、本書はそのような彼の信仰姿勢とは裏腹にロックアイドルとして売れていく姿をトレースしている。当時の熱狂ぶりがいかにすごいものであったか、そしてそのような在り方をキリスト教界に代表される大人たちはどう思っていたか。そのギャップが面白い。
しかし、筆者の島田氏も冒頭で語っているように、歴史的に見るならば、「キリスト教の信仰世界が、反体制・反権力のロックをそのなかに取り込んでしまった」ということになる。
日本人が「キリスト教」というと、筆者も言及しているように「倫理性が高い、むしろ知識人向けの信仰」というイメージが強くある。しかし米国の、特にミュージシャンたちの音楽遍歴を見るなら、そこに必ず「キリスト教(またはゴスペル)」が存在しているし、それをどう抗っても抗いきれず、またどう取り入れても日本人がイメージするキリスト教とはなり得ない。
それは言い換えるなら、米国社会における宗教(キリスト教)が占める独自の立ち位置を理解することに他ならない。そしてこの流れは、米国南部において他との相違という点で異彩を放っている。
ロックというと、若者たちの社会に対する反抗の手立てと見なされてきた歴史がある。しかしその半面においては、キリスト教の信仰と強い結びつきを持っていたことが、本書を読むことで分かる。
いや、そもそもキリスト教は歴史的に、そういった市井の人々の反骨精神を支え、それを推進する力を包含する側面を持っていたはずである。ローマ帝国に支配されながら、いつしか帝国を支配する力となり得たし、カトリック(普遍)一極支配に対するプロテスト(抵抗)が「プロテスタント教会」を生み出すきっかけとなった一面がある。さらに、英国においては議会制度を尊重しない王たちに対してピューリタンたちが信仰に基づいた革命を引き起こしたし、米国における黒人たちは、白人が思いもよらない形でキリスト教を享受したことによって、歴史的たくましさを表明し続けてきた。
確かに「キリスト教」は支配体制側の宗教であったし、支配機構にフィットする神学が構築されてきた。だが同じ「キリスト教」は、人間的な枠内に閉じ込めておけるほどおとなしく静的な存在でもなかったことは明記すべきことだろう。
そういった一種コペルニクス的転換の爽快さが本書にはある。私が最も賛同するのは、筆者の次のフレーズである。
現代では、ロックがキリスト教の信仰を広め、それを強化する役割を果たしているとすらいえるほどになっている。
確かにその在り方に賛否はある。だが、本書を読むにつけ、エルビス・プレスリー、ボブ・ディラン、ジョン・レノン、エリック・クラプトンなど、日本でも名の通ったミュージシャンが「キリスト教」を通っているのである。そうであるなら、その後の時代を生きる若者たちにとって、本書はキリスト教の敷居を低くする最も効果的な方策を提示していると受け止めることも可能ではないだろうか。
島田裕巳著『ジョン・レノンは、なぜ神を信じなかったのか ロックとキリスト教』(イースト新書、2018年2月)
◇