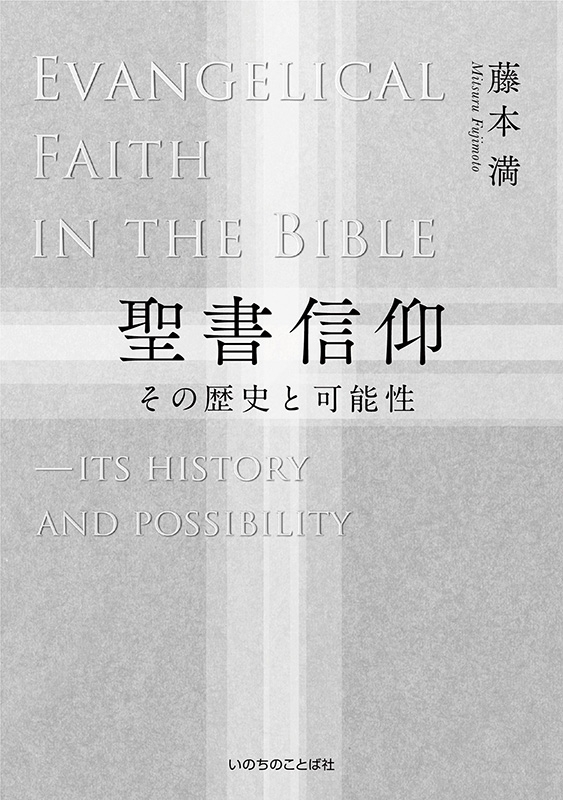「閉じられた神学と論争を越えて健全な議論を」という問題提起
前編では、13章までで提示された歴史的見地から見た聖書信仰の変遷について言及した。後編では、藤本氏が本書を書く動機ともなったであろう、モダン主義を越えた聖書信仰の在り方について、評していきたい。
13章で藤本氏は、今までの福音主義的聖書理解を、他学者たちの言葉を用いながらも次のように述べている。
「(聖書の)無誤論にこだわればこだわるほど、その内側の論争に終始することにそのエネルギーを使い果たし、人の言葉で記されている御言葉の真意を学術的手段をもって掘り下げ、またその真意を現代の課題に適用するという福音主義の最重要課題に取り組むことができない(後略)これは歴史的に実証されてきたのではないだろうか」
そして、このような姿勢を「守りの姿勢」と評し、「これゆえに、キリスト教信仰の中心的なテーマをあらゆる問題に対して論じるという周囲の期待を裏切ることになった」と、神学者アリスター・マクグラスの言葉を援用しながら述べ、こう続けて訴えている。
「だが、現実はその守りの姿勢を捨てて、批評学的成果を用いつつ、健全に論議できる時代が来ている」
閉じられた系としての福音主義に限界がきているという藤本氏の指摘は、多くの神学者も述べている点である。つまり、「聖書には全く矛盾がありません」とか「科学的見地から見ても真理です」と言い続けているだけでは、もはや多くの人々の賛同は得られないということである。そのような「守りの姿勢」を捨てることを、藤本氏は大胆にも訴えている。現代的な実践的側面と、伝統的な神学的側面との「健全な議論」が可能になるなら、それは「福音」主義が最も願っている「福音の伝播」が有効に行われているといえるだろう。
「教会共同体の知」を前提にした聖書解釈
ここで藤本氏は、拙著が詳述したファンダメンタリズム論争、それに連なるリベラリズムと根本主義者との歴史的対立を乗り越える道を具体的に示そうとしたのである。そして、ポストモダン時代に必要な聖書観を、次のように述べていることは、示唆に富んでいるといえる。
「(聖書は)何の前理解もなしに、純粋な白紙の状態で解釈されることがあり得ないのなら、聖書は最良の前理解、すなわち教会共同体の知を前提に解釈されるべきである」
「教会共同体の知」という表現は、今までの議論を包括的に受け止める視点が含まれているように思われる。かつては、プロテスタントがカトリックの教会ヒエラルキーに対抗する形で聖書を信仰の中心に置いた。やがて啓蒙主義の時代を迎え、理性が幅を利かせるようになる。その中で生み出された新神学(リベラリズム)は、既存の素朴な福音主義(プロテスタント)を結果的に崩壊させる方向へと導いた。これに対抗した根本主義者たちは、同じ時代性(モダン主義)の舞台で彼らをモダニストと揶揄(やゆ)した。
しかし、そう叫ぶ彼らもまた「別種のモダニスト」であって、それは共に前理解としての理性に基づいていた。だが、その理性すら、実は相対的な概念であったことが喝破され、時代は「ポストモダン」へと突入していく現時点では、モダン(近代)を主軸にして考えるため、時代的制約からは逃れられていない。つまり、キリスト教会2千年の歩みを、どれ1つとして無駄なものと捉えないで、おのおのの時代に生み出された教えや考え方の変遷をそのまま「教会(=共同体)が紡ぎ出してきた知」と受け止めるということである。
その混沌とした中にあって、藤本氏は「教会共同体の知を前提に解釈されるべき」と言い切ったのである。共同体としての教会にこそ重きを置く、ということは、今までの論争や対立の中を現実的に乗り越えてきた「歴史的教会」が保持してきた内容をリスペクトしようということである。それは単なる机上の空論ではなく、また一時的な興奮状態によって生み出された狂乱ではない。同時に、静的な真理を心の奥深くにしまい込んでおけばいい、というような「宝物」でもない。
常に時代と連動して動き、そして歴史的に人々の批判にさらされる中で、ある部分はびくともしない堅固さを示し、ある部分は現実に即して変化する。それによって現代人に対して開かれた福音が提示され続けることになる。聖書はその端緒となり最後の砦(とりで)となる。これを藤本氏はウォルター・ブルッゲマンを援用して「出来事や教えの記憶」と表現している。
17章以降、藤本氏の主張はさらに先鋭化し、従来の福音主義の在り方を改善する主張は具体性を帯びてくる。その中で特に目を引いたのが、以下の文章である。
「私たちは、今日性を危険視して、神の言葉の歴史性にこだわる。逆に、今日性を強調して、聖書の歴史性を分析しようとしない。外から投げかけられる挑戦に対していつも守りの姿勢を取っているとき、それらの論の欠けばかりを見つめ、過去性と今日性の緊張関係を解消して、どちらかをないがしろにすることになる」
そして、最後にこう言い切る。
「仮に福音主義が、聖書を啓示の完成であるかのようにみなし、聖書のテキストを分析することによって、窓の向こう側にある歴史的出来事と意味を確実に理解することができると胸をはって主張するとき、そこにはモダン主義のおごりが見え隠れしている」
拙著『アメリカ福音派の歴史』の発表以降、私が聖書信仰について考えていたことと、藤本氏が本書で提示していることには共通性がある。歴史性(過去)と今日性(現在)との二者択一を捨て去ることである。藤本氏はこれを聖書学的見地から訴えるため、現代の福音主義神学者を紹介することで、『聖書信仰』という著作を閉じている。
ここで1つ、私が氏に注文をつけるとするなら、後半部分を自らの神学的思索で深めてほしかったということである。藤本氏のこだわりと追究の成果を自ら語り直すとき、それは単なる概論や諸論に留まらない。むしろ、藤本満という神学者の存在を人々に訴える貴重な機会となったであろう。そういった意味でも、私は次回作を心から待望する。
一方、拙著発表後の私は、実践神学的に論を展開してきた。やはりどうしても現場主義が抜け切れないのだろう。例えば本紙に映画評を投稿したり、ゴスペルや一大統領選挙について言及しているのは、これらを通して現代的な聖書信仰の在り方を、まだキリスト教になじみのない方々に向けて紹介することを目的としているからである。
歴史性(過去)と今日性(現在)との二者択一を乗り越える方法として、藤本氏はポール・リクールらに代表される「物語(ナラティブ)論」に舵を切った。一方私は、むしろ「物語」的まとまりをも解体し、「格言」「標語」としての聖書を提案している。歴史性も今日性も、一端横に置き、聖書の言葉の文脈を無視し、直感的にいいと思えるものを取り込むことで、聖書に対する興味を持ってもらうことを提唱している。
例えば、就活に悩む学生に、聖書の励ましの言葉を前後の文脈から切り離して提示する。それを通して元気になり、聖書というものに興味関心を持ってくれたら、その学生にとって聖書は単なる書物ではなくなり、自分にとっての特別な存在となるであろう(ただし、これはビギナー向けであって、その後は系統的な学びは必須である)。
この両者の違いは何か? 藤本氏がこれを聖書神学的アプローチで手堅くまとめたのに対し、私は歴史神学の域を出て、やはり現場牧師の一実践として展開したからであろう。どちらがいいというよりも、この両方があってこそ、まさに藤本氏が言う「教会共同体の知」となると思われる。私たちは、どちらにも適応できる「聖書」という書物の懐の深さを知ることができるだろう。
両者に共通しているのは「言葉の働き」を重視し、聖書の言葉(藤本氏にとっては「物語」)と私たち自身の言葉(物語)が共有されるということである。これを信じることこそ、「聖書信仰」の本髄であると私は考える。
2回にわたって、書評というよりも内容に圧倒され、刺激された私の個人的なほとばしりとなってしまったが、誰が読んでも大いに考えさせられる1冊であることは間違いない。特に信仰歴が長い福音系キリスト教信者にとっては、もしかしたら頭をハンマーで殴られたような衝撃を受けるかもしれない。
しかし、それでいいのである。まさに人々の記憶に残る1冊は、必ずその方の人生を変えていくことになる。常にそうやってセンセーショナルな一面が新たな時代を切り開いていくのだから。
分厚さに気後れしないで、ぜひ手に取ってみてください!
藤本満著『聖書信仰 その歴史と可能性』(2015年、いのちのことば社)
◇