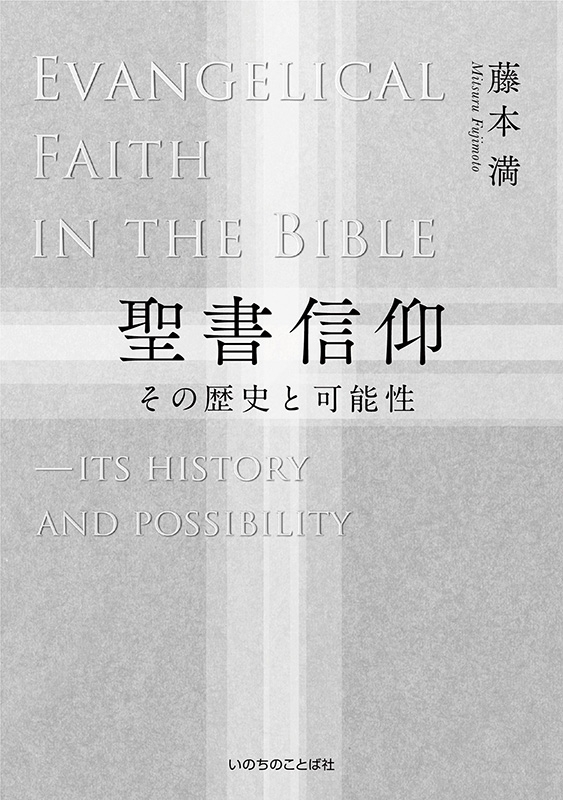もしもあなたが「聖書の書いてあることは本当にあったことなんだろうか?」とか、「こんな出来事が本当にあったとしたら、これをどう説明したらいいのだろう?」と一度でも思ったことがあるなら、ぜひ本書を手にすることをお勧めする。なぜなら、従来はこのような疑問を持つことは「不信仰」なことであり、まだキリスト教をよく分かっていない初心者が抱く「根本的な過ち」と考えられてきたが、今やそのような判断こそ独善的として非難される時代だからである。
このような疑問とそれに対する対応、その両者のパラダイムが異なっているのだ、ということを本書では喝破(かっぱ)している。
2012年に、拙著『アメリカ福音派の歴史 聖書信仰にみるアメリカ人のアイデンティティ』を上梓してからほぼ4年半がたち、再びこの課題に向き合う意欲が与えられた。そのきっかけとなったのが、今回取り上げる藤本満氏の『聖書信仰 その歴史と可能性』である。藤本氏とは、2012年の秋に東京で行われた日本福音主義神学会東部部会でお会いし、共に講師という立場で意見交換をさせていただいたことを覚えている。その時から氏の研究には大変心惹(ひ)かれていた。そして今回、『聖書信仰』を読み進めていくにつれ、なぜ私が惹かれたのか、その理由が分かった気がする。
それは端的に言って、聖書の「無誤性」および「無謬(むびゅう)性」に対する従来のかたくなな姿勢に対する批判的精神を持っているということである。この辺りは、言葉を選ばないとあらぬ誤解を招くことになるので慎重にならざるを得ないが、決して聖書の無誤性や無謬性(両者の違いも承知している)を頭から否定し、リベラリズム神学こそが真理だ、と声高に叫ぶつもりは毛頭ない。無誤・無謬が「聖書信仰」の根幹をなしていた時代が存在し、しかもそれを元に「福音主義」が成り立っていたことを否定するつもりはない。
だが、本書でもその経過が概観されているように、どんな教理や「真実」も時代とともに批判にさらされ、一部は侵食されていく。それでもなお残る「資質」こそ、後の時代に受け継がれていくことになる。同時に、新たな潮流に迎合するだけの在り方もまた批判されるべきで、それが先代から受け継いだ「レガシー(遺産)」にきちんとリンクしているかは、よく吟味すべきである。
それでは、中身を概観していこう。本書は全18章(「はじめに」を入れると19章)から成っている。大著であることは間違いないが、各章はとても読みやすく、おのおの独立したものと捉えることも可能である。しかし、やはり1章から順に読み進めていくと、聖書をめぐる滋味豊かな旅を堪能することができるといえる。
大きく分けて、12章までが「聖書」をめぐる歴史の概観である。そして13章以降では、前章までで浮かび上がった諸問題をどう解決へ導いていくかの方策が提示されている。つまり歴史的アプローチと、組織神学的アプローチの両面から本書は「聖書信仰」という課題に取り組んでいるといえよう。
“聖書無誤性への議論の集中”が福音主義神学のダイナミズムを損なった!?
「はじめに」で藤本氏は次のように述べている。
「プロテスタント正統主義は、聖書論に確固たる場所を与えただけでなく、それを神学全体を支える土台ともした。(中略)20世紀の聖書信仰はさらに進んで聖書の無誤性の教理を確立しようとした。(中略)だが結果として、福音主義『神学』は争点を聖書の無誤性に集中させることとなった。そうして福音主義の聖書論は、18世紀の敬虔主義や信仰復興運動が主張するような、神の今日的語りかけとその力を聖書に求めるというダイナミズムを神学的考察の対象とすることをわすれてしまった、と私は考えている」
この書き出しが本書全体の枠を与えていると言ってもいい。本書のタイトルになっている「聖書信仰」という言葉からも分かるように、聖書をある種の信仰対象として受け止めるキリスト教保守派は、永遠の課題として聖書を土台とする理性的な積み上げと、実際の現実社会で培われる経験的な積み上げとの齟齬(そご)をいかにして乗り越えていくか、という命題を引き受ける運命にある。
そして前者をかたくなに「不変の真理」としてしまうと、必然的に後者の解釈を改変することで、整合性を取らざるを得ないことになる。しかし後者の改変があまりにも公平性を欠き、キリスト教徒寄りの恣意(しい)的なものと受け止められてしまうと、福音主義神学は閉じられた系と見なされ、キリスト教を知らない多くの人が気軽にアクセスできないものとなってしまう。
だから、そうならないためにはどうしたらいいか、という疑問に答える形で、本書は成り立っている。
リベラルも福音主義者もまた“近代主義”の土俵の上での論争だった
前半(12章まで)で藤本氏が提示したことは、総じて言えば「モダン(近代)主義」に踊らされた聖書理解の変遷である。「ファンダメンタリズム論争」として米国において19世紀末から20世紀前半にかけて起こった論争は、確かに聖書をめぐる議論ではあった。相対立する主張、基本的前提、そして激しい論戦など、一見すると確かに好対照の両陣営ががっぷり四つに組んで、互いに譲らないように見える。拙著では、まさにこの“ガチンコ”の部分をかなり細かく描写した。
しかし、藤本はこれを俯瞰(ふかん)的に眺め、ファンダメンタリズム論争の中心にある共通性を喝破している。それが「モダン(近代)主義」である。根本主義者、リベラリズム共に、“聖書の内容を科学的なもの”、“理性で捉えることができるもの”、“そして近代的思考でも受け止められるもの”として自陣営に引き込もうとしていることをはっきりと指摘する。つまり、この論争自体が時代性を強く帯びた「一時的」なものであり、後半の「ポストモダン」という視点から見るなら、やはり前時代的な(古めかしい?)論争であったということを提示している。
本書は、単に各国の聖書の扱い、時代的な制約を並べているわけではない。このような近代性を乗り越えていく時代(ポストモダン)を迎えた現代において、ではこの聖書信仰はどう受け止められるべきで、どのような観点からこの有用性は語られるべきなのか? それが13章以下に展開することになる。
次回は後半に関して評してみたい。(続きはこちら>>)
藤本満著『聖書信仰 その歴史と可能性』(2015年、いのちのことば社)
◇