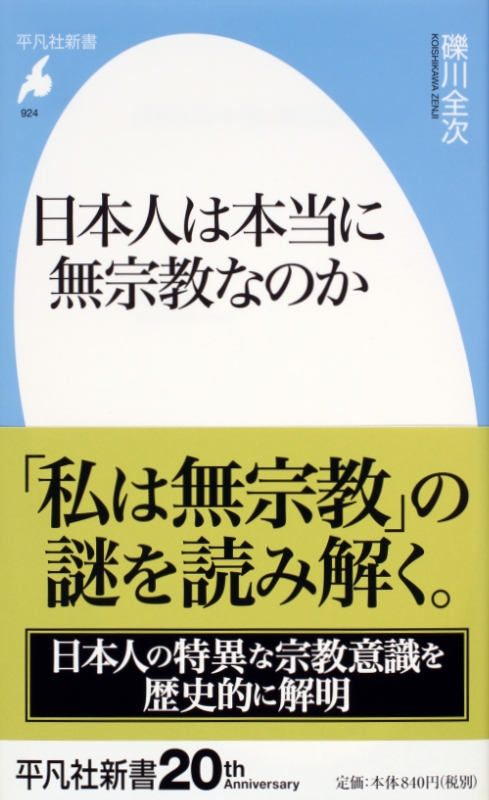2019年5月から元号が「令和」となり、新たな時代が始まった(とされている)。その変化を日本人として一番感じさせられたのは、他でもない新天皇の一連の即位式典である。その熱狂(ある人たちからすると「狂乱」)ぶりは、世界各国を巻き込み、天災による多少の遅れこそあれ、即位パレードが実施され、日本を代表する(していいのか?)アイドルグループ「嵐」が歌った奉祝曲を、多くの国民が耳にしたことだろう。あらためて「天皇制とは何か」を問う機会となった。
大学で私の授業を受講する学生から、「一部のキリスト教信者が天皇制を憲法違反だと騒いでいましたが、神道は宗教ではないのに、どうしてあんなに大騒ぎするのでしょうか」という質問が寄せられた。質問の内容はともかく、キリスト者としてこの問題にどう向き合うかはとても重要なことであろう。
そんな中、『日本人は本当に無宗教なのか』というストレートなタイトルの本書と出会った。著者は在野史家で、歴史民俗学研究会代表の礫川(こいしかわ)全次氏。つまり本書は、民俗学の視点から日本の宗教史をひもといているということである。全7章と終章で構成された本書は、そのほとんどを明治期の宗教制度の変遷にページを費やしている。そして江戸時代以降、常に宗教の問題には「キリスト教」が絡んでいるということが述べられている。
冒頭(第1章)では、平安、鎌倉、室町、江戸の各時代における「日本人の宗教性」が現れている著作を紹介し、「かつての日本人は宗教的だった」ということを示している。さらに、「キリスト教弾圧」という事柄の裏で、時の権力者と仏教一門が手を結び、政教一致にも似た様相が日本では生み出されていたことを喝破する。
しかし江戸中期以降、この宗教性が次第に失われていくことが2章から4章にかけて述べられていく。面白いのは、私たちが一般常識として習う程度の日本史の人物(本居宣長、平田篤胤〔あつたね〕ら)を、その前後の思想的変遷と比較しながら述べている点である。彼らのいわゆる「国学」という考え方の中に、実はキリスト教的な素養を見いだすことができる、というあたりは、読んでいてなぜかこそばゆい感覚になってしまう。
例えば、平田篤胤が「復古神道」を大成するに当たり、「天主教」(カトリック)、すなわちキリスト教の経典を意識していたとか、禁止された神学書を学んでいたというあたりは、人は何の参考書もなく形あるものを生み出すことはできないのだ、ということを思わされる。礫川氏はそのことを次のようにまとめている。
篤胤の復古神道は、(中略)キリスト教を強く意識し、それに対抗するために創造された「新宗教」である。おそらく篤胤は、当時の日本が置かれていた情況の中で、彼なりの危機意識を抱き、キリスト教に対抗できるような日本独自の宗教を「創造」せずにはいられなかったのであろう。(69ページ)
そう見ると、キリスト教伝来以来、日本の宗教体制は常にキリスト教との距離感を意識しながら歴史を重ねてきたということが透けて見えるのである。こういった歴史観は、考えてみるとありがちなことだが、考えてもみなかった。キリシタン禁制以来、私たちが日本で学ぶ「日本史」には、明治時代までキリスト教はほとんど出てこない(島原の乱を除く)。だからなかったかのように考えていたが、水面下では、時として脅威となり、時として指針となり、その捉え方はさまざまなれど、「西洋の宗教」としての威力を発揮していたことが本書から読み取れるのである。
そして本書の白眉は、何といっても終章である。礫川氏の考える日本的な「宗教」には、男女の性に代表される「習俗」との補完関係がある。
本書の考えるところでは、宗教というのは、習俗と結びつくことなしには成り立たない存在である。この場合、中世キリスト教のように、習俗を自己のコントロール下に置こうとする宗教(中略)がある一方、「かつての日本の仏教」のように、習俗に干渉することなく、それと共存し、相互に補完し合う関係にあるような宗教もある。(中略)いずれにしても、「宗教」という存在は、「習俗」という存在との関わりを避けることができない。(207ページ)
しかし明治期以後、習俗と混然一体となっていた日本的な宗教が息の根を絶たれてしまった、と礫川氏は語る。つまり日本人の「無宗教」は、意識的に、そして歴史的所産として生み出されたものだ、ということである。
いかにも民俗学的な指摘ではなかろうか。西洋社会の世界観では「文化」と呼ばれるものを、礫川氏は「習俗」と表現しているきらいもあるが、いずれにせよ、神道は実質的には国教(的)であったにもかかわらず、「宗教でない(非宗教)」とされてきた。これで習俗の役割を補完させ、「国家神道」を他の諸宗教を超えたところに位置付けることで、「国家神道体制」が完成したというのである。
よく明治期の日本に関して、西洋的な技術や物質的なものは受け入れたが、その精神(キリスト教)は受け入れなかった、と語られるが、礫川氏にとってそれは、明治政府が意識的に国家神道体制を敷くための一方策として選択したということだろう。それはつまり、日本的な意味での「宗教」の終焉(しゅうえん)を意味する。
令和という新しい時代が始まった今だからこそ、本書を読むことで、人々と議論したくなる思いに駆られるのも必要なことではないだろうか。ぜひ手に取って読んでいただきたい。
■ 礫川全次著『日本人は本当に無宗教なのか』(平凡社 / 平凡社新書、2019年10月)
◇