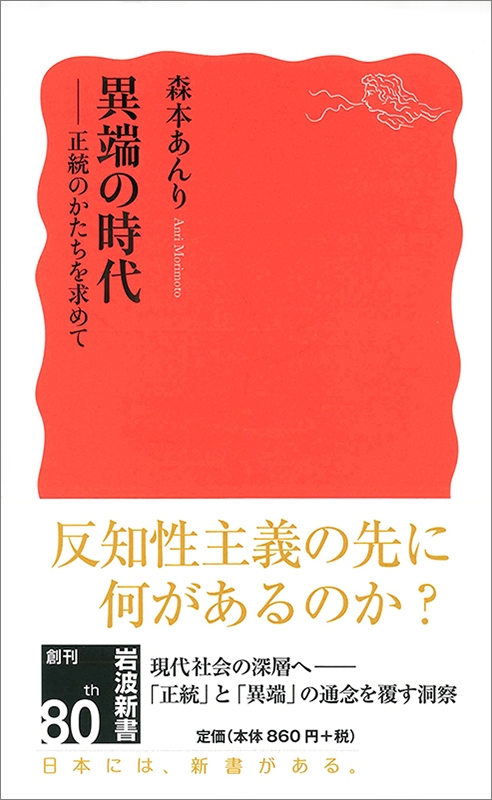前著『宗教国家アメリカのふしぎな論理』から約10カ月。森本氏の新刊が岩波新書から発売された。著者の代名詞ともなっている「反知性主義」を取り入れたキャッチフレーズ「反知性主義の先に何があるのか?」という本の帯は、本書を思わず手に取る人への刺激的な言葉となっている。
同時に、前著後半で展開された「正統と異端」の問題が本書では中心に来ており、しかもそこに新たな視点(丸山眞男〔まさお〕氏への言及)が加えられることで論の深まりと広がりを実感することができる。アウグスティヌス、オリゲネスという古代教会の神学者たち、ドナティスト論争、ペラギウス主義、秘跡をめぐる中世神学の歴史、ハルナック、トレルチなどの近現代神学と解釈学、これらが「正統と異端」というテーマに収斂(しゅうれん)されている。
読み終えて、「正統」「異端」という用語に対する哲学的な深まりが与えられると同時に、これらの言葉をキーワードとしたキリスト教2千年の歴史を分かりやすくレクチャーしてもらった満腹感を得た。さらに、現代を生きる私たち、特に大学生や社会人として日本社会を支えている血気盛んな年代層に向けて、「正統を担える存在となれ」という励ましのメッセージが熱く語られているようにも思えた。
私も含め、「正統」という言葉に何かうさんくささを覚えていた者たちにとって、著者が歴史的にひもとく「正統」の形成過程は、大きな衝撃をもって受け止められることになろう。キリスト教の歴史において、正統と異端は常に意識されることになる。単純に「正統からはみ出たものが異端」と神学校では教えられる。そして教理的な相違を列挙し、正統からいかに異なっているか、を示すことで私たちは「異端」というレッテルをその集団、教派に貼り続けてきた。
しかし歴史神学などを専門とする者からすると、それは「正統と主張する者たちが、自分たちと意見を異にする者たちを『異端』と宣告することで異端を生み出した」と捉えざるを得ない。それは直線的な歴史観においては正しい理解だといえよう。だが、本書はそのような視点をも踏まえた上で、「正統と異端」を重層的に解説しているため、従来の「正統」観がかなり限定的な理解であったことを思い知らされた。
本書の肝は、次の言葉であろうと私は考える。
正統が規範や原理や教義から作り出されることはない。初代教会の歴史を振り返ってみると、正統は正典や教義によって作られたのではなく、逆に正典も教義も正統によって作られたことがわかる。というより、正統はそもそも「作られる」ものではなく、おのずからして存在するものである。正統を「作られたもの」と考えている限り、正統の本来的な在処を突き止めることはできない。(116ページ)
本書前半は、丸山氏の「正統論」に続いて、「どうやって正統は規定されるのか」という問題を取り上げる。「正典」が正統を作るのか(第2章)、「教義」が正統を定めるのか(第3章)、「聖職者たち」が正統を担うのか(第4章)、という考察を加える中で、実は私たちがいつしかアプリオリに捉えてしまっていた「正統」観を覆していく。その結果が、上記にまとめられた言葉となる。
後半(第5章〜6章)は、正統に対する「異端」の在り様を克明に記している。つまり正統とは対極に位置するという意味での「異端」の在り方を開示しているということである。例えていうなら、存在論と認識論の相違である。
あらかじめ存在論的に正統であったものだけが、教義により認識論的にも正統と認められる、ということである。つまり、正統は存在論の領域にある。教義を正統の根拠とすることは、認識論的な理解の偏重である。(117ページ)
ということは、異端とは、正統に戦いを挑むべく徹底的に「認識論」から始まることになる。そして「『異端』のうちのあるものは『異教』へと成長し発展を遂げるが、あるものはそのまま歴史の彼方(かなた)へと消えてゆく」(135ページ)ことになり、新しい宗教が自己確立を遂げた段階で、「そこに新たな『正統』が成立し、今度はその中でまた正統と異端のせめぎ合いが始まる。歴史はこの繰り返し」(同)ということになる。
だが本書はこれにとどまらない。なぜならここで生み出された「異端」とは、「正統」に並び立つ存在として位置付けられるからである。現代は、このような意味での「異端」が存在しない、と著者は嘆く。森本氏の言葉では「現代には、非正統はあるが異端はない」(239ページ)ということになる。「現在の正統を襲ってこれに成り代わろうとする異端(中略)だけが真の異端」(同)だからである。
終章第4項の表題は、著者の嘆きを感じられる。「真正の異端を求めて」がそれである。私たちは終章に至って、著者が本書を書いた意図に気付かされる。それは、民主主義の浸透により、万民平等で個性を重視する社会となりつつある現代の病理といってもいいかもしれない。
現代人は、今まで存在していた「正統」に対して異を唱え、その論理的矛盾を指摘することに自らの存在意義を見いだしているのではないか。攻撃対象である「正統」に自らが取って代わったり、代替可能な「新しいもの」を構築しようとしたりする意欲に乏しいまま、「なんちゃって異端」になることで満足していないか、ということである。
本書は、「正統」の正統性を擁護する目的で書かれたものではない。それならば復古主義的なファンダメンタリズムが吹き荒れた20世紀初頭の米国キリスト教界と何ら変わりないことになってしまう。そうではなく、本書は約100年前に犯した誤ち(ファンダメンタリズム論争)を繰り返すことなく、歴史的・神学的な現代性をきちんと押さえつつ、来るべき未来に対して開かれた挑戦を促す目的で書かれているといっていいだろう。
著者は本気で「異端」が生まれることを願っていると思われる。やはり時代が進むにつれ、どうしても「正統」には時代とそぐわないところが露呈されていく。もしもそこに悪しきものが存在するなら、それを単に指摘するだけでなく、それに代わる存在とならんとする意欲と気概を持った「別の存在=異端」の到来を願っているといえよう。
本書は著者の次の言葉で締めくくられている。
日本に真正の異端が生まれ、その中から腹の据わった新たな正統が生まれることを願いつつ、筆を擱(お)く。(254ページ)
私もこの言葉を胸に刻み、一歩踏み出す勇気を出したいと思わされた。今読むべき1冊であることは間違いない。
■ 森本あんり著『異端の時代―正統のかたちを求めて 」(岩波新書 / 岩波書店、2018年8月)
◇