昨年12月に刊行された「聖書協会共同訳」の発行記念特別講演会が23日、上智大学(東京都千代田区)で開催され、約500人が参加した。同訳で採用された「スコポス理論」の提唱者として知られるオランダ・アムステルダム自由大学教授のローレンス・デ・ヴリース氏が「神の言葉と今を生きる私たち―なぜ聖書を翻訳し続けるのか」と題して講演した。またその応答として、上智大学神学部特任教授で立教大学名誉教授の月本昭男氏が「聖書翻訳と現代―『聖書協会共同訳』によせて」と題して語った。
日本ではこれまで、日本聖書協会やその前身が主となって出版した聖書だけでも、「明治元訳」(1887年)、「大正改訳」(1917年)、「口語訳」(55年)、「新共同訳」(87年)、そして昨年の「聖書協会共同訳」と、定期的に新しい翻訳の聖書が出版されてきた。キリスト教では、なぜこのように聖典である聖書の翻訳を繰り返すのか。ヴリース氏は講演で、歴史的、現代的、神学的の3つの観点から語った。
歴史的観点―ユダヤ教の伝統を継承した「翻訳の宗教」として
ヴリース氏によると、ユダヤ教における聖書の翻訳は、紀元前6世紀のバビロニア捕囚期に初めて現れる。新バビロニア帝国に征服され、異国の地へ強制移住させられたユダヤ人たちの多くは、現地の共通語であったアラム語を話すようになる。そのため、ヘブライ語で書かれた聖書をシナゴーグで朗読するとき、アラム語へ通訳する必要があったのだ。このアラム語による口頭の通訳または解説は「タルグム」と呼ばれ、後に書き留められるようになる。だがこのアラム語訳は、あくまでもヘブライ語の代用であり、一部の地域を除いては、聖典としての権威は持たなかったという。
しかし、アレクサンドロス大王が巨大な帝国を築き、ギリシャ語が広く用いられる紀元前3世紀以降になると、今度はギリシャ語への翻訳が始まる。そして、このギリシャ語訳聖書はかなりの権威を持つようになる。実際、多くがユダヤ人であった初期のキリスト教徒が旧約聖書を引用する場合、多くはヘブライ語聖書からではなく、ギリシャ語訳聖書から引用したという。当時のユダヤ教共同体が、ギリシャ語に翻訳された聖書であっても、それを「神の言葉」として受け入れていたのと同じように、キリスト教共同体はその誕生から、翻訳された聖書を聖典として認め、用いていたのだ。

ユダヤ教ではその後、紀元70年にエルサレムが陥落してからは、典礼の中心が神殿での犠牲祭儀からテキスト、すなわちヘブライ語で書かれた巻物(旧約聖書)に変わる。そしてまた、ギリシャ語訳聖書を用いたキリスト教への対抗心もあり、「神の言葉=ヘブライ語で書かれた巻物の聖書のみ」という排他的思想が強くなる。だがそれ以前のユダヤ教には、翻訳された聖書であっても「神の言葉」として受け入れる伝統があり、その根底には「神の言葉は特定の言語にしばられない」という考えがあった。ヴリース氏は、キリスト教はこうしたユダヤ教が本来持っていた「豊かな翻訳の伝統」を継承したと言い、それが後のラテン語訳聖書「ウルガタ」や、英語訳聖書「欽定訳」の登場にもつながっていると説明した。
現代的観点―聖書翻訳には賞味期限がある
一方、聖書を教会や日常生活、社会の中で用いることを考えるとき、その定期的な翻訳の必要性が浮かび上がってくる。なぜなら言語は常に変化し、また聖書の釈義に関する知見や、翻訳の元となる底本も時代によって変わってくるからだ。さらに翻訳に関わる技術の発展もある。そのため「聖書翻訳には、スーパーの棚に並ぶ食品と同じように賞味期限がある」とヴリース氏は言う。
そして、こうした継続的な翻訳の努力の背後には、神の言葉の「現実化」という強い欲求がある。「すなわち、神の言葉を、新たな状況に生きる新しい世代の人々のために、明瞭で、現実的かつ有意味なものにしたいという欲求です」とヴリース氏は説明する。

神学的観点―受肉としての聖書翻訳
この「現実化」について、ヴリース氏は「受肉」という言葉を用いて神学的観点から考察した。キリスト教において聖書が持つ目的は、「肉体を持たれた(受肉した)神の言葉(ロゴス)」であるイエス・キリストを証しすることであり、あらゆる言語と世界にこのロゴスをもたらすことだ。「ロゴスは、外国の服を着て、外国語を話す、遠くから来た見知らぬ旅人として人々を訪れたのではありません。むしろ、ユダヤ人のためにはユダヤ人になり、ギリシャ人のためにはギリシャ人となり、日本人のためには日本人となられたのです」とヴリース氏。翻訳とは、変わりゆく、そして多様な言語や文化の内にロゴスを受肉させることだと語った。
一方で、こうした「翻訳とは受肉」という視点から、特定の聖書翻訳のみを神聖化することに対しては警鐘を鳴らした。「特定の聖書翻訳の神聖化は、時代が経つにつれて翻訳の理解をますます困難にし、次の世代の人々の心と生活の中に神の言葉を現実化し、受肉させることを阻みます」。その上で、神の言葉は一つの言語や一つの「聖なる翻訳」にしばられないとし、「私のオランダ語や、皆さんの日本語をはじめとした、数百の言語によって救いのメッセージを宣(の)べながら、神の言葉を世の果てにまでもたらすことが私たちの務めです」と述べ、講演を閉じた。
「聖書協会共同訳」では実際にどう訳が変わったのか
続いて、ヴリース氏の講演への応答として語った月本氏は、「聖書協会共同訳」の翻訳では旧約の編集委員として重要な役割を担った。応答ではヴリース氏の講演を評価しつつ、主に「聖書協会共同訳」でどのように訳が変わったかを紹介し、それに対する自らの見解を語った。
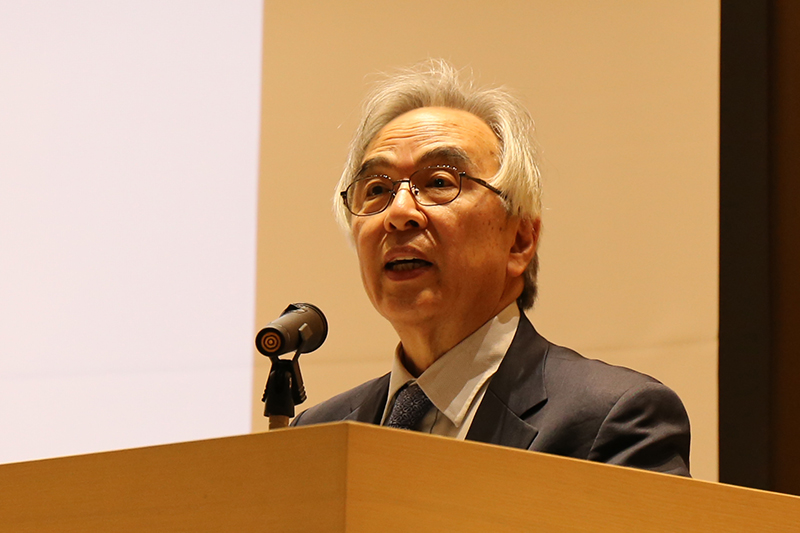
月本氏が一例として最初に挙げたのは雅歌1章5節。他の日本語訳聖書では「私は黒いけれども美しい(愛らしい)」などと訳されている箇所だ。しかし、「聖書協会共同訳」では「私は黒くて愛らしい」とした。原文では「黒い」と「美しい」は「ウェ」というヘブライ語の連結詞で結ばれているが、この連結詞は通常、「~と~」や「そして」など順接で訳される。だが、文脈によっては「しかし」「だが」などと逆接にも訳せる言葉だという。そのため、文法的には「私は黒いけれども美しい」「私は黒くて美しい」のいずれの訳も可能だ。しかし前者の場合は、根底に「肌は白い方が美しい」という価値観が潜んでいる。そのため、今回の訳に変更したという。
エレミヤ書6章13節などに出てくる「身分の低い者から高い者に至るまで」という箇所は、「小さな者から大きな者に至るまで」に変更した。ここは原文を直訳すると「彼らの小さい者から彼らの大きい者まで」となる箇所で、「身分」という語を最初に導入したのは「新改訳」だったという。「新共同訳」でもそれが踏襲されることになるが、人間の内面に眼差しを向けた預言者であったエレミヤが、果たして「身分」という視点のみに限定して社会を見ていたかと疑問視したという。そのため、曖昧さは残るものの従来の訳に戻すことにした。
この他、自然災害に対する解釈と関わってくる聖書箇所として、創世記8章21節は、「新共同訳」では「人に『対して』大地を呪うことは二度とすまい」と訳されていたが、「人の『ゆえに』地を呪うことはもう二度としない」と従来からの訳に戻した。自然が人間の罪や悪の故に滅びに瀕するということが、預言書には繰り返し記されているためだ。また女性に関する訳語では、「新共同訳」には「はらみの苦しみ」「お前は男を求め」(創世記3章16節)など、男尊女卑の価値観に基づく不適切な表現があったが、多くは改善されたという。
こうした改善点を挙げる一方、月本氏はさらなる改善が必要な箇所として幾つかの例を挙げた。エゼキエル書4章2節などに出てくる「破城槌(はじょうつい)」は、城壁を崩すための兵器だが、雄羊の姿に似ていたため、原語では雄羊を意味する「カル」が用いられている。このカルは、その「角」に当たる部分を、城壁の石やれんがの間に差し込むことで崩すもので、訳語に「槌」を入れることは必ずしも正しくないという。また、同16章10節に出てくる「メシー」は伝統的に「絹」という訳語が当てられてきた。しかし当時のイスラエルに絹が存在したとは考えづらく、「聖書協会共同訳」では「高価な衣服」と訳し変えられた。月本氏は「絹→衣服」の変更については評価するものの、それに「高価な」と付けたことで、値段で物の価値を計る資本主義的発想が忍び込んでしまったと指摘した。

翻訳の完成で終わらず、神の言葉を生きることへ
ヴリース、月本の両氏の後、最後には上智大学神学部長の川中仁氏が、まとめの言葉を語った。川中氏は、翻訳とは本質的にある時代における一つの試みにすぎないとし、「いかなる聖書翻訳にも、そこには避けがたい誤りがあり得るし、時代と共に古びて廃れていく」と指摘。だがそれは「今この時に、全力を尽くして、聖書の翻訳を通して、神の呼び掛けに応えようとすること」だと言い、その意義を強調した。
その上で「私たちは、受肉した神の言葉を生きるということ、自らの存在において、また生き方を通して、神の言葉を受肉させることへと招かれている。新しい翻訳を完成したことに満足するのではなく、神の言葉を生きることへとつなげていかなければならない。この課題に全力に取り組み、まっとうしたとき、真の意味で新しい聖書翻訳を完成させたということができるのではないか」と語った。
講演会前日の22日には、日本基督教団銀座教会で「聖書協会共同訳」の奉献式を兼ねた別の講演会も行われた。日本聖書協会によると、22、23両日の講演内容は後日、書籍化される予定。



































