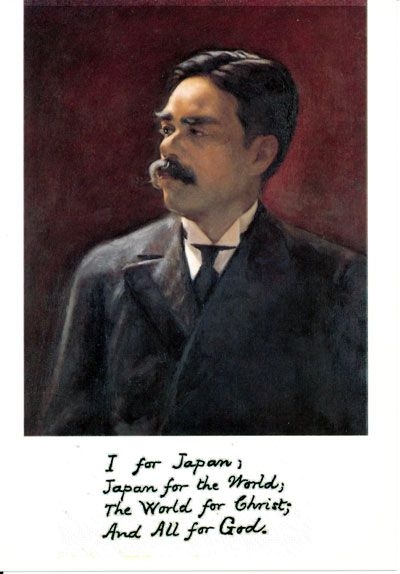9月28日、札幌農学振興会東京支部と北海道大学獣医学部同窓会関東支部の共催による講演会が学士会館(東京都千代田区)で行われ、元恵泉女学園短期大学学長で今井館教友会理事の大山綱夫氏が「内村鑑三と自然」と題した講演を行った。
大山氏はキリスト者としての内村鑑三の思想について、他のキリスト教思想家と異なる点について、「科学と信仰」を自然観の両輪として捉えており、自然に対する深い感性と畏怖の念を持っていたことを指摘した。また内村は教育勅語が施行された際、教育勅語に十分な敬礼をせず、日露戦争においては非戦論を唱えたことが現在の高等学校歴史教科書に掲載されており、個人として歴史にどうかかわっていくかを中心的に考えていた点も特徴のひとつとして挙げた。
内村の生きていた当時の日本社会においては、英語によって海外に発信することができる3人の優れた英文家のひとりでもあり、当時の西洋社会と日本社会をつなぐ大きな役割を果たした人物のひとりでもある。
大山氏は内村が他のキリスト教思想家と異なる点として、「自然を非常に身近なところで捉えており、自然を宇宙というところまで広げ、非常に大きなスケールで考えていた。それを描き出す内村の文章の特色は知的であり、敬虔であり、雄渾であると思う。一読するとハッとする力強さがあるのが内村の文章である」と伝えた。
内村の宗教観と自然観について、内村の息子である内村裕之は、「彼が札幌農学校で自然科学(水産学)を修めたことにもよるが、また天成のものでもあった。そしてこれが彼の宗教を乾燥した律法的なものよりも、より純朴なものとし、何びとの心にも訴えるものとしたのではあるまいか」と記していることを紹介した。
札幌農学校第一期生の強烈な伝道によってキリスト教徒となった内村の途方もない強い自然への感動を表す感性について、大山氏は「内村の宗教観と密接につながっている。内村の自然への関心を問うには、キリスト教信仰は絶対に落としてはならないものである。自然科学とキリスト教信仰を車の両輪として、内村の自然への発見が展開されていった」と伝えた。
内村の自然観を培った札幌の天然
内村が札幌農学校に在学していた当時の札幌は、現在では想像もつかない原始的な平野の中に置かれていた。内村は札幌において自身を薫陶してくれた教師は「人ではなく生けるそのままの天然であった」と著作の中で記している。
大山氏は内村鑑三全集の中で、「天然」という言葉が1033回、「自然」という言葉が539回も使用されていることを指摘し、内村が両方の言葉を同義で使用しているものの、「天然」という言葉をより好んでいたことを伝え、その理由として内村の自然観の中にある自然は「神の創造物」であるという考えがあるのではないかと伝えた。
札幌農学校を首席で卒業した内村について、大山氏は「卒業後内村は開拓使に就職した。どういう理由かわからないが、札幌農学校の教員にはなれなかった。水産学の分野でもしっかりとした調査研究をしており、もし内村がキリスト教伝道の道を選ばず、水産学の道を選んでいたなら、植物学における宮部金吾のように、水産学における天才的な学者に成り得たことを想像するに十分な業績を若いうちに上げていたのではないか」と伝えた。
内村は水産学研究としてアワビの研究をしており、アワビの卵子を顕微鏡で発見したことによる自然の秩序の発見に感動し、神に感謝の祈祷を捧げている。大山氏は若き日の内村の自然観について、「キリスト教徒になって解し得た神の創造の意図への感動と感謝を露わにしていた感性豊かな若い内村の姿が見られる」と述べた。内村が作成した「日本魚類目録」は、日本人の手による最初の本格的な日本産魚類の目録となっている。
科学と信仰、「二元論」の宮部、両輪として捉えた内村
また大山氏は内村がキリスト教伝道の道を歩む覚悟をしたアメリカ留学中に、同じくアメリカに留学していた宮部金吾との興味深いやりとりとして、宮部が留学中のハーバード大学研究室を訪れた内村が、「君ならば顕微鏡の下にヒューマニティを認めることができるだろうな」と問いかけたのに対し、宮部は無造作に「そんなものは見えない」と答えたエピソードを紹介した。
当時内村はアメリカに留学し、キリスト教の人格者に啓発されキリスト教伝道の道を歩む覚悟をしていたのに対し、宮部は科学者の道を歩んでいた。大山氏は、宗教熱が絶頂に達していた当時の内村と神の摂理を信じていた宮部の双方において互いの立場を理解する土壌があったものの、「宮部は自然科学と信仰とは別物であると二元論的に考えていた一方、内村はキリスト教と学問を切り離しては考えることができなかった。そういう思考をしていた人物であり、内村はキリスト教信仰と自然科学は車の両輪と考えていた」と説明した。また大山氏は、内村の書く自然に関する文章は、キリスト教観が入れられているのが特徴であると指摘した。
内村の自然観に変化をもたらした「足尾銅山事件」
自然に対する感動や賛美、感謝の念を伝えていた内村の自然観について、大山氏は「足尾銅山事件」および札幌開墾における石狩川の荒廃が生じたことを通して、変化が見られるようになったことを指摘した。
足尾銅山事件において内村は「最も耐へ難き災は天の下せし災いにあらずして人の為せし災いなり、天為的災害は避け得べからず、人為的災害は避け得べし、而して鉱毒の災害は後者に属し、その最も悲惨なるものなり」と記している。また札幌の開墾における治水工事においては、内村は石狩川を「旧友」と称し、人類は神の「良友」と称した上で「神を畏れず天然を愛せずして為した開拓はこんなものである。旧友石狩河に対し同情なき能はずである。船を雇い河流を横断する事二回、憤慨に充ちて家に帰った-石狩の河を渡りて知りにけり、蝦夷は開けて殺されにけり」と日記の中で記している。
これらの事件を通して大山氏は「内村の自然観は人間の歴史と信仰が連動する形で、信仰に大きな変化を遂げざるを得なかった」と指摘した。
自然を友達と見なし、神の良友である人間が自然を壊す事件を経験するようになって後、「自然をどう考えるか」に関する新しい見方が、この頃から内村の中に生まれるようになったと説明した。またこれらの事件や第一次世界大戦が生じる中にあって、1912年には愛娘のルツ子を病で失っており、これらの経験を通して内村は人間の力ではどうしようもならないことがあることを知り、「今の時代や生を超えるものに視点を向け始めるようになった」ことを説明した。