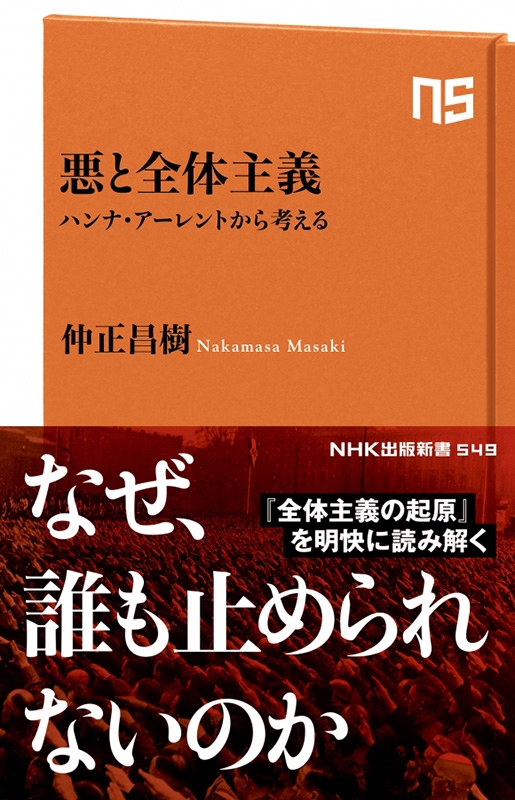悪とは人間離れした異常性ではない。私たちの傍らにあり、知らず知らずに誘惑されるもの。
6月に入って以来、暗いニュースが続く。例えば5歳の女の子が虐待死させられた事件。親は「指導」の一環と称して「ゆるしてください。もうしません」と女の子に反省文を書かせていた。この異様な親子関係に人々は震撼(しんかん)し、「どうして事件を防げなかったのか」と嘆き、「何てひどい親なのか」とやり場のない怒りが逮捕された両親へ向けられた。
また、新幹線の中で鉈(なた)を振り回し、無差別に人々を殺傷した事件が発生した。犯人の生い立ちや先天的な障がい(その判断には賛否ある)、そして歪んだ家族関係がクローズアップされた。ここでも「こんな事件を引き起こした犯人がどうして生み出されたのか」が問題となり、犯人の「心の闇」や環境の異常性が取り沙汰されている。
私たちはこのような事件に遭遇すると、有形無形を問わず、そこに「悪」の存在を見いだす。だがこのような「悪」は、私たちとはまったく隔絶されたところからやってくるのだろうか。マーベル映画などのスーパーヒーロー物で描かれているように、宇宙の果てから飛来して私たちの平和な暮らしを攻撃するように、私たちの外部から侵入してくる「異物」なのだろうか。
本書はそのような類の「悪」とはまったく異質な、そしてもっとリアリティーある悪の生成解釈について述べている。
著者の仲正昌樹氏は、ドイツの哲学者ハンナ・アーレントの『全体主義の起原(源ではない)』『エルサレムのアイヒマン』を基にして、社会の中に生み出される「悪」の一側面を鋭くえぐり出している。本書は単なるアーレント解説本の域を越え、最後には21世紀の社会状況下で生きる私たちへの問い掛けともなっている。
本書で語られる「悪」は、神の存在を知り真理に生きていると信じている私たちキリスト者をも決して例外としない。だからこそ取り上げる必要があるし、これをきっかけに語り合うことができよう。
第1章では、アーレントがこのような思索を深める直接的なきっかけとなった欧州における「反ユダヤ主義」の起源をたどっている。彼女がユダヤ人であったため、これは単なる人種と民族をめぐる歴史的な問題であるのみならず、彼女のアイデンティティーの根幹を問う問題であったようだ。
第2章から3章にかけて、ホロコーストへ突き進んでいったドイツを例に挙げながら、帝国主義がどうして「人種」思想を生み出すに至ったかを分かりやすく解説している。その成れの果てに「全体主義」が生み出される。これは近世から近代、そして20世紀に至る大きな歴史の流れの中で醸成されてきたという意味で、現在の私たちと決して無縁ではない。
むしろ現在の「トランプ現象」や「分断化傾向」という目に見える動向の変化は「氷山の一角」であって、その背景となって積み上げられてきたものは、その幾倍もあることが分かる。同時に、私たち個人における「甘さ」や「いいかげんさ」にも通じるものであるだけに、読み進めていくうちに、決して穏やかな気分ではいられなくなる(少なくとも私はそうだった)。
冒頭で取り上げた「暗い事件」の要因に、個々人の資質や性格のみならず、積み上げられた歴史の最先端に展開している「現代社会」の指向性があることに気付かされることになる。ここに至り、本書は「私たち」のことを描いていることが判明する仕掛けとなっている。
第4章では、ユダヤ人大虐殺を直接的に指揮したアドルフ・アイヒマンの裁判の様子を描く。アーレントはエルサレムで行われたこの裁判を特派員として傍聴し、どうしてホロコーストはなされたのか、どんなメンタリティーがこれほどの「悪」を行わせたのか、について真相を探ろうとしたのである。
しかしその結果は、大衆(特にユダヤ人たち)が求めていた「悪」の定義とはまったく異なるものであった。当初は彼女の趣旨がよく理解されず、期待にそぐわない論を展開したとして、アーレント自身にも非難の声が上がったが、著者の仲正氏はその後の時代を踏まえて、終章「『人間』であるために」へとつなげていく。
そこで投げ掛けられているのは、「分かりやすさ」の罠(わな)である。一見、物事は分かりやすい方がいいと思われる。しかしその「分かりやすさ」が人に与えるのは「何も考えないで、言われたとおりにすれば万事OK」という「思考停止状態」である。
人が苦しみや悲しみ、そしてやり場のない怒りを抱えてしまうとき、それをいつまでも持ち続けることができず、「最も分かりやすい理論・方法」に身を委ねてしまうことになる。アーレントは、そして著者はそのような人間の在り方に注意を促しているのである。
しかし、これは難しいことだ。例えば上述の幼児虐待にせよ、新幹線での殺傷事件にせよ、虐待した親や鉈を振り回した犯人の心情は、もしかしたら私たちだって陥るかもしれない誘惑である。また、そういった事件を目にして「真の原因」をジャーナリスティックに探ろうとするのが私たち「大衆」である。
勢い「何てひどい親だ!理解できない犯人だ!」と、宇宙から飛来した異星人のごとき異質な存在へ彼らを追いやることで、自分とは縁もゆかりもない存在へ貶めてしまうことになる。この思考もまた「悪」へ通じる第一歩だということを、アーレントは指摘したのである。彼女へのいわれなき非難や悪意を向けた人々の存在が、彼女の主張を皮肉にも裏付けてしまうこととなった。
また、これは「キリスト教保守派」といわれるキリスト者とも親和性が高い。明朗闊達(かったつ)な善悪二元論で世界を見たいと願うことは悪いことではない。しかしその基準を聖書に置くとしながら、その中の「分かりやすい箇所」だけを抜き出し、そこからすべての聖書記述を読み込んでしまうことはないだろうか。また「あの牧師先生が言うことだから」とその主張を丸のみし、いかにも自分が真理の代弁者のごとくにふるまってしまうことはないだろか。
そのようなキリスト者、また牧師の一人として、私の心に本書は大きな刺激と警告を与えてくれた。
私たちは一哲学者の思想を受け入れる必要はない。しかし彼女が詳(つまび)らかにした悪の構造の一側面を前に、しばしキリスト者として沈思黙考する必要はあるのではないだろうか。私たち個人の魂を救済する福音は、社会全体に対してもより有効に働くものであるはずだ。そうであるなら、本書によってマクロな視点で悪を捉えることは、翻って私的な領域に忍び寄る悪の別形態をきちんと監視し、チェックすることにもつながるからである
■ 仲正昌樹著『悪と全体主義 ハンナ・アーレントから考える』(NHK出版、2018年4月)
◇