日本キリスト教教育学会の第28回学会大会が24、25の両日、明治学院大学(東京都港区)で開催された。大きく時代状況が変動する中、キリスト教教育の在り方と、教職者に託されている使命を新たに問い、現代の子どもたち、若者たちに対する理解をより一層深め、課題を共有し、互いに学び合う時を持った。
大会1日目は、実際にキリスト教主義の学校や教育機関、教会で教育を受けてきた若者たちに話を聴くフォーラムが開かれた。3人の学生が、これまで受けてきたキリスト教教育について、自分たちの行動とどう関わり、どのような意味を持っているかを語った。
2日目のシンポジウムは、1日目のフォーラムで出された学生たちの声を受けて行われた。シンポジウムには、明治学院高校副校長の田丸修氏、日本キリスト教協議会(NCC)教育部総主事の比企敦子氏、明治学院大学副学長で同大会委員長の永野茂洋氏、同志社大学教授の原誠氏が発題者として登壇した。
最初に発題した田丸氏は、自身の人生を大きく変えた最大の出来事が、キリスト教学校で絶対者の存在を告げられたことだったと話し、自分自身が経験してきたキリスト教学校の人格教育について語った。中学から大学までキリスト教学校に通った田丸氏は、「自分は愛されている存在なんだ」と知ることが、競争社会の中でどれだけ大事なことかを話した。
その上で、キリスト教教育が直面する2つの課題について述べた。1つは、生徒を取り巻く家族・家庭といった内側からの問題。もう1つは、世論や政治の教育への介入など外側からの問題だ。田丸氏は、「キリスト教教育は、キリスト教学校だけでなく、教会、社会団体、さまざまなところで行われている。そうなると、キリスト教教育とキリスト教学校はどこに線が引かれるかのか」と、キリスト教教育の境界線のあいまいさについても言及した。
さらに、あるキリスト教学校ではクリスチャンの教員が1人しかいないことを明かし、キリスト教教育を誰が担うべきかと問い掛けた。田丸氏は、キリスト教に関することは、クリスチャンの教員から聞いたことしか残っていないと話す一方で、クリスチャンの教員でも心に残らないことがあるとし、クリスチャンだからといって全員がキリスト教教育ができるとは限らないと話した。

比企氏は、2校のキリスト教学校(中高)、全国キリスト教学校法人人権教育研究協議会、NCC教育部での経験から発題した。初めに、NCC教育部で体験してきたエキュメニカルな活動について話し、これまで参加してきた「マイノリティ問題と宣教」国際会議やアジアキリスト協議会(CCA)、東日本大震災国際神学シンポジウムで、国や民族、宗教を超えて、さまざまな活動が行われていることを紹介した。その上で、キリスト教学校がエキュメニカルな視点に立っているかを問い掛けた。
「エキュメニカルというのは、デノミネーション(教派)の違いというだけではなく、もっと広いものだと今は捉えている」と述べ、「人は生涯において、どこで信仰告白をするか分からない。私は、教派間の多様性や違いを認め合いつつ、他宗教への理解を促し、共感を得られる姿勢や活動を示していくことが、キリスト教学校でも必要だと思っている」と話した。これまでの活動を通して、他の宗教を認めなければ、宣教はできないことを知ったとも語り、エキュメニカルな視点をキリスト教教育の中で伝えていくことの重要性を強調した。
続いて、キリスト教教育としての人権教育、また人権の重要性に対する認識が、生徒や学生、教職員、保護者に十分に行き届いているのかを問い掛けた。比企氏は、「社会にある問題は教室にもある」と言い、「教師はマイノリティーの生徒が自分の教室にもいるだろうという意識を持って言葉を発すことが大切」と、マイノリティーの存在の受容と対応について話した。さらに「知らない人権は守れない」と力を込め、「表面的なことだけを見ていては、子どもや若者の人権は守ることはできない」「人権へのセンスは留まるところがないくらい磨かなければならない」と訴えた。
大学の教育現場での経験から発題した永野氏は、「ザラザラした人間関係の中にわれわれはいるはずなのに、コーティングされた日常生活を送っている」と話し、学生だけでなく、教員も既に「コーティング」の中に入っているのではないかと指摘した。コーティング剥がしの一つとして、明治学院大学が1995年に発行した戦責告白書『心に刻む』を紹介。その中で、戦時中の教員が、今では過ちとされる行為を日常の普通のこととして行っていたことなどを挙げ、「後になって間違いに気付く」ことのないよう、この告白をし続けていかなければならないと伝えた。
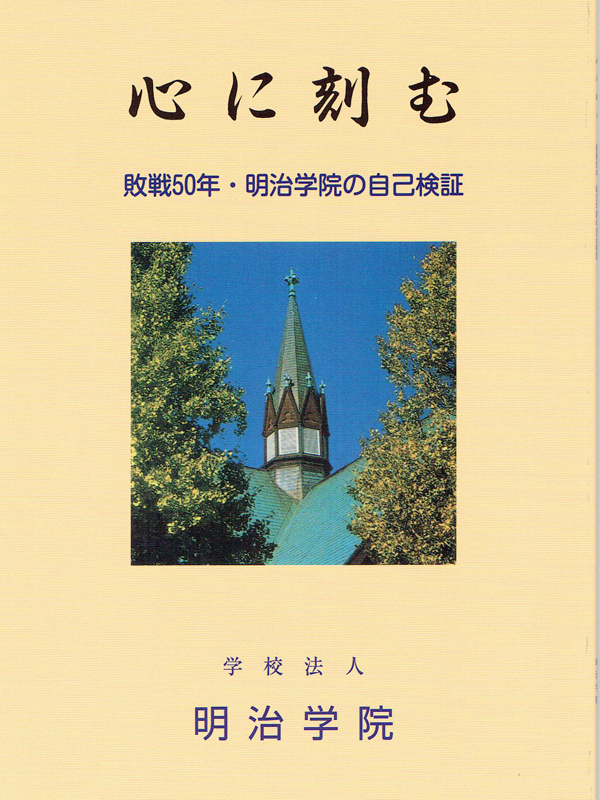
また、コーティングされた中では、学生の現実問題に触れることはできず、キリスト教的教育も表面的な教育で終わってしまうと話した。永野氏は、聖書の「善きサマリア人の教え」を引用し、学生たちの多くが「愛する隣人」の姿が分からないことや、たとえ分かっていたとしても、重荷が負いきれないと考え、イエス・キリストのストレートな教えにコーティングをかけてしまうと話した。そして、「私たちが、キリスト教学校で苦労するのは、そのコーティングを剥がすこと」だと語った。
「隣人のために自分を使ってもらおうと決意する人間を通して、神はこの世を動かしているならば、日本のキリスト教教育は危機的状況だと思う」と言い、「神が動かそうと思っている歴史に、コミットできない状態に向かっているのではないかと恐れを感じる」と話した。さらに、「この歴史をどうするつもりなのか。世界中で貧富の格差が大きくなっていく中で、日本は貧しい国にとって隣人はおろか『追剝ぎ』になっているのではないか。歴史への責任に向かう努力をしないといけない」と訴えた。
日本のプロテスタント史が専門の原氏は、同学会のいわば第三者的な立場で発題を行った。初めに、「キリスト教教育学会の主要な課題が、学校そのものなのか、キリスト教学校の教育の枠の中でのものなのか、あるいは教会での課題なのかよく分からないことがあった」と率直に述べた。また、前日のフォーラムの感想として、世代による違いを感じたとしながらも、「新しい動きが若い人たちの間で起こっており、可能性を感じる出来事が進行していることに共鳴する」と語った。
原氏は、宣教師によって建てられたキリスト教学校が、教育だけでなく、慈善や福祉といったこれまで日本では不要とされていたプログラムも負っていたことを話し、「こういった歴史的な展開の中で、キリスト教学校と教会は、『宣教』という広い包括的概念の中で捉えられ、そこに伝道があり、教育があり、奉仕があったことを認識し、教会と学校が別物ではないルーツを持っているという自覚が大事だろう」と語った。その上で、キリスト教学校の本質が『奉仕』として位置付けられると語った。
また原氏は、戦前の日本の近代化から始まり、戦後の民主主義に至るまで、日本は外圧でしか変わってこなかったと話し、現代のキリスト教学校の立場について話した。その中で、奉仕の概念、キリスト教のツールとしてのキリスト教学校は健在だが、信徒を増やし、地域の教会へ送り出す役割は既に果たせなくなっていると指摘。「キリスト教学校も一般の私立学校同様に、進学や就職ランキングから自由でなくなっている今、伝えるべき根本の価値観が何かが問われている」と語った。
これらのことを踏まえ、原氏は自身が学生たちと実践してきたタイでのスタディーツアーをはじめ、沖縄や韓国への訪問について語った。スタディーツアーで培われたことは、第一に「幾つかの目を持つべきこと」だった。それは、日本、欧米、アジアに対しての目と、国際、民際、人際という言葉を作って隣人を見て、「私を隣人としてくれた」という物語を読み取る目だ。第二には、日本のアジアに対する「3つの収奪」。日本が、アジアから利潤・利益だけでなく、知識や経験も収奪しているとし、学生たちがいかにこれをフィードバックさせ、連携し、共生することができるのかが今後大きく問われると話した。
最後に原氏は、クリスチャンの構成比が少ない教育現場では、教育の共同体をつくることが必要だと説いた。クリスチャンの数がかなり少ないキリスト教学校であっても、基本にキリスト教主義を置くことをやめたら「アウト」だとノンクリスチャンの教職員も思っているという。原氏は、そうした教職員が、キリスト教主義を大切にしていく教育の共同体をつくっていくことを提案した。そして、「その根っこには『奉仕・社会貢献』があり、それを大事なものとして提示し続けていくキリスト教学校であればいいのでないか」と語った。
次回の学会大会は、来年6月23~24日に西南学院大学(福岡市)で開催される予定。





































