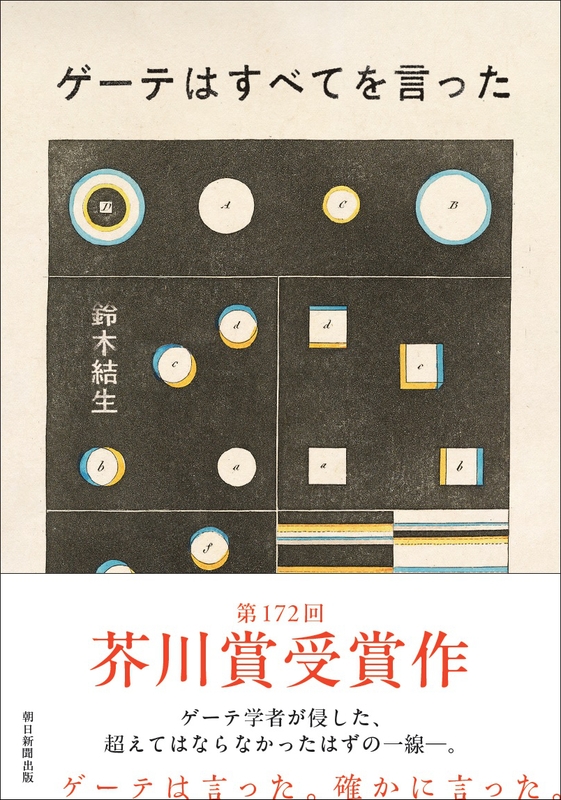本書は、今年1月に第172回芥川龍之介賞を受賞した作品です。著者の鈴木結生(ゆうい)さんは2001年生まれで、現在、西南学院大学大学院に在学中です。日本バプテスト連盟の牧師を父に持ち、幼い頃から聖書に親しんでいたことが報じられており、本書にはその影響が色濃くうかがえます。
小説の本編は、2023年12月5日(火)、つまりこの年のアドベント3日目から、恐らく翌24年4月28日(日)、つまり復活節第5主日の未明までを時間的舞台として書かれています。それぞれの日付は、その間の1月1日に能登半島地震が発生したと記されていることから、私が推測したものです。これが正しいとすると、本書の巻頭言に当たる「端書き」は、その6年後という設定ですから未来のことであり、そこには著者のユーモアを感じます。
登場人物は、国立大学の教授で、ドイツの文豪ゲーテの専門家である博把統一(ひろば・とういち)と、その妻の義子(あきこ)、2人の娘である徳歌(のりか)の3人が中心となっています。それに加えて、義子の実父で、統一にとっては義父であり恩師でもある芸亭學(うんてい・まなぶ)、統一の大学の同僚である然紀典(しかり・のりふみ)、そして統一と然の勤務する大学の学生である紙屋綴喜(かみや・つづき)や、義子の好むユーチューバーであるドイツ人のウェーバー女史が、重要な脇役として登場します。
統一は年に一度、クリスマスイブ礼拝にだけ出席する名ばかりのクリスチャンである一方、芸亭は弟が牧師で、聖書原文を写経するほどの筋金入りのクリスチャンです。義子は出席教会でオルガニストや花の世話をする教会員で、徳歌はその教会の聖歌隊のメンバーと、本書には登場人物たちの信仰的背景が記されています。
本編は、統一と義子の結婚記念日である12月5日に、徳歌が2人をイタリア料理店に連れて行ったことから始まります。その時に飲んだ紅茶のティーバッグのタグの部分に、「Love does not confuse everything, but mixes.(愛はすべてを混淆(こんこう)せず、渾然(こんぜん)となす)」と印字されており、その下に「ゲーテ」とあったのです。ゲーテの言葉ということでしょう。
けれども、ゲーテの専門家である統一は、この言葉を知りませんでした。果たして、ゲーテはそれをどこかに書いているのか、あるいは間違いなのか。この偶然出会った一つの言葉を巡って、縦横に話が展開されていきます。統一は、明くる年の4月28日(執筆者推定日)未明に放送予定であるテレビ番組に出演することになりますが、先行する収録時に、まだ解決のついていないこの「愛はすべてを混淆せず、渾然となす」という言葉を、「ゲーテが言っている」と発言してしまいます。
同時進行で、然の論文捏造(ねつぞう)問題が起こっています。2人の学者にとって、これらは死活問題のはずです。さて結論はどうなるのか。それをここに書いてしまうわけにはいきませんので、実際に本書を読んでお楽しみいただければと思います。
昨今、神学者による数年前の論文捏造問題が再び取り沙汰されていますが、この箇所を読みながら、そのことも考えさせられました。学者による捏造といわれるものは、果たして真の意味の捏造なのでしょうか。このことは、読者一人一人に考えていただきたいところです。
著者は幼い頃から聖書に親しんでいたということで、随所に聖句がちりばめられています。旧約聖書のコヘレトの言葉(伝道者の書)の愛読者である私には、コヘレトの言葉からの引用があったことは、うれしいことでした。また、統一が教会に行く年に一度の時であるクリスマスイブ礼拝の場面も、説教の内容がきちんと考えられており、好感を持ちました。
私は神学校の卒業時にイスラエル旅行に行き、ガリラヤ湖のほとりの店でピーターフィッシュといわれる魚を食べたことがありますが(「ルカ福音書を読む」第9回参照)、統一と義子の2年遅れの新婚旅行先がイスラエルで、そこでピーターフィッシュを食べる様子が記されていたことにも親しみを感じました。私が食べたときにはそうではなかったのですが、本書では、ピーターフィッシュの口の中に、実際にコインがあったとされています。
著者の鈴木さんは、20代前半とまだ若く、今後が楽しみです。また、本書ではゲーテの代表作『ファウスト』が頻繁に取り上げられていますが、恥ずかしながら私はまだ読んだことがありません。こうした古典を「ぜひ読まなければ」と思わせる一冊でもありました。
ただし、ゲーテの著書を読んでいなければ、読みにくいのかと聞かれれば、そうではないと答えたいと思います。しかし、聖書の知識があったために読みやすかった箇所はたくさんありました。それは逆にいえば、聖書をあまり読んでいない人には、聖書を「ぜひ読まなければ」と思わせる一冊でもあるということだと思います。
■ 鈴木結生著『ゲーテはすべてを言った』(朝日新聞出版、2025年1月)
◇