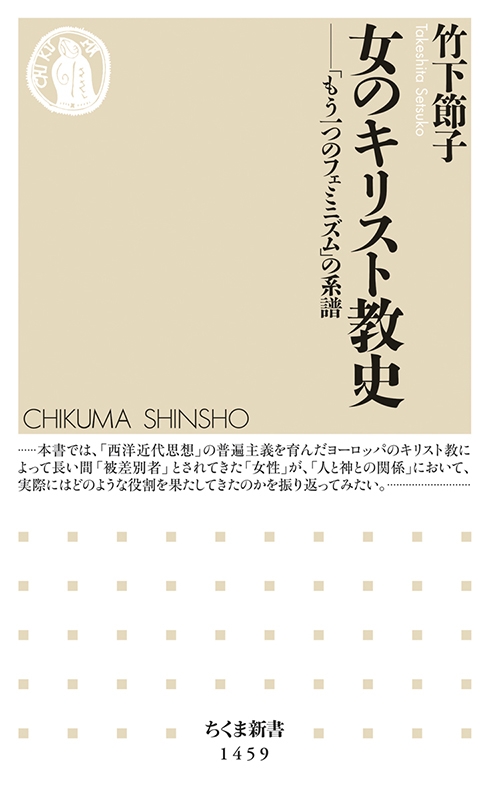性的虐待を告発する「#MeToo(私も)」運動に象徴される、現代の「男女同権」を目指すフェミニズムとは異なり、欧州にはカトリックを起源とする「もう一つのフェミニズム」の水脈があった。本書は、聖書の時代から現代までの長い歴史を精査しながら、キリスト教が女性をどのように扱ってきたのか、また、キリスト教を中心とする世界を女性たちがどのようにリードしてきたのかについて論じている。
筆者は、『ローマ法王』『キリスト教の真実―西洋近代をもたらした宗教思想』などの著書がある比較文化史家の竹下節子氏。序章の最後で、筆者は本書の趣旨をこうまとめている。
「この本は、フェミニズムが大きな問題として取り上げられるようになった今、『神と女』を通して西洋キリスト教史を読み直すものである。日本人の多くは、漠然としたアメリカン・スタンダード以外に、その背景にある『西洋キリスト教文化』の流れと違いが区別できていない。(中略)人類の半分を占める女性を対象とするフェミニズムの分析と考察なしには、覇権国の『白人』による潜在的な人種差別の問題や、国内における経済格差に由来する諸問題を解決することはできない。ひいては、覇権主義による戦争の脅威にも地球環境の破壊にも根本的な対応をすることは難しい」
第2章「イエスの登場」では、ユダヤ人の民族宗教から、救いに地縁血縁の縛りを設けない普遍宗教としてのキリスト教が誕生する過程で、イエスがどのように女性たちと触れ合ったのかに注目する。著者は「カナンの女」や「サマリアの女」とイエスとの出会いを「信仰と救いについての党派性をイエスが踏み越えた出来事」と捉え、それが知恵と信仰を併せ持つ女性の姿を通して描かれていることの意義を論じている。
第4章「聖女の登場」では、新約聖書でイエスに付き従った女性の一人「マグダラのマリア」から現代の聖女マザー・テレサまで、連綿と連なる聖女たちの系譜を概観する。筆者は、イエスの復活という福音を最初に告げたのが女性たちだった事実から、「信仰とは『希望することを信じること』だとすれば、キリスト教を立ち上げさせたのはまさに『婦人たち』だった」と指摘する。さらに、マザー・テレサをはじめとする聖女たちが「弱い人々に徹底的に寄り添うことはキリストを世話すること」というキリスト教の逆説を支える上で重要な役割を担ってきたと論じている。
終章で筆者は、イエスの十字架に象徴されるようにキリスト教が「徹底した弱さと非暴力」によって立つにもかかわらず、西洋キリスト教文化圏の近代文明が女性や弱者を差別するようになった原因とその解決策を論じる。
「『差別』をその一部分だけ取り出して、別の『差別』や『逆差別』で解消するのは意味がない」と筆者は断ずる。提言するのは、区別を「差別」にさせない、共感の関係を育むことのできる「場」を取り戻し、すべての違いや区別を「補完」的なものとすることだ。
「その『場』というのは開かれたもので、キリスト教で言うなら『聖霊』がつなげてくれる場所ということになる。『個』は他の『個』とは区別される唯一独自のものだが、互いに対等にコミュニケーションを取り合うことができる。これはカトリック教会では『コミュニオン(聖徒の交わり)』と呼ばれるもので、そこで出会う他者は、生者と死者の区別も、聖人と信徒の区別もなく、時間も空間も超えた『聖霊の働き』の中で一致することになる」
男性を女性の対立者とみなして「性差」の否定に向かう「フェミニズム」と一線を画すものとして、人類学と人文科学を補完する「フェミノロジー(女性学)」というフランス発祥の学問に言及した上で、筆者はこう結論付ける。
「ある時は『財産』として交換、所有され、ある時は欲望の対象として消費されてきた『女たち』のいる世界は、『神』の居場所ではない。神が人と交わる世界では、聖母や聖女たちへの崇敬、修道女としてリーダーシップを発揮する女たちへの畏敬、そして魔女や悪魔憑(つ)きの女たちへの畏怖が渦巻きながら続いてきた。欲望を『文化』に変える男と女との協働は、そのような世界に生まれ、養われる。神は、フェミニストでは、ない」
■ 竹下節子著『女のキリスト教史―「もう一つのフェミニズム」の系譜』(筑摩書房、2019年12月)