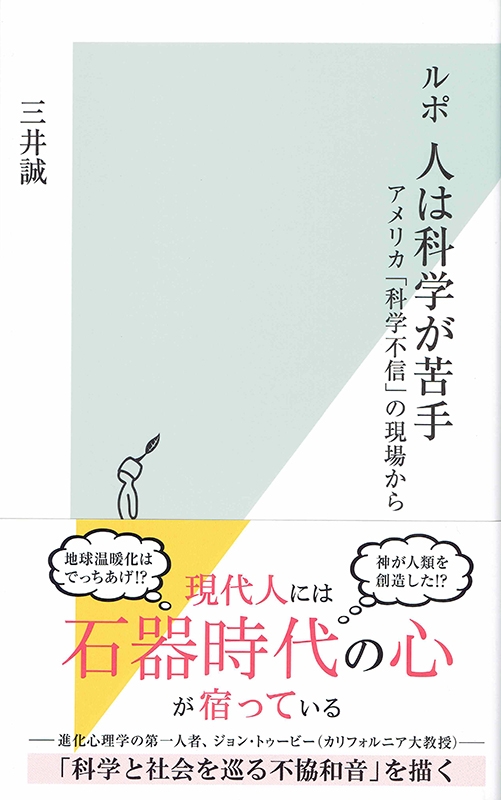著者の三井誠氏は、2015年から18年にかけて、日本の新聞社の米ワシントン特派員として大統領選挙、科学コミュニケーション、NASAの宇宙開発などを取材している。その時に感じた「科学と宗教」の相克を、ルポタージュという形でまとめたのが本書である。
科学大国として名高い米国に引かれた著者が、一方で宗教性に根差した「宗教大国」という米国のもう一つの側面に触れ、ドナルド・トランプ大統領のさまざまな反科学的な発言の源泉をたどるという形式で本書はまとめ上げられている。
一般の読者が興味を持って読めるように「ルポ」という形式を採っているが、根底にあるのは米国文化論であり、さらにマクロな視点から評するなら「米国式キリスト教」の原理主義的な側面をあぶり出しているともいえよう。
三井氏はこのことを、冒頭で次のように述べている。
「取材を繰り返すうちに、人は科学的に考えることがもともと苦手なのではないか、と考えるようになりました。人類が進化の末に獲得した『生きる知恵』と、科学が発達した現代社会に求められる『生きる知恵』には、根本的なずれがあるのではないか、と感じるようになりました。反科学的な姿勢を取るトランプ大統領は、そのずれの底からわき上がってきたのではないかと思えました」
そして、第1章、第2章では、私たちが当たり前のように受け止めている「科学的・理性的=善」という概念を覆す米国の事情を取り上げていく。それは、著者の単なる主観的な考察ではなく、ギャラップ調査の統計や、各々の分野の第一線で活躍している科学者たちへのインタビューから積み上げられた結論であった。
つまり、米国人のみならず人はすべて「見たいものだけ見える」存在であるということ、そして知識のあるなしではなく、「科学的・理性的=善」という偏見を幻想として抱いているにすぎない、ということを喝破するのである。その証左として、「『ノーベル賞学者』というラベル効果」という題で語られたコラムは、強烈な皮肉となっている。
しかし三井氏は、科学的であることと理性的であることを否定しているわけではない。人間がいわゆる「非科学的な存在」だからこそ、科学的であることに意味があるし、また理性的でなければならない側面もあるのだ、ということが訴えたい内容である。
本書が単なる「ルポ」で終わっていないのは、「現状はこんなですよ」と大風呂敷を広げて終わらないことである。第3章で「進化論と創造論」の対立の歴史、「地球温暖化論争」を取り上げた後、科学と宗教が乖離(かいり)しつつある現状をどのように乗り越えていくべきか、その具体的な方策にまで言及している。このことは、大いに評価すべき点であろう。
本書をこの「神学書を読む」のシリーズで取り上げた理由もここにある。私は、そのスタイルこそ異なれど、同じテーマを拙著『アメリカ福音派の歴史』(明石書店、2012年)で世に問うた者である。拙著では、19世紀末から20世紀初頭にかけての「ファンダメンタリズム論争」を取り上げた。19世紀後半に生み出されたリベラル神学に対抗し、聖書を字義通りに捉えることを声高に叫び始めた一派、いわゆる「根本主義者」たちの形成とその後の経過を、1925年のスコープス裁判(学校で進化論を教えることをめぐって争われた裁判)を頂点にして描き出している。これは拙著前半部の大きなトピックスとなっている。
三井氏が取り上げているのは、それから約100年後の世界である。しかし彼が列挙する「反科学的な人々」の特性は、「創造博物館」「実物大のノアの箱舟」「反地球温暖化論」と、そのフォーマットは新たなものに作り変えられているものの、本質においては拙著で取り上げた「根本主義者」のそれとまったく変わっていない。
一方はジャーナリズムの論法に則りルポ形式で、一方は神学的な論法で学術的に。しかしたどり着いた着地点は、両者とも酷似している。そういう意味で、拙著のリブート版のようなイメージで本書を読み進めることができた。
最も感銘を受け、昔も今も変わることのない「科学と宗教の相克」を克服する方法は、第4章第2項以降、「『福音派の科学者』は語る」という項目で語られている視点(209~216ページ)を獲得する以外に、現実的にはあり得ないのだろう。三井氏は次のように述べている。
「それぞれの信仰や価値観を通して相手とつながり、科学を伝えようと試みている。心を通して伝わる知識が静かに、そしてゆっくりと、人々の考え方を変えていくのかもしれない」
この視点は、私たちキリスト者が日本という「無宗教を自称する国家」と向き合う時にも求められる心情である。正しいこと(真理)を事実やデータから突き付けても、相手は決して受け入れない。そうではなく、自らの持っている知識やデータ、そして考え方を、肯定的に相手との融和や友好的な関係構築のために用いる「工夫」が求められている。
三井氏はジャーナリストとして「科学的・理性的」な立場から、異なる文化形態(宗教大国「アメリカ」)を理解しようとして、この結論に至っている。そうであるなら、私たちキリスト者もまた、己の中の真理・真実を相手の非を打つ道具としてはならないだろう。そうではなく、異なる価値観を今は抱いているとしても、その他者との距離を詰め、また友好的な関わりを構築するためにこそ、「神の言葉」を用いるべきである。
本書の中に、多くの「議論の種」を見いだすことができる。そういった意味で本書は、考えの異なる相手との建設的な話し合いを生み出す示唆に満ちているといえよう。
■ 三井誠著『ルポ 人は科学が苦手 アメリカ「科学不信」の現場から』(光文社 / 光文社新書)
◇