アダムが罪を犯し堕落したとき、私たちもアダムの罪に参加していた。それで、私たちはアダムの「罪性」を引き継ぎ、「堕落した者」になって罪を犯すようになった。神は、堕落した人の姿を見て怒り、罰として死をもたらした。これが伝統的な罪と死の理解であって、「原罪」と呼ばれてきた。その根拠に使われてきたのがローマ5:12である。その原文にある「エピ、ホー」を、「理由を表す接続詞」と見なすことでそうなった。
しかし、フィッツマイヤーの論文により、「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」だとするのは、今や誤りであったことが確定した。「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」であった。ならば、ローマ5:12はどのように訳すべきであり、どう解釈すべきなのかを見てみよう。またどうして、長きにわたり「理由を表す接続詞」として訳されてきたのか、その変遷も見てみよう。すると、面白いことが見えてくる。
【ローマ5:12の訳】
(1)罪を犯すようになった
新共同訳のローマ5:12を土台に、「エピ、ホー」の部分だけを「結果を表す接続詞」として訳すとこうなる。
このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。その結果、すべての人が罪を犯した。
ここで、「罪を犯した」と訳されている箇所の動詞はアオリスト時制である。アオリスト時制とは、過去の一回的な動作を表している。それゆえ、「罪を犯した」と訳すことは間違いではない。しかし、その過去の一回の動作は継続性のある動作の「始発」の場合もあるので、動作の「始発」を言い表す場合もアオリスト時制が使われる(参照:田中美知太郎著『ギリシャ語文法』岩波書店、144ページ)。
ならば、この場合はどうなるだろう。「エピ、ホー」を「結果を表す接続詞」として訳すと、この箇所は、人がどうして罪を犯すようになったのか、罪の始まりを説明した文章になる。となれば、この場合のアオリストは「始発」を言い表していることになるので、「罪を犯した」ではなく、「罪を犯すようになった」と訳すのが正しい。このことを踏まえ、ローマ5:12を私訳すると次のようになる。
それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)
「福音の回復」のコラムでは、この訳を何度も使ってきた。ただしこの訳は、あくまでも「エピ、ホー」を「接続詞」として読んだ場合であって、「代名詞」として読んだ場合は、「死の上にあって」という意味になり、次のような訳になる。
それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その死の上にあって、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)
こちらの訳の方が、より「死」が原因で私たちは罪を犯すようになったことが際立ち、パウロがこの先で述べている、「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)ともよくなじむ。とはいえ、ローマ5:12の「エピ、ホー」は「接続詞」として訳そうが、「代名詞」として訳そうが、言わんとする内容はまったく変わらない。そこで、「エピ、ホー」は一般に「接続詞」として解されることに配慮し、「福音の回復」のコラムでは「接続詞」として読んだ場合の訳を採用してきた。
このように、神との結びつきを失う「死」が入り込み、そのことで人は不安を覚えるようになり、見える安心をむさぼる罪を犯すようになったのである。つまり、「死」がなければ、私たちの「罪」も存在しなかったということだ。あくまでも「死」が先であって、「罪」はあとになる。そうである以上、入り込んだ「死」を、私たちがアダムにあって「罪」を犯したことへの罰とする原罪論は、あり得ないとなる。なぜなら、先に「死」がなければ、私たちは「罪」を犯すことなどできないからだ。この正しい訳は、そうしたことを教えてくれる。
では、本当にこの訳は正しいのか、そのことを他の御言葉との整合性からも確かめておこう。最初は、同じローマ書との整合性である。
(2)ローマ書との整合性
ローマ書5章は、「ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています」(ローマ5:1)で始まり、罪人を義としてくださる神の恵みの説明が展開されていく。そして神の恵みは、次のように成就したという。
私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められた時に、不敬虔な者のために死んでくださいました。(ローマ5:6)
キリストは私たちの与り知らないところで、不敬虔な私たちのために死んでくださったので、罪人であっても義と認められるという。ならば、神はどうしてそこまでしてくださったのだろう。その理由を説明したのが、ローマ5:12となる。
それによると、私たちの与り知らないところで入り込んだ「死」が、私たちの罪の原因になったからとなる。ゆえに、神も私たちの与り知らないところで死んでくださり、そのことゆえに、私たちを義としてくださるという。ローマ5:12を先のように訳すと、5章前半の話の展開と、実にうまくなじんでくれる。ならば、ローマ5:12の続きともなじむだろうか。
というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。(ローマ5:13)
ここでパウロは、先に述べた罪の原因は「死」にあるという話から、今度は「律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあった」と言った。というのも、罪の原因となった「死」は、律法が与えられなかったアダムからモーセまでの間も、人々を支配していたからだとした。
ところが死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムはきたるべき方のひな型です。(ローマ5:14)
パウロがここで、「律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあった」(ローマ5:13)という言い方をしたのは、その当時、神が律法を与えなければ違反という罪は生じなかったと考える人たちが大勢いたからである。彼らは、律法があったから人の欲が目覚め、人は罪を犯すようになったと思い、罪の責任を律法に負わせていたのである。それでパウロは、こうした言い方をした。
確かに、律法がなくても「死」が人を支配していたので、カインはアベルを殺したし、その後も人々は罪を犯した。ならば律法は何なのかと人は思うので、「しかし罪は、何かの律法がなければ、認められないものです」(ローマ5:13)と説明し、さらにこの先では、「それでは、どういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ、律法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう」(ローマ7:7)と、念を押している。
つまりローマ5:12~14は、アダムの罪に伴い入り込んだ「死」によって、すべての人が罪を犯してしまう仕組みが確立したことを説明している。そうであるなら、イエス・キリストの十字架の「死」によって、すべての人に「神の恵み」が満ち溢れるようになる仕組みができるのは当然ではないかとなるので、「アダムはきたるべき方のひな型」(ローマ5:14)だと言った。このことに関する説明がこの後も続き、ローマ書5章は次の御言葉で締めくくられている。
それは、罪が死によって支配したように、恵みが、私たちの主イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠のいのちを得させるためなのです。(ローマ5:21)
またしてもここで、人は「死」に支配されたことで罪を犯すようになったことを、「罪が死によって支配したように」と述べ、まことに人が罪を犯す仕組みは、人の与り知らないところで入り込んだ「死」によって出来たことを再度確認している。そのことで「永遠のいのち」を得させる「神の恵み」の仕組みも、人の行いには関係なく、私たちの与り知らないところでなされたイエス・キリストの十字架の「死」によって出来たことを再度確認している。
さらに先を見ていくと、「ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住みついている罪なのです」(ローマ7:17)とある。パウロはここで、罪のことを「住みついている」と言い、「私ではない」と言い切っている。もし私たちの罪の原因が「原罪」であって、人の本性にあったのなら、すなわち罪の責任が人にあったのなら、決して「私ではない」などとは言わなかった。ましてや、「住みついている」などとは絶対に言わない。それは「私自身であり」、自らの意志で「私がしている」と言う。すなわち、罪の原因は人にではなく、「死」にあることをパウロは知っていたので、こういう言い方をした。
このように、ローマ5:12を先のように訳し、罪の原因は人に住み着いた「死」にあるとすれば、後半とも実によくなじみ整合性が取れる。今度は、パウロの書いた他の手紙との整合性を見てみよう。
(3)他の手紙との整合性
パウロは、コリント人への手紙の中でこう書いている。
そして、もしキリストがよみがえらなかったのなら、あなたがたの信仰はむなしく、あなたがたは今もなお、自分の罪の中にいるのです。(1コリント15:17)
ここでパウロは、もしキリストの復活がなければ、「死」から贖(あがな)い出されるという信仰はむなしいと言い、そうであれば今なお「罪の中にいる」と言った。復活がなければ、今なお「死の中にいる」となるはずが、ここではあえて、「罪の中にいる」と言っている。それは、「死」が人の「罪」の原因になっているからだ。
これは重要なことなので、パウロはこの先で分かりやすく、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)と言っている。この原文を見てみると、意味を強調するために英語で言うところの「Be」動詞が省略されている。それを補うと、原文は次のような形になる。

すなわち、“「死のとげ」イコール「罪」”ということであり、「死の成分」が私たちの「罪」であるということだ。これとまったく同じ言い方を、パウロはローマ書の中でもしている。「肉の思いは死であり」(ローマ8:6)がそれであり、これも「Be」動詞が省略されている。
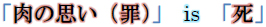
ここでは「罪」のことを「肉の思い」といい、ここでもそれは「死」だと言っている。つまり、「罪の成分」は、入り込んだ「死」であるということだ。罪を犯せば死という罰がある、ということでは決してない。もしそうであれば、“「罪」becomes「死」”と、書かれていなければならない。
このように、ローマ5:12を先のように訳さなければ、パウロの書いた一連の罪の理解とはまったく整合性が取れなくなる。実は、神の言われた罪の教えとも整合性が取れなくなる。
(4)神の言葉との整合性
イエスは、私たちが犯す罪については次のように教えられた。
あなたがたは、あなたがたの父である悪魔から出た者であって、あなたがたの父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。(ヨハネ8:44)
イエスは罪を犯す者を、「悪魔から出た者」と断言された。それは、人の罪は「死」によって生じるようになり、その「死」は悪魔の仕業によったからである。それで悪魔のことを、「死をつかさどる者」(ヘブル2:14、新共同訳)という。ゆえに、罪に至る流れはこうなる。

こうした流れをイエスは知るからこそ、罪を犯す者を「悪魔から出た者」と言われた。イエスの弟子のヨハネも、「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(1ヨハネ3:8)と証言する。まことにローマ5:12を先のように訳さなければ、罪に関するイエスの教えとも一致しなくなる。それだけではない。先のように訳せば、神の言われた次の言葉の意味も解決する。
わたしは、決して再び人のゆえに、この地をのろうことはすまい。人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。(創世記8:21)
神は人の思いを見て、「初めから悪である」と言われた。この神の言葉も、人の中に罪を犯す性質があったとする「原罪」の根拠に使われてきた。しかしそうなると、神はご自分が造られた人を見て、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)とも言われたので、そのこととの整合性が取れなくなる。そこで、人は何としても整合性を取ろうとさまざまな試みをしてきた。
だが、ローマ5:12を先のように訳すと問題は何も生じなくなる。その訳の理解に従えば、神が造られたアダムは「非常に良かった」となり、「死」が入り込んでからの人の思いは、「初めから悪である」となるからだ。つまり、アダム以降の者は「死」のせいで不安を覚えるようになり、生まれながらに見える安心をむさぼる「肉の思い」(罪)を抱くようになったので、神はアダム以降の人を見て、「初めから悪である」と言われたのである。ということは、神が言われたこの言葉こそ、ローマ5:12は先のように訳すのが正しいことを裏付けている。
まことにローマ5:12を先のように訳し解釈するなら、罪に関する聖書の教えは息を吹き返し、互いに整合性が取れるようになる。よって、先の訳は正しいということになる。すなわち、私たちを苦しめる罪の原因は、悪魔が人を欺いたことで入り込んだ「死」で間違いないのだ。それで聖書は、「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(1ヨハネ3:8)と教え、そのために十字架で悪魔を滅ぼし、それにより「罪」の奴隷となっていた人々を解放されたことを教えている。
これは、その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。(ヘブル2:14、15)
このように、キリストは罪の源になった「死」を十字架で滅ぼされたので、「キリストは死を滅ぼし、・・・」(2テモテ1:10)と教え、十字架で「死」を滅ぼすことは、私たちの「罪」を十字架で背負われたことを意味するので、「そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました」(1ペテロ2:24)と教えている。では、訳の総括をしよう。
(5)総括
ローマ5:12の「エピ、ホー」は「その結果」という意味であって、「because」ではなかった。そもそもパウロが本気で「because」という意味を言い表したかったのであれば、同じローマ人への手紙の中で4度も使われている「ディオティ」[διότι]という言葉を使っていた。なぜならパウロは、この言葉を「because」の意味でしか使っていないからだ。
にもかかわらず、使い慣れた「ディオティ」は使わず、あえて「エピ、ホー」を使ったということは、当然そこに込められた意味は「because」ではなかったということになる。この推論は間違っているだろうか。間違ってなどいない。であれば、この箇所は以下のように訳さなければならない。
それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)
この文章は、私たちが罪を犯すようになるまでの経緯を解説したものであり、それによると、私たちが罪を犯すようになった原因は、アダムの罪によって入り込んだ「死」にあったという。これが、ローマ5:12の意味するところとなる。つまり、こういうことだ。
神は人を「良き者」として造られたが、「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)、人は悪魔に欺かれて罪を犯し、「ただ、エバが蛇の悪だくみで欺かれたように」(2コリント11:3、新共同訳)、そのことで人の中に「死」が入り込んでしまった。「というのは、死がひとりの人を通して来たように」(1コリント15:21)。
「死」とは神との結びつきを失うことであり、人は神と一つ思いを共有する神の部分として造られていたので、「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)、それは人が「神と異なる思い」を持つことで生じるようになっていた。ゆえにイエスは、「神と異なる思い」を持つことが「罪」だと言われた。つまり、神を信じないことを「罪」とされた。「罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと」(ヨハネ16:9、新共同訳)。
悪魔は、そうした人の造りに目をつけ、人を欺いて罪を犯させた。それで「死」が入り込んでしまった。すなわち「死」は、神からの罰という「報い」ではなく、「罪」から来る「報酬」なのである。「罪から来る報酬は死です」(ローマ6:23)。そうであっても、「死」が入り込んだことで人の体は有限になり、神の愛が見えなくなった。そのことで一生涯「不安」になったので、聖書はそれを、「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」(ヘブル2:15)と表現した。
こうして、人は初めから「死の恐怖」につながれ、生まれながらに見えるものにしがみつこうとする「悪」を思い計るようになった。それで神は、「人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ」(創世記8:21)と言われた。つまり、「死」が入り込んだ結果、すべての人は罪を犯すようになったのである。ローマ5:12は、そうした経緯を説明している。
従って、罪を犯す人の姿は、「良き者」が病気になった姿となる。病原菌が入れば体はうまく機能しなくなり、その様子を人は病気になったというが、それと何ら変わりはない。それで神は、人の罪を「病気」として取り扱い、キリストの十字架がそれを癒やすという。
キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(1ペテロ2:24、新改訳2017)
このように、罪を犯す人の姿は堕落した「ダメな者」ではなく、それは「良き者」が病気になった姿なのである。まことに聖書の教えは、原罪の考えとは正反対になる。

これで、人を「ダメな者だ」とする原罪の最後の砦、「ローマ5:12」は陥落した。私たちの罪の原因は「死」(有限)にあることが確定し、人は「良き者」であることが証明された。こうした罪の理解はキェルケゴール以来、実存主義哲学者や心理学者にとっては常識的な話であり、近年における偉大な発見とされるが、実は聖書がすでに教えていたのである。
これで話を終わりにしたいところだが、そうはいかない。私たちの積み上げてきた「経験」が、この話に納得しないからだ。経験では、罪は自らの「欲」に起因するのであって、「死」とは関係がないとなるからだ。納得しないのは、パウロの時代も同じであった。そのため、ローマ5:12の「エピ、ホー」の意味に対しては、パウロの死後からさまざまな試みがなされてきた。そこで今度は、ローマ5:12の解釈をめぐる話をしたい。それは実に興味深い話であり、その話から、戦うべき真の敵が見えてくる。
【ローマ5:12をめぐって】
人は自らの「経験」から、どうしても「罪を犯す性質」が人の中にあると信じて疑わない。特に昔は、人の「体」にこそ罪の原因があると信じられていた。確かに、私たちの「体」は欲望を抱き、罪を犯してしまう。それでパウロの時代の人たちは、「死」が罪の原因だとはっきり述べたローマ5:12には違和感を覚えた。
そこで人々は考えた。パウロは「エピ、ホー」を、実はこういう意味で使ったのではないかと。そうやってローマ5:12については、自らの経験が納得のいく解釈が施されるようになった。このことは、これから見ていくローマ5:12における解釈の変遷を見れば容易に分かる。では、その変遷を見てみよう。
(1)解釈の変遷
パウロの時代、イタリア人は一般に公用語のギリシャ語と、母国語のラテン語を使っていた。そのため、彼らはギリシャ語で書かれた聖書を自由にラテン語に訳すことができた。そうした訳を、古代ラテン語訳という(参照:蛭沼寿雄著『新約聖書の成立』比叡書房、204、205ページ)。それを見ると、ローマ5:12の「エピ、ホー」は、「in quo」(インクオ)、「彼の中に」(In whom)と訳されていた。「その結果」ではなかった。このことから、「エピ、ホー」に対する新たな解釈は、パウロの死後すぐに始まったことが分かる。
この「彼の中に」(In whom)という訳は、「エピ、ホー」を「代名詞」として読み、「ホー」(それ)を、「このようなわけで、一人の人(アダム)によって罪が世に入り」の「アダム」を指すとしている。すべての人はアダムが罪を犯す中にあって罪を犯した、という意味に解したのである。アウグスティヌス(354~430)はこの訳を大いに支持し、その後は「原罪」の教理の砦となった。
ところが先述したように、「エピ、ホー」を「代名詞」として読んだ場合、「ホー」が「一人の人」(アダム)を指すとするのはあまりにも無理がある。というのも、「一人の人」という言葉が離れすぎているからだ。「代名詞」として読むなら、まずは直前の節の中から「ホー」に該当するものを探すのが自然な読み方となる。そうしたことから、これはギリシャ語を知らなかった人たちによる誤訳だと思われている(参照:ミラード・J・エリクソン『キリスト教神学 第3巻』いのちのことば社、211ページ)。だが真相は、ギリシャ語をよく知っていたからこそ、無理矢理このように訳したと考えるのが正しい。
その後も「代名詞」として読むさまざまな試みがなされたが、ほとんどは強引な解釈であった。例えば、ジョン・ウェスレー(1703~91)も「代名詞」として読み、「エピ、ホー」を「in that」と訳した。そして「that」はアダムを指すとし、「in Adam(one man)」と解し、アダムは全人類の代表であってすべての人はアダムにあって罪を犯したとした(参照:Jhon Wesley『Explanatory Notes upon the New Testament』The Second Edition、396ページ)。これは先のアウグスティヌスと同じ理解であり、自然な読み方ではない。とはいえ、「代名詞」としての読みは、こうした強引な読み方が実に多かった。これ以上は割愛するが、強引ゆえに広く支持されることはなかった。
ただし、中には「エピ、ホー」の「ホー」は直前の「死」を指すとし、「死の理由で」と訳した人たちもいた。そのことは、先のフィッツマイヤーの論文に書かれている。その人たちとは、ライポルト(J.Leipoldt)、シュリエル(H.Schlier)、ガリング(K.Galling)であった。これは最も自然な読み方であり、彼らは本書の理解と同じように、死が入り込んだことで、すべての人は罪を犯すようになったという意味に訳した。
ちなみに、『新約聖書釈義事典』の「死」[θάνατος]の項の2番を見てみると、そこにはこう書かれている。『〈死〉はパウロによれば、人格化された力として世界の中へ入り込み、疫病のように全人間に浸透し(ローマ5:12)、そして彼らすべてを罪を犯すようにそそのかした(1コリント15:56)・・・』(『新約聖書釈義事典Ⅱ』教文館、170ページ)。これは Beider Werner による解釈とあるが、これを見る限り、彼も「エピ、ホー」を「代名詞」として読み、「ホー」は「死」を指すとする自然な読み方をしたことが分かる。ただし、彼はこの箇所をそのように読んでも、従来の原罪論を展開した。
このように、「代名詞」として読んでも正しい意味に訳す人たちもいたが、それでも支持を集めることはなかった。なぜなら、そのように訳すと従来の原罪論を否定することになりかねないからである。
そうした試みとは別に、昔から「エピ、ホー」を「接続詞」として読む人たちもいた。ただし、「結果を表す接続詞」ではなく、理論上は可能となる「理由を表す接続詞」として読むのである。そうすれば、すべての人が罪を犯したから、すべての人に死が及んだと訳すことができ、従来の原罪論を擁護できるからだ。それで、次第にそうした読み方の方が主流になっていく。
そこで辞書はそのことに追随し、「理由を表す接続詞」の意味を記載するようになったと思われる。こうして、「エピ、ホー」の意味は歴史の中で漂流し、ようやく「理由を表す接続詞」として落ち着き、その後は今日のように訳されることになった。それにより、ローマ5:12は「原罪」を示す砦となった。
しかし、そこにフィッツマイヤーが登場し、古典ギリシャ文学で使われていた「エピ、ホー」の用例を調べ上げ、「エピ、ホー」は「結果を表す接続詞」の意味にしか訳せないことを明らかにした。ゆえに、それ以降に出版された権威ある註解書や、権威ある辞書は、そのことを記載しなければならなくなった。そうなると、今後は「エピ、ホー」を「理由を表す接続詞」とすることは困難になり、これまでのような訳に頼って「原罪」を主張することはできなくなったというのが、今日の現状である。
見てきて分かったように、フィッツマイヤーが「エピ、ホー」の意味を明らかにするまで、実に長きにわたり、ローマ5:12は誤って訳されてきた。ところが従来の訳の誤りが指摘されたことで、「原罪」の砦は崩壊の危機を迎えてしまった。そこで、この危機を何とかしようと、ローマ5:12の新たな解釈が登場する。では、その後の解釈の変遷を見てみよう。
(2)新たな解釈
ローマ5:12の後半が、「その結果、すべての人が罪を犯すようになった」と訳されていれば誰もが気づく。これは、私たちが犯す罪の「始発」は「死」にあることを教えた文章だと。そうなると、私たちが犯す罪の「始発」をアダムが犯した罪(原罪)に求めてきた人には、どうしても承服しかねてしまう。かといって、「エピ、ホー」は「理由を表す接続詞」(because)であると言ったところで、今さら説得力がない。「エピ、ホー」を「接続詞」として読んだ場合は、「結果を表す接続詞」の意味にしか訳せないことを知性が知ってしまった以上、知性に刃向かうことなどできないからだ。ならばローマ5:12は、もう従来の「原罪」の根拠には使えないのだろうか。
いや、方法はある。「エピ、ホー」は「代名詞」としても読めるので、昔の人たちがしたように読めばよい。「エピ、ホー」(それの上で)の「それ」を、アウグスティヌスがしたように、「一人の人によって罪が世に入り」の「一人の人」を指すとして読めばよい。ただし、アウグスティヌスと同じ読み方をしたのであれば、今さら支持は得られない。そこで、新たな試みが必要となる。
例えば、R・ジュウェットはローマ5:12の「エピ、ホー」の「ホー」を「代名詞」とし、「ホー」は、「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、・・・」の「世」を指しているとした。そして、「エピ、ホー」を「世において」と訳した。「世において」とは、人が罪を犯してきた領域を指しているとした。ゆえに、それに続く「すべての人が罪を犯した」とは、「世」という領域においては、罪が広がったことの責任は人にあることを述べたものだとした(参照:Robert Jewett 『Romans』 2006, Fortress Press、375、376ページ)。
何とも苦しい説明ではあるが、そうであれば、人が罪を犯すようになったことの原因を人の中に求めることはでき、ローマ5:12を従来の「原罪」の根拠として使うことができる。ただし、「世」を指すとするには、「世」と「ホー」とがあまりにも離れすぎていて無理がある。
日本に目を向けると、太田修司は「エピ、ホー」の「ホー」は、直前の「死はすべての人に及んだのです」の「死」を指すとした。ただし、「エピ、ホー」の「エピ」を、「目指して」という意味に解し、「それ(死)を目指して」とした。「それ(=死)を目指してすべての人が罪を犯したのです」という意味に訳した(参照:太田修司著『ローマ書におけるピスティスとノモス(1)』一橋大学リポジトリ)。
これであれば、人に入り込んだ「死」は、罪人である私たちが向かう先となり、「死」は罪に対する神からの罰とする従来の「原罪」を維持できる。ただし、「エピ」を「目指して」と訳すことに、どれだけの賛同が得られるかは疑問である。いずれにせよ、「エピ、ホー」を「代名詞」として読む新たな試みが、フィッツマイヤーの論文が出たことで再燃したのであった。
しかし、この箇所の「エピ、ホー」を「代名詞」として読んだ場合、何度も言うようだが、「ホー」は直前の節にある「死」を指すとするのが最も自然な読み方となる。そうなれば、私たちの罪の原因は「死」にあるという意味になるので、今さら「エピ、ホー」を「代名詞」として読み、従来の「原罪」を肯定しようと試みたところで説得力がない。ならば、何か別の手立てはないのだろうか。
実はある。それは、「その結果、すべての人が罪を犯した」という訳を素直に認め、ただし、その意味はこうであると、解釈によってこれまでの「原罪」を擁護すればよい。実際、そうした試みをした人が出てきた。それは何と、フィッツマイヤー自身であった。まず彼は、ローマ5:12を次のように訳した。
Therefore, just as sin entered the world through one man, and through sin death, and so death spread to all human beings, with the result that all have sinned.
それゆえ、一人の人を通して罪が世に入ったように、罪を通して死が入った。そのように、死はすべての人に広がった。その結果、すべての人が罪を犯した。(ローマ5:12)
そして、彼はその意味を次のように解釈した。パウロは前半で、アダムが罪を犯したことですべての人が「死」を背負わされたことを述べた。ただこれだと、「死」の責任が私たちにはまったくないような印象を与えてしまうので、追加説明として、「その結果、すべての人が罪を犯した」を書いたという。そのことで、私たちが罪を犯したことも死の要因になっていることを説明したという。この追加説明は、「死」の最初の因果関係はアダムの罪であり、2つ目の因果関係は、私たちが犯す罪にあることを述べているという。
こうしてフィッツマイヤーは、あくまでもすべての人はアダムが犯した罪の性質を受け継いでいて、そのせいで罪を犯し、罪に対する神の罰が「死」であったとする原罪論を擁護した。しかし、これはまことに苦しい擁護である。この箇所を、アダムの罪によって「死」が入り込んだ結果、私たちは罪を犯すようになったと解すのであれば、この訳に対し何ら弁解する必要も、説明する必要もない。訳の通りの時系列で理解すればよいので、苦しい釈明に追われることは何もない。
このように、正しく訳されるようになっても、ローマ5:12は再び漂流し始めたのである。ならば一体何が原因で、漂流してしまうのだろう。それは人の「経験」である。私たちの積み上げてきた「経験」が、人の中に罪の原因があるとするから、いつまでたっても漂流が止まらないのである。
これでは終わりがない。だが、このことから戦うべき敵の姿が浮き彫りになる。それは、自らの「経験」だと。まことに「経験」が、御言葉をふさいでしまう敵なのである。敵というと人は外部に目を向けるが、実は私たちの中にいる。そこで最後は、戦うべき敵について見ておこう。
【戦うべき敵】
(1)「有名な外科医」の話
積み上げてきた「経験」が、いかに真実を見えなくさせてしまうかを知る実験をしてみたい。そのために、次の話を読んでみてほしい。
有名な外科医がいた。彼のところに、ある日のこと、交通事故で大けがをした親子が緊急搬送されてきた。父親はすでに死亡していた。子どもは助かったが重傷であった。早速、有名な外科医は子どもを治療しようとした。その時、有名な外科医は叫んだ。「これは私の息子だ!」
この話を読み、重傷を負った子どもと、「有名な外科医」との関係を答えられるだろうか。多くの人は、こう答えるだろう。それは「父親」と子どもの関係だと。「有名な外科医」というと自らの「経験」から「男性」を連想するため、重傷を負った子どもと、この外科医との関係は、「父親」と息子の関係だと答える。しかしそうなると、死亡した父親という人は、一体誰なのかという疑問が生じる。
そこで人は、それを解決するためにさまざまな解釈を試みることになる。ある人は、この「有名な外科医」は離婚し、離婚した妻の再婚した夫が今回の事故を起こしたとする。またある人は、「有名な外科医」は何らかの理由で自分の息子を養子に出し、そこでの父親と事故に遭ったとする。さらには、この子は誘拐されて行方不明になっていた実の子であり、誘拐した男と事故に遭ったと考える人もいる。他にもいろいろあるが、そうやって人は、何としても「有名な外科医」が重傷を負った子の父親であったことを論証しようとする。
だが、どの解釈も不正解である。なぜなら、この「有名な外科医」は「女性」であり、重傷を負った子どもとの関係は、「母親」と息子の関係であったからだ。交通事故で死亡したのは自分の夫であり、実の息子が大けがをして運ばれて来たので、「これは私の息子だ!」と叫んだ。
この答えを聞くと、人は一様に納得し、それまでの無理な解釈を取り下げる。そして人は一様に思う。「何だ、実に簡単な答えではないか」と。ところが、「有名な外科医」は「男性」だと決めつけてしまう「経験」に惑わされ、こんな簡単な答えも見いだせないのである。ローマ5:12の話は、これと何ら変わりがない。どうして変わらないのか説明しよう。
(2)「経験」が人を惑わす
私たちは罪を犯せば、「悪い子だ」と責められ罰を受けてきた。良いことをすれば「良い子だ」と褒められ、褒美を手にしてきた。これを「賞罰教育」というが、私たちは生まれながらに「賞罰教育」の「経験」を積み上げてきた。そのため、誰もが罪を見ると本人が「悪い」となり、「罰」を受けるべきと思ってしまう。誰もが「罪人には罰」という眼鏡を掛け、それで人を知ろうとし、物事の判断を試みてしまう。当然、ローマ5:12を読むときも、「罪人には罰」という眼鏡が使われる。
そのため、「全人類が罪を犯した」という言葉を人は目にすると、自動的に「神の罰」を連想し、その罰は「死」だと思ってしまう。そうなれば、「エピ、ホー」を「because」という意味に解すしかなく、「こうして、すべての人が罪を犯したので、死が全人類にはいり込んだのである」(口語訳)という意味に訳してしまう。
しかし、そう訳してしまうと、人の罪の原因は人の中にあったことになり、人は神に似せて造られた神の作品なので、神が罪の創造者になってしまう。それはまずいので、さまざまな言い訳に迫られる。その代表的な言い訳が、自由意志であった。人には神に従うか従わないかを選択できる自由な意志が与えられていたとし、罪を犯したのは人の自由意志によるのであって神には責任がないとしたのである。だがそうなると、どうして神に従わない選択をするのかという新たな問題が生じ、さらなる言い訳が必要になる(参照:福音の回復(74))。
先に、「有名な外科医」という言葉から「男性」を連想した人は、事故に遭った子どもとの関係を説明するのにさまざまな言い訳に迫られたが、まさにそれと同じことが起きてしまうのだ。無論、「エピ、ホー」を「because」として読むのは本人が意図的にするわけではない。「有名な外科医」の話と同様、自らの「経験」が無意識にそうさせてしまう。これこそが、ローマ5:12をめぐってさまざまな解釈が施されてきたことの真相にほかならない。
このように、人は自らの「経験」に惑わされる。「経験」が勝手に意味を補完してくるために、簡単に惑わされてしまう。しかし、惑わしてくる相手がほかでもない、自らの「経験」であるため、人は惑わされてもまったく気付けない。そのことは、「有名な外科医」の話で体験した通りである。つまり、神の言葉を読むときはいつでも、私たちには「罪人には罰」という覆いが掛かっているということだ。
確かに今日まで、モーセの書が朗読されるときはいつでも、彼らの心には覆いが掛かっています。(2コリント3:15、新改訳2017)
この「罪人には罰」という覆いは、人が自らの経験で「罪」を理解し、「義」を理解し、「裁き」を理解するために起きる。ゆえにイエスは、次のように言われた。
その方が来ると、罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認めさせます。(ヨハネ16:8)
ならば、どう誤りを認めさせるというのだろう。
(3)誤りを認めさせる
人は生まれながらに、「・・・をしてはいけない」といった「行いの規定」を突きつけられ、それに違反することが「罪」だと教わってきた。「罪」を「行いの規定」で捉えてきたのである。そのため、「良い行い」ができるようになれば神に「義」とされ、できなければ「裁き」を受けると、勝手に思い込んでしまった。要は、「罪人には罰」である。
これでは、無条件に愛する神の愛がまったく見えない。神がいくら人を「良き者」として取り扱っても、人の方が「良い行い」ができない自分を勝手に「ダメな者」として、神の取り扱いを拒否してしまう。そこでイエスは、まずは「罪」の理解を次のように修正すると言われた。
罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと、(ヨハネ16:9、新共同訳)
イエスは、罪は「行いの規定」ではなく、ご自分を信じない「不信仰」だとされた。信じないとは「神と異なる思い」を持つことであり、神の御手を拒むことを意味する。次にイエスは、「義」の理解を次のように修正すると言われた。
義についてとは、わたしが父のもとに行き、あなたがたがもはやわたしを見なくなること、(ヨハネ16:10、新共同訳)
人は罪を「行いの規定」で捉えたので、良い行いができるようになることで神の「義」が得られると思ってしまった。しかしイエスは、「義」とは、ご自分が神のもとに行くことだとされた。それは天に上るということであり、そうすれば上から人を引き上げることができるからである。つまり、神が人を天に引き寄せることが「義」である。それでイエスは、「わたしが地上から上げられるなら、わたしはすべての人を自分のところに引き寄せます」(ヨハネ12:32)と言われていた。ならば、神は誰を引き寄せてくださるのだろう。
ここでイエスは、「わたしはすべての人を自分のところに引き寄せます」と言われている。それは、すべての人を分け隔てなく引き寄せてくださるという意味だ。ゆえに人は、誰の上にも分け隔てなく差し伸べてくださる御手をただ掴めばよい。それだけで「義」とされることになる。「良い行い」ができるようになれば神に「義」とされるわけではなく、人はただ差し出されている御手を掴むだけでよい。それでイエスは、御手を拒むことが「罪」だと言われたのであった。さらにイエスは、「裁き」の理解を次のように修正すると言われた。
また、裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。(ヨハネ16:11、新共同訳)
人は勝手に罪を「行いの規定」で捉えたので、良い行いができなければ裁かれると思っていた。「罪人には罰」という眼鏡を掛けていた。しかしイエスは、裁かれるのは、「この世の支配者」だけだと言われた。その支配者とは「悪魔」であり、悪魔の仕業による「死」である。というのも、人を支配していたのは「死」であり、人は一生涯「死の恐怖」の奴隷とされ(ヘブル2:15)、見える安心をむさぼる「罪人」にさせられていたからである。それゆえ、イエスの言われた「この世の支配者」とは、「悪魔」を指す。
つまり、イエスは人が悪魔の仕業で「罪人」となったことを誰よりもご存じだったので、「罪人」を裁くのではなく、そのようにさせた悪魔を裁くと言われたのである。このことは重要なので、たびたび次のようにも教えられた。「まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦(ゆる)していただけます」(マルコ3:28)。ただし、神は人を裁かれはしないが、人は神が差し出す御手に掴まらなければ救われない(義とされない)。
こうしてイエスは、「罪人には罰」という眼鏡は誤りであり、正しくは「罪人にはあわれみ」であることを教えられた。ただし、イエスは教えられただけで、実際に誤りを人に認めさせ、その間違った眼鏡を外させることができるのは「その方」だと言われた。「その方が来ると、罪について、義について、さばきについて、世にその誤りを認めさせます」(ヨハネ16:8)。ならば「その方」は、すなわち聖霊なる神は、どのように誤りを認めさせ、「罪人には罰」という眼鏡の覆いを取り除いてくださるのだろう。
(4)覆いを取り除く
人の積み上げてきた経験は「罪人には罰」という眼鏡となり、それが「人間的な標準」になった。人はこの「人間的な標準」で人を知ろうとし、キリストも知ろうとしたために、神の福音には覆いが掛かってしまった。それで聖書は、次のように教えた。
ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。(2コリント5:16)
この覆いを取り除くために、聖霊なる神は、私たちが罪と向き合うようにされる。「それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで」(ローマ2:4)。その導きに従い自らの罪と向き合うなら、あのパウロがそうであったとように、罪に絶望することになる。
私は、ほんとうにみじめな人間です。だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか。(ローマ7:24)
パウロはここでも、罪を犯してしまう原因を「この死の、からだ」と言い、「死」のせいでこうなったと言っている。では、キリストを信じる者が自らの罪に絶望すれば何をするだろう。その者は、どうにもならない病気に気付いた者は医者に助けを乞うように、キリストに助けを乞うようになる。神にあわれみを乞うようになる。
神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。(ルカ18:13)
神はこの祈りに答えてくださる。それは、その人の心に言いようもない平安を満たすことで答えてくださる。そのことで、その人は罪が無条件で赦されたことを知る。
もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。(1ヨハネ1:9)
この体験が、自分は無条件に愛される「良き者」であったことに気付かせ、「罪人には罰」という覆いを外させてくれる。
このように、福音を見えなくさせている覆いを外す方法は絶望する勇気である。自分をごまかすのはやめ、御言葉を通して自らの罪と向き合う勇気が、「私は、ほんとうにみじめな人間です」(ローマ7:24)という絶望になり、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)となる。これが、人を引き寄せようと差し出された御手を掴むことを意味し、イエスの言われた「義」になる。「この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:14)。
こうした一連の行程が、イエスの言われた「その方」、すなわち聖霊なる主の働きによるのである。「これはまさに、御霊なる主の働きによるのです」(2コリント3:18)。聖霊が罪と向き合わせてくださり、私たちをキリストの治療に向かわせ、「罪人には罰」という眼鏡を外させてくださるのだ。ここに神の福音がある。
(5)神の福音
私たちの与り知らないところで入り込んだ「死」が、私たちにおける罪の原因になった。加えて言うなら、「死」が入り込んだことで朽ち果てる体となり、「ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)、ケガや病気も覚えるようになった。また、被造物自体も、人に入り込んだ「死」によって滅び行く姿となり、「土地は、あなたのゆえにのろわれてしまった」(創世記3:17)、人は天変地異にも遭遇するようになった。
従って「罪」だけではなく、「病気」や「天変地異」も、みな悪魔の仕業による「死」に起因している。ゆえに、人が罪を犯そうとも、病気になろうとも、天変地異に遭おうとも、それは神からの罰でもなければ、人が「ダメな者」だということを証しする印でもないのだ。すなわち、神が造られたものはすべて、非常に良かったということである。「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)。「罪」や「病気」や「天変地異」といったものを背負う人の姿は、どこまででも「良き者」だということであって、「ダメな者」では決してない。
ゆえに神の福音は「死」を滅ぼし、人をキリストの似姿に戻すことにある。「良き者」から「良き者」へと、「栄光」から「栄光」へと、主と同じ姿に癒やされていくというのが福音になる。
私たちはみな、顔のおおいを取りのけられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じかたちに姿を変えられて行きます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。(2コリント3:18)
その福音を実行するために、神は誰に対しても次のように呼びかけてくださる。
疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。(マタイ11:28、新共同訳)
神は人を引き寄せようと、誰の上にも御手を差し伸べてくださる。その御手を掴むことが「義」であり、掴むことで主と同じ姿に癒やされていく。この福音を、ダイヤに譬(たと)えてみよう。
ダイヤは最も高価な宝石である。神の目からすると、人はまさしく「ダイヤ」であり、まことに高価で尊い者である。「わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している」(イザヤ43:4)。ところが、その高価なダイヤに泥(死)がついてしまい、本来の輝きを失ってしまった。そうなると、ダイヤである人は、自分は価値のない「ダメな者」だと思ってしまう。だが、ダイヤを造られた神はご存じであった。いくら泥がついてもダイヤの価値はまったく失われないことを。
そこで神は、ダイヤ(人)についた泥(死=罪)を洗い流すために来られた。「キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことを、あなたがたは知っています」(1ヨハネ3:5)。その泥は、神に無条件で愛されている自分を見えなくさせていたので、泥を洗い流すには、兎にも角にも、神がどれだけ人を愛してやまないかを明らかにする必要があった。それで神は、私たちのためならご自分のいのちさえ惜しまないことを十字架で示された。
神はそのひとり子を世に遣わし、その方によって私たちに、いのちを得させてくださいました。ここに、神の愛が私たちに示されたのです。(1ヨハネ4:9)
この「全き愛」が、神の愛が見えなかった「恐れ」を締め出し、「全き愛は恐れを締め出します」(1ヨハネ4:18)、「ダメな者」という罪の思いを洗い流してくれる。
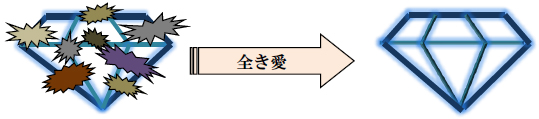
これが聖書の教えている福音であり、それは堕落した「ダメな者」を「良き者」にするという福音ではない。「良き者」にまつわりついた罪を、「まつわりつく罪」(ヘブル12:1)、洗い流す福音である。すなわち罪は、人の本性とはまったく関係がない。罪は死による「病気」なのであって、キリストの十字架は、それを癒やす薬である。
キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは、私たちが罪を離れ、義のために生きるため。その打ち傷のゆえに、あなたがたは癒やされた。(1ペテロ2:24、新改訳2017)
長きにわたり「福音の回復」のコラムを書いてきたが、それは「良き者」から「良き者」へと変えてくださる神の福音を回復するために書いてきた。キリストの十字架が、「あなたは無条件で愛される良き者だ!」と叫んでいることを知ってもらうために書いてきた。
最後にもう一度言うが、あなたが自分のことをどう思おうとも、あなたは「良き者」である。何があろうとも、神はあなたを無条件で愛し、弁護してくださるのだ。
もしだれかが罪を犯すことがあれば、私たちには、御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。(1ヨハネ2:1)
この弁護を知りたければ、周りに同情など求めないで、神の前で絶望したらよい。そうすれば、絶望にこそ希望があることを知るだろう。絶望という闇に輝くのが、キリストの福音だと知ることだろう。その輝きこそ、「あなたは無条件で愛される良き者だ!」と知らしめる、キリストの十字架にほかならない。
光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。(ヨハネ1:5、新改訳2017)
◇



































