――きっかけはティリッヒで、それから数冊「戦争とキリスト教」というテーマで書かれて、キリスト教の側からの反応というのはいかがでした?
「従軍チャプレンのことなんて研究すると、キリスト教主義の大学の就職に不利になるかもしれないよ」と言われたことはありました。実際にそんなことは全くなかったんですけれど(笑)。『キリスト教と戦争』も、牧師から「読んだよ」とだけは言われるんですが。特に中身についての感想は言われないんです。不思議な空気になりますね、いつも(笑)。
――『戦場の宗教、軍人の信仰』(2013年)の中で、自衛隊員のキリスト教徒が白眼視されていたことや、クリスチャンの自衛隊幹部が、日本基督教団の「こころの友」にエッセーを寄稿したら、牧師たちが「人殺しや侵略を正業とする自衛隊員は、実存的、社会的悪のただ中にある。(中略)自衛隊と連帯するよりも、拒絶こそ、教団にふさわしいのである」として、雑誌を焼却して激しい抗議活動を行い、編集部に謝罪記事を書かせる結果となったというエピソード、とても印象的でした。日本のキリスト教、特にプロテスタント、日本基督教団全体は全般的に左派的で、「反戦」以外で戦争を論じること自体許されない、存在すら認めない!というような風潮があるような気がするんです。それはなぜなんだろうって、ずっと感じてるんですけれども。
■ 関連記事:戦争とキリスト教を読む(2)戦場の聖職者、キリスト者軍人・自衛官の信仰から「戦争のリアル」を考える 『戦場の宗教、軍人の信仰』
これは私の印象ですが、「キリスト教が日本国憲法9条を支持している」のではなく、「憲法9条が日本のキリスト教に影響を与えた」のではないかと思ってるんです。宗教は社会に影響を与えるけれども、社会からも宗教は影響を受ける、影響は相互的であるというのは宗教社会学では常識な考え方です。
今のキリスト教徒たちは、自分たちの意思で憲法9条を支持していると思っている。でも、実は日本国憲法9条は、戦後にできた新しいものです。その憲法9条が「疑似宗教のようなもの」になって、日本のキリスト教に影響を与えたのではないかと感じるんです。「戦争放棄」という理想的なものがある以上、キリスト教も「理想」において負けてしまうから、支持しないわけにはいかなくなってしまう。だから、結果としては日本国憲法9条が、日本のキリスト教を極端な平和主義に走らせてしまったのではないかというイメージを、個人的には持っているんです。
だってキリスト教の主流派が、今ほど「平和主義・非暴力主義」にこだわるようになったのは、歴史的にも初めてなのではないでしょうか。もちろんクェーカーやメノナイトなどの歴史的な平和主義のグループは存在しましたけれど、主流派がここまで声高に反戦、原則非暴力主義、戦争反対になったのは初めてではないでしょうか。
ルターもカルヴァンも、条件付きで武力行使は認めていたわけです。「アウグスブルク信仰告白」「ウェストミンスター信仰告白」でも正しい戦争、合法的な戦争はある、という前提で書かれていて、それを継承しているわけですから。
――『キリスト教と戦争』の137ページで「認知的不協和」ということを書かれていて、とても腹に落ちた気がします。
少数ながらも、真の平和主義的キリスト教徒がいたこと、そして今もいることは十分に覚えておかねばならない。だが、彼らはあくまでも例外である。キリスト教界の多数派も、イエスの教えを文字通りに読めば、それらは確かに非暴力主義・平和主義であると認めざるを得ない。しかし、現実には大多数はそのように振る舞えない。だからこそ、彼らはそれを実践する「例外」の人々を念頭に「本当のキリスト教は平和主義です」と主張し、そうした人々をあたかも「本来の自分たち」であり「自分たちの代表」であるかのように思い込むことで、認知的不協和を軽減し、安心を得ておきたいのではないだろうか。
こういうことを書くから嫌われるんでしょうけれども(笑)。
――でも80代、90代の牧師さんは、本当に戦争を経験しておられますよね。例えば、広島で被爆して平和運動をずっとされてこられた宗藤尚三さんという牧師さんにインタビューしたときも、やはり経験した方だからこその「怒り」に、非常な説得力を感じました。
■ 関連記事:オバマ大統領のスピーチをどう聞いたか 18歳で被爆し反核運動に身をささげる宗藤尚三牧師に聞く
もちろんです。実際に経験した方には、自身の人生から存分に語っていただくしかない。でも、命に関わる価値観や戦争観は、時代とともに変わるものですから。アウグスティヌスもトマス・アクィナスも正戦を肯定していたわけです。そして現代では「いかなる戦争もだめだ」となっているわけです。だから、それぞれの時代の人々がお互いに声を上げていくしかないのだと思いますね。
――逆に言えば、少なくともその時代(1970年代)は、キリスト教界の中でも議論を巻き起こすぐらい同じ土俵が存在したということですよね。もう現代では、そんな議論すら起きないと思います。よくキリスト教徒は聖書を引用して平和や愛だと言いますけれど、旧約聖書にはいくらでも「ジェノサイド」が出てくるわけです。だから私は、聖書を一部引用しての議論には全く興味がないし、意味を感じないんです。
そもそも日本では99パーセントの人は聖書を読まないし、関心も権威もないわけですからね。日本のキリスト教徒はキリスト教より「日本人」としてのアイデンティティーが強いのではないでしょうか。だからこそ70年も昔の過ちについて謝罪する。それは間違っていません。でも本当に「キリスト教徒」であることがアイデンティティーの中心にあるならば、過去のキリスト教の蛮行についても謝罪するべきだと思います。十字軍も、南米の原住民虐殺も、原爆投下についても謝罪するべきだと思います。論理的に考えるなら。でもそういう人は1人もいない。それは実は「日本人である」ということに無意識の重みがあるからなのではないでしょうか。だから「日本人として」謝罪するという本音があるのかもしれません。
――「日本人として」なのに、外に対しては「キリスト教徒として」と語る、齟齬(そご)というか。そこではやはり韓国のキリスト教の歴史を思い出します。なぜ戦後、韓国でキリスト教があれだけ伸びたかというと、韓国は抗日運動でたくさんのクリスチャンが参加し、亡くなっています。それは「植民地を持った列強の中で、唯一日本が非キリスト教国だったが故に「世界史の中で唯一、キリスト教が『支配する側』としての負い目を全く負うことがなく正義の側に立てた」ことが大きいわけです。だからこそ、日本から独立後、数十年の間にあれだけキリスト教が一気に広がった。そして、南北に分かれていること自体も、旧約聖書のユダヤの北王国と南王国に分裂した歴史に重ね合わせているわけです。だから政治的、歴史的なものに重ね合わせているというのは、とてもよく分かります。
そこを意識の上で乗り越えるということは難しいことですよね。私は「キリスト教信仰と平和は、実際は無関係ではないか」とすら最近思うんです。日本は1パーセントもキリスト教徒がいませんけれど、世界的に見れば極めて平和で治安のいい国です。欧米やブラジルやフィリピンと比べても。とすると、国や社会の平和状態には現実的にキリスト教はほとんど影響も関係もないんですよね。それは、キリスト教にとっての「不都合な真実」かもしれませんけども。一人一人が信仰を持てば、その国は平和になるというのは、ただの幻想ではないかと思います。
――それは、牧師や聖職者は言えませんけどもね(笑)。
この本で一番書きたかったのは、「まえがき」に書いたことなんです。「キリスト教は、それ自体が『救い』であるというよりも、『救い』を必要とする救われない人間の哀れな現実を、これでもかと見せつける世俗文化である。キリスト教があらためて気付かせてくれるのは、人間には人間の魂を救えないし、人間には人間の矛盾を解決できない、という冷厳な現実に他ならない」。こういうことを書くと嫌がられるかもしれませんが。
――よく新書という分量でこれだけ盛り込まれたなと思うんです。一番面白かったのは、キリスト教では聖書の中で、信仰に関して「神の武具」「正義の胸当て」「信仰の盾」「キリストの兵士」とか、しばしば軍事や武器のイメージで語られていて、それは「単なるレトリック」と思われがちだけれども、修道士たちにとってそれは「気軽なレトリック」ではなく、むしろ「リアルな自己認識」というべきものだった。本質的に、信仰と軍事は親和性があるのものとして捉えられていたのではないか、という指摘でした。
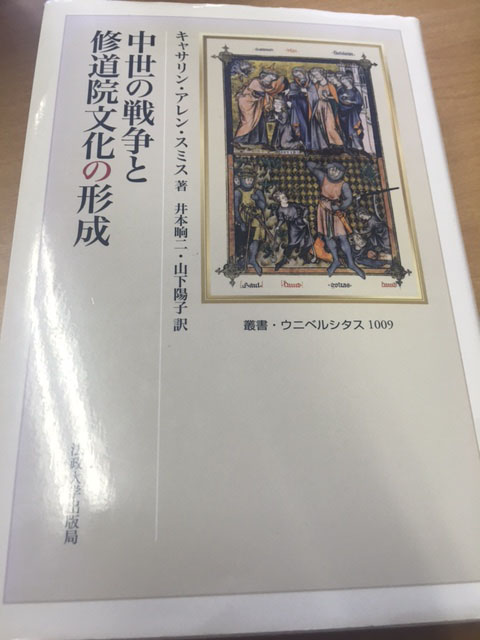
キャサリン・アレン・スミスという学者が『中世の戦争と修道院文化の形成』(法政大学出版局)という本の中で、修道士たちが、信仰の盾とか剣とかが出てくるのは単なるレトリックではなくて、本当に自分たちを戦士だと信じていたということを、かなり深く研究しています。また、アルフレート・ファークツは『ミリタリズムの歴史―文民と軍人』(福村出版)の中で、救世軍や元軍人のイグナチウス・ロヨラがつくったイエズス会を例に挙げながら、キリスト教が「宗教的博愛主義のために軍事的本能につけ込もうとする試み」を指摘し、「種々の教会組織も、軍事的な形態と心的傾向を利用してきた」と書いています。
――その中でそのような信仰を語るとき、そのような傾向への警戒感や自覚はあったんでしょうか。
それは無意識であり、当然だと思っていたのではないでしょうか。特にイエズス会は象徴的ですが、「ミッション」という映画で描かれるように、いきなり世界のへき地に行って宣教に命を懸けることを求められるわけですから。はっきり言って、軍隊よりも過酷ですよね・・・。
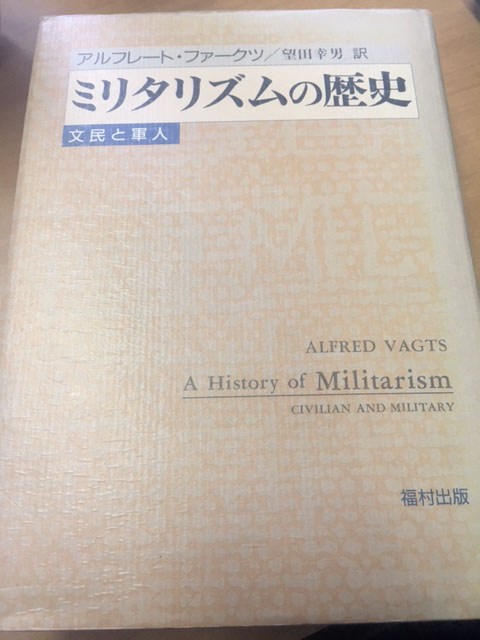
――以前元特攻隊員から、戦後イエズス会の修道士になられた大木章次郎神父様という方にインタビューをしたんです。
■ 関連記事:戦争経験者に聞く戦後70年(5):特攻兵器人間魚雷「回天」隊員からイエズス会士へ 大木章次郎神父の信仰と倫理と戦争
もう亡くなられてしまいましたけれど。戦中は人間魚雷回天の隊員をされていて、終戦後はイエズス会士になり、30年近くネパールの貧民地区で活動していた方なんです。ネパールではキリスト教への弾圧があって、朝起きたら、同僚の神父さんが首を切られて殺されていたこともあったそうです。大木神父様は「死ぬことは怖くないけれど、ネパールの汚い牢獄に投獄されてずっと中でいたらしんどいだろうな」と思って「特攻隊よりもずっと厳しい経験でした」とおっしゃっていました。しかも、それをにっこり穏やかに微笑しながらおっしゃるんです。私はそれに感動しながらも、本当に数百年の間に宣教のために血を流してきた歴史があるイエズス会のすごみを感じて、畏怖というか畏敬の念を感じたことがあります。軍隊よりもはるかに強い信念と結束というものを肌で感じました。
世界的な霊長類学者で、京都大学総長の山極寿一先生が、戦争が始まる3つの理由を挙げています。① 言語、② 土地の所有、そして ③ が「死者につながる新しいアイデンティティー」だとおっしゃっている。この3つが、大量虐殺を辞さない苛烈な戦争を人類が起こすようになった3つの原因ではないかと言っています。
まず言語があるから、国や民族など、幻想の共同体を人々が共有できるようになった。そして1万年前から農業が始まって、土地の所有が始まった。でも、人間が一生に所有できる土地の広さなど限られている。だからこそ「死者を利用することになった」と書いているんです。「この土地は先祖から引き継いだから自分たちのものだ」と主張できるようになった。だから「人間は死んだ祖先から利益を受け継ぐことができるという意味で、他の霊長類と違う」と解説しているんです。
―― ③ は動物ではあり得ないものですよね。
祖先の死者から利益を得ると同時に、祖先がやったことに負い目をも持つようになった。祖父がやった悪事を孫の代が謝ることがあるように、ネガティブなこともまた引き継ぐ。死者のプラスもマイナスも引き継いで生きるようになったから、人類は「祖先の名誉を守る」「祖先の悲願を達成する」など、アイデンティティーを死者と結び付け、つながるようになったということを書いているんです。
これは広い意味での宗教ともつながる問題なので、こういう視点から戦争の原因を考えるのは面白いなと感じたんです。ただ、ネアンデルタール人が仲間を埋葬していたという事実もありますし、どこから人が死を供養する観念が生まれたかは難しい議論ですけれども。
――人類学者ならではの興味深い視点ですよね。(続きはこちら>>)



































