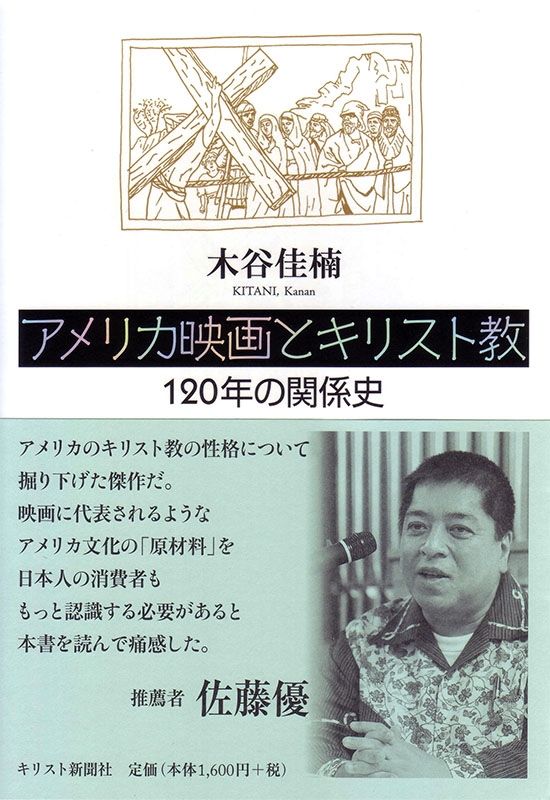ウィリアム・ワイラー監督の「ベン・ハー」(1959年)をご覧になった方も多いだろう。そこにイエス・キリストが登場する場面があるが、なぜか後ろ姿でしか映らない。その理由は、当時、アメリカ映画の倫理規定を定めたプロダクション・コードにある。「いかなる宗教的信仰も愚弄(ぐろう)されてはならない」という規定により、神の子キリストを人間の俳優が演じることが冒涜(ぼうとく)だとその頃は見なされていたのだ。
ところが、時代が変わると映画も一変する。最新作「沈黙」が話題のマーティン・スコセッシ監督による「最後の誘惑」(1988年)。キリストが女性と関係を持つこの映画が公開されたとき、日本のキリスト教界でもたいへん物議を醸したが、「私はこの映画を神への祈り、あるいは礼拝のように作った。私は司祭になりたかった。私の人生はずっと映画と宗教が占めていて、それ以外には何もないんだ」とヴェネチア映画祭での記者会見で同監督は語ったという。
チャールトン・ヘストンがモーセを演じ、紅海が割れるシーンが有名な「十戒」(1956年)。こうした数々の聖書的映画を作ってきたセシル・B・デミル監督によるキリスト映画「キング・オブ・キングス」(1927年)は、宣教師が世界各地で上映するなど、伝道のためにいちばん利用された映画だったと同監督は誇らしく述懐している。
一方、創世記の「カインとアベル」のエピソードが下敷きとなっている「エデンの東」(1955年)。これを映画化したエリア・カザン監督はギリシャ移民として差別され、当時「赤狩り」(共産主義者の追放)に大きく翻弄(ほんろう)されたこともあり、アメリカ映画界で認められるためには、あえてキリスト教的な物語を選ぶ必要があったという。
また、「アルマゲドン」(1998年)や「ディープ・インパクト」(同年)など、地球の滅亡が大スペクタクル巨編として描かれた映画が近年続けて製作されていたのは、「キリスト教福音派の持つ終末思想が一般に浸透したことにも遠因がある」(170ページ)とか。
このようにわれわれ日本人はアメリカ映画に触れる機会が多い。そして、それがどのような背景で作られたのかを知らずに、無批判に観ていることがよくあるのではないだろうか。しかし、ただ十把一からげに「キリスト教的な映画」と考えるのではなく、その「原材料」が本当はどういうものなのかを吟味してほしいと著者は訴える。
本書は、1890年代に映画が誕生してから現在までの120年間、アメリカの映画界とキリスト教界の関係がどのように変化していったかを時系列的に概観していく内容となっている。

執筆したのは、同志社大学神学部助教で日本基督教団賀茂教会伝道師でもある新進気鋭の女性神学者。日本のキリスト教界では貴重な存在といえる。
ただ本書は、福音派の人が読むと、手厳しい内容になっているかもしれない。たとえば、「キリスト教保守派の思想を文化に乗せて広めようとすることは、現代風に洗練された帝国主義的風潮」であり、福音派は「(昔、ローマ帝国が)他の宗教を迫害するための道具としてキリスト教を使ったように、自らが達成したいと欲する目的のためにキリスト教を利用する」人々であり、「自分たちだけが救われることを念頭に置いている」という。それに対してリベラルな立場の者は、「嘆き苦しむ民たちとともに苦しむ中で、神の御言葉を取り次ぐ役割を担う」といった宗教哲学者の言葉が紹介されている(184ページ)。
もちろん、福音派といっても、著者が否定的に考えるようなクリスチャンや教会ばかりではない。そういう善悪二元論的な単純な図式化はすべきではないだろう。しかし、保守的なキリスト教的文化が体制側に立ったときの危うさと問題点をキリスト者が心に刻み付けておく必要があることは確かだ。
どうしてもリベラルな立場から福音派はしばしば攻撃されるので、もう少し自己批判的な態度も併せ持ちつつバランス感覚のある内容になれば、さらに読み応えが増すのではないだろうか。
木谷佳楠著
『アメリカ映画とキリスト教―120年の関係史』
2016年12月19日初版
A5判 206ページ
キリスト新聞社
定価1600円(税別)