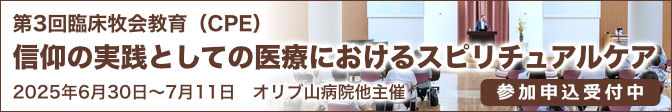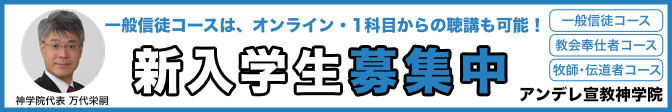今回は、第1ヨハネ4章15節~5章5節を読みます。
信仰に基づく愛
4:15 誰でも、イエスを神の子と告白すれば、その人の内に神はとどまってくださり、その人も神の内にとどまります。16a 私たちは、神が私たちに抱いておられる愛を知り、信じています。
前回お伝えしましたように、4~5章には、私たちの「愛」と「信仰」と「永遠の命(希望)」について記されています。第1ヨハネ書がこのことを書いているのは、「信仰・愛・希望」(第1テサロニケ書1章3節他)を強調しているパウロとよく似ています。ただ、第1ヨハネ書では、「神が人の中にとどまっている」という神と私たちの関係性、そして私たちの側からそれを表現する「信仰」と、そこに存在する「愛」が密接に関連付けられており、この15~16節aは特にその関連を示していると思います。
このことを理解していただくために、ここで2冊の注解書から、16節aに関する注解の一部を引用したいと思います。
信仰と愛との内的な関係はキリスト教的に見て、見過ごすことはできない。それは第一ヨハネが打ちたてているものであり、人間的に見て信仰が〔愛に〕先立つこと、また愛が信仰に依存していることをも含んでいる。神がたんに愛をもち、愛を行使するだけでなく、神ご自身が愛でありたもうということを知っているのは信仰だけであり、そして信仰は神の御子イエス・キリストの出来事からそのことを知るのである。(ハンス・ヨーゼーフ・クラウク著『EKK新約聖書注解XXIII/1 ヨハネの第一の手紙』380ページ)
神との交わりに与る人々の信仰共同体が「神の愛」によって強められていることを物語る。「神がわたしたちのうちに持っている愛」という少々回りくどい表現は、7節から15節まで、いろいろな形で述べられてきた「神の愛」を総括し、わたしたちの愛と信仰が、何よりも神の積極的な導きによるものであることを印象付けている。(三浦望著『NTJ新約聖書注解 第1、第2、第3ヨハネ書簡』297ページ)
このように、ここで示されている「私たちの愛は、信仰によって神様から頂いたものである」ということを伝えているのが、第1ヨハネ書全体の特徴であると思います。私はこの点において、第1ヨハネ書がパウロの「信仰・愛・希望」論を一歩凌駕(りょうが)しているように思います。
光と愛
16b 神は愛です。愛の内にとどまる人は、神の内にとどまり、神もその人の内にとどまってくださいます。17 このように、愛が私たちの内に全うされているので、裁きの日に私たちは確信を持つことができます。イエスが天でそうであるように、この世で私たちも、愛の内にあるのです。18 愛には恐れがありません。完全な愛は、恐れを締め出します。恐れには懲らしめが伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。
19 私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。20 「神を愛している」と言いながら、自分のきょうだいを憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える自分のきょうだいを愛さない者は、目に見えない神を愛することができないからです。21 神を愛する者は、自分のきょうだいも愛すべきです。これが、私たちが神から受けた戒めです。
第1ヨハネ書では、「神は○○です」という言葉が、1章5節の「神は光です」と並んで、この個所の冒頭に「神は愛です」と記されています。これは、ヨハネ福音書で伝えられているイエス様の言葉「私はある」(エゴー・エイミ)や「私は○○である」(エゴー・エイミ・○○)と似ています。
そのため私は、第1ヨハネ書がヨハネ福音書の伝え方を継承しているのではないかと考えています。そして、ヨハネ福音書おいてエゴー・エイミがとても重要なフレーズであるように、第1ヨハネ書の「神は光である」「神は愛である」は、この書において最も重要な言葉であると言ってよいのではないかと考えています。また、この書の背景に存在する異端者たちは、この2つのことを教えていなかったのではないかと思います。
1章6節に「神と交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、私たちは偽りを述べているのであり、真理を行ってはいません」とあります。「闇は真理ではない」のですから、「光は真理」ということになるでしょう。つまり、光と愛を大切にしているということは、真理と愛をこの書は伝えているということです。それは、既にお伝えしている第2ヨハネ書と、これからお伝えする第3ヨハネ書にも共通していることです。
ヨハネ共同体の核心教説
16節bからは、「神は愛です」ということが、さらに具体的に展開されています。神様が愛であるが故にそこにとどまるならば、私たちも愛し合えるということです。「互いに愛し合いなさい」という戒めが、既に3章から伝えられていましたが、それは「神は愛です」というこの命題を基に、そこにとどまるならば、その戒めを守ることができるということでしょう。
19節の「私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです」は、愛の神が具体的に展開されているこの部分のクライマックスといえるでしょう。ヨハネ福音書3章16節の「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された」という言葉をほうふつとさせます。
世に遣わされた「道」であり、十字架において命を与えることよって神様の愛を人々に伝えたイエス様が、その十字架を予知した最後の晩餐の席で弟子たちに語った「私があなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい」という戒めを実践していくべきだということが、この一節に集約されているように思えます。
ここに、ヨハネ共同体の核心教説を見るような思いがします。それは、「神様の愛を『道』であるイエス様が伝え、その愛を受け取った者が、隣人を愛する愛へと転換させていく」と要約することができるでしょう。そして、このヨハネ共同体の核心教説は、今日の私たちの教会においても、大切な教説でありましょう。
ヨハネ共同体の信仰告白
5:1 イエスがキリストであると信じる人は皆、神から生まれた者です。生んでくださった方を愛する人は皆、その方から生まれた者をも愛します。2 神を愛し、その戒めを守るなら、それによって、私たちが神の子どもたちを愛していることが分かります。3 神の戒めを守ること、これが神を愛することだからです。その戒めは難しいものではありません。4 神から生まれた人は皆、世に勝つからです。世に勝つ勝利、それは私たちの信仰です。5 世に勝つ者とは誰か。イエスが神の子であると信じる者ではありませんか。
前述したように、第1ヨハネ書では「私たちの愛は、信仰によって神様から頂いたものである」ということが伝えられていますが、ここにはその基になる信仰について書かれています。それは、1節の「イエスがキリストであると信じる」と、5節の「イエスが神の子であると信じる」という2つの信仰告白によって挟まれています。
ヨハネ福音書20章31節にも「これらのことが書かれたのは、あなたがたが、イエスは神の子メシアであると信じるため」とありましたから、これらはヨハネ共同体の信仰告白であったのでしょう。お伝えしてきたヨハネ共同体の核心である「神様の愛を基にした隣人愛」と、その共同体のもう一つの核心である「信仰告白」が、今回の箇所で織り交ぜられているように思えます。
この1~5節では、ヨハネ共同体を家族として見ているように思えます。神様を父として捉え、そこで生まれた子どもたち――恐らくこの場合は生命体としての子どもではなく、信仰者としての子どもを示している――をきょうだいとして、父を愛するならそこから生まれてきたきょうだいたちも愛することができると説いています。
ですから、きょうだいを愛するために父である神を愛し、その戒めを守るとことが大切であるということです。それが「信仰」とされているように思えます。その信仰に生きるならば、世に打ち勝つことができるというのです。世とは神の光と神の愛を信じない、ヨハネ共同体の背後にいる異端者たちのことでしょう。
今日でも、信仰によって私たちは、さまざまな「世」に打ち勝っていくことができ、隣人愛を実践することができるのです。(続く)
◇