英国の劇作家で、英文学の代表的な存在として語られるウィリアム・シェークスピア。「聖書を抜きにしてシェークスピアを語ることはできない」として、改革主義福音連盟三鷹福音教会(東京都武蔵野市)では、併設する福音総合研究所主催で年に2回、「シェイクスピア講座」が開かれている。その7回目が5日、同教会で開催された。シェークスピアの作品の中でも特に議論を呼ぶ戯曲『じゃじゃ馬馴らし』を取り上げ、同教会牧師で同研究所所長のラルフ・スミス氏が、「聖書に基づく結婚観」について話した。
日本の戦国時代、関ヶ原の戦いと同時代を生きたシェークスピアの作品は、今もなお色あせていない。書籍を通して、また舞台を通してシェークスピアの作品と出会うとき、悲劇は私たちの涙を誘い、喜劇は私たちの笑いを引き起こす。そこには、時代を超えて変わることのない真理が隠されているような気がしてくる。シェークスピアは、その作品の中で、歴史書や神話など、他の多くの書物について言及し、文章に深い奥行きを持たせている。スミス氏によれば、その中でも聖書への言及は圧倒的に多く、引喩(いんゆ)という比喩法を用いて、聖書の言葉を文の中に取り込んでいるという。聖書から引喩した箇所は、全37作品で何と2千にも及び、ただ量が多いというだけではなく、深い理解をもって的確に適用されているさまには、目を見張るものがあるという。
シェークスピアの作品には、必ず何かしらの教訓が隠されている。シェークスピア自身、作品を通してメッセージを語り、説教するということをはっきりと意識していたとスミス氏は話す。物語を通して、シェークスピアが何を伝えたかったのか解釈するためには、聖書が大きな影響を与えているという事実に立ち、その取り入れられ方を見ることが大切だ。
今回取り上げられた『じゃじゃ馬馴らし』は、シェークスピアの初期の作品で、第1作目だとも推測する学者もいる。そのため、後期の作品ほど洗練されてはいないが、劇中劇の手法が取られ、3つのストーリーを1つの物語にまとめた作品だ。スミス氏は、シェークスピアになじみのない人でも理解しやすいように、物語が書かれた歴史的背景や前提となる知識から説明を始める。説明は決して難しくなく、子どもたちでも理解でき、かつ知的好奇心を刺激するようなものばかりだ。日本語では「じゃじゃ馬」という翻訳がされているが、原題で使われている「Shrew」はトガリネズミのことで、「気性が荒く、キーキー騒ぐ、けんかっ早い」女性を指して使われる言葉でもあるというスミス氏の解説を聞くと、物語全体の印象が確かに変わって見える。
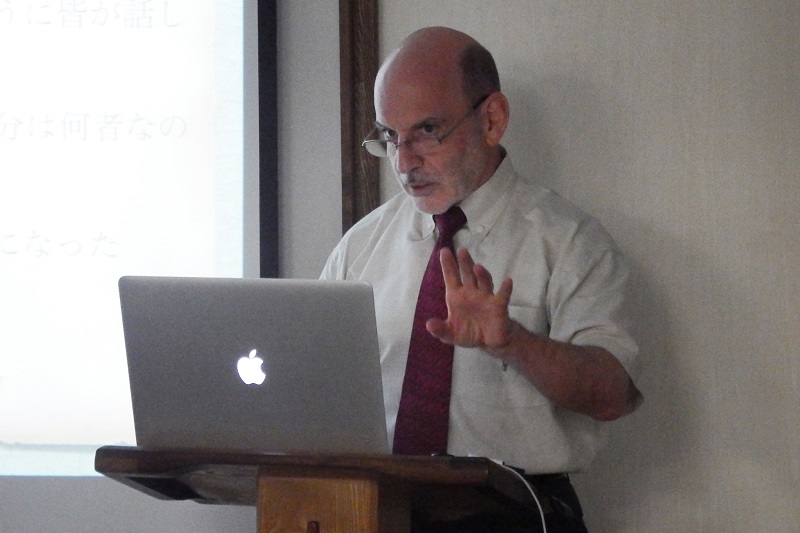
この物語の本筋は、資産家の娘で評判のじゃじゃ馬キャタリーナが、求婚者ペトルーチオによって貞淑な妻に変えられていくというもの。スミス氏は、「じゃじゃ馬馴らし」というモチーフ自体は、シェークスピア以前からも喜劇でよく取り上げられていたことを指摘した上で、ひどい暴力によって妻を馴らしていく他の作品と、言葉と愛によって妻が変えられていくこの作品とは圧倒的な違いがあると話す。男性上位社会、封建主義の影響が残る時代にあって、シェークスピアは、「妻は夫に従い、夫は妻を愛する」という聖書の愛に基づく結婚観、社会秩序を形成する家庭の基盤は愛であるというメッセージを、この作品を通して示しているのだという。また、スミス氏は、「夫婦の愛」だけでなく、「親子関係」「教育の方法と目的」など、さまざまな主題が盛り込まれていることも話し、参加者が各自で物語を読み直す際の新しい視点も提示した。
シェークスピアの作品と聖書の深い関係に興味を抱いたスミス氏は、1980年代からシェークスピア研究を続けており、米国やカナダ、そして日本各地で関連講座を開いている。地域への福音宣教の一環として開いた聖書の公開講座シリーズでシェークスピアの作品を取り上げたところ、非常に反応が良く、シェークスピアを扱った継続した講座を求める要望があったことから、この企画が始まったという。この日も、参加者約50人のうち、半数ほどが地域の人たちで、質問に多くの手が挙がるほど熱心に聞き入っていた。
両親と共に参加した同教会に通う中学生は、「シェークスピアの作品を自分で読んでも意味が分からないことが多いが、説明をしてくれる人がいるとすごくよく分かる。映像化された作品を見比べられるのも楽しい」と感想を話してくれた。両親によると、普段から家族全員でシェークスピアの作品を読んで共通の話題にしているといい、聖書の言葉を生活の中でどのように生かすか、適用の仕方を子どもと学ぶのに最適な機会になっているという。また、講座に参加することで、他の作品を読む際の視野が広がり、聖書を読むのも楽しくなると話してくれた。



































