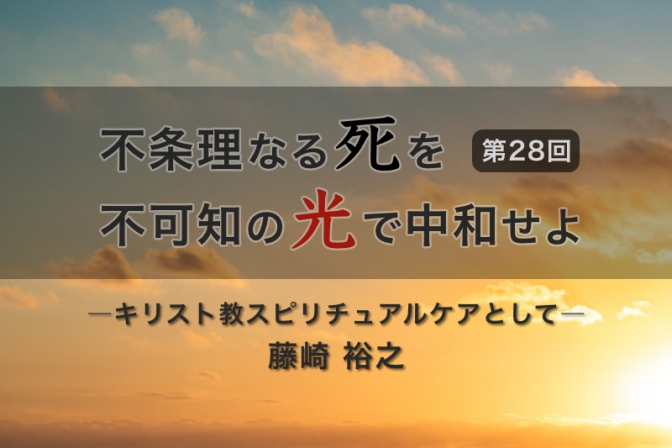不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(28)
悪霊がやはり気になる
イエスは悪霊の支配者ではないが、悪霊などはいとも簡単にどうにでもできる。と極端な言い方はしないほうがよいのかもしれない。もちろんイエスに可能なのは、悪霊を人間から押し出すことであって、悪霊を人間に憑依(ひょうい)させることではない。そもそもイエスには、悪霊が人間に取り憑(つ)くことを阻止する気がないようにも思えてしまう。救い主であるなら、人を苦しめている悪霊と呼ばれる者どもを根こそぎにしてくれたらよさそうなものだ。あるいは、ある人には二度と「邪」なるものが取り憑かないように封印でもしてくれたらよいのだ。そういう意味の「清め」をイエスは行わないのである。悪霊から遠ざかるのは人間次第ということであろうか。もちろん、そうではないだろうが。
さて、どうもキリスト教には「結界」という発想がないように思う。清めのお札のような習慣がないのは、ユダヤ・イスラエル的なのかもしれないが、聖書をくまなく探せば何か答えがあるのかもしれない。しかし重要なことは、悪霊の取り憑きを神罰だと考えない方がよいということだろう。悪人の上にも雨は降るし、太陽は昇るのである。雨が悪人にとって恵みの雨となることもあれば、太陽が善人にとって灼熱(しゃくねつ)の光になることもある。雨そのものに意味はないだろうし、太陽そのものが神でもない。雨や太陽の向こう側に何を見ているのか、というこちら側の問題である。
ある教会の祈祷会で東日本大震災について祈る機会があった。その時に、そこの牧師が「この度の震災と津波は神の罰として与えられたものであり、悔い改めの機会にしたい」と語っていたのを思い出す。その是非は書かないが、なるほどそのように受け止めるのだと思ったし、それがプロテスタント的なのだと強く感じたのである。神の計画しないことは実現しないということか。現実とは神が計画されたものであるから、そのように実現しているということか。それがいわゆる摂理ということだろう。
イエスは遺棄された?
確かにノアの時代の洪水は神罰であるように思われる。滅びゆく人々のうめきはいかようなものであったのだろうか、変に心情的にもなる。ノアの家族は舟の上からその様子を見ていたわけだし、いくら悪を働いた人々であっても、その死にゆく姿を目の前にするというのはかなりしんどいことではなかったか。むしろ、ノアの家族の救済こそが神の偉大さであると語るものと、開き直って受け止めるしかないのかもしれない。
遺棄された者たちという表現がなされたりするが、そういう場合、神は遺棄された者たちにとってもはや神ではないのか。ある人にとって神は神であるし、ある人にとって神は神ではなくなるということがあり得るのかどうか。遺棄されるといえば「イエス・キリストこそが神によって遺棄されたものである」とカール・バルトが好んで表現している。イエスが神に遺棄されたことによって、遺棄されるべき人間がその滅びをキャンセルされたというのが彼の考えの根幹にある。代理贖罪(しょくざい)ともいうらしい。いわゆる「主は私たちに代わって十字架の苦しみを引き受けてくださった」というわけだ。
イエスは助ける
そろそろ本論に入るのだが、悪霊はイエスによっては遺棄されない。ただ放逐されるだけである。その存在を消し去るということはしない。それはなぜだろうか。最終戦争で決着がつくまで悪霊の類いは放置されているのだろうか。恐らくこういうことである。イエスの関心は人間そのものである。悪霊退治ではない。悪霊どもが人間を苦しめるから追い出すのである。悪霊が存在しているから人間を助けるのではない。人が生きて、その結果として悪霊に苦しむことがあれば、その時々に応じて悪霊を追い出すのだ。
われらを汚すものとは?
「人の中から出てくるものが人を汚すのである」とイエスは言われた。もちろん排泄物のことではない。イエスは言われる「人の心の中から邪念が出る。姦淫(かんいん)、盗み、殺人、・・・すべて内部から出て、人を汚すのである」(マルコ福音書7章14節以下)。つまりイエスが言われるには、人を汚すものというのは、外から入ってくるものではないらしい。まあ、この場合は主に食べてはならないと定められた食物に関することであるが。
聖書に従えば、ブタは蹄(ひづめ)が割れていないから食べてはいけないはずである。タコとかイカの類いも鱗(うろこ)がないのでダメ? 確かウナギもダメだったはずである。それはなぜか、と問えばそれなりにいくらでも理由付けはできるのであろうが、大体どの文明にも食べてはならない禁忌というものがある。
ダメだと言われているから食べないだけならよいが、万が一食べてしまった場合はどうするか。黙っているというのが正解だが、ついつい善良な人は食べてしまったことを白状してしまう。誰かが禁止されている食物を食べているところを見た場合はどうか。見て見ぬふりをしたらよいのだが、そういう場合も黙っていることができない厄介者がいるのである。いちいち誰かが見張って誰かに告げ口をする、あるいは公然と言いふらす、全くもって厄介者だ。
結局は中身が問われる
何が人を汚すのか。そんなことを論じるよりも、お前自身の中身を知った方がよいのではないか、とイエスは問われているのだ。お前の中にある邪念こそがお前自身を汚しているのだ!ということだ。邪念というのも厄介なのだ。それはもともと人間に備わっているものなのか。むしろ、邪念については「そう、そう。そういうものが悪霊の正体なのだ」と言ってしまった方が簡単なのだが、そういうことをしたら宗教ではなくなる。それは心理学の世界だ。
われわれは自らに邪念があることは知っているが、なぜ邪念があるのかは知らない。邪念というものが自分自身も含めて人間社会を歪めていることを知っている。しかし、邪念の収め方は知らない。大抵の場合は、何とか邪念を押しとどめてそれが結果に表れないようにしているが、それでも言葉として、表情として、仕草として、ついつい外側にあふれてしまうこともわれわれは知っている。しかし、邪念なる心の汚れが自分自身を台無しにしていると承知するとして、承知したら消えるかといえば、答えはNOである。筆者は、邪念が消えた人間を見たことがない。であるからイエスは邪念がある人間が悪いと言っているわけでもなさそうである。
何を食べない、どこに行かない、誰と会わない、そのようなことに気を付けていたとして、結局それは体裁を整えているだけである。中身は変わらないのだ。その事実に気付かなければならない。いや、気付いている。気付いているからなおさら、そのような自分自身を超える何かに出会うことがなければならない。体裁を整える人生を超える、超えさせてくれる何かに出会うことが肝心なのだ。
いやでもキリストを知ることになる
イエスは誰にも知られたくないと考えてティルスの地方に出かけていった(マルコ福音書7章24節以下)。そこは異邦人の土地である。現在はレバノンに位置している。海岸沿いにあって大変に古い由緒ある町である。ガリラヤ湖から北西に進むとティルスの町に行き当たる。人目を避けるようにそこに行ったはずであったが、その場所に汚れた霊に取り憑かれた幼い娘を持つ異邦人がイエスの足元にひれ伏した。この女性はシリア・フェニキアの生まれであった。つまり現地の人ということになる。
イエスは隠れ通すことができない。神の子イエスは人に知られる方なのである。われわれ人間は、神の子イエス・キリストを知ってしまうのである。分かってしまうのだ。この事実は大変に重要なことである。
「キリストを知ってしまった」ことが分かると、人間というのは気持ちが楽になるものだ。そうでなければ信仰者といえども、キリストを知らねばならぬ、キリストと出会わねばならぬと思うと、われわれの心は焦るのである。焦ってはならない。われわれはキリストを知ってしまう瞬間を待つべきなのだ。そして知ってしまったらやはり、このフェニキアの女性のように躊躇(ちゅうちょ)しないことが肝心なのであろう。この女性の娘は汚れた霊に取り憑かれている。さあ、いよいよ汚れの問題にイエスとわれわれは直面していくことになる。(続く)
◇