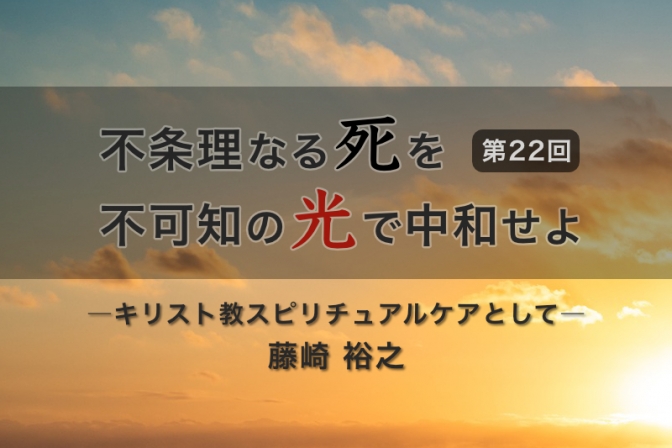不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(22)
福音を恥じる?
「わたしは福音を恥としません」とパウロは言う。われわれにとっては不思議に聞こえる言葉である。なぜなら、現代において福音を恥だとののしる人はまずいないからである。そもそも福音というのは、パウロにとってはハッキリとしたものであって、例えばギリシャ語を直訳して「良き知らせ」と言い換えて説明する必要もない。パウロにとっての福音とは、イエス・キリストに他ならないからである。そしてパウロにとって、このイエス・キリストこそが神であって、けして「良き知らせ」をこの世に携えて来られた単なるメッセンジャーではないのだ。
一方で、パウロの言葉から、当時は福音を恥とする者たちがいたと想像することができる。それはパウロが「ユダヤ人」という言い方をして少々揶揄(やゆ)している人々である。多くのユダヤ人にとって、イエスはキリスト(救い主)でもないし、まして神ではない。神が人間の姿を取るわけがないのだ。神は神であり、人間は人間である。両者の間には超えようもない隔たりがあることくらい常識的なユダヤ人は知っていたのだ。現代人においてもそれは同様である。
宗教世界が時として現人神的な思想に左右されることはあるが、それも大抵の場合は限定的なものである。つまり、人間がある時から、あるいはある事件を契機にして、神としてあがめられることはある。しかし、そうした場合も大勢いる神に仲間入りするというくらいであって、ただ一人の神と認知されるわけではない。だが、イエスの場合は、そう認知されたわけである。歴史的にいえば、こういうことになるだろう。ある人々が十字架で処刑されたイエスという人をキリスト、つまり救い主として信じるようになったのである。
これは当時のユダヤの人々も、ユダヤを治めていた幾ばくかの外国人にとっても驚くべきことであったと思う。いやむしろ、驚いたのはイエスをキリストと信じた人々自身であったかもしれない。彼らは、その人間的な魅力や宗教的な卓越性によってイエスを慕い、イエスと共に行動した人々であったが、本当の意味でイエスをキリストだとは信じていなかっただろう。せいぜい、ユダヤという国をその信仰においてもう少しマシな方向に導いてくれるだろうという期待を抱いていたにすぎないだろう。ところが、彼らの期待を大きく超えて、イエスは救世主と信じられるようになり、ついには神そのものであると確信されるようになる。それが福音の出来事なのだ。
信じていることを驚く
そういう意味において、このイエスを今や「救い主」として信じている自分自身に気付いた彼らもびっくりしたであろう。もちろん、われわれが通常、福音と呼んでいる事柄は、イエスの行動、言葉、十字架の死、そして復活を通して信じられていったわけで、信じるか否かの境界線というのは、彼らにとっても曖昧なものであったのかもしれない。何より語らなければならないのは、イエスの死、つまり十字架というものは、ある時点においては彼らにとって大きな「恥」であったのだ。
十字架刑は、反ローマ的な活動や奴隷の反乱など、社会に大きな影響を与えた犯罪者に適応されたらしい。処刑方法としては大がかりなものであるから、適応範囲も限られていたのであろう。イエスの場合は、ユダヤの民衆を扇動したということで、ユダヤ人指導者たちから告発されたのだった。死に方に良いも悪いもないように思うが、とにかく十字架というのは、公には悪い死に方として考えられていたに相違ないだろう。それ相当の悪事をしたから、それ相応の悪い死に方をするということである。それが一般民衆から見た十字架の印象であろう。であるから、弟子たちにとってはこのようなイエスの死というものは、ある時期まではやはり「恥」であったろう。つまり、十字架で死んだ恥ずかしい人間をキリストだと信じることは、大方のユダヤ人には恥ずかしいことであったのだ。
阻止すべき信仰
また、大方のユダヤ人にとって救い主ではない人物をキリストとして言い広めているという点においても、それはユダヤ人全体の問題となった。さらにいえば、イエスは人間を超えて神の子であるとか、神と等しい者であるとか、そういう広め方もされているわけで、伝統的ユダヤ主義者にとっては「これはいったい何だ」ということになる。
確かに、あのイエスは十字架で他の人間同様に死んだ。その姿をユダヤの指導者たちは見ていたわけで、幾ばくかの人々はイエスが十字架の上で何か奇跡を起こすのではないかと期待もしていたが、それも見事に外れたわけである。どう考えても、このイエスがキリストとして信仰される余地などないのである。どこをどのようにすればキリストとして信じられるのかと疑問を持つのも当然である。イエスが復活したという出来事にしても、それはけして華々しい登場の仕方ではなく、ごく少数の人々にごく控えめな姿として現れたわけで、当然のごとく、大勢のユダヤ人にとってそれはイエスがキリストである証拠とはならず、議論にさえもならないことである。
それにもかかわらず、時を経て、いや聖書に従えば、十字架と復活後のかなり早い時期から、イエスをキリストと信じる「迷信のごとき」現象が広まっていく。それが歴史の事実であって、今日においてはもはや迷信とはいえないものになっている。結局のところ、指導的ユダヤ人にはキリスト信仰を止められなかったのである。一方、われわれキリスト教徒は、それはたまたまそうなったのではなく、神ご自身の力によって必然的にそうなったと考える。要するにそれは不思議ではない。
しかし、ユダヤ人にとっては不思議を超えて由々しき事態となっていったわけで、この十字架で死んだ人をキリストと言い広める人々が民族の恥さらしとなる前に、何としても阻止しようと必死になったわけであり、その中に他ならぬパウロ自身がいたのである。パウロはある時期まで、熱心にキリストの教会とその信者たちを迫害していた。だから、キリスト教徒となったパウロが「わたしは福音を恥としません」と告白するとき、それは単なる哲学的な思考として語ったのではなく、かつて熱心なファリサイ派ユダヤ教徒として、このキリスト運動を恥じて迫害していた自分自身を思い出しながら語ったのであろう。何よりキリストを信じる「自分自身を恥とはしない」という強い信念があったに違いないのだ。
パウロの宣言
さて、パウロが「ローマの人々へ手紙」を書いた時点で、ローマにはイエスをキリストと信じる人々が幾らかいたわけである。その人数を把握するのはほとんど無理であるが、ネロ帝が紀元64年にキリスト教徒を処罰した記録が残されており、その時の様子をタキトゥスはこのように書き残している。
このキリスト教徒という呼称はディベリウス帝の時、総督ポンティウス・ピラトゥスによって処刑された「クレストス=Chrestos」の名に由来する。この呪われた迷信は、しばらくは抑えられていたが再び勢いを盛り返し、この災厄の発祥地ユダヤにおいてばかりでなく、あらゆる恥ずべき醜悪なものが四方から集まってきているこのローマにおいても氾濫していた。(J・ダニイル著、上智大学中世思想研究所編訳・監修『キリスト教史1 初代教会』180ページ)
ここではっきりと分かるのは、「呪われた迷信」「氾濫」という言葉から連想されるキリスト教徒をめぐる状況である。福音を恥ずべき迷信と認識する者たちがいたこと、ローマにおけるキリスト教徒の数は家庭集会程度ではなく、かなりまとまった数がいたであろうということが分かる。しかし、紀元64年という時期は、教会誕生からわずか30年ごろのことである。当時は、今のような通信技術があるわけでもない。そのため、その内容がローマの市民に広く認知されていたとは思えない。キリスト信仰がどのようなものであるか、一般には知られていない中で、「呪われた迷信」と認知する人々がおり、さらにそれをわざわざ言い広めた人々がいたわけである。要するに、悪評をばらまく人々がいたのだ。そしてありがたいことに、イエスがユダヤ総督ポンテオ・ピラトによって処刑されたこともきちんと伝えられていたのである。総督により十字架刑で処刑された人間を救い主として信じているのだ、これはまさに呪われた迷信だ、大いなる恥さらしだ、という告発がローマで行われていたであろうと想像できるのである。
それは誰によってなされたのか。もちろん、パウロのいうところの「ユダヤ人」である。そして、パウロはその同じユダヤ人として、「わたしは福音(キリスト)を恥としません」とローマの人々に宣言した。それが「ローマの人々への手紙」なのである。(続く)
◇