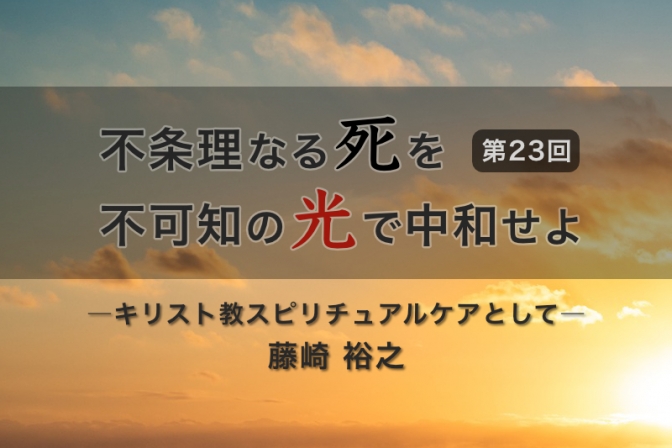不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(23)
※ 前回「福音は力である?(その1)」から続く。
経典の民
イエス・キリストが言い広められることを、ユダヤ人たちが「民族の恥」と考えていたことは、パウロも自分自身の経験から身に染みて知っていたのだろう。確かにユダヤ人には立派な経典があり、通常、われわれはそれを旧約聖書と呼ぶが、その経典はギリシャ語にも翻訳されて、ローマ・ギリシャ世界では少なからず影響があったはずである。世界の由来からユダヤ民族の歴史、そして預言の書や詩編、知恵の書と、このように多様な書物というものはそうそうに目にかかることがない。世界はそもそも何であるのか、人間とはどういう存在なのか、聖書はある時ははっきりと答え、ある時は読者に考えることを求める。それは哲学をする者にとっても大変に有意義であり、魅力あるものであった。だからこそ、ユダヤの言葉に限らず、ギリシャ語にまで翻訳されたのである。
もちろん、ローマ・ギリシャの知識人は、旧約聖書には来たるべき救い主(キリスト)が預言されていることも知っていた。また、このことはわれわれも知っておかなければならないのであるが、当時の地中海世界には、ユダヤの地を離れて生活しているイスラエルの末裔(まつえい)、つまり聖書の民が大勢おり、そういう人々が「経典の民」として生きつつ、各地の文化を取り入れながら生きていたのである。それでも十字架で殺された罪人が、まさか本当の救い主だと信じられるような発想を旧約聖書から受け取ることはできなかったであろう。
ガラテヤ
地中海の町々にあったようなユダヤ人のコロニーは、エルサレムの東西南北に広がっていた。バビロン捕囚を経験した人々の末裔は東にいたし、南にはエジプトを中心に、アラビアにもユダヤ人がいた。北はガラテヤということになるだろう。ガラテヤはガリア人の地という意味で、彼らはいわゆるケルト系である。ガリア人はフランス南部とガラテヤと呼ばれたトルコ中部が生活圏であったが、トルコ中部のガリア人の国家はローマとの戦いに敗れて属州化されており、当然に納税義務があった。しかし、もともとガラテヤは山岳地帯で貧しい土地であったので、経済的には困窮していたらしい。ローマに対する納税義務は奴隷奉公(この場合、多くは兵役)によって直接納税されていたといわれている。
離散したイスラエルの末裔がガラテヤに逃げ込んで、そこでガリア人と共存していたとしても何も不思議ではない。もっともイスラエルの離散は、ガリア人到達よりもずっと前のことであるから実際のことは私には不明である。しかし、それでも確実に言えそうなことは、ガラテヤにもユダヤの経典は到達していただろうということである。そうでなければ、パウロが短期間でキリストを伝えることは不可能であったと思うからだ。また、ユダヤと同様に、征服された民としてのガラテヤの人々にとって、ローマの価値観とは違う聖書の世界観というのは、ある意味で親近感を得やすいものだったのかもしれない。とにかく、ガラテヤはパウロにはなじみやすい場所であり、その地の人々とは共感し合える関係であったと想像できるのだ。
回心そしてアラビアへ
地中海世界におけるユダヤ的な背景はここでは論述しないが、ローマには前回述べたとおり、キリスト信仰を持ったグループがすでにおり、そうした人々はパウロが旧約聖書から語っても、「何のこっちゃ」ということにはならい。むしろ、パウロの言葉によってキリスト信仰を強化することができたのである。自分たちが抱くキリスト信仰が、反キリスト的なユダヤ人が宣伝するような「恥ずかしい」信仰ではなく、逆に旧約聖書から確かにたどることができる信仰であるという確証を与えられたのである。
パウロはもともと熱心なファリサイ派であったから、旧約聖書に関しては相当な知識があった。サドカイ派と違ってファリサイ派は預言者への尊敬心もあつく、救い主に対する待望もあった。だから逆に言えば、イエスに対しても大きな関心を寄せていたはずである。その証拠にネガティブではあるが、彼らがイエスの活動を絶えず気にしていたことは福音書から読み取れる。
パウロ自身はイエスの活動の目撃者ではないが、そのうわさは耳にしていたかもしれない。パウロがまさにサウロと名乗っていたときに、彼はキリスト教徒の迫害に手を貸していたのだが、ダマスコへの途上で復活のイエスに出会い、そしてキリスト教に回心したのである。それは紀元37年ごろであったと推察されるのであるが1、それから約3年間はアラビアにこもっていたらしい(ガラテヤ1:17)。地図を確認すると、ダマスコは今のシリアの首都とだいたい同じ場所であるが、ヨルダン川の東側、ガリラヤ湖から見ると北東方向に位置している。
回心してすぐに伝道には行かない
で、「アラビアとは?」ということになるが、アラビアに対する認識は、当時と現代では大きく違うようである。通常、われわれは今のサウジアラビアを含めた広大な地域を想像してしまう。ところが当時の認識では、ダマスコからペトラ遺跡くらいまでの地域で、ナバテア人の王国だった場所を示しているようである。ナバテア王国の歴史というのはあまり知られていないし、実際に王国としてキリスト教を受け入れていたわけでもないので、キリスト教史全般からすれば取り上げられない場所でもある。それでもシルクロードの街道沿いに位置しているから、当然のごとくいろいろな民族の交流があった場所である。ペトラには後の時代に造られたキリスト教の施設も残されている。ペトラ遺跡はヨルダン王国の中にあって今では立派な観光地になっている。そのペトラとエルサレムは意外に近い。エルサレムから南下し、ベエルシェバを経由して南東に進めば、ほどなくペトラに行き当たる。
パウロがペトラにこもっていたという証拠などないのだから無視してもよいのだが、ではなぜアラビアに退いたのかを考えることは重要であろう。要するに、彼はまずは逃げたわけであるが、第一に思い付くのは、ユダヤ人を恐れたということ。次に考えられるのは、じっくりと信仰を吟味するためではなかったかということである。いくら復活のキリストの顕現を体験したとはいえ、すぐに伝道者になれるわけではない。何より12弟子も、3年間はイエスと共に過ごして教えを受けているのである。そういう意味でエルサレムではなく、アラビアで3年過ごして、いわば半修道的な生活をしながらキリスト信仰を磨いていったのではないだろうか。これを内証と呼んでもよいのだが。
われわれの人生にも、思いもよらぬ感動はある。これぞ神の導きだと、びっくりしてしまうような出来事だ。しかし、感動だけで突っ走ってはならない。それはいわば、己の感情に従う行動だ。いったん心を冷まして、自分自身について感情だけではない、もう少し深い内証が必要なのだ。そうでなければ何事も失敗する。試練を乗り越えていけない。何よりもパウロ自身が「私が聞いたキリストの声」について吟味を重ねたことであろう。パウロはけして即席の使徒ではないのだ。そして3年を経た後、パウロはエルサレムへ行ってペトロと主の兄弟ヤコブに面会することになるのである。(続く)
- ジャン・ダニイルー著、上智大学中世思想研究所訳『キリスト教史1 初代教会』(平凡社、1996年)64ページ
◇