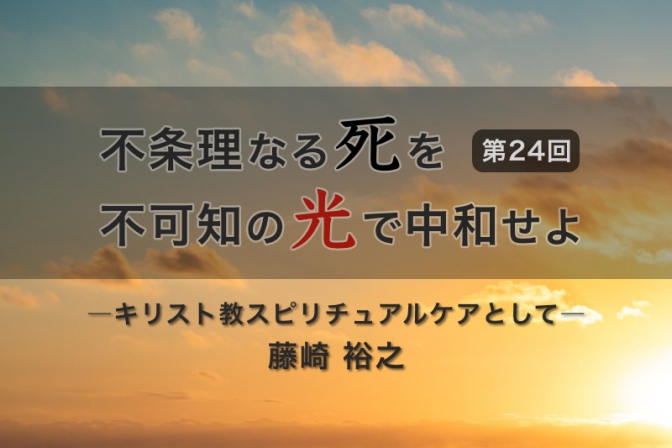不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(24)
※ 前回「福音は力である?(その2)」から続く。
パウロは決断しない
パウロにとって、キリストの迫害者からキリストを信じる者への転回は突然の出来事であった。一方で、伝道者としての道のりは、熟考されたものであったということを前回で確認できたと思う。パウロはダマスコ途上で復活のキリストに出会い、アナニアを通してキリストへと目を開かれるのであるが、使徒言行録では「わたしが選んだ器である」というイエスの言葉をもってパウロについて語られている。すなわち、パウロは信仰に目覚めて伝道者への道を決断したというよりも、キリストの迫害者であった人物を「キリストご自身」が選んでその器としたことが強調されているのである。その器とされるために、パウロはダマスコから南方へ向かい、アラビアで3年を過ごしたとパウロ自身が語っているわけである。使徒言行録だけを読むと、回心したパウロがすぐにダマスコで伝道を始めたような印象を受けるが、実際はそうでもなかったという点は押さえておきたい。
事情はどうであれ、パウロが熱心な迫害者からキリストを信じる者になったというこの大転回によって、彼自身はユダヤ人から命を狙われるまでになったわけで、そこに時に宗教が持つ「負の情念」のすさまじさを感じさせられる。棄教あるいは転教が命の危機を生む!それが当時の宗教世界であったならば、 われわれはそんな世界に生きているわけではないのだから、なおさら驚かされるのである。なお、追記しておくが、パウロが隠遁(いんとん)していたアラビアというのはトマスの宣教地域でもあった。
パウロが訪ねたエルサレム
そのようなパウロが、這々(ほうほう)の体でエルサレムにやって来たというのが使徒言行録の記述であるが、そこにおいて問題が起こる。それは、パウロ自身の証言によれば、ダマスコの回心から3年後のことになる。エルサレムでパウロは、キリストの弟子の仲間に入ろうと努めたがなかなかうまくいかない。というより、皆パウロを恐れてしまうのだ。
ここで言われる弟子というのは、12使徒ではなく、一般のキリスト教徒たちのことであろう。あるいは、信仰者ではなく、キリストの教えに学ぼうとする者たちだったのかもしれない。これは議論の余地があるとは思うが、当時のいわゆるユダヤ人キリスト教徒の実体を反映しているのかもしれない。それは律法を忠実に守りながら、キリストに従うというグループである。あくまでもユダヤ人として律法に従いつつ、その一方で、主にキリストの教えの部分について受け入れていくという立場だと表現できようか。またそのグループは、キリストの復活を信じ、キリストを物理的な救い主として受け入れつつも、再臨の時はすなわちエルサレムの解放の時であって、その時には新しい地上の王権を確立してくれると期待していたのかもしれない。つまり、天上の神の国よりも地上の王国優先ということか。
なにしろ当時は、キリストが語られた事柄や言葉はまだ文章化されていないわけで、キリストに対するいろいろな解釈がなされていた。であるから、エルサレム教会の中にも温度差があったと思われる。そのような人たちの目の前に現れたパウロという人間は、かつて彼らのキリスト運動を迫害したまさにその人であったから拒絶されるのも無理はない。
拒絶されるパウロ
そのようなパウロであったが、バルナバの執り成しで使徒たちと面会して大いに語り合えたようである。パウロはしばらく使徒たちと過ごしたが、エルサレムで主の名によって大胆に語り過ぎたせいか、またしてもユダヤ人から命を狙われるようになる。その事実について「兄弟たちはそれを知って」(使徒9:30)と書いてあるが、それがイエスの兄弟たちを指しているのかどうかは確かではない。
ここでエルサレム教会の実情について考えたい。ある時点からエルサレム教会の実権というか、教会的にいえば主教に当たる地位であるが、それは12使徒からイエスの兄弟ヤコブに移ったようである。口悪い人なら、ヤコブがイエスの兄弟であることを理由にエルサレム教会を実質的に乗っ取ったのだと批判的な目を向ける人もいる。果たしてそうだろうか。エルサレム教会にそんな魅力があったかどうかも怪しい。なぜかと言えば、イエスご自身はエルサレムで処刑されたわけであって、その記憶は町の人たちの中に強烈に残っているのである。そして、ローマによって十字架で処刑された人物を、救い主だと信じて活動している連中というのは、どう考えてもユダヤ人にとっては迷惑なのだ。いつもぶっつぶしてやりたいと思っていたはずである。
それに比べれば、エルサレムを離れて宣教していた12使徒の方が自由であったと考える余地もある。何にしろ、エルサレム教会の責任を負うことが権力と結び付くというのはあり得ないので、ヤコブと他のイエスの兄弟たちに汚名を帰せることは意味のないことである。むしろ、ヤコブは熱狂的なユダヤ人キリスト教徒と、パウロのようなヘレニズム的・普遍的なキリスト教を目指す者たちの間に立たされて難儀したのであり、結果としてエルサレムで殉教するわけだから、使徒的な教会が彼を聖人として記念するのには正当な理由があるのである。イエスとは直接の血のつながりはなかったともいわるが、とにかくイエスと共に育った者として、そのイエス・キリストの体たる教会に殉じたことも福音の力であったというべきであろう。ヤコブが殉教した後、その兄弟シメオンがその地位を継いだが、彼もまた殉教している。
エルサレムではなく
というわけで、パウロがエルサレムで自身の実体験を語るのはかなり危険であったし、この時点において、パウロが教会執事ステファノのように殺されてしまう可能性もあった。それは誰も願いもしなかったであろうから、結果としてギリシャ語を話すユダヤ人や異邦人への宣教者となるしか方法はなかったとも思われる。裏切り者というのは、いつの時代も憎まれるものである。また悲しいかな、ユダヤ人キリスト教徒の中にもパウロに恨みを抱く者もいただろう。だから、なおさら彼はユダヤにとどまることはできなかったはずだ。
ただし、その後もパウロ自身は何度かエルサレムを訪れているし、エルサレム教会に対する尊敬心を失ったわけではなかったようだ。また、パウロには類いまれな文才というか、とにかく言葉に優れていたし、キリストを信じるということをかなり掘り下げて証しすることができた。そのための学問的な裏付けもあったわけで、そういう意味でいえば、12使徒やイエスの兄弟たちとはまったく違っていたのかもしれない。とはいえ、パウロもまた人間であり、キリストの前には欠けたところの多い信仰者であったから、時には教会の人々や12使徒に対する愚痴のようなことも言ったり書いたりしている。まあ、それはご愛嬌(あいきょう)である。
福音を力として
そろそろ結論というか、終わりにしたい。福音とはイエス・キリストそのものである、というのが初代教会の理解であったと思う。「福音を恥としない」とパウロが語るとき、それはもちろんイエス・キリストを恥としないという意味である。かつてキリストを恥として、キリストの迫害者であったパウロが大転回してそのように語っているのだ。
それをパウロ自身も、使徒言行録も、パウロの熟考による決断とはけして語っていない。われわれは時に、迫害者パウロを変えたものは何かと考えてしまう。そこにいろいろと理由付けをしてしまう。しかし、実際のところは、その時のパウロに冷静さがあったわけではなく、それは何であったかと言えるものはないのだ。「これこれこういう理由でキリスト教徒になりました」という説明など不可能だし、パウロ自身には必要もなかったのである。まさにそれが、キリストのミステリーなのだ。パウロは冷静にユダヤ主義とキリスト信仰を比較検討などしてないのだ。その事実が大事である。ある日、突然にイエス・キリストが私の救い主になる。これもまた人生である。繰り返しになるが、キリストが私の救い主になるという事実が大事なのだ。
むしろ、比較検討していたのはユダヤ人であり、またキリストに学ぶことがあったとしても、それでもやはりユダヤ人のように生きなければならないと考えた人々である。ユダヤそのものがなくなったときに、その人たちの信仰傾向も消えてしまったのは言うまでもないことだが。
福音を恥としない、キリストを恥じない、というパウロの生き様が彼の信仰の原点であると著者は考えているわけだが、時としてイエス・キリスト本人よりも、イエスの行動や教えに重点を置いてしまう傾向はいつの時代にも存在した。イエスの生き様が大事、イエスに学ぶというのはその通りであるが、しかしなお、それを超えているのが福音である。福音とはイエスの生き様ではなく、キリストのミステリーなのだ。不思議なのだ。神秘なのだ。神の出来事なのだ。12弟子やイエスの兄弟を、そしてパウロを動かしたミステリーなのだ。
そういう意味において、キリスト教という名称も多少は誤解を与えるのかもしれない。キリスト教が意味しているのは、イエスの教えではないし、聖書の教えでもない。キリスト教が意味するのは「福音」そのものなのだ。(終わり)
◇