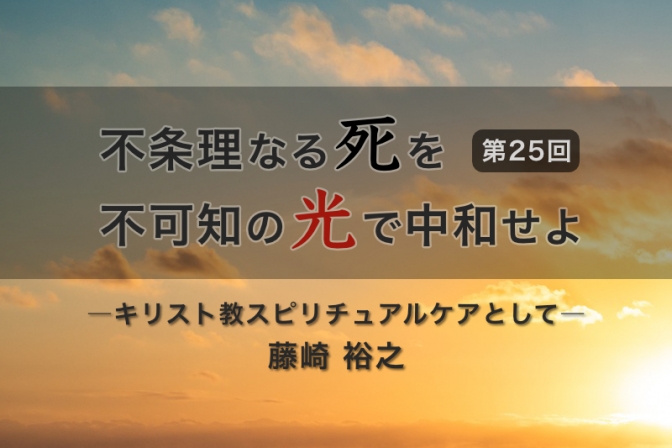不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(25)
虹を見たら
虹は美しい。人は虹を見てなにを思い浮かべるだろうか。近年は人間の多様性を虹に象徴させる傾向があるので、直感的にはLGBTQの課題だろうか。虹はそもそも、空気中の水滴がプリズムのように機能し、太陽光線が波長分解されて見えるものである。科学的な言い方をすれば、光という電磁波が分解されて可視光域に分光されたものである。しかし可視光というのは、光という電磁波のものすごく狭い領域でしかない。それでも虹は、われわれから見たら一色にしか見えない光が、実は多様な色の光が集まったものであることを物語ってくれるのである。
これはこじつけなのであるが、世界で起こるさまざまな現象の源を神に求めたがるのが人間である。恵みの雨があれば災いの雨もあって、本当はどちらも雨という気象現象にすぎないのだが、そうした事柄に対してもわれわれは「神意」を読み解こうとする。さあ、この現象を科学的に考えてみようと頭を切り換えない限り、この世の事象を宗教的に考えてしまうのが人間である。だから実のところ、虹を見て「神の平和の訪れ」と感じたところで、それは全く当たり前のことなのである。気象現象は科学的な分析と解釈によって説明可能にはなるが、実際は人間が分かっていることは多くはない。科学はあれやこれやと雨が降るという出来事を一生懸命に考えるのであるが、実は雨乞いの祈祷の方がずっとずっと人間らしいのだ。そして、しばしば雨乞いの祈祷は実現もする・・・。長々と書いたが、虹という言葉一つからもさまざまなことを考え得るということだ。
雲もまた味わい深し
神は虹を約束の徴(しるし)とされた(創世記6章から9章におよぶノアの箱舟の物語を参照)。それは大洪水を生き延びたノアとその家族に対する約束である。虹が見えるときに神は約束を思い出すと言われる。水はもう二度と肉からなるものすべてを滅ぼす洪水にはならないと約束されたのだ。この時に神は不思議な表現をされた。「わたしは雲の中にわたしの虹を立てる」。まず雲から何を連想するだろうか。筆者はまずは出エジプト記13章21節を思い浮かべる。場面はモーセが率いるイスラエルの民が、これからアラビアの荒れ野に向かって旅を進めようとしているところである。「主は彼らの前を行き、彼らが昼も夜も進むことができるよう、昼は雲の柱をもって彼らを導き、夜は火の柱をもって彼らを照らされた。昼は雲の柱、夜は火の柱が、民の前から離れなかった」と書かれている。
ノアの物語を聞かされる人々は当然のごとく出エジプトの出来事を知っている。特に神がイスラエルを自ら導かれたことは大切にしたい事柄だから、人々は何度もこの話を聞かされてきたはずである。そういう前提に立って聖書を読むと、「雲」という言葉は、単なる「雲」ではなく、神の臨在を示す「雲」であることが分かるはずだ。神を「不可知の雲」と表現した古代教父もいる。そういう雲の中に虹を立てるのである。だからそれは単なる気象現象ではない。むしろこう考えるべきであろう。雲の中に立つ虹は、実は神の多様性を象徴していると。神に多様性があると語るのはまことに不遜であるが、要するに神はわれわれ人間には不可知過ぎて虹色そのものなのだということではないかと思う。神という方はけして単色モノトーンではないのだ。
神は「このような方」であると語り尽くせぬ方であって、ディオニュソス・アレオパギデスという人は「神」とは語り得ないものとして「無」であると表現したほどである。正確には「無」あるいは「闇」の中に神がおられるということである。光を照らして神を知るなど、言い換えれば、理性のみで神を語るなど、神ご自身とは全くの無縁ということになる。
神から遠ざかっている人間ほど神を語る際に多弁であるとディオニュソス・アレオパギデスは言っているのであるが、だから「虹」という現象の中に神を見るというのも趣があるわけである。知性的に複雑な思考を重ねて神を実感するよりも、ただボーッと空を見て、たまたまそこに虹があったとして、「あー、今日も神がおられるかもしれない」という実感があるなら、それにこしたことはないのだ。「わたしは雲の中にわたしの虹を立てる」。何とも趣のある言葉だ。もし私たちが虹を見るたびに、かつて神がノアに約束されたことを思い出すなら、われわれの人生は百点満点ではないだろうか。
人間は踏ん張る
かなり遠回しになってしまったが「神意」を読み解くというのは、人間の日常行動でもある。だから「神意」を計るために占いが行われたり――キリスト教はそれを禁じてはいるが――、またこのようなことをすれば神が喜ぶに違いないと考えたりする。いやむしろ、こう言うべきかもしれない。「神は時に人を滅ぼすに違いない。だが、神の滅びから逃れる手段もあるはずだ」と。つまり、人間の先読みである。
実のところ人間は常に神を恐怖している。畏れ敬うというよりも、恐怖が先行している。その恐怖というのはもちろん「先に生きた人々の滅び」の記憶による。滅びの記憶はなかなか色あせない。むしろ語り継がれるべきこととして記憶されるのである。かつて「滅び」があったという強烈な記憶の継承はかなりの部分で人間の行動を抑制している。あのノアの時代の人間たちがどのように生きたか、逆説的ではあるが、あの人々から学ぶことはあるのだ。
「滅び」と「神意」が重なり合う部分で宗教というのは成り立つわけである。これは宗教の永遠のテーマなのだ。むしろ個人的な悟りや解脱を求める哲学的な宗教はまれであろうし、故に魅力的なのかもしれない。しかしそれよりも、人間個々が属している集団そのものの「死活」というものを意識するが故に、さまざまな祭りが営まれるのである。個々人の内なる人格のためにわざわざ大勢が集まって祭りを行うことはない。
とにかく「滅び」に関わる宗教の記述と表現は実にリアルに継承される。その証拠に、創世記の最初の10章のうち、多くの部分が直接的な「死」に至らずとも滅びをテーマにしている。例えば、アダムとイブがエデンから追放された記事も楽園の喪失という意味で「滅び」の一種であろう。ノアの洪水物語に至っては人間存在の滅びそのものであろうし、そういう滅びの記憶とその記憶に悩まされるが故に、後の人々は「神意」を先読みして何とかこの地上に踏みとどまろうとしているのだ。それはもう人間のいじらしさそのものであるし、全くもって涙ものではないか。
次回からバベルの塔の話を具体的に扱っていくが、この話が神に対する単なる反逆事件であると考えてはならない。彼らにとって「神は滅ぼす者」であったのは間違いのない事実であり、逆に言えば、その神を打ち破る力が人間の側にあるとは思ってもいないし、そこまで傲慢ではないのだ。
しかし、彼らは神が不可知な存在であることを知らなかったのだ。それに気付かなかったのだ。それ故に彼らは大きな間違いを犯してしまった。次回からは、そのことについて語って行く予定である。(続く)
◇