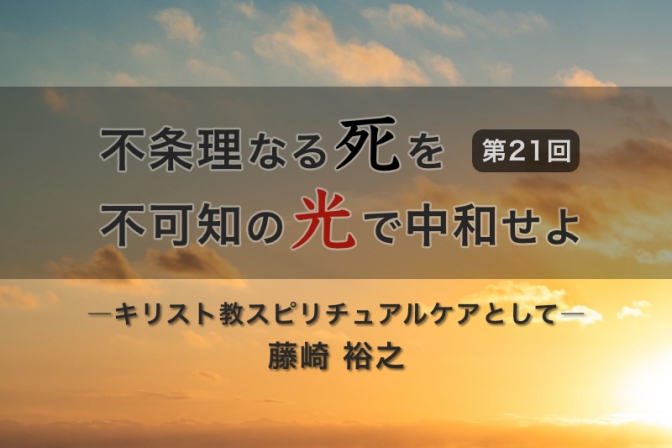不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(21)
※ 前回「口数の多い死体? ヨブ記考察(その2)」から続く。
ヨブは善き教えを聞いていたのであろう
「わたしたちは神の手から善いものを受けるのだから、悪いものも受けるべきではないのか」。ヨブは苦しみの中にあって、妻にこのように伝えたのである。何と美しい言葉であろうか。われわれは「神からは善いものを受け、悪いものは例えばサタンから受けるのだ」とつい口にしてしまう。まさか神が悪いものをも与えるわけがないと。しかし、ヨブはここにおいて悟るのである。神からは悪いものも与えられるのだ、と。では、ヨブのこのような心境はどこから生まれたのか。これはやはり、ヨブの妻の悪意に満ちたあの言葉への答えなのである。「神を呪って死んだらよいでしょうに」。この言葉を聞いたヨブは、妻の愚かしさを嘆きつつも、神を呪うことはなかった。そして、神からは善いものも悪いものも受けるべきなのだと悟るのである。
私は、ゲツセマネで祈った主イエスの姿を重ね合わせてしまう。神が与えようとしている杯、十字架の苦しみを前にしたあの祈りの姿である。マルコによる福音書14章33節には、「イエスは深く恐れ、悶(もだ)え始め」と書かれている。そして、イエスは地にひれ伏して、「アッバ、父よ、あなたにはおできにならないことはありません。わたしからこの杯を取り除いてください」と祈るのである。それも三度も祈ったことを、聖書はわれわれに語り続けるのである。
ヨブを知り、イエスを知る
灰の中に座って耐えるヨブと、ひれ伏して祈る主イエスが、どうしても重なってしまう。違いがあるとしたら、ヨブはまだ神とは向き合っていない。神について考えてはいるが、主イエスのように、神に心を向けてはいないのではないか。
主イエスは3人の弟子たちを連れて祈りの場へ行った。ヨブの場合は3人の友人がヨブを心配して駆け付けてきた。3人の友人の目にヨブがどのように映ったか、聖書はこのように語っている。「彼らは遠くから目を上げて見たが、ヨブと見分けることができないほどであった。そこで彼らは声をあげて泣き、それぞれ、マントを裂き、灰を頭の上にまいた」
ヨブの精神力は見事であるが、ヨブの友人たちもさすがである。ヨブだとは見分けがつかないくらいボロボロになったそのヨブの傍らで、彼らは七日七夜、ヨブと一緒に地面に座っていたのである。3人は苦しむ者に寄り添うのである。あえて誰もヨブには話し掛けなかったというのであるから、これもまた現代のスピリチュアルケア理論がいう傾聴の大切さに見事に合致している。本人が語り出すまでは、辛抱強く待つしかないのだ。本人が語るままに聞くしかない。これが傾聴である。七日七夜も寄り添えるなんて、すごいことなのだ。しかし、どうも教科書通りに事は進まない。いや、むしろ言葉を掛けられないなら、ヨブの側から一時的であっても離れるべきだったのかもしれない。さらに聖書は語る。「あえて彼に話しかける者は一人もいなかった。彼の苦しみがあまりにもひどかったからである」。このような場面では、どんな人間にも答えなどない。確かに言えることは、変わり果てた姿をしたヨブは、この寄り添いによって何かが変わったように見えるということだ。
独白(1)
まさかこの苦しみの中で、これ程長く生きているなんて。どう見ても死ぬようにしか見えない人間が生き続けている。このものすごい苦痛の中で、なぜ私はまだ生きているのか。私は苦しみが終わらない時間を生きている。いや、生きているという実感がない。苦しみが生きている。苦しんでいる私を、私が見ている。眠ることなく、休むことなく、苦しみが私の体を支配している。苦しみはまだ生き続けていくのか。体は滅んでいくのに。心も滅んでいくのに。苦しみだけが衰えずに生きている。苦しみというやつが、私を包んでいる全世界を支配し、よどんだ空気を蓄え、人の心をむしばみ、もはや言葉すら口にできなくさせる。誰も何も語れない。ならば私は語らねばなるまい。苦しみを押しのけて、私の体を取り戻し、私は語らねばなるまい。
そして、ヨブは独白する。「滅びよ。わたしが生まれた日」と。
死に憧れる
ヨブはとうとう口を開く。ヨブは自分自身の存在を呪う。彼の生まれ日さえも呪う。「なぜ、わたしは母の胎を出た時に死ななかったのか。なぜ、生まれ出た時に息が絶えなかったのか」。生き続けてきた事実を呪う。どのように恵まれた人生を生きてきたとしても、今、この時の苦しみがすべてを台無しにしているとヨブは訴えるのだ。「なぜ、苦しむ者に光が与えられ、心の痛む者に命が与えられるのか。死を待っても彼らには死は訪れない」。本来、光も命も尊いものだ。われわれが手を伸ばしてつかみたいと望むものだ。しかし、それさえもヨブには余計なものなのだ。彼が求めるものは苦しみを終わりにする「死」である。死に憧れる人、それがヨブだ。台無しだ、すべては台無しだ。苦しむ者への光も、心の痛む者への命も、死を待っている者には死が訪れないとしたらすべてが台無しなのだ。おそらくこれは人間の本音である。死ぬほかに解放がない人間には、やはり死が必要なのだ。そう考えると、われわれは頭を抱えてしまうだろう。「安らぎも、静けさも、憩いもない。ただ悩みだけが訪れる」のである。
独白(2)
死は滅びであろうか。死は罰であろうか。ならば死ぬわけにはいかない。滅びゆくわが身を見つめつつ、神妙に「わが罪を悔いる」べきだろうか。確かにキリスト教には、そのような教えもある。潔く自らの罪を悔い改めて、命を終えるのが良いとされる。罪ある者の結末としての滅びを、罰を、苦しみを納得して受け入れて、悔いる心を持って死を待ち望むべきなのだ。しかし、あえて言いたい。善きものを与える神が、今は悪しき時間を用意したのだ。いにしえの信仰者たちに倣って、私も心穏やかに死を過ぎ越していけるのだろうか。この苦しみの後に用意されている甘美な神の正しき御手を信じて、乗りきっていけるのだろうか。私はもう死ぬと覚悟をしたのに、まだ私は生きている、まだわたしは苦しみの中にいる。神が何を考え、何を用意しているのか、私には計り知れないのに。改悛だけが余生の頼りだろうか。何か足りない、納得できないではないか。私に対する神の考えを知りたい。私に対する神の今後の扱いを知りたい。謎だらけの人生はもう生きていけない。せめて死に直面している今だからこそ、神を知りたいのだ。
ヨブ記とは
ヨブ記は、ヨブと友人たちの会話を中心に構成されている。ヨブが嘆き、友人たちがヨブの言葉に対して応答していくのである。ヨブの言葉には、神を恨み呪うような言葉が随所に織り込まれている。しかし、ヨブはけして神は悪であるとは言わない。というか言えない。ヨブには今や、神の真意がまったく分からないのであろう。要するに、「わが人生はどうなっているんだ」ということである。神を信じる人であれば、なおさら神の真意が分からなくなる。
それに比べれば、友人たちはどこか神の側に立って擁護しているように思える。彼らが考えていることは、「これが神のなさることであるから、ヨブには言い分もない」ということであろう。それが苦しむ者を目の前にした友人たちの考えだ。それはその通りなのだ。天においてヨブの体がサタンに任されており、神はその様子を見ておられるだけだなんて、誰も想像できないのではないか。けれども実はそうであったのだ。天においては人間が思いもできないようなやりとりがなされていたのだ。
事実として神はヨブの様子を知らなかったわけではないし、ヨブの声を放置していたわけでもない。そして、ヨブ記がわれわれ人間に答える言葉があるとしたら、神には神の言い分があるということなのだ。人間は「なぜ」と問う。神はその「なぜ」について明確には答えないが、神には言い分がある。いや、このように言うべきか。「神にはすべての人に対する意図がある。それを人間が理解できないとしても、納得できないとしても、それが正しいとか間違っているとか、そういうことではなく、神はご自身が決めたことをなされる」。つまり、神はヨブに対して無関心ではない。それは同時に、自分の人生を問い、神を問う人々に対しても同じではないか。神は、われわれに対して無関心ではないのである。
ヨブへの答え、われわれへの答え
神はヨブに答える。要約するなら「お前に何が分かるか」ということだ。要するに、神が何を考え、どのように行動するのかは、人間にはどこまでいっても「はっきりしない」ということであろう。さもありなんである。分かれば苦労はない。分かれば宗教などいらない。分からない。分からないが、われわれには答えが必要なのである。平穏に生きていくだけなら、おそらく大抵のことは世の中に答えがあり、自分自身にも答えがある。世に問い、自分に問えば、大抵のことは何となく分かるし、また、うまくいかないとしても、納得せねばならぬと自分に言い聞かせることもできる。大抵のことは!である。しかし、実は答えがないところにわれわれの命が置かれている。
そもそも命が分からぬ。体が分からぬ。心が分からぬ。死が分からぬ。人生は答えなき問いで満たされている。無回答のままで時が過ぎていく。誰もがそのような中で死と向き合っている。そして、いよいよ答えをもらわねばならないという時が来るのだ。さあ、誰がその答えを与えてくれるのか。それは善いものでも悪いものでもない。ただの答えである。命とは何ぞや。死とは何ぞや。死が訪れて肉の塊になって朽ち果てていく、このわが死とは何ぞや。その時、わが心は、わが魂はどうなっているのか。まだ死体の中にとどまっているのか。それとも、あっという間に「天国」という場所に移されるのか。その答えが必要になるその時が来るのだ。さあ誰が答えてくれるのか。
答えにならなくとも「答えはある」とわれわれは答える
ヨブが知らねばならぬと悟った答えは何であったのか。「神を呪って死ぬ」前にぜひともに手にしなければならなかったその答えは何であったのか。実は、ヨブ記そのものは答えていない。なぜなら、ヨブ記の作者にも答えられないのだ。誰も神に成り代わって、その答えを語ることはできないからだ。では誰がその答えを語ることができるのか、人間ではないとしたら誰なのか。しかもそれは、人間が理解できる答えでなければならないのだ。納得はできなくとも、少なくともその答えによって何とか日々やり過ごせるようなものでなければならないのだ。神よ、答えよ!である。
神の答えそのものを十分には咀嚼(そしゃく)できないとしても、答えがあるならありがたい。なければ、宗教の意味がないといっても過言ではないのだ。私に言えることがあるなら、もちろん、その答えはイエス・キリストである。これが神の答えだ。神の子は永遠から永遠にいます方。不在の時はない。故にヨブの側にそっと立ち、同時に神の側にもいた方。真の神であり、真の人であるイエス・キリストがヨブの傍らにもおられるというのが優等生的な答えである。肩すかし的な文言でしかないが・・・。
しかし、人間の生においてキリストがいる、人間の死においてキリストがいる、人間のよみがえりの時にキリストがいる。あなたを救う者がいる。これがキリスト教の答えである。どう頑張ってひねってみても、これ以外の答えはない。キリストがこの世に生まれ、十字架で死んだ後に復活したという事実をもって、ヨブ(神を問う者)に答えたといつまでもいつまでも言い続けるしかない。
結語
良きにつけ、悪しきにつけ、神を思わぬ、神を問わぬ人間は、肉体という「死体」を抱えて生きているようなものだ。「わたしたちは神の手から善いものを受けるのだから、悪いものも受けるべきではないのか」と語るヨブは、私には口数の多い死体にしか思えなかった。しかし、ヨブは神を思い、神を問う。そのようにしてヨブは沈黙に伏する。その時初めてヨブは苦しむ聖者となるのだ。聖者に神は答える。「私が神である」と。(終わり)
◇