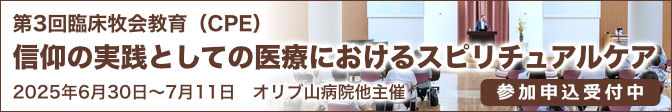11月18日から4日間にわたって在日本韓国YMCA(東京都千代田区)で開催された第3回「マイノリティ問題と宣教」国際会議の初日には、同志社大学大学院ビジネス研究科教授でカトリック信徒のエコノミスト・浜矩子氏が「ヘイトスピーチ化する日本 ここをどう乗り越えるか」と題して一つ目の主題講演を行った。その要旨は次の通り。
◇
日本経済について、経済活動は本来人間を幸せにするものであるはずなのに、全然そのように機能しなくなっていることを、とても強く感じている。この経済活動が人間を幸せにできなくなっていることは、今の日本の政治状況が大きな要因になっていると思う。もっと端的に言えば、安倍政権という現政権が展開している経済政策に非常に大きな問題があると思っている。安倍政権の経済政策であるアベノミクスについて、私は別の名前を発明した。すなわち、「アホノミクス」である。このアホノミクスが、実を言えば、ヘイトスピーチが日本で広まっていることの大きな要因になっていると私は思う。
この日本のヘイトスピーチ社会化の背景に、アホノミクスという現政権の政策展開が大きな要因として横たわっていると考えている。私が申し上げることは大別して2点ある。ポイントその1は、日本のヘイトスピーチ化をもたらしているものであり、ポイントその2は日本のヘイトスピーチ化をせき止めてくれるものである。
1. 日本のヘイトスピーチ化をもたらしているもの
第1のポイントについては、三つの対立が日本のヘイトスピーチ化を促していると考えている。その1は、融合と分断の対立である。その2は、自助対公助である。その3は、教育対訓練である。
融合と分断の対立
雇用の形態・働き方を多様化するとか、教育の多様化を後押しするとかいう言い方をすると、あたかもそれは多様性を容認し、多様なる者たちが融合していく社会を作りたいと言っているような印象を与えてしまう。しかしながら、よくよく考えてみると、そういうことではない。「多様化」の名の下に「分断化」が進むことになると、結局、だんだん人々が自分と違うタイプの人間たちに思いを馳(は)せ、自分と違う人々の考え方や行動が理解できない状況に追い込まれていくことになってしまう。お互いに相手を理解できないというこの感情は、だんだん相手のことを疑う感情につながり、そして疑いは恐怖を生むことになってしまう。この恐怖がヘイトスピーチの背後にあることは異論のないところだと思う。
自助対公助
安倍政権の下においては、自助能力がある者を助けるのが公助の役割であると言われている。しかしながら実は、これは公助という言葉に関する完全に誤った理解だと私は思う。公助というのは、自助能力がない、あるいは自助能力を発揮しようとしてもそういう場面に恵まれない人々を助けるためにある。それが正しい公助の役割であると私は思う。つまり、公助というものの最大の役割は弱者救済である、というのが正しい理解だと思う。ところが、今の政府は自助能力がある者、自分でしっかり自己展開できる人にチャンスを与えることしか考えていない。そのようになると、おのずと自助能力がないと見なされる者に対しては、非常に社会全体としても差別的な意識が芽生えることになってしまう。ところが、自助能力がないと見なされている人々は、必ずしも本当に自助能力がないわけではなくて、自分が持っている自助能力を発揮できる場面を奪われているケースも非常に多い。このような弱者に対する見方を植え付けてしまう政策環境は、ヘイトスピーチを惹起(じゃっき)する側面を持っていると考えられる。このような形で自助対公助の対立は、非常に人々の中に欲求不満を生み出し、怒りのはけ口を求める心理をかき立て、従ってヘイトスピーチ的な行動につながってしまうと思う。自助対公助の対立をもたらす政策は、人々から寛容さを奪っていくことになる。寛容さとヘイトスピーチ心理ほど、遠いものはない。その二つは、東が西と隔たっているほど遠い。
教育対訓練
教育という分野において、安倍政権下で非常に大きな問題が生じていると私は思う。安倍政権の一つの政策として出てきたのが、大学におけるリベラルアーツを排除しようという方向性である。安倍政権の趣旨としては、リベラルアーツのように考えたりすることに時間を費やす部門は無駄であるという考え方である。そのように考えたりする暇があれば、腕に技術を付けてスキルを磨くほうがはるかに生産的な社会の一員になれると、安倍政権は考えているようである。スキルは非常にハイレベルで身に付いているが、考える能力がない人間ばっかりできてしまったら、どういうことが起きるだろうか? スキルはあるけど頭空っぽという人には、イマジネーション(想像力)というものが全然働く余地がない。イマジネーションが欠落しているとはどういうことかというと、自分と違う人々の考え方を理解することができない、自分と違う感性を持っている人の思いに同情することができないことになっていく。従って、スキルはあるが頭空っぽで想像力が欠けていることの最大の悲劇は何かというと、自分以外の人の痛みが分からないことである。そして人の痛みが分からないということこそが、まさしくヘイトスピーチの温床になることは間違いないと思う。
以上、申し上げた安倍政権下における三つの対立というのが、非常に日本のヘイトスピーチ化を促していると考える次第である。
2. 日本のヘイトスピーチ社会化をせき止めてくれるものは何か
これには三つあり、その三つを大別すると、それは「二つの出会いと、一つの合言葉」に整理することができると思う。
出会いその1:多様性と包摂性の出会い
ここでいう多様性というのは、安倍政権下で言っている「多様化」とか「多様な」とは全然意味が違う。私が使う「多様性」という言葉の意味は、非常に相異なる特徴とかライフスタイルとか、もちろん、人種とか文化とか宗教とか、そういうものが異なるタイプの人々がたくさんいるという意味での多様性である。そういう多くの異なる特性を持つ人々がお互いに抱き止め合う、共に生きている、まさにフュージョンした形で生きているのが、包摂性ある社会といえると思う。この多様なる人々がお互いに腕を開いて抱き止め合うことができる状態は、まさにそこには自分と違う人の思いを豊かな想像力を持って理解することができる人々がいることだから、お互いに同情することも容易にできる人々の共同体がそこにできてくることになる。それが一つの理想的な社会の姿だと思うが、下手をすると多様性はあるが包摂性がない社会状況が意外と容易に表れてきてしまうともいえる。
今の日本の社会は、従来に比べれば非常に多様性が大きくなっているといえるが、問題は多様性の拡大に包摂性の深化が伴っているかだと思う。多様性ある社会を考えると、すぐわれわれの頭に浮かんでくるのはヨーロッパの世界である。ヨーロッパにおいてはある程度まで多様性が包摂性と一体化した状態にあったといえる。しかしながら最近においては、ユーロ圏の中でのいろんなもめ事とか、あるいはウクライナ情勢をめぐる対立に表れているように、多様な欧州人たちの間に包摂性ではなく次第に排他性が芽生えてきてしまっているように見える。そこが非常に今の現状において心配なところだと思っている。
他方、過去の日本の社会においては、包摂性は非常にしっかり存在しているけれども、一方で多様性を容認しない傾向があったといえる。みんなと同じことをやっている、みんなと同じ姿形をしている、いわば均一性のルールに従っている人である限りにおいては喜んで包摂してあげましょうというのが、過去における日本の社会だったといえる。頭を紫に染めたりしなければ包摂してあげましょうというのが、過去の日本の社会であるというわけである。次第におのずと多様性が広がるという方向になってきているので、問題はそこで同時に包摂性も豊かに深化していくかだと思う。包摂性と多様性をしっかり出会わせることができればできるほど、日本社会はヘイトスピーチ社会から遠ざかっていくことができると思う。
出会いその2:正義と平和の出会い
この言葉は旧約聖書の詩編の中に出てきている言葉である。詩編85編11節に次の言葉がある。「慈しみとまことは巡り会い、正義と平和は抱き合う」。非常に美しい、とても感動的なイメージであるといえる。しかしながら、実際にわれわれが当面している現実を考えると、正義と平和が抱き合うというのは実に難しいことだと気が付いてしまう。誰かにとっての正義と、もう一人の別の人にとっての正義が出会うと、そこに出現するものは何であるかというと、それは往々にして決して平和ではなく戦争になってしまっているわけである。残念ながらパレスチナ情勢は、本当に長きにわたっていかに正義と平和が抱き合うことが難しいかをわれわれに示し続けて今日に至っている。そして最近のところでいえば、ある意味でもっと悲劇的なのが、いわゆる「イスラム国」(IS)を名乗る人たちの正義と、その他の世界が持っている正義のイメージとの鋭い対立である。従って、現実の世の中においては正義と平和を抱き合わせることは実に難しいことだと言わざるを得ないだろう。
だからといって、諦めてはいけないわけで、正義と平和をしっかり抱き合わせることができ、そういう社会をわれわれがつくり出すことができれば、そこにもまたヘイトスピーチが存在する余地は間違いなく、なくなっていくと言ってよいと思う。正義と平和を抱き合わせるのは難しいと申し上げたが、実を言えば、一つの国として正義と平和を抱き合わせることを目指すと宣言している一つの文書がある。それが日本国憲法である。日本国憲法はその前文において、日本国民が諸国民と共和することを言っている。そしてそれを可能にするために戦争を放棄すると宣言しているので、これぞまさしく正義と平和が抱き合う場所を目指すのだと宣言していると言っていい。ということは、日本国憲法が成り立っている社会においては、決してヘイトスピーチが入り込む余地はないと間違いなく言える。ところが、そういう素晴らしい存在である日本国憲法を、アホノミクスの面々は変えてしまおうとしているわけである。従って、私はこれからもっともっと一段と力を入れて打倒アホノミクスに励まなければならない。
一つの合言葉
それは「陰謀」という言葉である。希望のための陰謀、平和のための陰謀である。われわれは平和と希望、そして正義と平和を抱き合わせ、多様性と包摂性を出会わせるために、一緒に陰謀を企んでいかなければいけないと思う。何しろ、人間は陰謀を企んでいる時ほど楽しいことはない。居酒屋とかパブの片隅で「あいつらをどうやっつけてやろうか」と陰謀を練っているときほど、連帯感が芽生え、そして頭がよく回ることはない。陰謀ほど連帯をもたらすものはないといえる。われわれは日本のヘイトスピーチ社会化を阻んでいくために、あらゆる知恵を出し合う陰謀の場をこれからたくさん持っていかなければいけないと思う。そこで皆様に提案というかお願いが一つある。ここでお目にかかったことをきっかけとして、このホールの中にいるわれわれ全員が一つの陰謀チームを形成して、ヘイトスピーチ社会化の打倒に向かって闘っていきたいと思う。
最後に実はもう一つ、お願いがある。冒頭でご紹介した「アホノミクス」という言葉の普及にぜひご協力をお願いしたい。特に日本国内にお住みでない方々は、お国にお帰りになったところで、ご自分のお国の中でこの「アホノミクス」をはやらせていただきたい。
さらにもう一点。アホノミクスの「ア」の上に「ド」をつけると、「ド」というのは「とても」という意味である。それも併せて覚えておいていただければと思う。
【関連書籍】浜矩子著『さらばアホノミクス 危機の真相』 毎日新聞出版 2015年11月17日発行