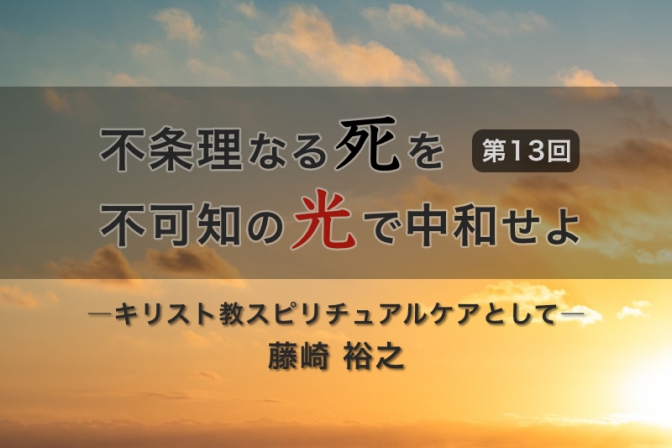不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(13)
※ 前回「人生は三度くらいおいしい(その1)」から続く。
光はわれわれに自己を知らしめる
「神は光ではない」と書くと驚くであろうか。確かにキリストは世の光であるが、神は「闇でもある」と、少々ひねったことを言うのもキリスト教である。光は神というよりもキリストの領域だ。とはいえ、キリストがそのまま光というわけではないし、光を拝むというのもキリスト教的ではない。では「光とはわれわれにとって何ものであるのか」といえば、それは光の向こう側を意識するための手段である。また、光はわれわれ自身を映し出すものでもあるので、光によって己を知るということも可能である。このような場合に光をキリストに置き換えれば納得いただけるのではないかと思う。われわれは、キリストによって自分自身を知らねばならないのだ。
そういう意味で、「御言葉」イコール「聖書」と置き換えてしまった宗教改革は、いささかキリスト教を矮小化してしまった感がある。そもそも神の言葉、つまり御言葉とは、本来はキリストを差し示していたわけで、聖書を神の言葉と置き換えた時点で、塩で塩を味わうというようなおかしなことになったのではないかと思うのだ。
神の言葉であるキリストを信仰するのがわれわれの使命だ。だからモーセの出来事も、キリスト教徒としてはやはり、「やがて来るキリストの到来」を前提にして読み進めるべきなのではないか。つまり、キリストの光によって照らしを受けている者として、闇の中で神に出会ったモーセを主題として味わっていきたいと思うのである。
モーセは今日も羊を追う
さて、モーセは今日もしゅうとであるエトロの羊の群れの世話をしていた。御年80歳のじい様は、今日もこき使われ状態か、と心配になる。あるいは、80歳になっても嫁の実家を大切にしているというのは何とも大した男だとも思うわけだ。羊を連れて荒野の奥の方へと入っていくモーセ! これはそのままイエスの姿とも重なる。われわれはイエスのイメージとして羊飼いを想像するし、それは正しいことである。同時にある程度モーセを想像しながらイエスを語るのもまたよしだ。
さて、話をモーセに戻すが、筆者が大学にいた1980年代には、構造学的文書解釈論がもてはやされ、筆者もまんまと尻馬に乗ってしまった。羊の群れを連れて歩くモーセは、やがてイスラエルの民を引き連れて旅をすることになる。つまり、羊と人間(イスラエルの民)はパラレルなのだ。構造主義的には置換可能となる。では、羊とイスラエルの民は何が違うか。分かりやすくいえば、人間は頻繁に文句を言う点だろう。人間は放置されると、怒るし、いじけるし、どうもよからぬ方向へ向かってしまう。それに比べれば羊はかなり従順だ。大抵は羊飼いを信頼し待っている。羊を飼う者が人間を導く預言者へと大変身する、つまり変えられていくのである。
神の山
さてモーセがホレブの山に来てみると、主の御使いが燃え上がっている柴の炎の内にモーセに現れた。柴の木が燃える場面には遭遇したことがないので確かではないが、この柴はアラビアの荒野地帯に生えている木である。当然のごとく乾燥していることだろう。荒野地帯には背の高い木はほとんどなく、上に伸びるというよりも、低く広がっているというイメージだろうか。何となくバリバリという音を立てて燃えそうな感じがする。モーセにはその炎の中に天使が見えたのである。誰か人間が燃えているとは考えないらしい。むしろ炎の中にいるにもかかわらず、穏やかな顔をしていたと解釈すべきかもしれない。だから天使なのだと直感するということか。
表情を見て取るというのは日本語特有の表現であるが、実は大事なことでもある。カトリックや正教、聖公会などは、聖書と共に聖画も用いる。聖画というのは不思議なもので、聖画と言われなくても聖画に見える。おそらくそういうものなのだ。天使は天使であると言われなくても天使に見えるのだ。天使に会ったという人はたまにいるし、聖母マリアやキリストに会ったと語る人はもっと多い。なぜそうだと分かったのかと問うと、「その時は分かったのです」とその人たちは言う。だからやはり、そういうものなのだ。そういう感覚は実に大事なのだ。
じいさんは好奇心だらけ
天使を包み込んでいる柴はいつまでたっても燃え尽きない。本来ならさっさと燃え尽きるはずなのに燃え尽きない。不思議だとモーセも感じた。この不思議を感じる力というのは、何においても大切だ。不思議を感じる力を失うと、人間の心は濁るのである。不思議に向かっていく力というものと、宗教心(われわれは信仰心と呼ぶが)は同じものかもしれない。モーセは言う。「この大いなる光景を見に行こう」と。この好奇心こそが、80歳のじいさんであるモーセを、われわれに若い人だと勘違いさせるのだ。とにかく逃げるくらいなら前進前進だ。神事とは対面あるのみ。
道をそれる?
神はモーセが「道をそれて」見に来るのをご覧になった。何とも微妙な言い回しなのだが、こういうところが古い文章の粋な計らいである。道をそれるとはどういうことだろうか。通常の日本語では「道をそれる」というのは悪い行動に出るときに使われる。「道を踏み外す」という言い方もある。とにかく道というものは、そこから足を外さないことが肝心なのだ。しかし、それはそもそもが人間都合でいうところの「道」である。
日本古来の信仰に「神道」というものがある。「神教」ではない。神の道である。神の教えではない。この点もなかなか面白いと思うのであるが、神道には制度化された教義がない。だからキリスト教の一部には、神道は劣った宗教だと本気で考えている人もいる。しかし、長ったらしい説明をしなければならない宗教(むろんキリスト教はそういう類い)の方が実は程度が低いのではないかと、著者は時々本気で悩むことがある。
言葉足らずでよい世界
6世紀にディオニュシオス・アレオパギデス名で書かれた著作『神秘神学』1によると、神から遠ざかっている存在ほど神を語るときに無用な意味付けを多用するらしい。つまり、神について語るのは「無言」でよいということである。まあ、それで教会のコミュニケーションが成り立つなら、ほぼ無言でよいのだ。確かにディオニュシオス・アレオパギデスはそのように教えている。つまり、言葉が少なければ少ないほど、宗教表現としては良いものとなろうか。だからこそコミュニケーションツールとしての儀式というものが成り立つのである。
信仰の儀式化ということについていえば、キリスト教というものも、それなりに優れた面があり、音楽や視覚的効果などをうまく利用して宗教儀式を成り立たせてきた。ところが16世紀になって、ドイツやスイスで始まったプロテスタント主義は、あまりにも反カトリックを強調するが故に「聖書のみ」という本来はあり得ない原理をキリスト教の中に持ち込み、長い時間培ってきた教会儀式をかなり無形化してしまったのである。音楽なし、聖画なし、十字架のシンボル以外はなしなしの無味乾燥地獄を生み出したカルヴァンごときやからの所行によって、キリスト教の半分が言葉地獄へと突き落とされたのである。神秘神学のレトリックに従えば、何でもかんでも言葉で説明しなければいけない宗教というのは、やはりうさんくさいということになる。
人間の本道はどこだろうか
モーセは道をそれて燃える柴へと近づいていく。ここに神とモーセとの邂逅(かいこう)が生まれる。宗教というのは、いろんな意味で人間が人間という営みから少し道を外れて出会うものだろう。特にわれわれ現代人にとってはそういうものである。
わが心の故郷なるピューリタンは、信仰と生活の両立を是とした人たちだが、彼らにとって人間の本道とは何であったのかと思わされる。彼らの本道はもちろん信仰の道であって、その信仰の道の内側に生活の道を重ね合わせたかったわけである。信仰において生活が問われる。最も大事なことは日曜日に礼拝に行くこと。次は聖書に書かれている事柄を守ること。身近な例を挙げるなら、祈りによって始まり、祈りによって終わる一日。それが毎日の繰り返しである。だから夜な夜なパブに行って酒に酔うというのは、「祈りによって終わる」一日にはふさわしくないのだ。目覚めは祈りで! 就寝も祈りで! とはいえ、修道院ではそれが当たり前なのだが、そういう修道院をぶっつぶしたのもまたピューリタンではある。何とも皮肉である。
神に対する人間の向き合い方
道をそれて不思議へと向かうモーセ。その瞬間、彼を包み込んでいるのは「無」であると、ディオニュシオス・アレオパギデスは語る。彼はそれを「無知の闇」に入ると表現している2。不思議を知ろうとそこに入っていくのだが、そこには神がおられるので、モーセは無知の闇に出会うというのだ。不思議にクビを突っ込むのは好奇心である。しかし、その不思議の根源が神の場合、人間は無に入るのだ。だから言葉を超えていくのだ。
物理など科学の不思議に心引かれるとき、われわれが期待しているのは知恵である。知恵深くなりたいと欲している。だから、神の不思議というのはまったく逆の方向へわれわれを向けていくということになるのであろうか。少なくとも崖の上に立って石を投げ上げても、結果として石は崖下に落ちていくという意味の知恵にわれわれが導かれるわけではない。つまり、道理を知るとか、道理を身に付けるとか、そういうことではない。それが神との邂逅である。神との出会いは、教えを受けるというところからははるかに超越しているのだ。「無」になれるかどうかは別として、知性の深みを求める方向とは違う。それが「神」に対する人間の向き合いであるということを、ディオニュシオス・アレオパギデスはわれわれに語り掛けているのだ。われわれも、どこまで己を無知化して神に向き合えるのか考えてみる必要があるだろう。(続く)
- 上智大学中世思想研究所編訳・監修『中世思想原典集成 精選1』(平凡社、2018年)418ページ
- 同上417ページ
◇