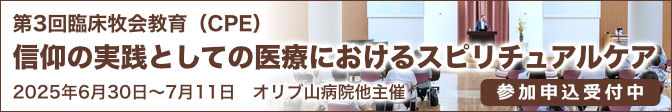つい先日、ヘルマン・ヘッセ(Hermann Hesse、1877〜1962)が、14歳(1891年)の頃に在籍していたマウルブロン修道院(神学校)を訪問するという貴重な機会がありました。知らない方のために簡単に紹介しますと、彼は1946年にノーベル文学賞を受賞したドイツ生まれの小説家・詩人です。代表作に『車輪の下』『デミアン』『知と愛』などがあります。
彼が生まれた19世紀末のドイツ(特にヴュルテンベルク地方)は教育熱心なプロテスタントの家庭が多く、その中でもヘッセの両親は、宣教師でした。そのような家庭で育てられたヘッセは、非常に成績優秀であり、両親や周囲の人々に「当然、あの子は牧師になる」と期待されていました。
そして、彼は地域の名門校であるマウルブロン修道院(神学校)に入学することになります。ところが、そのような彼は、いつしか「神に従う敬虔な子であれ」という強いプレッシャーに押しつぶされそうになり、学校からの脱走を繰り返すようになります。ついには自ら命を絶とうとするほどに追い詰められてしまい、最終的には精神療養所に入らなければならないほどになってしまうのです。
私自身も、牧師の家庭に育ち、幼い頃から聖書を毎日読むことを義務付けられるような生活をしていましたので、ヘッセが感じていたであろう「敬虔な子であれ」というプレッシャーがどのようなものであったのか、少しは分かる気がします。そして今回、マウルブロン修道院を訪問した際に、14歳当時の彼の心中に思いをはせました。
石造りの修道院は、長年の先達たちの信仰と知的な営みにより刻み込まれた厳粛で重厚な歴史の重みがあり、俗世から離れて神学と祈りに没頭できる静かで落ち着いた最高の環境でした。しかしその半面、感受性の鋭敏な10代のヘッセにとっては、融通の利かない「石の上に書かれた十戒」のように固く冷たいものであり、石造りの厚い壁、閉ざされた回廊、礼拝、聖歌、沈黙、規律、それら全てが、彼の若く柔らかい心に重くのしかかったのかもしれません。
これは単なる私の想像ではありません。これらのことは彼の作品に色濃く反映されています(以下多少のネタバレを含みますので、作品を先に読まれたい方は、読まれてから、戻ってきていただければと思います)。
例えば、代表作の一つ『車輪の下』では、まさに神学校で優等生として期待されながらも、自由を求めて苦しみ、次第に心を病んでいく少年「ハンス・ギーベンラート」の心象風景が描かれています。彼は、自然の中で釣りをする時間や、友と語らうひとときにこそ本当の喜びを感じていました。しかし、厳しい規律と周囲の期待の中で、その心は次第に押しつぶされていき、神学校を去ることになります。そして、物語の最後は、悲しい結末となってしまいます。
このヘッセが感じた重圧こそが、欧州においてキリスト教が衰退した主な理由だったのだと思います。もちろん、他にもいろいろな要素があるでしょうけれど、若いヘッセが感じていた重圧を理解しない限り、教会は無意識のうちに若い人々の魂に同様のプレッシャーを与え続けてしまうことになります。
このように聞くと、ある人たちは「やはりキリスト教は固く融通の利かない道徳宗教であり、敬遠すべきだ」と一面的に捉えてしまうかもしれません。しかし、もしそれだけであったなら、ヘッセは苦悩しなかったでしょう。別の代表作の一つ『知と愛』では、理知的な神学と信仰の世界に重きを置くナルチスと、感性的で肉体的・放縦な生き方を追求するゴルトムントという2人の対照的な人物が描かれています。
2人は互いに異なる道を歩みながらも、深い友情で結ばれていきます。この作品に流れる根本的な問いは、まさにヘッセ自身が若き日に神学校で経験した、神聖さへの渇望と自由、信仰と生の躍動との間の葛藤そのものといえます。そして、これらの対立を乗り越えようとする試みが、彼の作品群の全体を貫いているのです。
印象的なシーンとして、ゴルトムントが自身の苦悩をナルチスに打ち明ける場面において、ナルチスは、彼の思いを受け止め、自身もまた、より深い矛盾や悩みを抱えていることを認めながらも、包み込むように友を指南します。
また、ゴルトムントは放縦な生き方をしつつも、自己の信仰や精神性の表象として、ヨハネやマリアなどの信仰者たちの像を彫るのですが、それは修道院にある他のどの彫刻よりも卓越したものでした。
これは三浦綾子さんの『ひつじが丘』という作品に登場する「良一」という人物に通じるものがあると私は感じます。「良一」は、自堕落な生活を送り、周りの人からは人生の敗北者のように見られていましたが、終盤において、彼は信仰に導かれ、最後に自身の信仰告白となる非常に印象的な宗教画を残します。これらの作品は、最も高潔な人の中にも罪や矛盾があることを、そして最も自堕落な者の中にも、魂の美しさが内包されていることを示唆しています。
両者に共通しているテーマは、形式的な教義、血の通っていない戒め、暗く冷たい宗教への批判とともに、神ご自身への信仰や生の奥底にある神聖さへの希求です。そして、同様の神聖さへの希求を、現代の若者たちも持っています。だからこそ、どんなに「宗教は古臭い」「神は死んだ」などと言われたり、コスパや合理性が優先されたりするように見える社会においても、信仰を持つ人々は後を絶たず、科学や経済が世界を主導しようとも、それだけでは満たされない魂の渇きがあらわになっているのです。
では、どうすればよいのでしょうか。それは、若いヘッセがプレッシャーを感じてしまったような硬直化した宗教ではなく、キリストが体現した神の愛、父子聖霊(三位一体)なる神との生き生きとした交わりに回帰することです。
本来のキリスト教は、パウロがコリント人への手紙第二3章で語っているように「石の板にではなく、人の心の板に書かれたもの」です。また「文字(もんじ)は殺し、御霊は生かすからです」とあるように、御霊による真理と命に満ちたものであり、「あなたがたは真理を知り、真理はあなたがたを自由にします」(ヨハネの福音書8:32)とあるように、重圧ではなく真の自由を与えるものです。
つまり、宗教的道徳を厳粛に守らなければならない、さもなければ罰せられるという硬く冷たい石の壁のような教えではなく、最も放縦で罪深い者であっても受け入れられ、赦(ゆる)され、愛されているという、十字架の恵みと父なる神の心に根ざしたものなのです。
そして、神様から一方的に赦され、無条件に愛されていることを知ることによって、隣人を宗教的義務から愛さなければ「ならない」のではなく、心から内発的に隣人を愛し「たい」と願うもの、主と同じ姿に変えられていくのです(2コリント3:18)。
実は「車輪の下」というタイトルそのものが、構造化された社会や厳格な宗教教育という巨大な「システム」が少年たちの若い柔軟でセンシティブな感受性を、その歯車や車輪で押しつぶすという比喩になっています。そして、同様の重圧は現代の若者たちの魂をも押しつぶそうとしています。
しかし今述べた通り、キリスト教の本質は、重圧ではなく真の自由を与えるものです。確かにヘッセの作品は、自殺未遂を起こすほどの重圧や苦悩と、神聖さへの渇望との葛藤の故に、読者の魂を揺さぶり、多くの人々の共感を呼びました(私もまた一時期、彼の作品に魅了されました)。
このような読書体験は、傷ついた心を大いに慰撫(いぶ)し、あるいは一筋の光明を与えます。ただ、それだけでは、彼のように傷つく少年たちや時に命を落とす者たちがその後に続くことを止めることはできません。
これは、教会だけの問題ではありません。一般社会においても、成長至上主義、自己実現や成果追求というキーワードが、あたかも新たな福音であるかのように語られています。
このような時代において、ぜひとも必要なことは、教会が石の板に書かれた文字ではなく、神の愛によって心の板に刻まれるメッセージを回復することです。それは新しいものではなく、2千年前から聖書に明確に書かれているのですが、決して人の知恵によっては悟ることのできないものです。
律法は「隣人を自分自身のように愛しなさい」という正しい戒めを宣告し、その劣化コピーである自己啓発の指導者たちは「ギバー」であれ、「夢や目標」を持てなどと教え、その言葉の正しい響きの故に、青年たちの心に偽りの全能感を付与します。
しかし、人は愛されることなしに隣人を愛することはできません。また、与えられたり、徴収することなしに「ギバー」となることはできません。無神論者である限り、どんな崇高な目標や大きな夢を持ったとしても、あなたの人生の意義はその途中で霧散してしまいます。
このような現実を真摯(しんし)に見つめて、本当の意味で自らに絶望するときに、敬虔で正しい子だから受け入れられるのではなく、能力や努力によって称賛や存在意義を勝ち取らなければならないのでもなく、「ありのままのあなたを深く深く愛している」という父のメッセージが、どれほど「有り難い」ものであるのか、そのメッセージを体現するために十字架で死なれたキリストの姿がどれほど真実であるのかが、身に染みるようになるのです。
◇