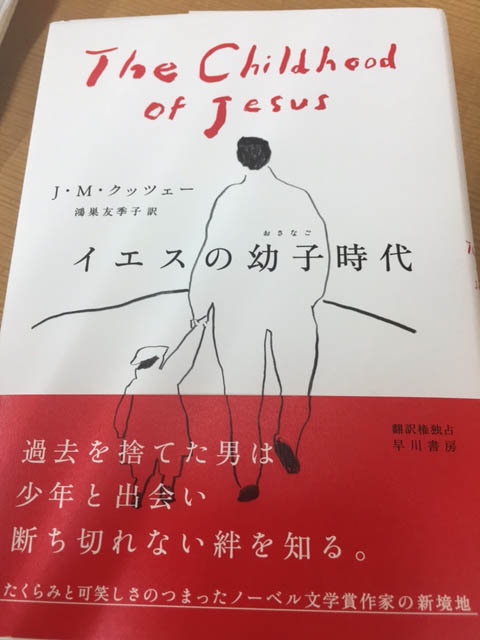ジョン・マックスウェル・クッツェーは、2003年にノーベル文学賞を受賞した南アフリカ出身の小説家。現代世界で最も評価の高い小説家の1人だ。ノーベル文学賞受賞の際に「数々の装いを凝らし、アウトサイダーが巻き込まれていくところを、意表を突くかたちで描いた。その小説は、緻密な構成と含みのある対話、素晴らしい分析を特徴としている。しかし同時に、周到な懐疑心をもって、西欧文明の持つ残酷な合理性と見せかけの道徳性を容赦なく批判した」と評価されたという。
本書は、そんな評価がぴったりだなと思わせる、どこか不思議でありつつ神学や哲学を盛り込んだ遊び心(?)に満ちた、現代のイエス・キリストをめぐる家族の物語だ。
主人公は、中年の男シモンと少年ダビード。2人は移民として(?)船の中で出会った、血はつながっていない赤の他人、でもはたからは親子のように見える。その2人がノビージャという町にやって来たことから物語は始まる。名前も入国管理施設(?)で勝手に付けられたもので、本当の名前は分からない。過去が説明されることもない。そして、町の移民収容所(?)のような施設で生活を始めることになる。
場所も時代背景も説明はないが、スペイン語が話されていることから、舞台はスペインか南米のどこかの国を思わせる。町は清潔で、人々は礼儀正しく善意にあふれているが、規則に厳しく融通がきかない。そしてパンを食べ、水を飲むことで満足し(!)、仕事が終わると市民講座に通い哲学を学ぶ、つつましい生活を送っている。
社会福祉が整い、穏やかに管理されたどこか無機質な町。翻訳者の鴻巣友季子さんは、この小説はいわば一種のディストピア(反ユートピア)小説である、と指摘しているが、そこに流れる雰囲気は殺伐としてはいない。清潔で無機質で穏やかな管理されたディストピアの空気は、映画化もされた(ノーベル文学賞候補にもたびたび名が挙がる)カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』に少し似ているかもしれない。
登場人物の多くは、聖書やキリスト教の伝承から名前が取られている。ダビードは言うまでもなくダビデ。マタイ福音書の冒頭に記されているように、イエスがダビデ王の系譜にあることを指している。母イネスは「神聖・純粋」を意味し、いわば聖母マリアの役割だ。
ダビードに献身的な愛を注ぐシモンは、やはりイエスの養父ヨセフを思い出させる。そのほかにもステファノ、エレナ、ディエゴ(スペイン語でヤコブを指す)など、聖書のおなじみの登場人物たちの名前を持つ人物が登場する。
新約外典などを下敷きにしたイエスの少年時代?
あとがきで翻訳者の鴻巣さんは、「(キリスト教や聖書の)寓意に捕らわれるとつまらないので」と書いているが、一応クリスチャンの身としては、やはりいちいち聖書からのメタファーの背景をほじくり出し、想像しながら読むのが楽しい(笑)。
福音書には、イエスの少年時代について、生誕物語以外はほとんど記されていない。わずかに、ルカの福音書に12歳になったイエスが両親と共にエルサレムに巡礼し、神殿でラビたちと語り合っている様子について書かれているぐらいだ。イエスが30歳になって伝道を始めるまで、どんな少年時代を送ったのかは、永遠の謎なのだ。だからこそ、小説家が想像によって物語を「創造」する余地があるのだ。
一方、キリスト教会で正典として認められていない「外典」には『トマスによるイエスの幼時福音』などのイエスの幼児物語が存在する。現代の研究では、2世紀ごろ、キリスト教が広がるにつれて作られた伝承であり、史料的な裏付けはないとされ、教会には承認されていない。しかし、これらの物語は古くから広く読まれ、民衆の間での信仰や宗教画などに大きな影響を与えてきた。この小説でも、それらのイエスの幼児物語が下敷きになっている。
例えば『トマスによるイエスの幼時福音』には、こんな物語があるという。文字を知らない少年イエスを父ヨセフが教師のところへ連れて行くと、イエスは教師を見つめて「あなたはアルファの本性をも知らないのに、どうしてほかの者にベーターを教えるのですか。偽善者よ、もし知っているならまず第一にアルファを教えなさい。そうすればベーターについてもあなたを信じましょう」と話す。教師は少年イエスに答えることができなかった。
この物語の主人公ダビードも賢くユニークなものの考え方をするが、それ故に学校にはなじめない。教師を言い負かして叱られ、嫌われる。こまっしゃくれて、甘えん坊のなかなかやっかいな少年だ(笑)。
そんなダビードを、血がつながらない“父親役”として心配し、たしなめ、献身的に愛を注ぐのがシモンだ。その姿からは、養父ヨセフもこんな苦労をしたんだろうなぁと同情し、思わず応援したくなってしまう(笑)。
そして、子どもには“母親”が必要だと考えたシモンは、町で、ダビードの母となる女性を探す。そしてダビードと、“母親”イネスと、“父親”シモンの3人の生活が始まる。しかし、“母親”イネスは、感情的で甘やかすばかりであまりいい“母親”といえず、これまたシモンの悩みの種となるのだが(笑)。
随所にちりばめられた聖書の“ギャグ”と“パロディー”と“言葉遊び”
本書の一番の魅力は、なんといってもシモンとダビードの会話に張り巡らされた、聖書や神学や哲学を下敷きにしたギャグとパロディーと言葉遊びだ。
例えば、ダビードはシモンに、将来何になりたいかを聞かれ、ライフセーバーか脱出奇術師か手品師(マジシャン)になりたいと語る(!)のだ。
またシモンはダビードに、ソーセージは豚の肉が入っていて不衛生だからあまり食べないようにと語る。「豚を食えば、豚みたいになるんだ。きみの一部がね」「キリスト教で言う“共存説”というやつだ。この考えなくして、どうして人食い族が存在すると思う? 人食いというのは、共存説をまじめに実践する人々なんだ。他人を食べれば、その人間が自分の一部になる。人食いたちはそう信じている」
共存説とは、カトリックの聖餐におけるパンとぶどう酒が、実際にキリストの体と血に変化するという「実体変化」説に対して、ルターによって提唱された“パンとぶどう酒の実態は変わらず、パンとぶどう酒の実体と共にキリストの体と血が共に現存する”という神学的な説明のこと。しかし、それを豚肉や人食い人種で例えるとは、牧師や神学者が聞いたら怒って卒倒しそうな会話だ(笑)!
でも、ギャグばかりではない。ダビードに「ふたご座」について聞かれたシモンはこう語る。これほど分かりやすく詩的に「三位一体」を語った言葉があるだろうか?
「空のふたつの星は括りつけられているわけじゃない。星と星の間には小さな隔たり(ギャップ)、つまりすきまがある。それが自然の摂理なんだ。恋人同士を考えてみるといい。年がら年中たがいに縛り付けられていたら、愛しあう必要もなくなるんじゃないか。一つになってしまうんだから。求めあうものがなくなる。
だから世界には隔たりというものがあるのさ。なにもかもが、この宇宙のなにもかもが、ぎっちりとすきまなく詰めこまれていたら、きみも、わたしも、イネスも区別がなくなってしまうだろう。
たったいまも、きみとわたしが話しあうこともなく、沈黙が続くだろうね。―なにもかもが一つになって、黙りこくる。そんなわけで、まあ、何かと何かの間に隔たりがあること、きみとわたしが一つではなく二つに分かれているのは、総じてよいことだよ」
かように何重にも張り巡らされた仕掛けや遊びは、さすがはノーベル文学賞作家と、うならされる。ただあまりに玄妙で、読んでいるこちらがどこまで分かっているのか試されているような気がしないでもないが(笑)。
さて物語の後半、賢いが学校教育になじめない(まあそうでしょうね・・・)ダビードは、特別な学校に入れられるが、脱走して2人の元に戻ってくる。そして一家は車で町を離れ、別の町での生活を目指す道中、「ファン(John=ヨハネのスペイン語形)」というヒッチハイカーを乗せ、4人で旅に出る。
そして「でも、そこで何をするの?」と尋ねるダビードに、父シモンはこう答えて物語は終わる。
「こう言うんだ。『おはようございます。わたしたち、いま着いたところなんです。どこか泊まれるところを探しています』」
この福音書のイエスの有名な派遣の言葉で物語が締めくくられているのは、毎週のようにニュースで報じられる現代世界最大の課題である、国を追われ、行き場を探してさまよう移民や難民の人々の中にこそイエスはいる、そしてそれをどう迎えるのか?というノーベル賞作家クッツェーの極めて現代的な問いが込められているように思える。
クッツェーは、今年秋にはこの小説の続編(『イエスの学校時代』)を出版する予定だという。ダビードは、カリスマ教師のいるダンスアカデミーに入学(!)するとか。果たしてどんな学校生活を送るのだろうか!?続編を手に取り読むことのできる日が、今から楽しみでならない。
ジョン・マックスウェル・クッツェー著『イエスの幼子(おさなご)時代』鴻巣友季子訳 早川書房 2484円(税込)