2022年の大学入試は、いろいろな意味で波乱尽くしである。まず何と言ってもコロナ禍。昨年10月以降、収まったかに見えた感染状況が、年明けに一気に変化した。連日「感染者○○人」というニュースが報じられていることからも分かるように、受験生にとっての敵は他の受験生ではなく、100年に一度と言われる「目に見えない敵」となりつつある。そのストレスは計り知れないものがあろう。
続いて、今年から始まった共通テスト。従来の基礎的な知識を問うものから、「総合的な学力を測る」という名目で、数学の問題文が現代文のそれくらい長くなるなど変化した。結果、数学の平均点は過去最低を記録してしまったという。
これらに加えて、大学入試に関わる青少年の犯罪が頻発した。共通テスト1日目の朝、試験会場の一つとなった東大の前で、高校2年生の男子生徒が受験生を含む3人を刺傷してしまった。生徒はその場で取り押さえられ、やがて身元が判明する。愛知県の出身で、県下でも有名な私立の中高一貫校に通っていたという。
続いて事件は、試験会場内で起きた。19歳の大学1年生が共通テストの世界史の問題を動画で撮影。それをネット上に公開し、東大生らに解答を依頼する事件が発生した。彼女は母親に付き添われて警察署に出頭。捜査の過程で、家庭教師紹介サイトを利用し、周到に計画を練っていたことが判明した。しかしその一方で、IPアドレスなどは本人名義のものを使用しており、まったく稚拙で素人の犯行であったことが分かり始めている。
1970年代から80年代に姦(かしま)しく使われた「受験戦争」という言葉は、大学進学率が6割を超えようかという現在においては死語となっている。しかし統計がどうあれ、迫りくるプレッシャーから自らが「戦争状態」にあると認識する若者が絶えないことが、こうした事件を通じて示されているような気がしてならない。
私は愛知県出身であるため、刺傷事件を起こした生徒が「愛知県の有名私立進学校に通っている」という報道を聞いてピンと来た。「あそこしかない」と思ってしまった。そしてそれは残念ながら当たっていた。そこから私の関心は、(申し訳ないが)刺傷された人たちに対してではなく、この少年に向いた。というのも、私もこの中高一貫校を受験していたからである。私の場合は中学受験だったが、この学校に合格するということは、ちょっとしたヒーロー気分を味わえることを意味していた。地域の人たちが、合格した子の家にお祝いに駆け付けることもよく目にする光景だった。幸い私も合格通知を手にできたが、結果的に入学を辞退した。理由はいろいろあったが、今振り返るなら、超進学校としての校風の前にビビッてしまったということだろう。
この事件を知り、「もし私があのまま入学していたら・・・」と考えると、空恐ろしい気持ちにさせられた。今回の事件を起こした少年は、もしかしたら自分だったかもしれないからである。だからこの事件は他人事とは思えなかった。また、自分が大学入試で「カンニングしてでも合格したい」というどす黒い欲望を抱えていたことを覚えているだけに、カンニング事件を起こした学生についても、私は大上段から断罪できないと思う。
やるかやらないか、これは天地ほどの差があるが、しかしそんな危うい一線に近寄りたいと思う者は数多く存在するだろう。彼らは皆、疲弊している。不安を抱えている。その不安を押し殺すことができるか、それとも不安に「具体的に対処」しようとするか、の違いでしかないとしたら、いつ激情に駆られてその一線を越えてしまうか、その危険性と常に隣り合わせであることを、私たちは忘れてはならないだろう。それは、わが子も含めてである。
そんな悶々(もんもん)とした思いの最中、一冊の新書に出会った。かつて『アメリカンインディアンの教え』で一世を風靡(ふうび)した心理学者・加藤諦三氏の『不安をしずめる心理学』である。本書で加藤氏は、「不安」について次のように述べている。
不安には、現実的な不安と神経症的不安の二種類があります。(中略)より深刻なのは、もう一つの神経症的な不安のほうです。こちらは現実には怖くないものを怖いと思って、怯(おび)えているような不安です。日常生活ではこれが非常に大きな問題になるわけです。(46ページ)
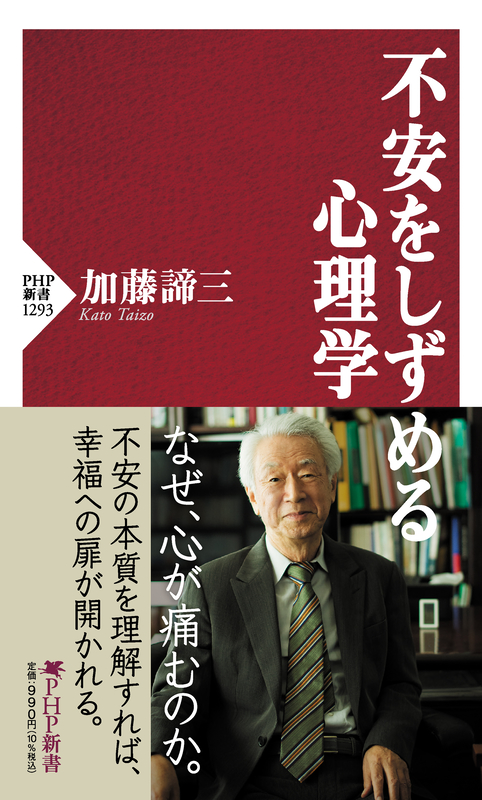
東大の刺傷事件も、共通テストのカンニング事件も、まさにこれに当たる。受験までまだ1年もあるのに、どうして「もう駄目だ」と思ってしまったのか。カンニングという不正行為を犯してでも「大学を変えたい、変えなければ駄目だ」とどうして思ってしまったのか。これらの現実の事例の中に、加藤氏が指摘する「神経症的不安」が見え隠れする。
さらに予言的でびっくりしたのは、4章で次のように語られていた部分である。
社会を驚かすような罪を学生が犯した時に、テレビや新聞などの報道では「模範的な生徒だった」と言われることがあります。(中略)社会的には、うまくいっているように見えるし、社会的に適応しているようにも見える人が、実際は「危険な土台の上に立っている」ということです。(106~107ページ)
本書が今年1月に発刊されていることからすると、今回の刺傷事件やカンニング事件が起こる前に、これらのことを一般論として言及したことになる。しかし残念ながら、加藤氏の言葉は「予言」となってしまった。私は読み進めながら震えが止まらなかった。
そして、心から思う。神経症的な不安を取り除くには、神経症的な不安を抱えているそのままを受け入れる環境が必要だ、ということを。「北風と太陽」の小話のように、真に心を照らす「太陽」が求められているのだろう、と。
私は牧師である。だから教会がそういった場になってくれたらと心から願っている。しかし翻って考えるとき、果たしてそうなり得ているかと自問自答せざるを得ない。
加藤氏の著作は、時々購入して読み続けてきた。そしてはっきり分かるのは、彼が講演や著作でなしているのは、聖書が語る「律法」の役割であるということである。つまり、暗闇の世界に光をともすことである。ただし断っておきたい。それは「光をともすだけ」である。暗闇に光がともされるなら、起こっている出来事が赤裸々に分かる。見える。多くの人々(決して青少年だけでない)が「神経症的不安」を抱えていることが見て取れる。これは有用なことだ。しかし、ここまでである。もちろん、直接加藤氏のカウンセリングを受けたり、心療内科で手厚く面談してもらえたりする人はいい。しかし、聖書の律法が人間の罪を指摘するのみにとどまるように、本書は神経症的不安の渦中にある人の決定的な助けにはならない。なぜなら「赤裸々に現状を示すのみ」だからである。
教会は、そうした彼らに手を指し伸ばそうとしている。だが、教会にも問題がある。それはすべて「聖書」「福音」で何とかなると思い込んでいることだ。自分たちが「真理」を握っているから、それで何とかなると思っている。率直にいえば、高をくくっている。
私たちは、自らの立脚する福音を信頼しつつも、それを敷衍(ふえん)するためには実践的な学びが必要であることを忘れてはならないと思う。福音は素晴らしい。しかしこれは、車でいうなら片方の車輪でしかない。それを原動力として、実社会に有効な方法でトランスミットしなければならない。そこに、加藤氏のような心理学的な素養が必要不可欠であろう。
大学入試をめぐる事件はセンセーショナルであり、人々のどす黒い本能(少しでも自分が他者より上になりたい)を刺激することになる。しかしそれらに真摯(しんし)に向き合うために、教会に必要なのは「福音の躍動感」である。教派的真理に凝り固まった神学ではなく、泥臭くも生き動く、若者たちと格闘する中で少しずつ体得していく「聖書からひもとかれる知恵」である。その知恵を際立たせてくれるのがアカデミックな視点、学びであろう。暗闇を照らす光が必要なのである。
そのことを思いながら、また今日も聖書を開き、この社会で必死に闘っている人々の心に届くメッセージ、そして実践を模索している。この営みは決して終わることがないだろう。
◇































