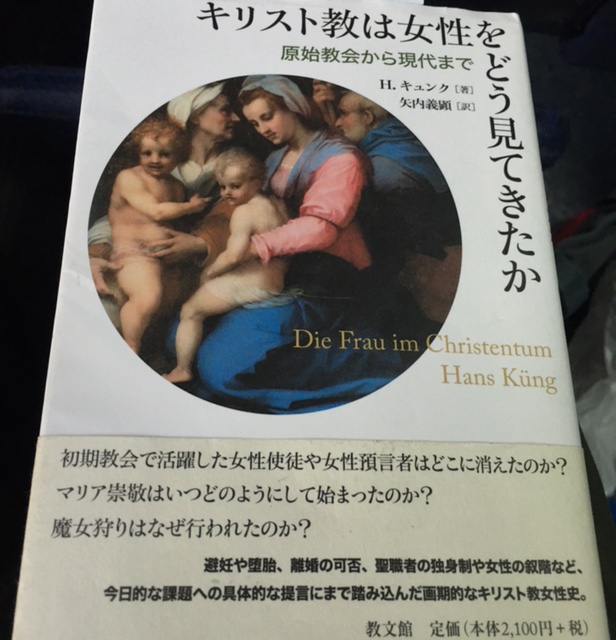マリア崇敬
本書の中で最も興味深いのは「マリア崇敬」に関する問いだ。カトリックとプロテスタントの信仰理解の最も大きな違いの1つは聖母マリアの位置付けだ。
プロテスタントではマリアの「無原罪」を認めないし、その名によって祈りをささげることもない。しばしばそれを「聖書的ではない」と言って批判することもある。
女性教職者を認めるプロテスタントは、「男女平等である」と主張する。しかし、本当にそうなのだろうか?(特に私が所属する日本基督教団の)教会の中にいれば、そこがいかに男性中心的であるかは肌で感じることが多い。実際多くの教会では、女性牧師は副牧師だったり、「牧師夫人」としてしか認識されていない。
私自身はプロテスタントだが、カトリックのミサに参列すると、むしろ“女性的な感性”や“やさしさ”を節々で感じられてほっとすることが多い。ちなみに最も“ほっと”するのが「ロザリオの祈り」の時間だ。そこにリゴリスティックなプロテスタントと異なる“母性的なもの”を感じるからなのだろう。
しかし、本書は教会史をたどりながら、「マリア崇敬」が男性中心で女性が排斥され続けてきた教会の中で“代償行為”として教義的に構築されてきたのではないか、という鋭い問いを投げ掛けている。
キリスト教における聖母マリアの位置付けは、5世紀の「テオトコス(神の生母)」論争のように古くからあり、6世紀にはミサのテキストにその名が取り入れられ、東方正教会では祝日が導入されるなど存在感を増していき、12世紀のアッシジのフランチェスコの下で、子どもたち、貧しい者たちなど周縁化された人々の助け手として「下から」「民衆の敬虔」として広がっていったという。
そして13世紀から15世紀以降には「ロザリオの祈り」が行われるようになった。しかし、教理になったのは、科学や啓蒙主義に対抗しようとする近代のカトリックの保守主義の中においてだった。(「マリアの無原罪の御宿り」が教理として決定されたのは1854年、「教皇不可謬性」の宣言は1870年。マリアの「被昇天」が教理宣言されたのは1950年)
キュンクは、ヨーロッパで最初のカトリックの女性教授カタリーナ・ハルケスの「マリアは、女性には抑圧的で男性には無批判な、つまり教会が(女の)性と聖人仲介との間につくった裂け目を正当化すべき、可能なモデルなのか」という問いを踏まえて「位階組織が、マリアという人物によって、独身聖職者にとって『精神的な仕方』で親密さ、親切、女性性、母性を経験できる、代償となる人物像を作り上げたのである」とまで述べる。そして20世紀のプロテスタント神学者ユルゲン・モルトマンの言葉を引用する。
「これまでのマリア論は、――誠実に、冷静に確認しなくてはならないことだが――超教派的というより、むしろ全教会的なものに反対するように作用してきたのである。マリア論の発展は、キリスト教徒をユダヤ教徒から遠ざけ、教会と新約聖書の距離をつくり、プロテスタント教会とカトリック教会を分離させ、キリスト教徒全体を現代の人間と隔ててきたのである。教会のマリア論の教えるこのマドンナ〔聖母マリア〕は、イエスの母親であるユダヤ人ミリアムとはたして同一人物であろうか。このミリアムを、聖母マリアのうちに発見できるだろうか。教会の聖母マリアの名のもとに生じた分裂と分離を念頭において、ユダヤ人の母親ミリアム自身をもう一度問い直してみる必要はないだろうか」
そして次のように主張するのだ。「マリアの姿を男性的――独身性的な聖職者位階制の理想像からも、女性による代償的なアイデンティティー探しの理想像からも解放され、エキュメニカル(超教派的)なマリア像のために道を開かなければならない」。そしてこの項目を以下のように締めくくっている。
「マリアとイエスの口から、女性に対して沈黙の命令も服従の命令も発せられることはない。この2人は、女性がこの世界のすべての悪に責任があるとする『エバの神話』をまったく知らない」。この問いはラジカルかつ極めて鋭いと言わざるを得ない。
宗教改革で女性の地位はどう変わったか?
マルティン・ルターは修道士だったが、聖職者の独身性を否定し、結婚して子どもをもうけた。キュンクは宗教改革によって、結婚が高く評価され、司祭叙階の優位性が日々の家族生活に取って代わられ、修道女の理想は、妻、母の理想に取って代わられ、セクシュアリティーの蔑視は自然本性的な欲求として肯定されるようになった、と一定の評価をする。
ルターは神学的に「神の被造物としての男性と女性は、ともに神の姿として創造されている。身体性と性別は、彼らの自由になるものではない。それらは、神の賜物であり、それ自体として評価されるべきである」という立場を取り、女性の教育、就学など実践的にも女性の価値を高めることに寄与した。
しかし同時に、キュンクは「宗教改革のパラダイムにおいても社会構造は徹底的に家父長的なまま」だったことも指摘している(これはまさに現代の日本の教会にも当てはまるといえるだろう)。社会の中で、結婚は両親によって整えられ、経済・法律、政治的に男性の下に置かれたままであり、手工業、商売、医師など職業上においても平等の権利・賃金が伴うことはなかった。教会でも女性が重要な役職や聖礼典執行、説教をすることは禁じられていた。
「女性たちは、依然として、国家、教育制度そして教会における決定に参加することは全くなかった」。さらに、かつては未婚の女性の安全で意義のある生活基盤だった女性修道院が消失したことで、その生活基盤が奪われた。
魔女狩り
さらに、猛威を振るったのが、「女魔術師は、生かしておいてはならない」(出22:17)という言葉による「魔女狩り」だ。今日の研究では、中世から近世にかけ最低でも10万人の死刑執行が行われた。「男性たちによる女性たちの大量殺人」は、カトリックとプロテスタント、どちらの国々でも広く一般に行われた。研究者たちはその動機として以下のような女性への偏見を指摘している。
- 農村の下層階級の女性たちが持つ気難しさや悪態に対する反動。
- 身寄りのない孤独な女性と、彼女たちが持つ極めて実際的な医学と避妊技術の知識に対する家父長制の抱く不安。
- 専門的に養成された医師たちが、民間医療と専門的に養成されたのではない産婆や治療師に対してとった敵対的な態度。
- 性的不能と不妊、凶作、家畜の伝染病、大災害、病気と、死に関するスケープゴート的な考え。
- 一般的な女性嫌悪。
- 独身の教会の審問官たちの持つ官能的快楽に貪欲な女性たちという幻想。
魔女狩りは17世紀になり下火になっていくが、1786年になってもブランデンブルクで大量の火刑が行われたという。このような魔女狩りが終わり、女性の地位を根本的に変化させたのは、「宗教改革」ではなく、次に続く「啓蒙主義」だった。
近代の教会は女性の解放を阻止したのか、それとも促進したのか?
近代になると、合理性を重視するパラダイムの変化の中で、女性たちが過去数千年の間どれほど冷遇され、道具化され支配されてきたのかが初めて自覚された。しかし、それにも長い時間が必要だった。
女性の参政権が認められたのは、ニュージーランド(1893)から始まり、オーストラリア(1902)、オランダ、ソビエト(1917)、カナダ、英国、ドイツ(1918)、米国(1920)、フランス、イタリア、日本(1945)、スイス(1971)と、長い時間を要した。
産業革命によって女性も安価な労働力として工場で働く中、女性の権利を求める運動も始まったが、それは教会ではなく、自由主義者(特に社会主義者)によって始まった。キュンクは次のように厳しい指摘を行う。
「教会は、結局、社会的な変化の現実、つまり近代世界をせいぜい部分的にしか受け入れず、決して根本的には受け入れなかった」
当時、女性運動は教会においてほとんど支持されず、特にカトリック国家ではこの傾向が強く、それは現代にも残っているという。一方でプロテスタント諸国では、女性たちは教会の社会奉仕活動を形成し、女子社会学校(職業訓練校)を設立し、有給のソーシャルワークのプロジェクトを行い、政治活動を行っていった。(例えば、今年大きな話題になったNHK連続ドラマ「あさが来た」の広岡浅子は女性教育に尽力した成瀬仁蔵牧師の影響を受け、日本女子大やYWCAの創立に尽力したことも、この中に歴史的に位置付けることができるだろう)
しかし、キュンクは「キリスト教に失望し、多くの女性たちは、決してキリスト教共同体への道を戻ることはなかったのである」と、やはり厳しい指摘がなされている。
そして現代へ
第2次世界大戦が終わり、1948年の世界教会協議会(WCC)や、1962年からの第2バチカン公会議が始まった。キュンクはこれらが女性に開放的な影響をもたらしたとしながらも、避妊や中絶、同性愛に対して厳格な態度は変わることはなく、カトリック教会ではその後停滞しているとも指摘する。また、60年代からは、世界的なフェミニスト運動の中、フェミニスト神学も生まれ、活発な議論が広がっていった。
キュンクは、「彼女たちの信仰において、もはや男性たちの経験を借用して生きることはせず、彼女たち自身の経験の現実を発見し、彼女たち自身の神学の主体となることを開始する」「キリスト者の女性であることと社会的な解放は、もはや矛盾しない」「女性は誰でも単に彼女たち自身の尊厳を確認できるだけでなく、教会と社会のあらゆる領域における共同決定と関与に固有の権利をもち、それらが決して男性の諸権利に劣るものではないことを確認できるのである」と高く評価しながらも、まだその解放が少数の女性たちしか手にできていないと述べる。
キュンクの教会への改革の要求と「あきらめてはならない!」というメッセージ
その上でキュンクは「具体的な改革の要求」を以下のように求めている。
- 夫への妻の従属は、キリスト教的な結婚の本質に属することではない。それは共同で引き受けられるものである。
- 責任をもってなされる産児計画は真の女性解放に寄与する。堕胎については女性の身体・精神的な結果と社会的な地位、家族や養育に対する責任も考慮して考えるべき。
- 公会議を含む聖職者の意思決定機関全てに女性が出席するべきである。
- 女性たちがカトリック神学を大学で学ぶことを促進し、奨学金によって男性と同様に援助されるべき。
- 男子修道会に比べて、援助が少ない女子修道会への援助の拡充。
- 原始教会にあるように女性の助祭職を導入し、女性が典礼での役割を担うことを認める。
この著作の出版は2001年だが、この要求の多くが、聖職者による性的虐待の世界的スキャンダル以降、カトリックや世界のキリスト教が向き合わざるを得ない現実であることを考えると、その鋭さにはやはり驚かされる。
ハンス・キュンクは、最後に「あきらめてはならない!」という以下のような文章で本書を締めくくっている。
「私は冷静に確信する。私が、位階組織が分別をもつまでさらに25年待たなければならないのだとしたら、私はその根本的な変化を確実に見ることはないであろうし、私と共に歩んできた他の何人かの男女もそうであろう。私たちは決して希望を捨てることはない」
「だが同時に私たちは続行することにしよう。教会は『下から』生き、『上にあるそれ』は、遅かれ早かれ、女性の同権との戦いに敗れるであろうし、それは『魔女』との戦い、民主主義と人権との戦いに敗れたのと同様である。このために女性たちはすでに自ら備えている。最後に私は本書を、私の歩みをつねに励ましてくださった全世界の数えきれない女性たち、とりわけ、何十年にもわたり喜びと苦悩をともにし、私の使命を活動的に支えてくださった女性たちへの心からの感謝の言葉で閉じることにする」
「私たちは決して希望を捨てることはない」という一文は、ローマ4:18「私たちは希望に反して希望を持つ」を引用している。カトリックの中で教会の権威性を批判し続けてきた「戦う神学者」ハンス・キュンクの情熱と信仰が叩きつけられているかのような一文に身が震える。
読み終えて思うのは、本書は膨大な資料を駆使しながら、極めてラジカルな教会批判の書といえる。しかし、それは今世界のキリスト教会が向き合わざるを得ない現実を鋭く批判している。その意味で、本書はやはりこの数年で最も重要な神学書なのだと思わされる。教会はその問いに応答することができるのだろうか?
ハンス・キュンク著『キリスト教は女性をどう見てきたか―原始教会から現代まで』矢内義顕訳、2016年4月、教文館、定価2100円(税別)