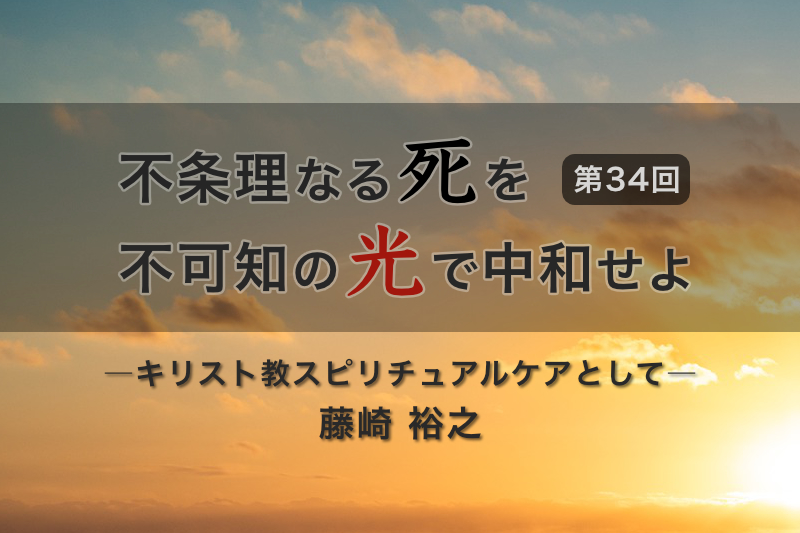
不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(34)
※ 前回「そもそも預言は聞かれたのか(その1)」から続く。
え、神の言葉ですって?
エレミヤを話題にしているが、エレミヤ書を一意に読み解くつもりはない。大体が預言書というのはややこしいのだ。一通り読み解いたことがあるが、正直同じような内容の繰り返しである。誰かのお説によると、エレミヤ書というのは、エレミヤが預言をした順番通りにはまとめられていないらしい。とはいえ、エレミヤが預言をした順番を再現したものというものにも、お目にかかったことはないので何ともいえない。
とあるお偉い註解者によると、エレミヤは悲劇の預言者なのだそうだ。一口で言うと、ほとんどの人が彼の語る預言を聞いてくれなかったということらしい。また、預言者としての尊敬もほとんど受けることなく、ユダ王国の滅亡時には拉致されて、つまりドナドナされて、恐らく国外で殺されたようなのだ。そういうことを含めて、悲劇の預言者と呼ぶにふさわしいらしい。いわゆる「結果悪し」ということであろうか。
エレミヤが殺されたという証拠はない。そのあたりはどうなのだろうと思う。殺されたことにしておけば、悲劇の預言者として語りやすいということだろうか。もっとも、預言者というのは現在進行形としては「結果悪し」の人々なのであろう。大抵の人にとっては耳障りなのだ。なぜかといえば、それが神の言葉であるからだ。
「神の言葉がわが身に湧き起こった」と自覚する人間のその言葉が聞いてもらえないわけだから、居たたまれない。この居たたまれなさが、エレミヤ書の行間からビシバシ伝わってくる。神の言葉なのに、ほとんど誰もが拒絶する。まあ、それはある意味でイエスも同じだったわけだ。
神の言葉だから聞いてもらえないと言い換えてもよいのかもしれない。神の言葉を聞くというのは、なかなか大変な作業だ。日常の通常運転の精神なら、とてもじゃないが聞いていられない。聞き手としても、ギヤチェンジが必要なのではなかろうか。宗教とはそういうものなのだ。
また「これが神の言葉じゃ!」と上段一撃のごとく語る人間の言葉など、われわれからすれば、あまり聞きたくないのである。聞く気持ちがなければ騒音でしかない。「聖書にはこう書いてある」と言っても、「この神の言葉を何と心得る」と言っても同じことで、宗教心が希薄になってしまう日常生活の中では、「そんなこたぁ、どうでもいいじゃん。今日の務めで精いっぱいだ」と思うわけである。
いちいち神の言葉である、などと言われると、現代人としては「どうしても必要なら、家に帰って自分で聖書を読むわ」なのだ。しかし、われわれは、せいぜい聖書を紹介する程度で済ませればよいものを、時には聖書を利用した人格攻撃にまで至ってしまう。特にそういうのはリベラル人権派に多いのではないかと辟易(へきえき)しているのだが、聖書を利用して誰かを攻撃するというのは、それこそ黒魔術の世界なのだ。聞く人にとっては、大きなお世話なのだ。「聖書は自分のために読みなさい」、あるいは「教会で読まれる聖書の言葉を味わいなさい」「聖書を読んだ感想を仲間と共有しましょう」と言うだけで十分なのだ。というようなことを考えるから、筆者は伝道が下手くそだったのであるが。
お前の言うことなんか知らん
エレミヤの預言に、同世代の人たちはほとんど聞く耳を持たなかった。そりゃそうでしょうと思うわけだ。バビロニアから武力の圧力を受けて散々な目に遭っている人たちだ。彼らは何とかダビデの国を守りたいと真剣に考えているのだ。また、神がアブラハムに与えた契約を思い起こしながら、あるいはモーセの出来事も含めて、神の特別な計らいというものを信じているのだ。
であるにもかかわらず、エレミヤが口にしていることは「今や神の思いはユダ王国にはない。神の刃はバビロニアではなくて、ユダ王国に向いている。それはユダが神を軽んじ、神に背いたからだ」というものなのだ。つまり、一生懸命なユダの人々に対して、「無駄なことだ」「むしろ滅亡こそが神の意志だ」とエレミヤは預言者として語っているわけである。
そんなことを言われれば、「誰がそんな言葉を聞くか!!!」となる。「お前こそ神の契約を軽んじて、神を卑しめている」と、エレミヤを非難するのも当然のことなのだ。エレミヤの預言というのは、元から人々に歓迎されなかったし、特に王家やその取り巻きに聞いてもらえる代物ではないし、むしろ、語れば語るほど、エレミヤの身は反感と迫害にさらされるだけなのだ。
まあ、反感を買ったということは、ある程度は聞いてもらったということではある。エレミヤの預言というのは、きちんと聞いてもらえなかったかもしれないが、心に骨が刺さるようなものであったのは確かなのであろう。
あ〜、神意は実に難しい
「着てはもらえぬセーターを、寒さこらえて編んでます」という歌があったが、エレミヤの場合は切なさを超えた悲劇である。聞いてもらえないと分かっている神の言葉を語らねばならないのだ。こういうことは、歴史の中ではいろいろありそうだが、実はエレミヤの中に湧き起こる神の言葉は、彼自身をも相当に打ちのめしている。
今や神は自分たちを滅亡させるが故に「神はまさに神である」というのは、諸宗教ではありがちなことなのかもしれないが、少なくともモーセ以降の人々は、そういう神を知らないし、受け付けない。しかも諸宗教では世の終わりを神が実行するというコンセプトはあるにせよ、エレミヤが語る神は「敵に栄光を与え、自分たちを滅ぼす」神なのだ。どうせ滅ぼすなら敵も、と思うのが心情だ。
確かにユダヤは神を軽んじ、神に背いたのであるが、実のところそんなことは世界中で毎日行われているお決まりの行事である。なのに、なぜ今になってその罪が問題なの?となる。われわれの先祖も、今と同じように罪を重ねていたではないかと。むしろ人は問うであろう。「この世界で誰が神に忠実に従い得るのか」と。あるいはユダの人々は言うであろう。「神に望みを置いているわれわれになぜ滅びを? 神が守ってくれると信じているわれわれがなぜ?」と。
そう、都合良く神に望みを置き、都合良く神の守りを信じていたということだろう。それはそれで、現代の信仰者とあまり変わりはない。都合良く、あるいは自己都合で信仰を生きる。これが人間の姿である。肯定も否定もしないが、それで仕方ないとも思わないのだ。
神の希望に生きること、それに勝る忠実がどこにあるのであろうか。われわれの神なら、必ず困難を打ち破り、われわれを守り、われわれにダビデの繁栄を取り戻してくれるだろうと、どうして期待してはならないのか。筆者がそこにいれば、必ずそのように考えるのだ。神に望みを置く神への信心の故に、期待もし、耐えもする。踏みとどまるのだ。信心がなければとっくに逃げ去るではないかと。
そう、エレミヤの苦悩と悲劇はそこにあるのだ。本当に信仰があるなら、敵と戦わず今は逃げろと告げる、それがエレミヤに告げた神の真意であったのだろう。しかし、そういう難しいことは、半端な信仰がある故に人は受け入れないのだ。
「耐え抜く、信じ抜く、この身は果てても踏ん張るのだ!」 ああ、美しい精神だ。かくありたいと思う。信仰死守、教会死守。筆者も現役の牧師をしていたときは、いつもこだわっていた事柄だ。「諦めてはならない、逃げてはならない、耐えねばならない」。結果はどうであれ、自分を鼓舞するものは信仰死守、教会死守であったのは事実だ。
でも、神としてはどうも違うらしい。神はわれわれの思いを超えている。時には逃げるのが正解ということもあるのだ。(続く)
◇