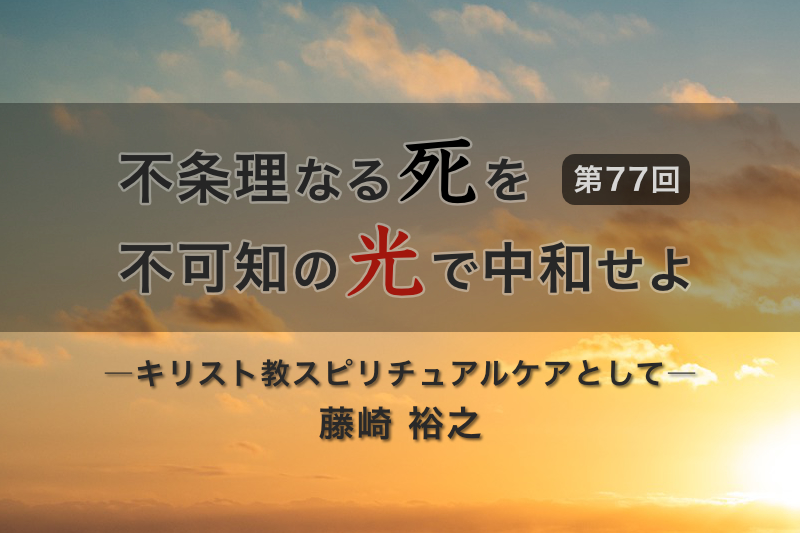
不条理なる死を不可知の光で中和せよ―キリスト教スピリチュアルケアとして―(77)
※ 前回「罪とは都合の良い言葉である(その1)」から続く。
たとえ、ご一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。(マルコ14:31)
聖書が語るペトロの姿は多様である。と言えば驚くであろうか。ほとんどの人が思い浮かべるのは、ガリラヤ湖で漁師をしているペトロの姿ではないだろうか。イエスがペトロを弟子としたのは、ガリラヤ湖畔での出来事だ。そしてその次が、大祭司の家でイエスのことを知らないと言った事件ではないだろうか。
実際には、ペトロにはあと2つ印象的な姿がある。1つは使徒として書簡を残している点である。2つの書簡が残されているが、聖書の研究家にとって、この2つの書簡は「ガリラヤ湖で漁師をしていた者」が書いたとは思えないほどに神学的な深みがあるという。漁師と書簡の作者は一致しないと言われるなら、私には何とも受け入れ難い思いがあるが、まあ、そのように感じる人もいるということである。
私にとってペトロという人物が最も印象深く、ある意味でペトロらしさが伝わってくるのが、ヨハネによる福音書21章の場面である。いつ読んでも20章とのつながりが悪く、どうにも考え込んでしまうのであるが、本来は20章で終わっていたと解説する人もいる。あるいは、少し期間をおいて、ヨハネが21章を付け加えたのだという穏健な解釈もある。今回は、その21章を掘り下げてみたいと思う。
復活のイエスとペトロとの最初の再会の場所は、エルサレムであった。そして、二度目は21章に書かれているように、ガリラヤ(ヨハネはあえてティベリアスという名称を使っている)湖である。ティベリアスという名前はローマ皇帝に由来している。ちなみにルカは、ゲネサレト湖と書いている。これは、たて琴という意味である。確かにガリラヤ湖はたて琴の形をしている。つまり、これらの福音書から分かることは、ガリラヤ湖には3つの名前があったということだ。もしかしたら、当時はガリラヤ湖という呼び名そのものが、ポピュラーなものではなかったのかもしれない。
そのガリラヤ湖でペトロは復活のイエスと二度目の再会をするのであるが、そこでは全く漁師とは無縁であった者が思い付きで魚を捕りにいったかのような印象もある。あるいは、元漁師がしばしの中断を経て漁に出かけていくというイメージだろうか。
話を元に戻すが、ペトロがペトロである最も適切な表現は「人間をとる漁師」である。つまり、人々をイエスの元へ導く者である。それはもちろん、マタイ、マルコ、ルカの各福音書に書かれているからご存じであろう。かつてイエスはペトロに「人間をとる漁師にしよう」と約束された。その言葉をペトロはどのように理解していたのであろうか。
とにかくペトロはガリラヤに戻った(なぜ戻ったのか不思議ではあるが・・・)。ペトロと同行した者には、トマス、ナタナエル、ゼベタイの子たち、つまりヤコブとヨハネ、他に2人がいた。彼らは舟に乗り込んで湖に出ていった。
かつて漁師であったが、数年を経てガリラヤに戻ってきたのである。そして、もともとの職業に戻って人生を立て直そうとしたのか。しかし、すっかり勘が鈍って夜通しの漁にもかかわらず、何も捕れなかった。あるいは、全く漁師の経験がない人間が何かの思い付きで漁をしてみたが、やはり未経験であるが故に全く捕れなかった。どちらにしても、ヨハネによる福音書が伝えているのは、彼らが「収穫ゼロ」だったということである。
賢明な読者は、舟が教会を象徴する言葉であることに気付くだろう。ガリラヤ湖は地図で見ると小さいが、実際には向こう岸が見えないほどの大きさである。油断をして岸から離れてしまったら遭難もあり得る。ガリラヤ湖は特に突風が吹き荒れることで有名だ。マルコによる福音書4章35節以下を読んでいただきたい。そこには、夜にこの湖にこぎ出すことがいかに危険であるかが書かれている。
しかし、ヨハネがガリラヤ湖をわざわざティベリアス湖と表現したことによって、読者の視点はユダヤからもっと大きな世界に導かれているのだ。そこは皇帝の名前を冠した場所である。つまり、そこは単に地理的な意味の湖ではない。皇帝の名が響き渡る世界を暗示しているのだ。そこへ弟子たちが乗り込んだ舟がこぎ出していく。ペトロの教会は、そのようにユダヤの外の世界へ向かい始めたのである。明らかに、ヨハネの記述にはそのような意図があるように読める。そうでなければ、20章と21章がつながらないのだ。
21章では失意の弟子たちがガリラヤに帰って、やることもないので元の漁師に戻ったと読めば、そのようにも読める。魚を捕るプロフェッショナルがもはや、かつての力量を失ってどうしようもなく湖のただ中に漂っている。確かにそういう光景も目に浮かぶ。そのような無力な弟子たちが、復活のイエスと二度目の再会をしたのである。と言えば少々感動的な場面となる。それはそれで良い。
しかし、ガリラヤ湖をティベリアス湖として眺めてみると、ペトロを頭とした初代(まさに初代である)教会の奮闘というか、全くうまくいかない空回りの状況が頭に浮かんでくる。エルサレムでは少々うまくいってそれなりの人が集まったかもしれないが、皇帝の世界に出ていくと、途端に空振りだらけというわけである。
初代教会がいかなる道筋をたどっていったのか、実はあまり詳しくは知られていない。エウセビオスという主教が書いたキリスト教会の歴史書には、多少のエピソードが語れているが、何せおよそ300年後に書かれたものだ。その史実性は確かではない。使徒言行録によれば、初代教会はその出発から相当な人々を獲得したかのように見える。しかし、実際はどうであろうか。私はヨハネによる福音書21章には、ペトロとその仲間たちがたどった「収穫ゼロ」時代のことが暗示されているように思えてならないのだ。
そういう厳しい現実と経験を重ねたペトロという人物が、もう一度復活のイエスに会うのである。そういう人物が書簡を書いて、今や使徒の書として全世界で読まれていると考えてみてはどうだろうか。随分と味わい深いものとなるのではないだろうか。(続く)
◇