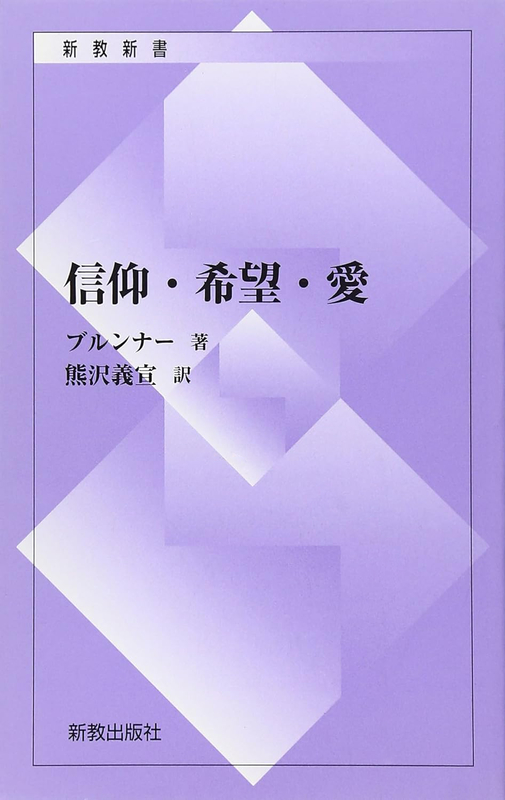
本書『信仰・希望・愛』は、スイス出身の神学者エミール・ブルンナー(1889~1966)の著作です。私は現在、コラム「ヨハネ書簡集を読む」を連載しており、これまでに第2ヨハネ書と第1ヨハネ書の3章まで執筆しました。次回からは第1ヨハネ書の4~5章をお伝えしますが、どうもこの部分は、パウロが第1コリント書13章や第1テサロニケ書1章で展開している「信仰・希望・愛」について、ヨハネ共同体の視点で書かれているように思えました。
しかし、聖書の中でもよく知られているこのテーマについて、ストレートに書いている著作はそう多くありません。ブルンナーの著作を読んだことがあまりなかったこともあり、タイトルがずばりそのままの本書を手に取りました。
実際に読んでみると、私の思いに合致して、ブルンナーは本書全体にわたって、パウロ書簡よりもヨハネ福音書と第1ヨハネ書から多く引用していました。「ヨハネ書簡集を読む」では次回以降、本書で引用されている「信仰・希望・愛」に関するさまざまな聖句についても触れたいと思っています。
ブルンナーはカール・バルト(1886~1968)と同時代の人であり、出身も同じスイスであることから、バルトと並べて語られることが多いと思います。しかし、知名度ではやはりバルトの方が勝っているでしょう。邦訳書も圧倒的にバルトのものの方が多いように思います。
本書は、ブルンナーが戦後しばらくの間日本に滞在し、国際基督教大学(ICU)で教鞭を執っていた1955年に、米国を短期訪問した際に行った講演が基になっているようです。この時代にICUで学んでいた人が、私が神学校で学んでいたときに在学しておられ(年輩になってから入学された人でした)、「ブルンナー先生」と呼びながら、当時のことをよく話していたことを思い出します。
本書は、「序章」「信仰」「希望」「愛」で構成されています。その序章において、「新約聖書の解答は、はっきりと次のような三つの言葉で与えられています。わたしたちは信仰によって過去に生き、希望によって将来に生き、愛によって現在に生きているのです」と書かれているように、「信仰・希望・愛」と「過去・未来・現在」をそれぞれつなげていることが、本書の特徴といえるでしょう。
これはまた、パウロの「このキリストのお陰で、今の恵みに(現在)信仰によって導き入れられ(過去)、神の栄光にあずかる希望(未来)を誇りにしています」(ローマ書5章2節)という言葉も思い起こさせます。
「信仰」の章では、私たちの信仰は歴史的に実存したイエス・キリストに起因しており、それは第1ヨハネ書1章1節の「わたしたちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手でさわったもの」という言葉において強調されているとしています。そして、そのことは「特にキリストの十字架を指し示しています」と言い、十字架という過去の一回限りの出来事が、私たちの信仰のただ一つの根拠であるとしています。
「希望」の章では、「キリスト教以前の人々は決して将来を希望を持って、つまり人生の真の意味が実現されるという期待を持って、待ち望むということをしませんでした」「キリスト教信仰についてまずいわれなくてはならないことは、最初の講義(「信仰」の章)で指摘されたように、それが過去の事実にもとづくということです」と述べ、この地にキリストが一度来られたという事実が希望につながるとしています。
さらに、「キリスト教的な希望は、合一(union)ではなくて、交わり(communion)を望みます」「神と人とが顔と顔を会わせる――交わりこそが、聖書が永遠の生命についてわたしたちに与えている姿なのです」と述べ、「わたしたちは信仰によって、神がキリストにおいてすでになしとげたもうた事柄(十字架の出来事)においてそれを知るのです。(中略)その事実を信ずる者にとっては、それは希望のよきおとずれなのです」としてこの章を結んでいます。
私たちは、キリストの十字架によって神と交わることができるようになり、それによって永遠への希望を抱くことができるとするのが本章の要点であろうと思います。
「愛」の章では、「愛は、神がわたしたちの現在を変革する方法」だとし、「わたしたちを過去と将来の束縛から解放することによって、キリストはわたしたちに神の愛と、神の赦(ゆる)し、彼のアガペーを与えてくれました」と述べています。そして、過去からの解放とは十字架による罪責からの解放であり、将来からの解放とは「思いわずらう必要はない」と語るキリストの言葉によるとしています。
神の愛(アガペー)について、ブルンナーは、スウェーデン出身の神学者アンダース・二ーグレンの『アガペーとエロース』に多くを負っていると述べています。この本は私も読みましたが、「アガペーとは『愛される者の質の故に愛する愛』ではなく、『にもかかわらず愛する愛』であり、『自分を満たすのではなく、相手を満たすもの』である」ということが主論とされており、ブルンナーもそれを強調しています。
本書は、熊沢義宣氏(1929~2022)が翻訳しています。熊沢氏は、東京神学大学で長く教鞭を執られた神学者です。私が前回のコラムにおいて、「『良い人間になりたい』と思って洗礼を受けたにもかかわらず、全くそのようにはなれなかったからです。そんな折、教会の修養会で講師のある先生のお話を聞いて、大変納得したことを覚えています」と書いた「ある先生」とは、実は熊沢氏です。
本書には、熊沢氏によるものと思われる注が至るところに記されており、分かりやすく、それもとても良かったです。また、私がかつて聞いた熊沢氏の講演は、ブルンナーの影響をかなり受けたのものではなかったかということも、本書を読んで感じました。
この場で書き足りなかった部分については、次回以降のコラムで、聖書のテキストと関連付けながら引用し、展開していくことができればと考えています。
■ エミール・ブルンナー著、熊沢義宣訳『信仰・希望・愛』(新教新書 / 新教出版社、1957年9月第1版、2000年7月復刊)
◇