映画のプロパガンダ性への警戒と現代の多文化共生を考える
――「百人が百様に解釈する」「見た人に委ねる」映画ということにこだわるのなぜなのでしょう。
僕は映画や芸術表現はどうしてもプロパガンダの問題を考えなければならないと思うんです。特に映画は、戦中にプロパガンダとして散々利用されてきた歴史があります。それは、複製芸術である映画は人の心を巻き込む強いパワーがあるからです。だから日本でもアメリカでもナチスでも使われてきた。その時代を経て映画を作る以上、表現の持つプロパガンダ性を作り手は考えなければいけないと思う。
何もナチス・ドイツや戦中だけでなく、現代でも例えば「家族」を描くとき、それはポリティカルなことでもあるわけです。政治が諸手を挙げて推進する伝統的な家族観が存在する。今日本で家族を描くときに、それに対してどの立ち位置から描くか、それを政治性を考えずに作るのはものすごく危険なことだと思う。
それは、1つのあるべき家族のイメージを拡散することになるし、家族を作れない人を排除してしまっている可能性もあるわけです。
プロパガンダが最大の力を発揮するのは、強烈に人の気持ちを巻き込んで「感情のプロパガンダ」になるときです。見ている人を主人公に同化させ、一緒に泣き笑いさせて、ハードルを乗り越えたらうれしいし、だめならその悲劇に涙を流す、その感情の同化をうまくやればやるほど、プロパガンダは力を持つわけで、実は危険であるとも言えるわけです。
いかに理解し得ない他者と共に生きるか
現代に生きることの本質は、特に多文化共生の現代において“いかに理解し得ない他者と折り合いをつけて生きていくか”ということなのだと思います。デリダの「歓待」の思想に近づいていくと思うんですけど。共感できることを前提とすると、共感できないものを排除してしまうことになってしまう。いかに共感できない他者と向き合うか、が大事なのだと思います。芸術や文化表現の1つの持ち得る役割としては「共感を求めない1つの価値観として社会にあり続ける」ことの方が重要なのではないかと考えていくと、ああいう作品になったんだと思います。
もちろん作品としては、章江に共感できるとか、細かい共感を呼びながら進んでいくことは大事で、だからなるべく3人称で描くようにして、見る人によって共感できる人が変わるように作っている。細かい共感を誘いながら、最終的にはこの映画は何なんだろうと、映画自体が理解できない他者としてある作品の方が、自分が作る作品としてはいいなと思っています。
もちろん、映画表現は多様であっていいと思います。スカッと笑えて、スカッと泣いて終われる映画もあっていいと思う。でも、あんまりみんなが気持ちよくなるのを促す映画は、警戒した方がいいと思います。
多文化共生の教育、装置としての映画
――今の日本の、特に映画界で、そこに共感されずに立ち続けるというのは大変なのではないですか?
ヨーロッパだったら、もっと自分は楽だったかもと思います。そういう表現というのは、ある意味で大ヒットは初めから求めていないわけです。カタルシスより見え方の幅を重視しているので、娯楽性が減るのは仕方がない。だってゴダールがスピルバーグと同じぐらいヒットしたら逆に気持ち悪いじゃないですか(笑)。
ヨーロッパでは、全ての映画がリュック・ベッソンみたいにヒットするのが大事なわけではなくて、3万人が見る映画も300万人が見る映画も共存できるのが大事であり、それが文化の多様性なんだというところで、文化の助成制度やビジネスの仕組みが設計されています。でも、日本の場合はより市場原理主義的で、どれだけの経済価値を生むかというところで映画も芸術文化も価値が図られる世界なので、当然生き残りにくいです。
例えば、フランスでは小学校が月1回映画を見る授業があるんです。小学生が「小津安二郎」の映画を見ているんです。
――小学生が小津を見るんですか!?
小津の「お早よう」という、子どもが主人公の映画があるんですよ。圧倒的に多様性に対する広がりがありますよね。クラシカルかつ日本の一家族を描いた映画を見ることで、他の文化への理解の土俵が広がることは容易に想像できるわけです。そういう意味での多様性への広がりは、日本はまだ不足してるんじゃないかと感じます。
それは多くの国で取り組まれています。韓国も基本的にはフランスの制度をモデルにして制度を作っていますが、映画の評価に関して「多様性映画」の規定を設けて、異国の文化を描いているか、などの項目をクリアしたら助成金が出るようになっています。
――一律の規定を作るとまた問題もあるのかもしれませんけど、文化の多様性への取り組みの真摯(しんし)さはありますよね。
日本では少し前に、橋本徹さんが文楽に対して劇団四季みたいにやったらどうかという発言をしていて、それが日本の文化への考え方の1つの象徴なんだなと思いました。一時代の経済的価値では計り切れないのが文化芸術なわけですし、それだけで求めていたら、当然マイノリティーの価値を描いた作品は生き残れなくなってしまいます。それは、ヨーロッパではある意味スタンダードな捉え方になりつつあると思います。日本の場合はまだまだなのかもしれませんね。
「家族」を描くこと
――外国メディアの取材で「家族を描いた最近の日本の映画はスイートなものが多いが、この映画はビターなのが良い」と言われたそうですが、そう感じられますか?
具体名は挙げませんけど、そう思います。そういう映画では、家族の絆が良いものという前提があり、時にはそれが壊れたことの悲しみが描かれている。でも僕は、家族が壊れたことを悲劇として描くこと自体が古いというか、どこかで甘いと思ってしまう。それは結局、伝統的な家族観に対する作り手の立ち位置の問題です。それを基本的に善きものとして受け入れている限り、悲劇としても甘いものになってしまうと思う。
――とても分かるんですが、なぜそこまで厳しくなれるんですか? フランスのル・モンド紙に「怒れる日本の映画作家」と書かれたそうですけど。ル・モンドにそう書かれるのはすごいかっこいいなと思ったんですが(笑)。
そう(笑)。これからは大島渚みたいに「ばか野郎!」みたいなキャラを作らないといけないのかと思いましたけど(笑)。
ル・モンドには「日本の価値観へのカウンターだ」として書かれたんだと思います。それは、自分の生い立ちによって醸成されたものだと思う。私自身の過去を言うと、前半の夫婦の風景は、ほぼ両親がモデルなんです。物心がついた頃から、両親の会話を一度も聞いたことがないんです。家庭内の事務連絡ぐらいはあるけど。だから、あの家族像を特殊な夫婦として描いているつもりはなくて、夫婦はそれぐらいがスタンダードだと思って描いてるんです。
それを言うと周りから「不気味だ、不気味だ」と言われるんですが(笑)。それはそれで、理解できない他者に映画がなっているということでいいと思うんですけど。今思うと自分が育ったのは変わった家だったと思いますが、でもそれがつらかったと思ったことはないんです。一方で、テレビや映画では、いろいろあっても結局は家族の絆を謳(うた)い上げるフィクションが圧倒的に多いことへの違和感は強くありましたね。
――そこはすごく分かります。私がクリスチャンになる前に牧師さんと話していたとき、「理想の家族なんて本当にあるんでしょうか? だって聖書に最初に出てくるのは兄弟殺し、親と息子の対立、嫁と姑、そんな話ばっかじゃないですか。幸せな家族なんてCMにしかいないんじゃないでしょうか」と言われたことがあって(笑)。キリスト教は、そんな本を2千年読み続けているんですよね。
その気付きは重要ですよね。家族の物語に関して、いまだに最も現代的な日本映画として海外で評価されているのは小津安二郎ですよね。「東京物語」はものすごくビターな物語です。老夫婦が東京に出て来て、実の息子たちにものすごく冷たくされて、一番優しくしてくれたのは息子の嫁という他人だったというのが描かれている。
考えてみると、その当時は「お妾さん」とか「本家と分家の格差」とか、家族制度のいびつさにみんなどこかで耐えて、必要悪として受け入れながらも、経済的にも社会的にも結びつかないと生きていけなかったわけです。
伝統的な家族観、家庭の中の役割に男女を押し込んでいくことを、“善きもの”として推進していくのは、近代の教育ではないかと思うんです。特に最近の自民党が、夫婦別姓だと家族の形が壊れると言っているのも、その流れだと思います。そういう教育は、どこかに常にあるのだと思います。家族とは大変だということは、どの時代の人も思ってたんじゃないですかね。カインさんとアベルさんにしても。日本の神話も家族の中の確執ばっかりですし(笑)。だからこそ「三本の矢」みたいな理想論的な教育が必要だったのだと思う。でも、その上積みのような理想論だけが家族のスタンダードな形として普及してしまったのかもしれませんね。そして、近代以降の情報社会でメディアがそうした家族像を強化させ、浸透させたのかもしれないなと思いますね。
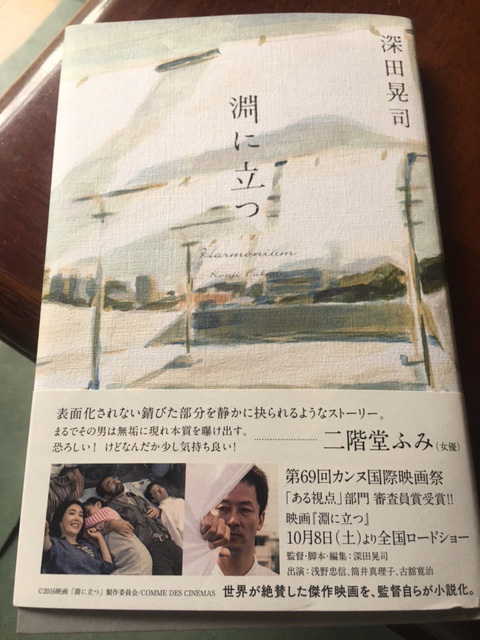
――小説の方が、ずっと寒々しい家族だなあと感じました。
小説のほうが登場人物の外見的な個性がオミットされるので、核にあるものが際立ってくるんだと思います。たぶん小説の方が自分の寒々しい家族観とかがよりダイレクトに出ているのではないかと思います(笑)。
――10年前、「暴力」をテーマとして描きたいと思ったのは、何かきっかけがあるのでしょうか。
直接的には覚えてませんけど、自分が10代の時に起きたオウム真理教事件、阪神大震災、あるいは神戸の14歳の少年の殺傷事件などがしょっちゅう報道されているのに触れていて、常に私たちは得体の知れない暴力にさらされているのだ、というのが実感として感じて、その延長線上に八坂という人物が出てきたのだと思います。
――2016年アカデミー賞を受賞した「スポットライト」という映画が公開されました。日本の聖職者や牧師による性的な虐待事件があるか取材をしていたんですね。そういう中で実際に伺ったお話に、どうしても物語や八坂という人物を重ね合わせてしまったんです。加害者は、普段はとても誠実で優しくて魅力的な人物なんです。でも気付くと、圧倒的な暴力性を周りにふるって人を傷つける。そして事件が発覚すると、人前で泣いて謝る。だから周りは「赦(ゆる)す」。でもまた同じ事件を繰り返す。もちろん私は、加害者本人に会ったことはないんですが、そこで聞いた話から思い浮かべる姿が、浅野忠信さん演じる八坂にどうしてもかぶってしょうがないんですよね。
そうなんですか。それはシンクロですね・・・。そういう人いるんですね・・・。韓国の「シークレット・サンシャイン」という映画も構造が似ていますよね。あれはまさにキリスト教の話ですよね。密陽という街の話なんですが、そこに来た親子の子どもがいなくなって、母親がそれを捜しながらの葛藤が描かれるんですが、まさに「赦す」「赦せない」という主題が描かれていました。
私は、八坂は単純に性欲が人を変えるということで、あまりそこに観念的な意味や哲学を込めたわけではないんです。
――最後にお伺いしたいのですが、西欧の映画を見ていると、その背後にほぼ必ず「キリスト教的モチーフ」を感じます。そのような歴史や文化がない日本で映画を撮ることは、メリットあるいはデメリットを感じられることはありますか?
それはないです。表現で、世界で評価されるということは、いかに自分の根っこまで降りていって、それを作品に刻み込むか、視点があるかどうかということなのだと思います。別に英語ができれば世界に通用するというわけではないのと同じことです。自分が立っている場所、そこからしか見ることができない世界をいかに刻み込むか。
歴史家のE・H・カーは、歴史家が歴史を書くとき、それは自身の主観で編さんされた歴史でもあると書いています。主体から逃げることはできない。それは芸術も同じです。客観的に映画を作ることなどできません。作り手自身の立ち位置を自覚した方がいい。それをないふりをして描くと、軸のない作品になってしまう。自分は日本に生まれた人間として、あえてオリエンタリズム的に評価されるような作品を作りたくはありませんが、自分の根っこを自覚することが、逆に普遍的なものにつながる。世界に届くには、それが一番の近道ではないでしょうか。
――ありがとうございました。次回作はもう決まっていらっしゃるんですか?
同時並行に幾つか進めていますが、まずは来年夏にオールインドネシアロケする作品が決まっています。
――とても楽しみにしています。今日はありがとうございました。