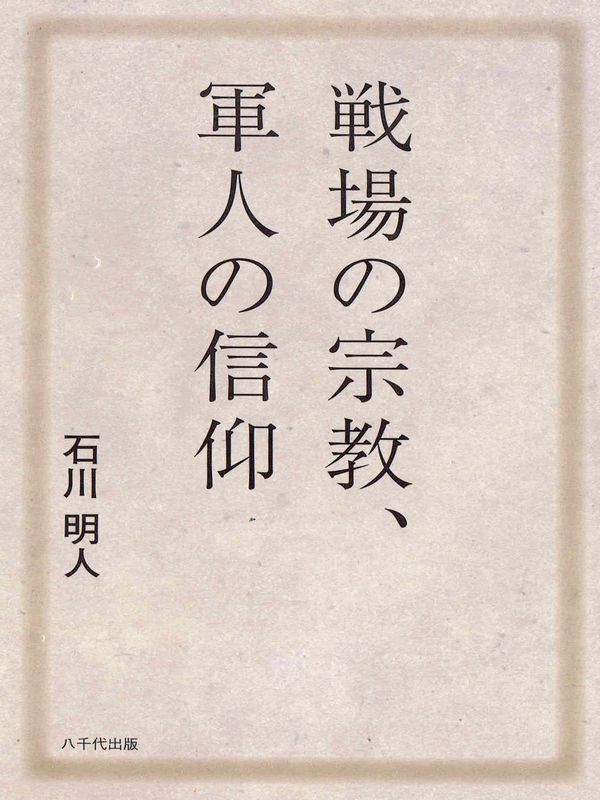
著者の石川明人氏(桃山学院大学准教授)にお会いしたとき、戦争と宗教に興味を持ったきっかけをこう語っていた。「宗教にしろ、哲学にしろ、極限状況でこそ立ち現れてくるものがある。それが戦争だと思うんです」
本書では、米軍の従軍チャプレン、旧日本軍と自衛隊の中のキリスト教、クリスチャンの特攻隊員など5つのテーマが扱われている。そこでは、抽象論ではなく、現実の軍隊の制度、その中の軍人たちの心情・信仰が、豊富な資料に沿って紹介されている。
石川氏は、本書の結びで、自身は従軍チャプレンや軍人の信仰の真偽を問うているわけではなく、宗教と戦争協力を批判的に振り返ることは重要であると述べている。しかし同時に、戦争や軍事に関する一切をとにかく否定しさえすれば、「平和主義者」でいられるわけではない。むしろ、宗教と戦争について議論する手前の段階として、ある歴史的事実や思想、軍人のたたずまいをありのままに見つめ、素朴に反省した先にこそ、「平和」についての正当な考察があるのではないか、と本書を執筆した経緯を書いている。
その問題意識は、キリスト教の研究書の中でもきわめてユニークで、貴重といえるだろう。
軍隊の中の聖職者=従軍チャプレン
第1章で扱われているのは、軍隊専属の聖職者で、映画『地獄の黙示録』(1979年)や『プライベート・ライアン』(1998年)にも登場する従軍チャプレンだ。世界の多くの国にこの制度があり、プロテスタントの牧師やカトリックの司祭のほか、さまざまな宗教の聖職者が関わっており、米軍では、「チャプレン科」は「歩兵科」の次に作られた2番目に古い歴史を持つという。
米陸軍のホームページには、従軍チャプレンについて写真入りで紹介されており、人種もさまざまで、女性も半分近くいる。
米国では建国当初から、聖職者が兵士の戦闘に付き添っており、1945年には陸軍のみでも8141人のチャプレンが従軍し、478人が死亡した。湾岸戦争ではアジア南西部に560人が派遣され、2004年にはムスリムのチャプレンも17人が配属されているという。
また、広島に原爆を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」が基地を離陸する直前には、従軍チャプレンのウィリアム・ダウニー牧師が乗組員のために礼拝を行い、「彼らが命じられた飛行任務を行うとき、彼らをお守りくださるように」と祈ったというエピソードも紹介されている。
従軍チャプレンの存在が、米憲法の政教分離の規定に反するのではないかという批判は根強いが、「軍は特定の宗教を推奨するのではなく、あくまで兵士たちのニーズに応えるための環境を作るだけ」という建前によって維持されている。
果たして従軍チャプレンの存在をどう考えればよいのだろうか、と石川氏は問い掛ける。
戦場で殺人を行う軍隊に聖職者がいることは、破壊や殺人の黙認や宗教的な正当化と紙一重であり、倫理的な問いが生じるのは当然といえる。しかし一方で、仲間が銃で撃たれ、爆弾に手足を吹き飛ばされ、心身共に過酷な生活を強いられる戦場で、兵士たちは「神」について考えずにはいられないだろう。
太平洋戦争で日本軍には従軍宗教者制度は存在せず、兵士は肉体的に追い詰められ、精神的な援助は全く行われず、組織に見捨てられ死んでいった。軍隊組織として、どちらが人間性をより尊重しているといえるのだろうか。
石川氏は、この章をこう締めくくっている。
「そもそも戦争をするかどうかを決めるのは軍人ではなく政治家、そして国民全体である。軍から聖職者を追い出せば戦争がなくなるわけでもない」
「兵士たちの祈りも、兵士たちの信仰も、立場が違えばそれに納得や共感はできないにしても、決してそれ自体として虚偽なのではない。平和を望みながら戦争をしてしまうというところに、戦争の悲惨さの根源がある。そうしたことを念頭に、あらためて『平和』について考えていくべきであろう」
陸海軍軍人伝道義会とコルネリオ会
第2章では、旧日本軍と自衛隊の中のキリスト教伝道の歴史が紹介されている。
「旧日本軍にはチャプレン制度こそなかったものの、さまざまな形でキリスト教伝道がなされていた。そしてそれらは、必ずしも一方的に日本の戦争を支持したり、あるいはそれに反対したりという性格のものではない。(中略)ただ素朴に、軍隊という特殊な社会のなかで働く者たちに信仰を伝えようとするものなのであった」
1899年に、米国人女性宣教師エステラ・フィンチと黒田惟信(これのぶ)牧師によって、陸海軍軍人伝道義会が設立された。また日清戦争が始まると、当時日本のキリスト教界で指導的立場にあった本多庸一牧師は、『軍人必読義勇論』というパンフレットを配布して、キリスト教の立場から軍人の心構えを説き、慰問などを積極的に行っていたという。
さらに現在の自衛隊には、「コルネリオ会」(使徒言行録10章に登場する百人隊長コルネリウスから)というキリスト教サークルがあり、2011年の時点で、現職・OBなど約320人の会員がおり、英国や韓国など諸外国の軍隊のOCU(Officers Christian Union)とも交流を持っているという。
コルネリオ会のニュースレターには、「兎角(とかく)反自衛隊的な空気の多い教会に於(お)いてキリスト者自衛官のあかしを立てつつ苦闘しておられる兄弟もあるかと思いますが」「一部の教会では自衛隊さんは歓迎しないという雰囲気があることは否定できない」などと書かれていることも多いという。
かつてはこの傾向が強く、1971年に同会会員の陸上自衛隊幹部が、日本基督教団の月刊誌『こころの友』に「ある三等陸佐の願い」というエッセーを投稿したときには、同教団の岩本二郎牧師が、教団の機関紙である『教団新報』に「人殺しや侵略を正業とする自衛隊員は、実存的、社会的悪のただ中にある。(中略)自衛隊と連帯するよりも、拒絶こそ、教団にふさわしいのである」として、『こころの友』を廃棄、または焼却した例も数多く知っていると書くなど激しい抗議活動を行い、編集部に謝罪記事を書かせる結果となったという。
石川氏は、この論争により、以後自衛官が教会関係誌などに寄稿することはタブー視されるような奇妙な雰囲気が作り出されることになった、と指摘している。
しかしその後、阪神・淡路大震災や東日本大震災における自衛隊の災害救援活動によって、自衛隊に対する一般国民の視線は大きく変わった。
石川氏は、これまで日本のキリスト教界は、自衛官も一人の人間として信仰上の指導や支えを求めていることについて、十分に目を向けてきたとは言い難い、とこの章を締めくくっている。
神風特攻隊員だったクリスチャン林市造の手記から
この他、3章では1945年に神風特攻隊員として戦死した林市造(1922~1945)の日記や手紙についても紹介している。
お母さん、でも私のようなものが特攻隊員となれたことを喜んでくださいね。死んでも立派な戦死だし、キリスト教によれる私たちですからね。
でも、お母さん、やはり悲しいですね。悲しいときは泣いてください。私も悲しいから一緒に泣きましょう。そして思う存分に泣いたら喜びましょう。
私は賛美歌をうたいながら敵艦につっこみます。(林市造が母に宛てた手紙より)
本書の中で、石川氏は繰り返しこのように書いている。
「軍人と自衛官たちほど『戦争』をリアルに感じながら『平和』を祈る人たちもいないのではないだろうか」
冒頭に紹介したように、著者は、軍人の信仰、戦場の宗教の真偽を問うているわけではない。ただ現実として存在する事象を取り上げ、問いを投げ掛けている。日本のキリスト教界で、戦争反対や平和主義の声は大きい。私はそこに同じキリスト者として誇りを感じる。しかし、同時に私たちは軍隊組織の実態や戦争の現実、軍人・自衛官の心情の現実についてどれほどのことを知っているのだろうか。目を背けてきたものがあるのではないだろうか。「戦争反対」「平和」を唱えるならば、まず現実を知らなければ、説得力と現実的な議論を提起することはできないのではないだろうか。
その意味でも戦後70年の今年、本書は他に類がないきわめてユニークかつ重要な著作であり、もっと広く読まれる価値を持っているといえるだろう。
■ 戦争とキリスト教を読む:(1)(2)