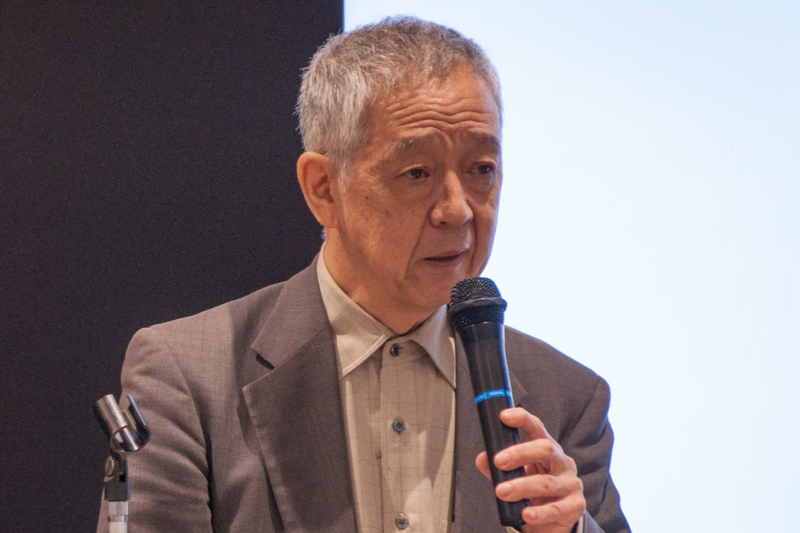
阪神宗教者の会(代表世話人・岩村義雄牧師)が主催するオンラインの集会で、宗教学者の島薗進氏(東京大学名誉教授)が講演し、「限界意識とケアのスピリチュアリティー」をテーマに語った。
「救済宗教」には距離感、でも「救い」は身近
島薗氏は初め、宗教のうち「救い」の概念が中核にあるものを「救済宗教」と呼ぶと説明した。世界三大宗教とされるキリスト教、仏教、イスラム教もこれに当たるが、現代社会では距離感を持つ人々が多い。その一方で、「救い」は宗教という枠組みを離れ、映画や歌などの芸術作品の中に見られ、今も身近な存在だという。
その一例として、米フォークデュオのサイモン&ガーファンクルが1970年に発表した「明日に架ける橋」を挙げた。この世界的なヒット曲は、生きることに絶望し、疲れ果てている人に語りかけるような歌詞が特徴的だ。一方、この歌詞は、59年にヒットした黒人ゴスペル曲「Mary Don't You Weep(泣くなマリア)」の影響を受けているという。そして、このゴスペル曲は、ラザロの死を嘆くマリアをイエスがいたわる場面(新約聖書・ヨハネによる福音書11章)が基になっている。
「明日に架ける橋」自体は、宗教的な「救い」を歌った曲ではない。しかし、その根源にはキリスト教という伝統的な救済宗教の思想がある。そして、それは形が変わっても現代人に何らかの「救い」を提供している。島薗氏は、夫がうつ病となり自身も苦しい状況にあった知人の女性が、この曲に救われたと話していたエピソードを紹介した。
新宗教の始まりに「限界経験」あり
伝統宗教に加え、多くの新宗教も救済宗教とされる。天理教は、農家に嫁いだ中山みき(1798~1887)が、後継ぎ息子の病気という苦難に直面する中で誕生した。金光教も、金光大神(1814~83)が子どもを次々と亡くし、自らも病を患い悲嘆に暮れる中で生まれている。こうしたそれぞれの教祖が経験した苦難や悲嘆は「限界経験」と呼ばれ、そこからの「救い」の体験が新しい信仰の出発点になっている。
島薗氏は伝統宗教の特徴として、死後の救いを強調し現世を否定する傾向や、平信徒に対して聖職者が優位にあるようなエリートの優先性、また自らに唯一の真理があるとする排除性などを挙げた。これに対し、新宗教は現世利益に強調点があり、教祖が必ずしもエリートではないと説明。また、伝統宗教に比べると、真理を巡る排除性は弱まると話した。その一方で、組織への所属の有無や指導者への従順度合いといった基準による新たな排除性も生まれ、一般人からは「カルト」と見られてしまう場合もあると話した。
「ポスト救済宗教」として台頭したスピリチュアリティー
伝統宗教や新宗教を含め、救済宗教の敷居が高くなる中、「ポスト救済宗教」として1970年ごろから台頭してきたのがスピリチュアリティーだった。「spiritual but not religious=SBNR(宗教的ではないがスピリチュアル)」と自認する人々が増え、欧米では「ニューエージ」、日本では「精神世界」などという言葉でこの動きは広がっていった。
インドのヨガや瞑想(めいそう)、東洋の気や陰陽、アフリカなどの先住民の宗教に関心が高まり、それらが評価されるようになった。2014年には国連が「国際ヨガの日」を定めており、ポジティブ心理学やマインドフルネスは現在も人気が高い。特に、仏教の瞑想を基に考案されたマインドフルネスは、米グーグル社など世界的な企業が社員研修に取り入れたりしている。
これは、それまで社会の世俗化を進めてきた「宗教なしの社会こそが標準であり、それこそが公共領域の条件」とする世俗主義とは異なるものだ。島薗氏は、現代は「ポスト救済宗教」だが、それは「ポスト世俗主義」でもあると指摘。時代は宗教を否定するのではなく、新たな宗教性や精神文化を求めるようになり、それがスピリチュアリティーという言葉で捉えられるようになったと話した。
限界意識のスピリチュアリティー
一方、これらのスピリチュアリティーの多くは、人間の潜在能力を伸ばそうとするような上昇志向の「自己変容のスピリチュアリティー」といえる。しかしその陰で、自身の限界を認めることから始まる「限界意識のスピリチュアリティー」も展開されてきたという。島薗氏はその事例として、アルコール依存症の自助グループ「アルコホーリクス・アノニマス」(AA)や死生学、世界保健機構(WHO)が健康の定義に取り入れたスピリチュアルペインなどを挙げた。
AAは、アルコール依存からの回復の道を12のステップでまとめている。その最初のステップは、自身がアルコールに対して無力であり、思い通りに生きられなくなってしまったことを認めることだ。この12のステップは、他の自助グループなどでも採用されており、島薗氏は「救済宗教が持っていたものが合理化されたものだ」と話す。
12のステップを用いた自助グループでは、互いを批判することなく、それぞれが思っていることをただ話す。そして最後には、「セレニティー・プレーヤー(平安の祈り)」を祈る。これは、米神学者のラインホルド・ニーバーが作者とされる祈りで、「神よ、変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ」と、自らの限界を明確に認める内容になっている。
島薗氏はまた、1970年代に広がりを見せた水俣病患者の救済を求める運動の中に、限界意識のスピリチュアリティーの先取り的な要素があるとし、水俣病患者の家族や運動に関わった人々の言葉を紹介した。
死生学については、死と向き合う中で、「死後の救い」といった伝統宗教が提供してきた従来の答えだけでは不十分だとし、死にゆく人々への新たなアプローチを考える中で出てきたものだと説明。さらにそこから、死別を含めた悲嘆を癒やすグリーフケアが生まれてきたとし、「新たな限界意識のスピリチュアリティーと新たなケアの文化の台頭と捉えることができる」と話した。
「新たなケア」と「利他」
最後に島薗氏は、現代社会は人々がますます孤立し、能力や業績の向上が重要視され、ケアが軽視される「ケアしない社会」になってしまっているが、それを見直そうとする意識が芽生えつつあると指摘。こうした「新たなケア」を模索する動きは、スピリチュアルな要素を伴っており、それは「利他」の精神の回復ともいえると話した。
その事例として、子ども食堂の全国的な増加や、コロナの給付金を寄付に回した若者などに言及。ドイツのカトリック女子修道会が運営するエイズ患者のためのホスピス「マリア・フリーデン」や、日雇い労働者が多く住む東京・山谷(さんや)などで活動するNPO「訪問看護ステーションコスモス」などの取り組みも紹介し、限界意識のスピリチュアリティーに根ざした新たなケアの表れではないかと話した。
阪神宗教者の会は、東日本大震災後にキリスト教の牧師、仏教の住職、神道の禰宣(ねぎ)が、宗教者の視点で震災後の復興について意見交換しようと始めた。毎月第4金曜日にさまざまな分野の専門家を招いた例会を開いており、島薗氏は昨年11月の例会で講演した。島薗氏はそれ以前にも数回にわたり講演しており、22年には「震災後とコロナ後のケアと公共空間」、23年には「宗教と教育勅語」をテーマに語っている。