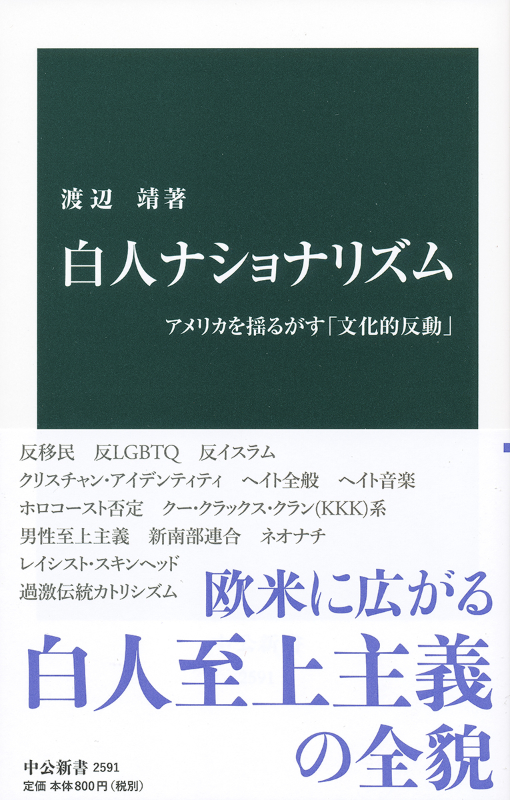
米国が揺れている。新型コロナウイルスで世界最悪の感染者と死者を出し、さらに5月25日に発生した白人警官による黒人男性の窒息死で、さらなる混乱と混迷が深まっている。そんな最中に読むべき最適の一冊が本書『白人ナショナリズム』である。
人々が「人種の融和」を訴え、「憎しみではなく愛を」と声高に叫んだとしても、残念ながら米国はこの手の事件を常に引き起こし続けている。「その根本的な要因は何か」という問いに対し、明確な回答はない。しかし本書は、この問いに対する一つの答えを提示してくれる。
まず、帯に注目してもらいたい。そこにはメディアで一度は目にしたことのある用語が並んでいる。「反移民」「反LGBTQ」「ヘイト」「ネオナチ」「KKK」など。その中に「クリスチャン・アイデンティティ」というものまで含まれているのは看過できない。どういうことか?と思い、早速購入したというわけである。
読み進めていくと分かるが、本書は、慶応義塾大学の教授でアメリカ研究が専門である著者の渡辺靖氏が、詳細に調べ上げた米国の団体や人物、そしてその背景を一気に紹介している。そのため、最初読んだ時は正直面食らってしまった。というのも、ほとんど知らない、あるいはどこかで聞いたことのある程度の団体名や人名が次々と出てくるからである。おそらく本書は、ある程度の知識を前提としないと、取り上げている具体例をしっかりと理解することは困難であろう。だが、心配することはない。各節のなかに的確にまとめを記してくれているので、その箇所だけ何回か読み返すことで、本書で登場する団体や人物は「適用例」だということが分かるからである。
一読者として本書を読み終えて、これからこの本を手にしようとする人にぜひお勧めするのは、最初に「あとがき」から読むことである。渡辺氏は本書に付加すべきことを簡潔に次の三点としてまとめている(198~199ページ)。
一点目は、白人ナショナリストを敵視すればするほど、彼らはかえって自らの大義の正しさを確信し、リベラルな社会体制、さらにはリベラルな国際秩序への不信を深めてゆくという点だ。
二点目は、米国の人種問題を見つめる日本からの眼差しだ。文化的に同質性の高い日本から多民族国家・米国の人種状況を批判することは容易(たやす)い。(中略)米国を批判するのは良いが、自らを省みない他者批判はみっともない。
三点目は、今回の新型コロナウイルスの感染拡大が米国内のトライバリズムや白人ナショナリズムに与える影響だ。(中略)自らと異なる集団を敵視し、分断と恐怖を煽(あお)る風潮がますます先鋭化する可能性も否定できない。
驚くべきことに、ちょうど本書の発刊日(5月25日)に、この3点を現実的な問題として突き付ける事件が起こってしまった。
多くの人も指摘しているように、ジョージ・フロイドさんの事件は単なる「白人警官による黒人への暴力」ということだけではない。この事件によって明らかにされたのは、格差社会の歪んだ構造、人種をめぐるさまざまな対立の歴史的背景、そしてそれを見つめる観察者たちの眼差しである。渡辺氏が挙げたこの3点は、まるで旧約聖書に登場する預言者のように、的確に未来を捉えていたといわざるを得ない。
本書は、「アメリカを揺るがす『文化的反動』」という副題が付けられているように、「文化的反動」がテーマの一冊である。しかし、白人が正しいか、黒人が正しいか、というような二分法で区分けできない複雑な事情を本書は詳細に語っている。
第1章では、「白人ナショナリスト」と称される人々の心理と彼らが抱く思想構造について実例を挙げて紹介している。それを読みながら背筋が凍る思いがした。それは、私が属する「キリスト教福音派」の、社会に対する向き合い方と非常に酷似しているからである。それを端的に言い表しているのが、先に引用した著者の1つ目の指摘である。「敵視すればするほど、彼らはかえって自らの大義の正しさを確信し、リベラルな社会体制、さらにはリベラルな国際秩序への不信を深めてゆく」という在り方は、米国に限ったことではなく、日本の福音派内にも存在する一種のルサンチマン(恨み)的な心情である。
第2章、第3章には、「白人ナショナリスト」と呼ばれる集団を生み出した歴史的経緯と現代の諸相が描かれている。日本人にとって「KKK」などという集団は、過去の遺物か映画の中の敵役でしかない。しかし彼らが現在、どのような姿勢でどんな活動をしているのかについて知ることは、翻って私たち日本人の在り方を間接的に示すことになる。そしてその姿勢の中にも、聖書を人生の指針とする生き方に共通するものを見いだしてしまった。やはり日本のキリスト教は、米国からの影響を強く受けていることを思い知らされた。
本書最大の白眉は、135ページで紹介されている「ノーラン・チャート」(米リバタリアン党創設者デヴィッド・ノーランが1971年に作成した図)と、それをもとにした著者の解説であろう。この図そのものよりも、これを用いて著者が語る現在の米国の動向(第4章、第5章)は、何度も読み返すことで新たな視点を手にすることになるであろう。従来の二大政党、保守・革新というような切り口では、もはや米国(そして米国のキリスト教も)を語ることはできない。
今回の事件について最後に述べるなら、本書を読むことで、「ヘイト心情」の克服のみでは、事件は解決に至れないことが分かる。表面的に見えているもの以上に、隠された部分に、民族的、人種的、そして歴史的な「ねじれ」が存在しているからである。それを抜きにして相手に説教を垂れようとするなら、それは単なるアジテーションと変わりない。悲しいかな、対処療法的な反応はどうしてもこの域にとどまってしまう。
例えば、米福音派誌「クリスチャニティー・トゥディ」に6月1日、「白人福音派は謙虚になる必要がある」(英語)と題したインタビュー記事が掲載された。これは、米宗教専門通信社のRNS通信が5月29日に配信した記事だが、もともとの見出しは「ジョージ・フロイドの死、白人と黒人のクリスチャンを分断しているもの」(英語)である。事件のあったミネソタ州ミネアポリスで多民族の教会を設立し、現在はカリフォルニア州で3千人を超える規模の教会を共同牧会しているエフレム・スミス牧師に、RNS通信のボブ・スミエタナ編集長が話を聞いたものである。自身は黒人で、『ポスト黒人・ポスト白人の教会』(英語)の著書があるスミス牧師の口調は明快で、そして厳粛なものである。だが、隠された「ねじれ」を理解しないままに大上段から語ることは、「白人福音派」を単なる「白人ナショナリスト」に変えてしまうことにもなりかねない。
本書は、心情的な部分をあえて抜きにして、現実に存在する団体や人物と、彼らがアウトプットした事柄(事の善悪は判断しない)をもとに描き出した「現代アメリカ」の姿である。ここにキリスト教会も含まれることを認めなければならない。「神の愛と聖書信仰によって裏打ちされた善良な人々」という中立地帯は、米国にも、そして米国を「観察」している日本のキリスト者にも存在しない。その厳しい「現実」を踏まえながら読み進めるとき、私たちは本書を通して新たな強さを獲得することができるだろう。
■ 渡辺靖著『白人ナショナリズム』(中央公論新社 / 中公新書、2020年5月)
◇