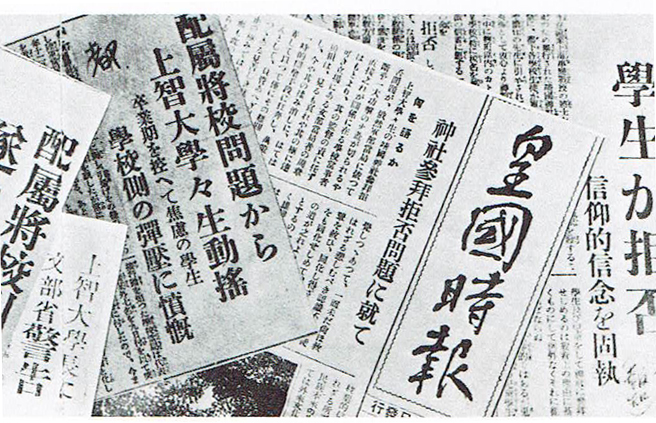
戦前日本が軍国化していく中で、キリスト教への弾圧として知られる上智大学靖国神社事件。この事件は1932(昭和7)年、学校教練のために上智大学予科に配属されていた陸軍将校が、学生60人を引率して靖国神社を参拝した際、カトリック信者の学生3人が参拝を見送ったことが発端とされる。カトリック教会の神社に対する方針に大きな転換をもたらし、現在でもこの方針を越えたものは示されていないといわれるこの事件について、新たな研究が生まれている。
日本思想史が専門で、戦前の日本における宗教と神社、国家と神道の関係を研究する上智大学国際教養学部国際教養学科名誉教授のケイト・ワイルドマン・ナカイ氏は、この事件に関してはいまだに謎が残されていると指摘する。まず、学生3人が参拝を拒否したことについてだ。当時の学長だったヘルマン・ホフマン(1864〜1937)は、靖国神社、伊勢神宮、明治神宮も含めた神社参拝を禁じていたことを認めており、学生たちはこの言いつけに従った形となる。だが、もしそうであれば、靖国神社自体へ行くことを拒否してもよかったのではないか。学生たちは、禁止されている靖国神社に行ったにもかかわらず、なぜ参拝は拒否したのか。単に「信仰の固執から参拝を拒否した」ということだけでは捉えきれない、さまざまな要素が絡み合った複雑な出来事だったという。
ナカイ氏は、同事件に関して「上智大学・靖国神社事件から見る1930年代の国家神道研究」というテーマで研究に取り組んでおり、同事件に関する史料を網羅的に収集、翻刻(ほんこく)し、当時の社会状況も踏まえた上で、同事件を通して「明治憲法下の宗教と国家の関係」「国家神道の本質」「軍部の権力拡大の経過」といったことを明らかにしてきた。既に論文「Coming to Terms with “Reverence at Shrines”」(Kami Ways in Nationalist Territory、Bernhard Scheid 編、Austrian Academy of Sciences 出版、2013年に掲載)も発表している。この論文では、同事件が起こった経緯、事件発生後の大学、政府、陸軍、カトリック教会の対応、そして「神社参拝」受諾をめぐるそれぞれの思惑が明かされている。

まず、神社に対する政府の立場である。国家の中に神社をどう位置付けるかは、明治から大正、昭和初期にかけて論争されてきたという。法律上および行政管轄上、神社はキリスト教や仏教、教派神道とは異なる扱いだった。1900年以降になると、神社は神社局、キリスト教・仏教・教派神道の教団は宗教局の管轄下に置かれ、さらに1913年には、宗教局は内務省から文部省へと移管され、両者の境界はより明確になった。その頃になると1910年に起きた大逆事件の影響もあり、国民道徳の育成のために神社の崇敬や支援の奨励が持たれるようになっていく。神社が「宗教的か否か」については、学識者や宗教団体をはじめ、神社に関する事柄を検討するため1929年に設立された神社制度調査会の意見も一致しないまま、上智大学靖国神社事件が起こることになる。
神社参拝をめぐっては、これまでもカトリック信徒と政府関係者の間でたびたび問題が発生していた。しかし、同事件ほどの規模にはならなかった。同事件がこれほど複雑化し、注目を浴びたのは、やはり陸軍が直接関与したことにある。この間、1932年の5・15事件などで政府内の陸軍の力が増大しており、さらに日本軍兵士の戦死者が増えたことで、靖国神社など陸軍と直接関連する祭祀の場に関心が集まることになった。

ところで、学校教練は、1925年に陸軍と文部省の共同事業として始まっている。陸軍は中・高等教育機関に現役将校を配属将校として割り当て、基本的な軍事訓練を行った。この訓練を受けた学生は、将来徴兵されたとき、幹部候補生に任命され、数カ月の兵役を免除された。陸軍からすれば、このような訓練の参加は特権であり、一方学校側にとっては、配属将校の存在は、社会的地位を得るために欠かせないものとなった。この当時、在学中に軍事教練を受けた証明を持っていることは、卒業後の就職を有利なものとし、将校引き揚げによる教練中止は学校経営面の死活問題だった。陸軍の将校引き揚げの脅しは、国家秩序における陸軍の権威を示すものであった。文部省にとっても、大学令により上智大学を専門学校から大学に昇格させる許可を出した監督責任を問われるため、どうしても避けたいことだった。そのため、数カ月にわたって文部省は、上智大学、カトリック教会と内密に協力し、配属将校引き揚げの回避を模索した。
1932年秋、東京のカトリック指導部と文部省は、靖国神社の参拝が「教育の一手段」であり、神社で行われる行為は「純粋に世俗的で政治的なもの」と公的に示し、教会が神社参拝を受け入れられるようにする妥協案を捻出した。日本カトリック教会の東京大司教であったアレキシス・シャンボン(1875~1948)は9月22日付で靖国参拝に対して文部大臣鳩山一郎宛てに手紙で妥協案を提示し、9月30日付の文部次官粟屋謙からの返信で、「敬礼ハ愛国心ト忠誠トヲ現ハスモノ」との回答が届いた。とりあえずカトリック教会は、この返信をもって「靖国参拝は宗教行為ではない」と理解し、神社参拝を許容することで事態の収拾を図ろうとした。
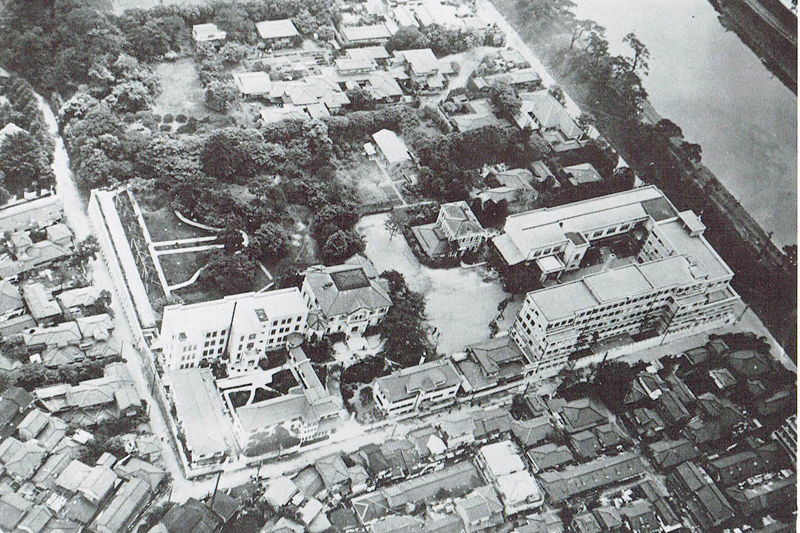
しかし、10月になると事件がさまざまな新聞に大々的に取り上げられたことで、文部省とカトリック教会の間の妥協は波乱を引き起こすことになる。このことについては、陸軍が文部省とカトリック系学校に圧力をかける新たな戦術として自らメディアを利用することで、上智大学に対して陸軍が不満を抱き、配属将校引き揚げを要求していることを世間に広めることが目的だったのではないかという。いくら陸軍といえども、学校教練が文部省と軍部の両方が管轄するものであるからには、勝手に将校を引き揚げるわけにはいかなかったからだ。この間しびれを切らした陸軍は、配置換えと称して配属将校を移動させ、その後任者は「適任者人選中」としたのである。
その後、陸軍が最終的に、上智大学の教育方針を国体と一致するものとして受け入れ(その背景は定かでない)、1933年11月中旬に将校を再配属することで、ようやく上智大学靖国神社事件は終わりを迎えることになる。
ナカイ教授は、カトリック教会の神社参拝の受諾は、単に一方的に押し付けられたものではなく、相当程度、文部省と東京のカトリック教会代表による合作だったと主張する。そして、両者の協力はどちら側からも積極的なものではなかったかもしれないが、最終的には、陸軍からそれぞれの利益を守るという共通の必要性によって促されたとし、この事件に新たな見解を示している。
ナカイ教授の論文については、今後、日本語版が国学院大学デジタル・ミュージアムに掲載される予定。